![]()
![]()
これらを軸として、平成6年12月以来、当院で運用されているシステムについて紹介したい。このシステムは決してゼロから出発したシステムではなくアメリカの医療材料の調達・管理システム、日本におけるスーパーマーケットの物流システムからベンチマーキング(比較検討)の結果、“応用編”として生まれてきたものであることを強調したい。
病院側と商社側の思惑が一致したところで、平成6年9月のヒアリングからわずか2ヵ月後の12月1日の運用開始までにお互いのパートナーシップのもと、集中的に準備を進めることができた。
まず、各部署の定数を設定し、その定数に見合った小分けパッケージを作成する。例えば注射器を例に取ると、一診療科の外来の注射器パッケージの入り数は5ないし10本となる。これに対して使用量の多い病棟においての小分けパッケージの単位は50ないし100本入りの箱単位となる。この単位ごとに在庫部署、材料品目、入り数、さらに単価が記載されたバーコードカードが添付される(図1)。
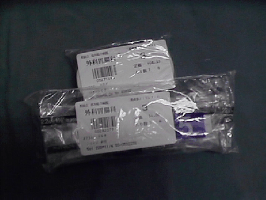
このような小分けパッケージをSPD業者の院外サプライセンターから院内の各部署までSPD業者によって配送・配置し、病院側が医材使用時にパッケージを開封し、バーコードカードを取り出した時点で請求対象となる。具体的には各部署でバーコードカード入れを設置し、ここに入れられたバーコードカードをSPD業者が回収し、当院の用度課に集められる。用度課に設置したコンピュータがバーコードを読み取り、その情報は院外サプライセンターに電送される。週3回の配送のため、電送した使用物品は翌々日には同じ部署の同じ棚に配送されることとなる(図2)。
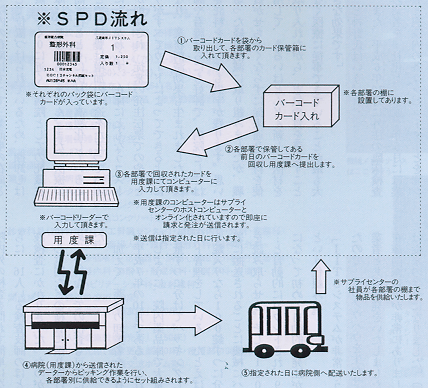
これにより、バーコードカード=請求伝票となり、各部署は物品管理・請求業務から一切解放されることとなる。これはとりもなおさず、本来のミッション(使命)と異なる物品管理の主役であった看護婦の間接業務からの解放につながり、本来業務である看護の質の向上に寄与されるものとなった。
さらに、現場の部署側は安心のためにより多くの在庫を抱えたいというバイアスが働くのに対し、業者側は業者在庫であるためより少ない在庫にしたい、しかし欠品のたびにサプライセンターより臨時発送はしたくないというバイアスが存在する。この両者のつばぜり合いの結果、より適正な在庫が自律的に設定されていった。
また、4年におよぶ運用の経過でこれらバーコードカードのなかで、保険請求できるものには請求漏れ防止のための色付きカードを、最近はバーコード対応を目玉として構築された当院のオーダリングシステムで保険請求時に利用することができるバーコード入りシールを添付している。
現在、64部署に、2,275種類のバーコードカード(計8,081枚)が運用され、平成9年度のSPD業者に支払った診療材料費は約5億7,000万円である。
SPD導入によって、診療機能が変わるものではない。したがって、初年度の導入効果は大きなものになる。それ以降に関しては、新たな在庫は生まれないものの、使用診療材料費比率が変わるものではなく、この比率はあくまでも診療内容に規定されていくものである。しかし、バーコードによるコンピュータデータは明らかに蓄積される。いつ、どの部署で、何が、どれだけ使用されたかという詳細なデータが蓄積され、それと医事データの突き合わせとともに診療機能の把握や請求漏れの調査が可能となった。
ここで初年度の導入効果を示す(表1)。数字に出ない効果として、院内の診療材料倉庫は消滅した。この後、さらに平成7年の薬剤管理システムの導入とともに、5名配置していた用度課職員は3名に減員できた。
|
倉庫在庫 |
7,400万円 |
|
直接効果:在庫金利削減、医材ロスの解消、請求漏れ改善 |
3,490万円 |
|
間接効果:ナース・用度課の医材管理業務の削減 |
2,250万円 |
|
システム導入料金:調査費、コンピュータ関連、棚の整備 |
△1,090万円 |
|
経済効果合計 |
4,650万円 |