 �ߋ���E��
�ߋ���E��
 �ߋ���E��
�ߋ���E��
�@
�c��`�m��w
�y�X�R�E���w�z�c��`�m��w
���
�@���e�͎������邽�߂ł���s���e�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�m���ɐl�Ԃ̗��j�͎����Ƃ��ĕs���e�Ɋ�Â��Η����o�����Ă������A������悭����Ί��e�ւ̓��ł���B���Ȃ킿�A�����ێ��̂��߂̝|��_��́A���҂���҂�����I�ɖ��E����悤�Ȏ��Ԃ�����ӎu�Ɋ�Â������̂ł���B�l�ԓ��m�̊W�͗����E�m���E�l�Ԑ��Ɋ�Â������̂ł����āA�������݂������̂ւ̐��قɂ��Ă��A�l�Ԃ̗ϗ�����O�����̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������������ւ̔��t�ɂ͒��������P���i�W������ӎu������A�����̉��b���A��������낤�Ƃ���҂͂�������Ȕᔻ�̌_�@�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�]���āA�s���e�̖\�����~�߂�̂́A��͂芰�e�̗͂ł���B
���
�@���͕M�҂̎咣�������ł��Ó��Ȃ��̂ƍl����B�Ⴆ�A���A�����͂�p���ĕ����������ɓ������Ƃ��鎞�A�����ɂ͐����I�Ȏ��R�▯���`�����`�ł���A�ƍق�N���͐��`�ɔ�����Ƃ�����{�I�F��������B�������A���݂̍��ە����͂��Ă̐����ɂ��A���n�x�z�������ƂȂ��Ă�����̂������B���Ȃ킿�A�ȑO�͐A���n�ɑ��ĕs���e�������卑���A���͊��e�����K�v������Ƃ������R�ŕ��͂��s�g����̂ł���B
�@���������̒��ŕ��a�����߂邽�߂ɂ́A���Ȃ𑊑Ή����鎋�_���K�v�ł���B��̓I�ɂ́A�����̗��j�ɑ��鑼�̍�����̔ᔻ������A�^���Ȏ��Ȕᔻ�ƕ⏞���Ȃ����ׂ��ł���B����ɁA�������ׂĂ�������m��A�������g�Ŕ��f�������鎩�R���K�v���B�����������e�̗��ꂩ��̎��݂ɂ��A���Ȃ̗���𐳋`�Ƃ��Đ�Ή����A�ߋ��̕s���e��Y���댯�����炷���Ƃ��ł���Ǝ��͍l����̂ł���B
�y�X�S�E���w�z
��I
�@�@�B�d�|���̃J�u�g���V�ɑ���_�[�N�X���̑ԓx�́A�S�������Ȃ��u�@�B�v���u�E���v�ƌ������Ƃɑ����R���E��a������A�u�@�B�v�̂͂��̃J�u�g���V�ɑ���u����v�ւƕω����Ă���ƌ�����B����́A�_�[�N�X�����g�́u�@�B�͐S�������Ȃ��v�ƍl���Ă���ɂ�������炸�A�@�B���u�S�������́v�Ƃ悭�����s�����������߂ɁA�u�@�B���S�����悤�Ɋ������v����ł���B�S����ϓI�Ȃ��̂��Ƃ���ƒ��ڊώ@�͂ł��Ȃ����A�S���u�����v�Ƃ��đ���������̂��Ƃ���A�s���̊ώ@�ɂ���Ă���Ώۂ��S�������ǂ����𐄘_���邱�Ƃ��ł���ƌ�����B�_�[�N�X���̑ԓx�̕ω�����l����ƁA����́u���o�v�ŕЂÂ�������̂ł͂Ȃ��B
��II
�@���҂́A�u�S�v�ɂ��čl���邽�߂ɂ́A�u�S�̋@�\�v�ɒ��ڂ��ׂ����Ǝ咣���Ă���B����ɐ��m�Ɍ����A���҂̂����u�@�\�v�͊ώ@�\�ȓ����Ɍ��ʂƂ��Č��т��u�@�\�v�ł���ƌ�����B���������u�S�Ƃ͉����v��������ł���̂́A������u�����̐S�ȊO�̐S��m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v����ł���B���Ƃ������̐S�ł����Ă��A�ώ@���悤�ƒ��ӂ�������A�����ɕω����āu����̂܂܁v�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��u�S�v�Ȃ̂ł���B�]���āA�S�̓������O���Ɍ��ꂽ�@�\����T���Ă䂭���҂̗���́A�S�𑨂��₷���Ώۂɂ���Ƃ����_�ł͗L���ł���B�������A�ϑ��ł��Ȃ��悤�ȐS�̓����A�Ⴆ�Έӎ��̂Ȃ����҂̔]�̋@�\��m�낤�Ƃ���悤�ȏꍇ�A���̕��@�͍���ɒ��ʂ���B�u�ӎ��̂Ȃ��l�Ԃ͐S�����ƌ����Ȃ��̂��v�u�S�������Ȃ���ΐl�ԂƂ͌����Ȃ��̂��v�Ƃ�����肪�����ɐ����邩�炾�B���҂̗���ɂ͂����������E������Ǝ��͍l����B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�R�E�����z
�@�u�v�҂��z�����ׂ����Ƃ���v�̒��ōł��d�v�Ȃ��̂́u�x���V�X�e���̍\�z�҂Ƃ��Ă̐v�҂̎��ȔF���v�ł���Ǝ��͍l����B���̏ꍇ�́u�x���V�X�e���v�Ƃ́A�v�҂ƌڋq�Ƃ����݂ɉ����҂ƂȂ��Ă�����\�����A���̒��Ő�������l�X�������炵����������悤�Ɏx�����s�Ȃ��Љ�V�X�e���ł���B
�@���������ߑ㍇����`�Ɋ�Â��Ĕ��B��������̋Z�p����ł́A�l�Ԏ�̂��q�̂ł���Ώې��E������I�ɑ����A���p����Ƃ�����ώ�`�I�ȍ\�}�����R�̂��ƂƂ��Ď�����Ă���B���͂Q�ƂR�ɂ���u�`���I�v�Ȑv�҂ƌڋq�̊W���A�v�҂���̂ƂȂ��Čڋq�Ɂu�^����v�W�ł���ƌ����悤�B���̏ꍇ�A�v�҂̍s�ׂ̍�������ʂ̐l�X�Ɠ��l�Ɏ����̗~�]��M���ł���B�܂�A�v�҂͎Љ�S�̂�����ɓ��ꂽ���@�ɂ���ē�������Ă���̂ł͂Ȃ��A�v�҂Ɣނ����芪������ȎЉ�̗ϗ��ςɂ���ē�������Ă���̂ł���B��������A��K�͂ȊJ���v��ɂ����j���[�U�[�����̐v�����܂�Ă��܂��̂ł���B
�@�����������ɒ��ʂ��āA����̐v�҂́u���ȂƊ��Ƃ̑��l�ȊW�̉\���v�ɋC�t���Ȣf���Ă���ƌ����邾�낤�B���͂P�ɂ���u�Ӓn���Ȗ��v���Ȃ킿�u�v�Ɋւ���K�͂̑��Ή��v�u�v�V�X�e���̕s���S���̔F���v�u�S�̑��\�z�|�����̍���v�͂��̌˘f���̌����ł���B
�@����䂦�ɁA����̐v�҂ɕK�v�ƂȂ�̂́A�u�S�̐��E�������v�ɂ��傫�ȉ��l��u���p���ł���ƌ����邾�낤�B���͂Q�ɂ���u�Z�p�̌l�ɑ���K�����v�A���͂R�́u���݂ɃR���g���[�����������Ƃƌڋq�i�Љ�j�v�̔��z�͂������������ŗ����ł���B�����������z�Ɋ�Â��u�x���V�X�e���v�ł́u���҂Ƃ̋����Ƌ����v�u�����̐�����ꏊ�ł̎��H�v���d�������B�]���āA���R�j������l�Ԃ̐������R���g���[�����Ď��R�Ƃ̒��a��ۂ��Ƃ��I��A�u���v�v������������̐l�Ԃ��ア����̐l�Ԃ���w�тȂ��狤�ɐ����邱�Ƃ��I��A�u�S�́v�Ƃ��Ă̐l�Ԃ𑨂��邽�߂ɕ����I�ȑ��ʂƐ��_�I�ȑ��ʂ����ɑ��d�����B�����������ʂɔz�����邱�ƂŁA�v�҂��܂��V���Ȏ��ȂƐV���ȐE�ƓI�g�����ł���̂��Ǝ��͍l����B
�y�X�R�E��������z
�@�ߑ㐼���́u�Ȋw�̒m�v�̖��_����ɂ܂Ƃ߂�A����́u�S�̘_�I�Ȏ��_�̑r���v�ƌ�����B���q�_�Ɋ�Â��v�f�Ҍ���`�̌��E�������Ɍ����Ă���̂ł���B
�@�f�J���g�ȗ��̗v�f�Ҍ���`�E���͎�`�Ɉˋ�����Ȋw�́A���݂̋��ɂ̒P�ʂ����߂邱�ƂŐ��E�̏����ۂ�����ł���ƍl�����B�����ł͎�̂ł���l�Ԃ��q�̂ł��鎩�R����Ɨ����Ă���ƍl�����A�l�Ԃ͎��R��ΏۂƂ��Ēm��A���̒m���ɏ]���Ď��R�𐧌�ł���ƐM����ꂽ�̂ł���B���ꂪ�Ȋw���_�ł͕��͂b�́u��ӓI�@���ɂ��A���ԁE��ԓ��ł̎��ۂ̋L�q�v�Ƃ��Č����A�Љ�W�ł͕��͂a�́u���Ɛl�ԁv�̒f��A���͂`�́u���ȂƑ��ҁv�̒f��Ƃ��Č����Ă���̂ł���B����ɐl�Ԑ����u���_�v�ɊҌ����闧�ꂩ��A���͂a�́u�g�̂ɑ��鐸�_�̗D�ʁv�������ꂽ�B
�@�m���Ɂu�Ȋw�̒m�v�͋Z�p�ƌ��т��Đl�Ԃ̊������g�債���B�������A����ł͂��́u�L�p���v�h�����鎖�Ԃ����X�ɋN�����Ă���B����͎��R���̔j��⋐��V�X�e���Z�p�̕s����Ȃǃ}�N���ȑ��ʂ���A����ڐA�ɂ�����Ɖu�@�\�̗}���̍���Ȃǃ~�N���ȑ��ʂɂ܂ŋy��ł���B�����́A�F�������̂ł���l�Ԃɂ���Ď��R�E�̒���������I�ɗ^������Ƃ���l�����̌��E�ł�����B����䂦�A�����Ɏ�́E�q�̂̍\�}����u�S�̘_�v���K�v�ɂȂ�B���̏ꍇ�́u�S�́v�́u�S�̂̓���ƕ����̓Ɨ���ۂV�X�e���v�Ƃ��Ắu�L�@�́v�ƍl����悢�B
�@�������āA�u�����̒m�v�͗L�@�̘_�Ƃ��Ă̑S�̘_�Ɋ�Â������̂ƂȂ�ׂ��ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�B����ł́A���͂`�̕M�҂���Ă���u�R�X�����W�[�v�u�V���{���Y���v�u�p�t�H�[�}���X�v�͂����ɂ��Ď��������̂��B����́u�`����w�̕����v�ɂ���ĉ\�ł���B�u�Ȋw�̒m�v�ȑO�ɂ́A�����ɂ����Ă������ɂ����Ă��A�@���ɗR������N�w�I��b�Â����K���K�v�Ƃ��ꂽ�B���̓N�w�I��b�Â��͎Љ���̒��Ől�X�������l�X�Ȋ���ɈӖ���^���āA�t�ɐl�X������ɗ�����Ȃ��悤�ɒm���Ɗ���̃o�����X���Ƃ铭�������Ă����ƍl������B�u�Ȋw�̒m�v�́A�_���Ώd�ɂ���Ă��̃o�����X�����������̂ł���B�]���āA����̊w��I�ۑ�́A�_���`�Ȃ��V���Ȍ`����w���A�L�@�I�Ȓm�̑����҂Ƃ��āA�܂����E�̖L���ȈӖ��Â��̊�ՂƂ��ē������邱�Ƃ��Ǝ��͍l����B
�y�X�S�E�����z
�i�P�j�T
�i�Q�j
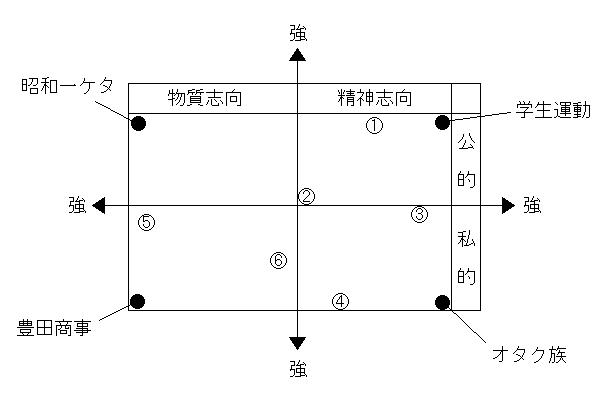
�@���́A�P����U�܂ł̎��������ꂼ��u�Η��W�v�������Ă���ƍl����B���ꂼ��̑Η����ڂƂ́A�����P�u�����I�E���_�I�v�����Q�u�O�ʓI�E���ʓI�v�����R�u�����u���E�ߋ��u���v�����S�u�m���E�o���v�����T�u�^�e�}�G�E�z���l�v�����U�u�h���Nj��^�E�̂�т�^�v�ł���B
�@�����̋��ʓ_������ɂ܂Ƃ߂�ƁA�傫�������āu���I�E���I�v�u�����I�E���_�I�v�Ƃ����j���̊W����A���ꂼ����ʒu�Â��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�}�ɂ́A�����Ɏ�����Ă���u�������v�̈ʒu���L���Ă���B�u�L�����v�������̊W���番�ނ���ƁA�u���I�ȖL�����v�Ɓu���I�ȖL�����v�A�u�����I�ȖL�����v�Ɓu���_�I�ȖL�����v���Η����闧��Ƃ��čl������B
�@�����]�ށu�L���Ȑ������v�Ƃ́A���I�ȖL�����𑽂��̐l�����L���A���_�I�ȖL�����ɂ���ĕ����I�ȖL�����́u���v��ς��Ă����悤�Ȑ������ł���B����́A�Љ�W�̑��ʂ��猩��u�Љ�⑼�̐l�X�̂��߂ɂ����v�������ƌ��������邱�Ƃ��ł���B�����Ƃ��A���́A���a�ꌅ����́u��Ɛ�m�Ƃ��Ă̖Ŏ�����v��A�c��̐��オ���S�ƂȂ����Z�Z�N��w���^���́u�l���g�D�v�Ƃ������u�������v�����悤�Ƃ͎v��Ȃ��B�������߂�̂́A�{�����e�B�A�����Ȃǂ�ʂ��A�����̐����������g���āA�Љ�Ƃ̂Ȃ�������߂鐶�����ł���B
�@����Љ�ɐ����鑽���̐l�Ԃ́A�Љ�ƊȊW���������Ă��Ȃ��B�o�u���o�ώ���̏ے��Ƃ�������u�L�c���������v��u�I�^�N���v�́A�ǂ�������I�ȗ��v�ɕ�������_�ł��̎���ł���B���������u�Љ�I�Ȃ���̑r���v�́A�W�c�̒��ŁA�ォ��Ǘ�����鐶��������N�����Ă�����ł���B����䂦�A���͂܂��n��̃R�~���j�e�B�[�����Ɏ�̓I�ɎQ�����A���ɎЉ�I�Ɏア����̐l�X�Ƌ��ɐ�����o����ς݂����B���̖ʂł́A�u�L���Ȑ������v�Ƃ́A�u���ҁv�̐������������̐������̒��Ɏ�荞��ł䂭���Ƃ��ƌ�����B����́u�������V�l�ɂȂ����炱�����������v�Ƃ����悤�ɁA�������̐V���ȉ\���ɋC�Â����Ƃł�����B�[�I�Ɍ����u���҂̂��߂ɂ������o�����J�͂��o���v�u�����̍l�������т��v�u�l�Ɛl�Ƃ̂Ȃ���̒��Ŋw�ԁv�Ƃ��������������͖]�ށB
�y�X�S�E��������z
�@�����ɂ́u�ݕ��Ə��̃O���[�o�����v�u���Ƃ̗��O�̑��Ή��v�u�C���_�X�g���A���Y���E���x�����Y���ƍ������ƌ`���̖��ڂȊW�v�Ƃ����O�̑��ʂ��猩�����Ƒ��̕ω���������Ă���B
�@�ߑォ�猻��ɂ����Ắu���Ɓv�Ƃ������t�̈Ӗ��Â��́A�u�����v����u���l���v�ւƕω������ƌ�����B�u�����v�̖ʂł́A�����^�����獑�����Ƃ̌`���ւƂ��������̉�������ɁA���ۘA�����ʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B�������A�u���l���v�̑��ʂł́A�\�A�����A�č��̐��E�����ւ̔����͂���܂����ŁA�n��I�Ȏ����^���̍��g�����E���u����v�Ɍ����킹�Ă���̂ł���B�����A�V���Ɏ�����ڎw������n��̑�������i���ɉ�����v�����Ă���悤�ɁA�����Ɠ����ɐ��E�I�ȋ��͂����߂���p���h�b�N�X���A����̍��Ƒ��G�ɂ��Ă���̂ł���B
�@���̃p���h�b�N�X�́A�o�ςɌ���������B�����P�ɂ���悤�ɁA�����ł́A�P�Ƀ��m������������鍑�ۖf�Ղɗ��܂炸�A���Z�A�T�[�r�X�A���A�����ĘJ���͂Ƃ��Ă̐l�Ԃ܂ŁA�������z���đ�ʂɈړ�����悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B���č��ƌ��͂̎x�z���ɂ������e���o�ς͐��E�o�ς̈ꕔ�ɑg�ݍ��܂�A�s��o�ςƓ����ɂ�����x���閯���`�̃V�X�e�����������z���ė��ꍞ�ށB�����R�������悤�ɁA���ꂪ���剻�Ǝ����^���̍��g�������炵���ƌ�����B����琭���̋nj����ƌo�ς̃O���[�o�����́A���Ƃ̎匠�ł͐���ł��Ȃ��A���R���̍������z�����j��ƈٕ����Ԃ̖��C�������N�����B�Ⴆ�A�M�щJ�т̌������o�j�n�Ȃǂ́u�����������P�s�ׁv���A�O�҂͐�i���́A��҂͓r�㍑�̎匠�̔ے�ƍl������B
�@�����ŁA���͂��ꂩ��̍��Ƒ��Ƃ��āu���Ƃ��Ă̍��Ɓv���l�������B�u���v���Ώې��E�Ɛl�ԂƂ̊Ԃɐ�����������ߒ��������u�S�́v�ł���悤�ɁA���Ƃ��u�L�@�I�v�ȁA���Ȃ킿�u�������Ɨ����Ȃ���A�����ɑS�̂̓��������Ȃ��v���݂ł���ׂ����B���̈Ӗ��ŁA�l�ԂƁu���ƂƂ������v�̌����ߒ���j��s�ׁA�Ⴆ�Ε��͎x�z����j��Ȃǂ̎��Ȕے�I�s�ׂ������ɒ��~���A�u�����̓Ɨ��v�Ƃ��Ă̑��l�Ȑ������������ɕۏႷ�邩���V�������ƂɂƂ��Ă̎�v�Ȗ��ł���Ǝ��͍l����B
�y�X�T�E�����z
��P�@�w�P�|�g�@�w�Q�|���@�w�R�|���@�w�S�|��
��Q
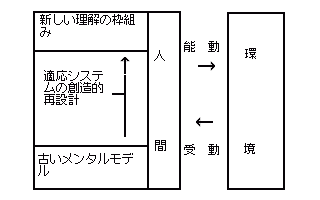
�i�P�j�u�l�ԂƊ��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����v�ɂ��ƂÂ����V�����w��̂�����B
�i�Q�j
�@���͓�̕��͂����ƂɁA�u�l�ԂƊ��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����v�̏d�v�����A�O�̒i�K�ɕ����Ę_�������B
�@���͂`�ŏq�ׂ��Ă���̂́A�l�Ԏ�̂��q�̓I���E�ł�����Ə���}��ɂ��Ċւ��u�R�~���j�P�[�V�����v�̊�b�I�ȉߒ��ł���B�����̂���l�Ԃ͎��͂̊��������Ȃ�ɗ������A���p���Ă����B���̍ہA�u�����v�̊�b�ƂȂ�̂́A������^�����鑽�l�ȏ��̒��ɊW�E�\���E�K�������o���A���G��������������S�̓����ł���B�����āA�����l�ԂƊ��̊ԂɃR�~���j�P�[�V�����Ƃ����o�����I�ȉߒ����l����̂́A���̒i�K�ł́A���̐S�̓��������o�m�o���x���́u�I�ȓ����v�ƁA�����F�m���x���́u�\���I�ȓ����v���琬�����Ă��邩��ł���B
�@���������A�l�Ԃ��Ώۂ����A���f���鎞�A�����ɂ͎�ς������B���͂`�̃����^�����f������ς̓����ł��邪�A��ς͂������R�I�ɓ����̂ł͂Ȃ��B���ɂ��܂��K�����邽�߂ɁA��ς͂��̏�ɂӂ��킵�������^�����f�����\�z����̂ł���B�������A��x�͈��肵�����f������@�ɒ��ʂ��邱�Ƃ�����B�Ⴆ�A���m�̌��ۂɏo��������⑼�҂Əo��������A�u������̓��������v�ɂ���Ď�ς͕ύX��]�V�Ȃ������B�ǂ̂悤�Ɂu���̂̌����v��ύX����Ί��ɓK���ł��邩�Ɛl�Ԃ͍l���A�V�������f���ɏ]���Ċ��ɓ���������B�����ɁA���̒i�K�ł̊��Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������܂��̂ł���B���ꂪ���͂a�Ō����Ă���u���z���ɂ����̉����v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@����ɁA���̃R�~���j�P�[�V�����ߒ��́u�w��̊�b�v�ł�����B�w��̖{���̖ړI�́A�l�Ԃ����R�⑼�҂��܂߂��u���v�ɓK�����Ȃ��玩�Ȃ̈ʒu���m���߁A��̓I�ɐ����邱�Ƃɂ���B����䂦�A�����ς��A�����Ȃ闝�_������ݏo�����l�X�́u�l�����̘g�g�v���̂������j�I�E�����I����ɂ���Ĕے�I�ȁu����v�ƂȂ�\��������B��ʂ̏�����邾���ł͊w��ɂȂ炸�A�n���I�ɐ����邱�Ƃɂ��Ȃ�Ȃ��̂͂��̂��߂ł���B�]���āA�w��̊�b�ɁA����܂ł̊w��̂��u�m�I�g�g�݁v�𑊑Ή����錴�����K�v�ɂȂ�B���ꂪ�A��̕���ɕ�������Ȃ��w�ۓI������f�[�^�x�[�X�\�z�ȂǁA��O�̒i�K�Ƃ��Ắu�J���ꂽ�R�~���j�P�[�V�����v�Ȃ̂��Ǝ��͍l����B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�T�E��������z
�@�ۑ蕶�`�a�ɋ��ʂ̘_�_�́u���_�̕��Ր��v�ᔻ�ł���ƍl������B���̏ꍇ�́u���Ր��v�Ƃ́A���_�I�Ɍ��o���ꂽ�u�@���v���ϑ��҂ł���l�Ԃ���Ɨ����āA������A�n��I�ȕ����̍��ق��đÓ����邱�Ƃ��ƌ����邾�낤�B
�@�f�J���g�ȗ��̗v�f�Ҍ���`�E���͎�`�Ɉˋ�����Ȋw�́A���݂̋��ɂ̒P�ʂ����߂邱�ƂŐ��E�̏����ۂ�����ł���ƍl�����B�����ł͎�̂ł���l�Ԃ��q�̂ł��鎩�R����Ɨ����Ă���ƍl�����A�l�Ԃ͎��R��ΏۂƂ��Ēm��A���̒m���ɏ]���Ď��R�𐧌�ł���ƐM����ꂽ�̂ł���B�������A���͂`�ɂ���悤�ɁA���R�̒��ɂ͖{���I�Ɂu�s�m�萫�v�u�������v���g�ݍ��܂�Ă��邱�Ƃ��킩��ɂ�A��ΓI�ŕ��ՓI�ȗ��_�����߂�Ƃ����u�m�v�̂�����͌��������悤�ɂȂ����B
�@����A��̂̑����瓯����������A���͂a�ɂ���Ƃ���A�u�Ӗ��Â��̑��l���v��F�߂邱�Ƃɂ���āA�R�~���j�P�[�V�����̕��ՓI�Ȑ������^���Ă�������炩�ɂȂ�B�������҂Ƃ̍��ӂ��K�v�Ȃ�A���̊�b�͎���̃A�C�f���e�B�e�B�����킸�Ɂu�Ӗ��Â��̋��L�v���Ȃ���邱�Ƃł��邪�A����́u�Ӗ��v���̂��s�m�萫���͂��ł���ȏ�A�Ӗ��Â�������Ƌ��ʂ̂��̂ł��邩�ǂ����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̓_�ł��A�u�ߋ��Ƃ̑Θb�v�u���҂Ƃ̑Θb�v���\�ł���Ƃ���ߑ�̗��_�́A���Ր��̍����������Ă���ƌ�����B
�@�������A�������A���_�̑Ó�����R�~���j�P�[�V�����Ɋ�Â����ӂ��s�K�v���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�ނ���A���l������������錻�ゾ���炱���A�����͒m�I�����ɕs���Ȋ�Ղł���ƌ����悤�B����䂦�A��X�͎����̐����Ă���u��v���ɂ��Ȃ���A�����ɑ��҂Ƃ̍��ӂ��\�Ƃ�����̂̌�����������m�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A�u���_�̕��Ր��v����̂���藣�����ƂƂ͋t�ɁA���_����X�́u�����v������E�Ƃ́u���a�v�ƌ��т���m�I�w�͂ɂ���ĉ\�ɂȂ�B
�@�����ɊҌ���`���́E�q�̂̍\�}����u�S�̘_�v�u�V�X�e���_�v�̔��z���K�v�ɂȂ�̂ł���B���̏ꍇ�́u�S�́v�́u�S�̂̓���ƕ����̓Ɨ���ۂV�X�e���v�Ƃ��Ắu�L�@�́v�ł���B�����l�ԂƂ��̑Ώۂ��݂��ɉe����^�������čs���悤�ȊW�ɗ��w���ڎw���S�\�����A�ߑ�ȍ~�̕����̎���ς��Ă����Ǝ��͍l����B
�y�X�U�E�����z
��P
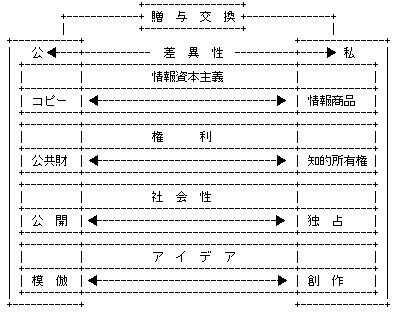
�@���͍��x���Љ�ɂ�������{�̉ۑ�Ƃ��āu�̑��d�ƌ������̗����v�u�Ƒn�̎x���v�u���̔��M�v�̎O�_���d�v�ƍl����B�����́u��В��S�Љ�v�u���^�������Ӂv�u�ӌ��m�ɕ\�����Ȃ��v�Ƃ����O������̓��{�ᔻ�ɑΉ������ۑ�ł���B
�@���ɁA�����P�ŏq�ׂ��Ă���悤�ɁA�`���I�ɓ��{�ł͖������Ђ̗͂������A�l�����d����Ȃ��B���̂��߂ɁA���I�ȃA�C�f�A�Ɉˋ�����Ƒn�͐��܂�ɂ����B�����Ɂu�������Ƃ͏ォ��̖��߂ɏ]�����Ƃ��v�Ƃ����ӎ��������A�u�����̂��߂ɃA�C�f�A�����v�Ƃ������z���R�����B���ɁA���{�l�͗��w���ċZ�p���w�Ԃ����w���͎��ꂸ�A��������b�����ւ̓����͂킸���ł���B���̌��ʁA���E�I�Ɉ��p�����_���̖{���͏��Ȃ��A�H�Ɛ�i���ł���Ȃ���m�[�x����҂����Ȃ��B��������u�����̃A�C�f�A�𓐗p���ē�������N�Q�����v�Ƃ�������������u���{�������_�v���o�Ă���̂ł���B�����Ă��̖�肪�R�~���j�P�[�V�����ɔ��f����ƁA��O�́u���{�l�͏���������Ŕ��M���Ȃ��v�Ƃ������ɂȂ�̂ł���B
�@�����̖����܂Ƃ߂�A�}�̂悤�ɁA���{�ł́u���v�ɑ�����̈悪�y������A����炪�u���v�̗̈�ɏ]�����Ă���ƌ����邾�낤�B�������A�{���u���v�Ɓu���v�́A�u���l�������������R�Ȍv���A�т��āu�������v���x����Ƃ����A�����������̂ł���B����������A�������������̊Ԃɍ��ق����邩�炱���A�������͋��ʂ̗��Q�����o���Č��������铹��T��˂Ȃ�Ȃ��̂��B�䂦�ɁA�����R�ɂ���u���ِ��v�́A���{��`�̌����ł��邾���łȂ��A����Љ�́u���v�Ɓu�������v�����Ɏx���錴���ł�����B�Ⴆ�A�����P�A�Q�̓������E�m�I���L�����N�����A�R�s�[���×����ď�i���������Ȃ��Ȃ�A���̌��ʏ�铽����Č������Ƃ��Ă̒m�����낤���Ȃ邾�낤�B
�@�]���āA�����̉ۑ���������邽�߂ɂ́A���ɁA�`���I�u�W���V�X�e���v���瑽�l�������l�����d�����u���U�Ɠ����������������Љ�V�X�e���v�ւ̕ϊv�A���ɐV�����m���̌n�̊�b�ƂȂ镪��ւ̎x���A��O�ɒN�����A�N�Z�X�ł���R�~���j�P�[�V�����x���V�X�e���̍\�z���Ȃ����ׂ��ł���B�����̏�Ɂu���v�Ɓu���v�̑Η��𒆘a����u���^�����v�̌����������A���{�̐��E�ɑ���v�������傷��Ǝ��͍l����B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�U�E��������z
���P
�@�l�̃e�L�X�g�ɋ��ʂ��鎋�_�́u����Љ�ɂ����鏤�i�̃V���{�����v����сu���̈Ӗ��Â��Ɛ����l���̖��ڂȊW�v�ł���B
�@�`�ł́A���i�̓��퐶���ɂ�����Ӗ����A���i���̂̏ے��I���l���\�����邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B���̉ߒ���S���̂��L���ł���B�a�ł́A����L���Ȃǂ̃}�X�E�C���[�W����Ď������̐����l���ɂȂ��Ă��邱�ƁA���ɃA�����J�ł́A�����J���҂̐������x�z���Ă��邱�Ƃ��w�E����Ă���B�b�ł́A���i�̂��Ӗ����Љ�S�̂̈Ӗ��Â��V�X�e���̒��ɑg�ݍ��܂�A�������͌ʂ̃��m�ł͂Ȃ��u���m�̑̌n�������m�v�Ɗւ�邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B�����ł́A�l�ԍs���̌����ł���~���́A�u�ڕW�i�d�m�c�j��ڎw�����Ɓv�ł���Ɠ����Ɂu���p�̏I���i�d�m�c�j������v�ł���A����͎Љ�̉��l�̌n�A�܂蕶���ƌ��т��A����X�^�C���������̃X�^�C���ƂȂ�B�c�ł́A���i�̍��ق����l�ݏo������Љ�ɂ����āA�������������i�̍��ق�₤���̂��L���ł��邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B�������A���̍L�����������ƍ��ى��̈��z�Ɋׂ��Ă���̂ł���B
�@����炩��ǂݎ��邱�Ƃ́A����Љ�ɐ�����l�Ԃ����m���V���{���𒆐S�Ƃ������������Ă��邱�Ƃł���A������ړI�����m��}��ɂ��Ȃ���Ό�����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�Ⴆ�A�u�K���ȉƒ��z���v�Ƃ����ړI���l���悤�B�����I�ɖ������肽�Љ�ł́u�K���v�͍L���ɂ���ĈÎ�����钊�ۓI�Ȃ��̂ł���A���ꂪ��̓I�ɉ����Ƃ������Ƃ͎����ł��킩��Ȃ��B��������������i�́u���l�ƍ������A�K�����ے����郂�m����ɓ���邱�Ɓv�ł���B�������A�₦�����������V���i�̂��߂ɂ��̗~�]�͖�������邱�Ƃ��Ȃ��A�u�K���̒Nj��v�͌��R���ɔY�܂���Ȃ���V�������m��ǂ�������s���ɂ�������Ă��܂��ł��낤�B���ꂪ����Љ�̐l�ԑa�O�ł���Ǝ��͍l����B
���Q
�@�d�́A�u���퐫����̒E�o�v�Ƃ������ۓI�ȖړI���A�E�C�X�L�[�Ƃ������m��}��ɂ��ĕ\�����Ă���L���ł���B�u�����{�[�̗��̐��E�v�Ɓu�����v�̋��E���A�C���[�W�̗���ɂ���ĞB���ɂ���Ă���B����䂦�A�ِ��E�ɗ������߂ɂȂ�����̎����K�v�Ȃ̂��A�l�͂�����l���Ȃ��B�z���C�g�A�I�[���h���烍�[�����A�R��ցB����Ȍ���������A�R�s�[�́u�����v�Ƃ́A�I��肪���̎n�܂�ł��������x���錇�R���ł���B
�y�X�V��@�z
�@�ۑ蕶�ł͓��ɓd�q���f�B�A�ɂ���ē`�����̊Ԑڐ����u�^�������v�ƌĂ�ł���B�ł́A�u�����v���邢�́u�������v�Ƃ͉��ł��낤���B���́u�������v�Ƃ́A�l�ԂƊ��Ƃ̊ւ������琶�܂�銴�o�ł���ƍl����B�Ⴆ�A������X�ɂƂ��đΗ�������̂ł���A���̒��Ő������т悤�Ƃ��鎞�u��R���v������A����́u����������v�ł���A�u�������v�ݏo�����̂ł���B�������A������X�̎v���ʂ�ɕς��A��������̂����R�Œ�R�����Ȃ����A�u����������v�܂茻�����͋H���ɂȂ�B
�@�Ȃ��d�q���f�B�A�����B�������x��Љ�ł́A���������ɂȂ�̂��B����͂܂��A�����F�����u���o�v�ɋɏ�������Ă��邱�ƂɌ���������B�u�t���[���ɂ���ʂ̐���v�u�N���ȉ摜�v�u���ߊ��̂Ȃ��v�Ȃǂɂ���āA�{���A�S�̓I�Ȋ��o�ł���u����������v���A���o���S�̊��o�ɕώ����Ă���̂ł���B�Ⴆ�A�J�����ɂ���Đ���ꂽ�����̒��ł́u���v���u���v���P�Ȃ�摜���ɂȂ�B����ƁA���Ǝ��̃R���g���X�g�ɂ���Đ��܂��u���̏[���v�u���̌��l���v�̊��o��������B
�@����ɁA�d�q���f�B�A�ł́A���Ƃ̑��l�ȊW���琶�܂��A�u���l�Ȋ��o�����ꂳ�ꂽ�S�̂Ƃ��Ă̌������v���ώ��������Ƃ�����肪����B�e���r�Q�[����C���^�[�l�b�g�ł́A���R�Ǝ����Ƃ̊W���A���l�Ǝ����Ƃ̊W���A���ׂăf�W�^��������A�t�@�C�����ꂽ���̃f�B�X�v���[�o�͂Ƃ��Ă����o�����꓾�Ȃ��B���ꂪ���퉻�����Љ�ł́A�S�Ă��u���l���v�ɂȂ�Ɠ����ɁA�����̒��Ɂu���l���v���N�����Ă���B�Ⴆ�A���l�̃S�V�b�v�ɑ���ߏ�ȊS�ƁA�d��Ȑ������ɑ��閳�S�Ƃ́A�������̓�̌����Ȃ̂ł���B
�@���̏̒��Ō����I�Ȍo���́u�S�̐��v������ɂ́A���炪�u��̓I���M�ҁv�ɂȂ邱�Ƃ��K�v���B���̂��߂ɂ͏����W�߁A�I�����A�������邽�߂̓Ǐ��ȂǁA�u�X�g�b�N�����m���v�𑝂₷���߂̓w�͂��K�v�ł���B�܂��A��̓I�Ȋ������d�v���B�Ⴆ�A�n��̎s���^���E�{�����e�B�A�����ւ̎Q���ł������Ōv�悵�����ł��悢�B�������g�̏����ȑ̌�����o�����邱�Ƃ��A���́u�^���������v�u�ώ����v�ɒ�R��������ł���A��b�ł���Ǝ��͍l����B
�y�X�V������z
�@���́A��Z�p�ɂ����̓`�B�E�L�^��Ƣ�m���ɂ���������̃o�����X���Q�P���I�̎Љ�ɕK�v���ƍl����B
�@�܂��A��Z�p�ɂ����̓`�B�E�L�^��̑��ʂŊ��҂����̂��C���^�[�l�b�g�̂悤�ȃl�b�g���[�N�E�V�X�e�����܂߂��}���`���f�B�A�ł���B�܂��A����ɂ���Ď��o�E���o�E�v�l�ɓ����ɑi����R�~���j�P�[�V�������\�ɂȂ�B����ɁA�o�������A���A�L�^�����������u���Α��v�̃R�~���j�P�[�V�����E�V�X�e���́A�����̐l�����߂���ƁA���l�Ȍl�����߁A���M���������̋����A���Ȃ킿�����Q�́u�ʗL�v���\�ɂ���B�����̓_�ŁA�}���`���f�B�A�̃l�b�g���[�N�́A���܂ł̂ǂ̃��f�B�A�����l�����R�ɔ��M���A�܂����R�ɃA�N�Z�X�ł���A�L�@�I�ɐl�Ɛl�Ƃ̌��т������߂郁�f�B�A���ƌ����Ă��悢�ł��낤�B���ꂪ�A�����P�́u�d�����V�����Љ�v�̍����ł���B
�@�������u�m���ɂ��������v���Ȃ���A�l�b�g���[�N�ŏW�߂�������������Ȃ��B���̏ꍇ�́u�������v�Ƃ́A�u������������̖��Ƃ��đ����邱�Ɓv�Ɓu�����̃v���Z�X���\�z���A���̎��H�̌��ʂ������邱�Ɓv�ł���B�O�҂�������A�l�b�g���[�N���p�҂͎����̏��j�[�Y�����ł����A���͒P�Ȃ��ʐ��Y�̏��i�ƂȂ�A������o��邾���ɂȂ�B�܂���҂�������A�l�b�g���[�N�ɗ������̎��W�E�I���E�����Ɣ��M�̂��߂̎�̓I�ȓw�͂��Y����A�v�l��K�v�Ƃ��Ȃ��A����₷�������ʂɗ������҂����̃l�b�g���[�N�E���[�U�[���x�z������t�@�V�Y�����o������B�܂�A�����R�Ŕᔻ����Ă��錻��́u���ő�E�b�q�ŏ��v�̎Љ�Ƃ́A�m���ɂ������������@���Ă���Љ�Ȃ̂ł���B
�@����ɁA�u�������v�̑Ώۂ͋�̓I�E�Љ�I�Ȗ�肾���Ɍ��肳���킯�ł͂Ȃ��B�����S�Ɂu�m���̓�d���v�Ƃ��Ď�����Ă���悤�ɁA��ϓI�E���_�I�ȕ���̖����A�m���ɂ��������̑Ώۂł���B������ǂނ��ƁA���҂ƒm���E���������L���邱�Ƃ̏d�v���͂�������o�Ă���B�]���āA�������ē�����m���Ɋ�Â��l�̎�̓I��M�E���M�\�͂��A�l�b�g���[�N�Љ�̏�ʂ��x������V�X�e�����A�u�m���v�Ɓu���v�̃o�����X���Ƃ��ŕs���ł���Ǝ��͍l����B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�V�E��������z
�@�u���Ƃ̖����v���l���邱�Ƃ́A���Ƃ��u���Q�̒����g�D�v�Ƃ��čl���邱�Ƃł���A�Z�̎��������̑��ʂ���ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B�����̎����͓�g�̑Η����ڂɂ���ĕ��͂ł���B����́A���Ɂu�~�]���K�����鑕�u�Ƃ��ċ@�\���A���͂ւ̕��]�𑣂����Ɓv�Ɓu��̓I�ӎv������x�����A���Ȏ����̎��R��ۏႷ�鍑�Ɓv�̑Η��ł���A���Ɂu�����̗ʓI�[�����x���鍑�Ɓv�Ɓu�����̎��I�[�����x���鍑�Ɓv�̑Η��ł���B
�@�����P�A�Q�́A���ꂼ��u�K���ɂ�铝���̌����ƌ������v�u�����̗ʓI�[���̕K�v���v���咣���A���̑Η����ڂł́u���͂ւ̕��]�v�A���̑Η����ڂł́u�����̗ʓI���ʂ̏[���v�ɑΉ�����B�������A�Ñ�ɂ����Ă������̎��I�[�����d������l�����͂���A�����R�́u�~�]�̊O�I�ȋK���v�Ƃ����_�ł͎����P�A�Q�Ƌ��ʓ_�������Ȃ���A�u�����̎��I�[���v�𗝑z�Ƃ���v�z��\���Ă���B
�@�����S�A�T�A�U�ɂ́A�Ñ�̎v�z�ɂ͌����Ȃ��u�����I�Ȑl�ԁv�Ƃ����A�ߑ�̐l�ԊςɊ�Â����咣���q�ׂ��Ă���B�ߑ㉻�ɂ���āu�i�V���i���E�~�j�}���v���[�����A���������͗ʓI�ɖL���ɂȂ�B�������A����ł��Ȃ��u�����̎��I���ʂ̏[���v�Ƃ����ۑ�͎c��B����́A����Љ�ł͕����̗ʓI�[���̂��߂̍��ƃV�X�e�����������āu�O�I�K���v�Ƃ��ē����A�t���I�ɌÑ�̂悤�ȁu���͂ւ̕��]�E�ˑ��v�ݏo���Ă��邩��ł���B���{�̍��������̉��E���i�����ʂ́u�J���ӗ~�̑r���v�����̗�ł���A�ߏ�ȕ������u�ꑮ�ւ̓��v�Ɣᔻ���鎑���T�̎咣�͂������������Ɋ�Â��Ă���̂ł���B
�@����䂦�A����̍��Ƃ̖����Ƃ́A�O�q������̑Η����ڂɂ�����u��̓I�ӎv����̎x���E���Ȏ����̎��R�̕ۏ�v�Ɓu�����̎��I�[���̎x���v�ɂ���ƌ�����B�{���A���Q�W���猩�����Ƃ̖{���Ƃ́A�u�����I�Ȑl�Ԃ����R�ɐ����邽�߁A���҂Ƃ̑����₷�邽�߂ɍ�鋤���̑��u�v�ł���B�����S�A�T�́u�s���Q���v�u���{�E�s��E�m�o�n�E�C���t�H�[�}������̋����ɂ��Љ�^�c�v�́A�����������Ƃ̋@�\�������������邽�߂ɕs���ł��邪�A������肾���łȂ��A�����ȂǁA�O���[�o���ł���Ɠ����Ƀ��[�J���Ȗ��Ɏ��g�ނ��߂ɁA����̍��Ƃ͒m���E�ӎv����E�s���̖ʂł��s�����x������V�X�e���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝ��͍l����B
�y�X�W������z
�@�l�̎����́A�l�X�ȑ��ʂŁA�\���ɂ����錾��Ǝ��o���f�B�A�̊W���q�ׂ����̂ł���B������m��Ȃ�����A�l�Ԃ̌o���ł��鐢�E�͐�������������̓I�Ȃ��̂ł������͂��ł���B�������A���o�̐��E�ɑ��A����ɃV���{���̐��E���D�ʂɗ��悤�ɂȂ����B����́A�l�Ԃ����͂̎��R�����߂����p����ߒ��ŁA���̌o���������Ƃ����V���{���\���ɂ���Ė@��������A��������@���╶�w�����܂ꂽ����ł���B
�@�����A���t���g���ĕ\�����邱�Ƃ͓����ɁA�����Q�ɂ���ʂ�A���t���x����_���̐���A�܂��A�l�X�̍l�����̘g�g���̂������j�I�E�����I�Ȑ����Ƃ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł�����B���̓_�ŁA�G��͎����R�Ŏ��l���q�ׂ�悤�ɁA���j�ƕ��������u�i���v�̕\���A�܂��������疳���̖L���ȉ��߂��\���ƂȂ�\�������B
�@���̔��ʁA���o���f�B�A�ɂ���ĕ\�����S������邱�Ƃ�����B���o���f�B�A�͓���̊���ɑi����傫�ȗ͂������A��̓I�Ȏv�l�͂�������r�������B�����S�łփ����O����i�̎��ɋ����Ă���u���͂Ɨ͊W�v�Ƃ́A�������e���r�W�����Ȃǂ̑�ʕ������f�B�A��p���Ĉ���I�ɑ�O�̊���𑀍삷��A����́u�}�X���f�B�A�Ƃ������́v���������Ă���̂ł���B�������A�R���s���[�^�̔��B�ɂ���Đ��܂ꂽ�C���^�[�l�b�g��}���`���f�B�A���g���ĕ\�����悤�Ƃ���A�}�X���f�B�A�ƈ���đo�����I�ȕ\���͉\�ɂȂ邪�A�[�������̒��ڐ��ɂ���čĂѓ�����肪������ł��낤�B���f�B�A���V�����Ȃ��Ă��A�g�������ς��Ȃ���A�u�\���v���V�����͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@���������ꃁ�f�B�A�̗͂��u��̓I�ȕ\���v�Ƃ��Ďg�����߂̎��݂��A�փ����O�Ǝ����P�̃N���[�̍�i�Ɍ���Ă���B�փ����O�́u�������v�Ƃ�����@�ŁA�R�s�[�ɕ`���������A�R�s�[�𑊑Ή�����I���W�i���̕\���A�P���ł��邪�䂦�Ɍ���l�l�̖L���ȉ��߂������\�������H�����B�N���[�́A�Ӗ�����`�Ԃ��A�܂��`�Ԃ���Ӗ����ǂ̂悤�ɔ������邩���A�����I�ȃ��x�����琸���ɖ₢�������B�ǂ���̎��݂��A���Č��ꂩ�琶�܂ꂽ�l�Ԑ��_�̖L�������A��葽�l�ȃ��f�B�A�E�\�����@�ōč\�����悤�Ƃ�����̂ł���B�ȏ�̂悤�ɁA�ǂ̂悤�Ƀ��f�B�A�����B���悤�ƁA�����Ǝ�̎�̐��������ŖL���ɏo��\�����ł��d�v���Ǝ��͍l����B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�X�E�����z
�i�P�j
�@���́u��k�i���̐��ݏo�������v�ɂ��ďq�ׂ�B�������A�����ł́u��k�i���v�Ƃ́A�Q�O���I�I���ł���u�ߑ㉻�̒x��v���傫�Șg�g�݂����B���W�r�㍑�͂���܂ŕn������I�s����ɋꂵ��ł������A�����ɂ͐����I�ߑ㉻�Ƃ����ǂ������߂̖ڕW���������B�������A�Q�P���I�ɖ��ƂȂ�̂́u���������ɂ͒ǂ����Ȃ��v�Ƃ����s���ł���B���ɁA���̎l�����I�ɐ���������ꂽ���x��́A�����l�b�g���[�N�̕����I��Ղ̏�ɐ��藧���Ă���B�Œ���̎Љ�{������������Ă��Ȃ��Љ�́A��Ɏx����ꂽ�o�ϋ����ɎQ�����邱�Ƃ����ł��Ȃ��B����䂦�A����Łu����E�Y�Ɖ��̒x�ꁨ�l���������Q��E�G�l���M�[��@�E���j��v�Ƃ������z�͏������A��������ł́u�r�㍑�ɂ͂��Ă̐�i���Ɠ��l�A����j�錠��������v�u�H�ƁE�G�l���M�[�E����Ɛ肷���i���͂��͂�ڕW�ł͂Ȃ��v�Ƃ����r�㍑������̋��₪�����邾�낤�B���ꂪ�Q�P���I�̐V���ȕ����ł���B
�i�Q�j
�@����܂Łu�����̌��E�v���c�_����鎞�A���S�I�Ȗ��́u���R���v�ł������B�������A�u���v�Ƃ́A�P�Ɏ��R���ɂƂǂ܂炸�A�u�Љ���v�u�������v�ɂ܂ōL�����Ă�����̂ł���B���m��Ȋw�Z�p���S�́u�r�㍑�x���v�́A�����������̑��`�����y�����錇�_�����B���̌��ʁA�x�Ə��̕s�ύt���u�k�̐�i���ɂ���̓r�㍑�x�z�v��ł��錻��̗��Ԃ��Ƃ��āA�r�㍑�͑S�ʓI�ɉ������̎x���V�X�e���Ɉˑ�������Ȃ��Ȃ�B�Q�P���I�ɂ́A����Ƃ͋t�́u���݂̎����Ɋ�Â���k�̍��ӂƋ����v���K�v�ɂȂ�B���̊�b�́u���̑��l�Ȃ�����Ɋւ��鑍���I�����v�u�r�㍑�ɑ��鋳��E���̑��ʂł̎x���v�u���ƊԂ̎x�z�Ə]�����z�������Ԍ𗬁i���ۉ��j�v�u�ߑ㉻�����̌������v�ł���B���������H���邱�ƂŁA�r�㍑�́u��i���̖͕�v����́A��i���́u����Ȃ�����Nj��v����̒E�p�������ł���Ǝ��͍l����B
�i�R�j
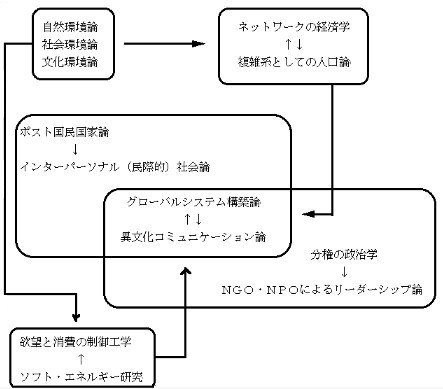
�y�Q�O�O�O�E�����z
�@�Q�O���I�̉Ȋw�Z�p�̓������ۑ蕶����ǂݎ��A�u�ړ��̋Z�p�̐i���v�ƌ����邾�낤�B��́u�l�E���m�v�̈ړ��ł���A������́u���v�̈ړ��ł���B
�@�A�[�~�b�V���̐l�X�͎����ԂȂǂ̈ړ���i��F�߂Ȃ��B���̂��߁A�����͈͂͋����Ȃ�A�����K���i�������ō��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�ނ�̓e���r�A�d�b�A�R���s���[�^���������Đ����Ă���B����ɂ���ď��͏��Ȃ��Ȃ�A�R�~���j�P�[�V�����ł���͈͂������Ă���B����ɑ��āA�������̐����͕֗��ł���B�ړ��́u�����E�����E�ʁv����ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǑ傫���B�l��m���ʂɁA�����A�����܂ʼn^�Ԃ��ƂŁA�~�������̂����ł��A�ǂ��ł���ɓ���B�������͐��E���ɍL����A�C�O���s��r�W�l�X���e�ՂɂȂ����B�܂��A�}�X���f�B�A�̔��B�ő�ʂ̏��𗘗p�ł��A�d�b��C���^�[�l�b�g�͏��̎��R�Ȍ������\�ɂ����B����炪�Ȋw�Z�p�̃v���X�ʂł���B
�@�������A��ʂ̏��̓��m�ɑ��鏊�L�̗~�]�Ə��������Ȃ����傳����B�܂��A���ʂ���m����������ƁA�����W�����ȖړI�����āA���̂��߂ɏ����W�߂Ă���̂��킩��Ȃ��Ȃ�B����ɁA�R���s���[�^�͘J���̎���ς����B�@�B�ɍ��킹�ē����̂Łu�Z�p�v���l�Ԃ��x�z���A�P���ȍ�Ƃ͘J���̈Ӗ������킹��B�܂��A�l�Ԃ̈ړ�������I�ɂȂ�ƁA�n��Љ��Ƒ��̓o���o���ɂȂ�A�l�͌Ǘ�����B�A�[�~�b�V���̐l�X�̉ƒ�ƒn��Љ���ɂ��鎿�f�Ȑ������A�`���I�Ȃ�Ƃ���������������́A����̂����̐����ƑS���t�ł���B�����͉Ȋw�Z�p�̃}�C�i�X�ʂł���B
�@�Q�P���I�̉Ȋw�Z�p�̔��W�ƕ�炵�̊W�́A�����̃}�C�i�X�ʂ�������������ɐi�ނ��Ƃ��]�܂����B�ł����v�Ȃ͎̂����I�ɗ~�]���R���g���[�����邱�Ƃł���B�Q�P���I�ɂ́A��葽���̏�l�b�g���[�N��ʂ��ė����B��X���������̓I�ɑI�����Ȃ���A�܂��܂����ɗ�����A���ʂȏ���ɒǂ��A����j�邱�ƂɂȂ�B�����ɁA�Q�P���I�̋Z�p�́A�V���ȎЉ�W�̑n���ɂȂ���\�������B����̓l�b�g���[�N�Љ�̉\���ł���B�n��⍑�����Čl���A�т���Љ�A����܂ł̍��ƃV�X�e�����琶�܂������������A���Ēn��Љ�����Ă����A�шӎ���������\�������B�����̖��Ǝ��g�ނ��Ƃ��Q�P���I�̃e�[�}�ł���Ǝ��͍l����B
�y�Q�O�O�O�E��������z
�@�ۑ蕶�ň����Ă��錻��̋Z�p�v�V�ŁA�ł��d�v�Ȃ��̂͏��Z�p�̊v�V�ł���B�����P�ɂ���悤�ɁA�Z�p�v�V�͎Љ�V�X�e���S�̂�ω������邪�A���Z�p�̊v�V�͎Љ�S�̂��u�{�[�_�[���X�v�ɕω��������ƌ�����B
�@�o�ςɂ�����e���ōő�̂��͎̂����Q�̓d�q������ł��낤�B�l�b�g���[�N�ɂ��������Ŋ�ƋK�͂̑召�Ɋւ��Ȃ��s��ɎQ���ł��A�����������������������e�ՂɂȂ����B����́u�K�͂̃{�[�_�[���X�v�Ɓu�n���I�{�[�_�[���X�v�̎����ł���B���̌��ʁA�s��͕����ʂ�O���[�o�������A��ƁA�l���킸�A���E�o�ς�����ɓ��ꂽ�o�ϊ�������ʉ������B
�@�������A�{�[�_�[���X�Ȍo�ς͌l�⒆����ƂɍL�͂Ȍo�ϊ����̋@���^�������ʁA�����R�́u�����Њ�ƁE�����Ɗ�Ɓv�̌��͂�����ɂ����B�Ⴆ�A�}�C�N���\�t�g�̂悤�Ȋ�Ƃ̓l�b�g���[�N�E�V�X�e�����x����f�B�W�^���Z�p���x�z���邱�ƂŁA���i����E�s���E����ȂǁA������Љ�V�X�e���ɉe����^���邱�Ƃ��ł���B���̌��ʁA���Ƃ̃��[�_�[�V�b�v���h�炢�ł���̂ł���B����́A���Ƃ̂悤�Ȓ����W���I�V�X�e���ɔ�ׂāA�l�b�g���[�N�̕��U�V�X�e�����A����Љ�ł͂������I�ɋ@�\����Ƃ������Ƃł���B
�@�������A����͍��Ƃ��s�v���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�ނ���A�l�E��Ƃ����R�Ɋ������邽�߂ɂ́A���Ƃ̎x�����K�v�ł���B�����R�ň����Ă��鍑�ۓI�ȋ������[���̖��͂��̑�\�ł���B�O���[�o���Ȍo�ϊ������\�ɂ���͎̂��R�������A���ۓI�ȃ��[�����Ȃ���A���ۋ������e���̍����K���̍��ŕs�����ɂȂ�����A�t�Ƀ��[�������m�łȂ������������S�̂悤�ȕی�f�Վ�`�ւ̌X�����߂邱�Ƃɂ��Ȃ�B�����������[���͋����V�X�e���̕K�v�����Ӗ����邪�A���ꂩ��̍��Ƃ͋����V�X�e���Ƃ��Ă̖�����S���ׂ��ł���B����Ɠ����ɁA�����T�ɂ���u�匠�����l�v�̖������d���Ȃ�ƌ����悤�B���Ƃ������̂��߂̃V�X�e���ɂȂ�A�����ł͌l�̎����I�Ȏ��ȐӔC����苁�߂��邩��ł���B�܂�A���Ƃ��l�ɑ����Č���������V�X�e������A�l�����ƂƂ����x���V�X�e���𗘗p���Č���������V�X�e���ւ̕ω����K�v���Ǝ��͍l����B
�y�Q�O�O�P�E�@�w���z
�@���҂̎w�E����u���A���v�Ƃ͐l�ԂƊ��Ƃ̊ւ������琶�܂�銴�o�ł���B�Ⴆ�A������X�ɂƂ��đΗ�������̂ł���A���̒��Ő������т悤�Ƃ��鎞�ɒ�R��������A����́u����������v�ł���A�u���A���v�ݏo�����̂ł���B
�@�������A���̑�����̒�R�����傫�����Ċ��ւ̓������������̕ω������ݏo���Ȃ����A��X�́u���A���v�������邱�Ƃ͂Ȃ��B�Ⴆ�A�����̓����̃C�f�I���M�[�I�Η��́A���������ߑ�Ȓ�R���ł������B��킪�I���A�\�A�����邱�Ƃ�\���ł����҂͂��Ȃ������B�ۑ蕶�ɂ���u�x�������̕ǂ̕���v�������������������̂́A�u���A���Ȍ����v�����̒���ł��j��A��������������ꂽ����ł���B
�@�t�ɁA�����v���ʂ�ɕς��A��������̂����R�Œ�R�����Ȃ������A�u���A���Ȋ��o�v�͋H���ɂȂ�B�Ⴆ�A���@�[�`�����E���A���e�B�́u���l�T���v�̃r�f�I�Q�[���̂悤�ɁA�{���A�S�̓I�Ȋ��o�ł��鐶������������o���S�̊��o�ɕώ������A����̗~�]����̂��番�����ċǕ�������B�S�Ă��\�ɂ���S�\���̓��A���̑�p�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���̓_�ł͉Ȋw�������A���m�̉\���ւ̒����Y�ꂽ�C�f�I���M�[��@�������l�ł���B
�@�����ɑ��A���A���̍Ō�̋��菊�Ƃ��Ē��҂́u���v�������Ă���B�m���ɁA��X�́u���܂ꂽ���́v�ł���Ɠ����Ɂu�����ׂ����́v�ł���A���Ǝ��̗��҂����S�̂Ƃ��āu���A�����Ɂv�����Ă���Ƃ����������u���A���v�ł���B����ɉ����āA���l�Ƃ̊W�ł́u���Ȃ����݂��邾���łȂ��A���҂��܂��ʂ̎��ȂƂ��đ��݂���v�Ƃ����u���҂ɑ��鋤���v���u���A���v�ł��낤�B�������A��ËZ�p�̍��x���ɂ���Ď����������牓���Ȃ�A�C���^�[�l�b�g�ł́A���l�Ǝ����Ƃ̊W�����ׂăf�W�^��������A�t�@�C�����ꂽ���̏o�͂Ƃ��Ă����o�����꓾�Ȃ��B�����ł����A���͋H���ɂȂ��Ă���B
�@�u�����̐����̃��A���Ƃ̐G�ꍇ���v�́A�����炭�C�f�I���M�[�ł��@���ł��Ȃ��A�Ⴆ�Βn��̎s���^���E�{�����e�B�A�����Ȃǂ̑��l�Ȍo����ʂ��āA�����ƈَ��ȔN��̐l�X�A�����ƈَ��ȕ��������l�X�ƌ𗬂��ď��߂ĉ������̂ł��낤�B�������u�����ϊv�̉\���v�̂Ȃ����A���́A�ȒP�Ɍ����ǔF�ɑ�����B���̈Ӗ��ŁA���l�Ȍo���Ɠ����ɁA�V���Ȏv�z�ݏo���w�͂����A���̉ɕK�v���Ǝ��͍l����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c�W��
�E�o��̌X���c�e�[�}�I�ɂ͕p�o���̈�B���w���̂X�V�N�x�o��̗ޑ�ł���B���_��������Ă������Ȃ�A����ɂł��ł���B�r�e�b���_���[�~�̓~���P����T�ޑ�B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����E�Q�O�O�P�z
�i�P�j
�@�Q�P���I�̃r�W�l�X���Ƃ��āA���́u���o�C���E�^�E���v�T�[�r�X���Ă������B����͌g�ѓd�b�����f�B�A�c�[���Ƃ��āA�X������l�X�Ɏ��Ӓn��̏��������̂ł���B��̓I�ɂ́A�f�o�r���邢�͂o�g�r�̈ʒu���T�[�r�X�ƌg�ѓd�b��g�ݍ��킹�A�X������ƌ��݈ʒu�̎��͂̓X�̏��A�n�}���A��ʏ��Ȃǂ��[���ɕ\�������B���X�g�����Ȃ烁�j���[�A�a�@�Ȃ�f�ÉȂ�f�@���ԁA���X�Ȃ�o�[�Q�����A���̑��n�}�⎞���\�Ȃǂ������P�ɂ���S�Ă̌`�̃R���e���c�ŗ�����B��������Q�A�S�ɂ���悤�ɁA�g�ѓd�b�E�Ɠd���i�̋@�\�i���ɔ����āA�ƒ���ł������̏������R�ɗ��p���邱�Ƃ��ł���B
�@���̃T�[�r�X�͂Q�P���I�̎Љ��ς���͂������Ă���B����Љ�ł͌l���Ǘ����A����ŎЉ����������A�Ǘ����O�ꂵ�ăR�~���j�e�B�̊����������Ă���B�N�����s�s�̒��ł́u�悻�ҁv�ɂȂ��Ă��܂��̂��B�������A���o�C���E�^�E���̃T�[�r�X�ɂ���ĊX�Ɂu�悻�ҁv�͂��Ȃ��Ȃ�B�X������S�Ă̐l�����̊X�́u���ʁv�ł���A�Â�����̏Z�l�̂悤�ɃR�~���j�e�B�̈���ɂȂ��̂ł���B���҂̑��ɂƂ��Ă��A�ʂ̐�`�R�X�g�ɔ�ׂĊ����ŁA�n������u���v����郁���b�g������B
�@�u���v�͒P�Ȃ�f�W�^���R���e���c�ɂ���Ăł���̂ł͂Ȃ��B���ۂɊX������A�����ŏo��l�X�ȏo�������o�����āu���v�����܂��̂ł���B�܂�A�u���v�͎����R�̃G�N�X�y���G���X�ł���B�G�N�X�y���G���X�͏o��ɂ���čL������̂ł��邩��A���o�C���E�^�E���̃T�[�r�X�͏o��̋@��𑝂₵�A�o��̃��x����[�߂�ƌ�����B����͎����T�̎����Q�P���I�^�̃R�~���j�e�B�n���̗͂����B���̃T�[�r�X�ɂ���āu���m��ʊX���A�����̊X�ɂȂ�v�̂ł���B
�i�Q�j
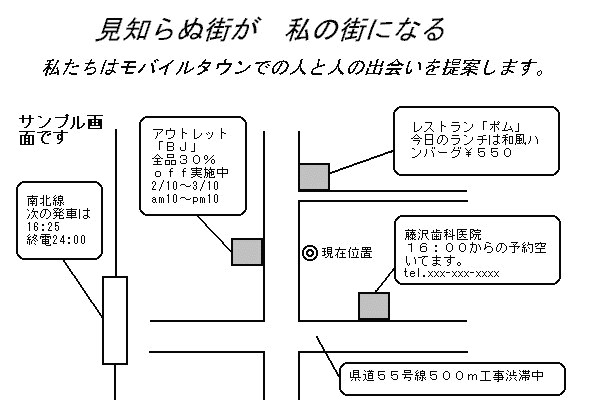
�E��Փx�c����
�E�o��̌X���c�e�[�}�I�ɂ͕p�o���̈�B�������A�����e���i���A��含���������B�C���^�[�l�b�g�₉���[�h�̃R���e���c�T�[�r�X�𗘗p���Ă��邩�ǂ����ŗ���x���傫���ς�邾�낤�B�L���f�U�C���̐}���͐V�X���B�r�e�b���_���[�~�̓~���Q����R�ޑ�B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�O�Q�z
�@���͒��҂́u��邵�����́v�ɑΒu����錾�t�Ƃ��āu�n���������́v��I�ԁB�ۑ蕶�ł́u��邵�����́v���u�u�Ă���́v�Ƃ��đ������Ă���B����͕����I�ȗ�ł͐�݂œy�̓y��Ɛ�̐����u�Ă�R���N���[�g�̌�݂ł���A�̂Ŏ��R�Ɛl�Ԃ̐G�ꍇ�����u�Ă锒������̕֊�ł���B����ɁA�u��邵�����́v�͐l�ԊW�ɂ����Ắu��t�̑����v�u�m��Ȃ��ӂ�v�Ƃ��ďq�ׂ��Ă���B����͕K�v�ɉ����Đl�ԂƐl�Ԃ�藣�������������Ă���̂ł���B
�@����䂦�ɁA�u�u�Ă���́v�ɑΒu����錾�t�́u�n���������́v�ł���B���R���ɂ����ẮA�R���N���[�g�Ōł߂Ă��Ȃ��y�ɂ͐������݂��݁A�^����h���A�A������Ă�B�y�͐��Ɛ����̔}�������u�n���������́v�ł���B�̂ł͖̑f�ނ�|���o���������R�Ɛl�Ԃ̊ԂɁu����v��u�v���v��n�������āA�����Ɂu����v��u�A�ȁv�ݏo���B�l�ԊW�ɂ��Ă��A����ւ̎v�����u�n�������v���Ƃ���u�l��v��u�v�����v�����܂��B���̂悤�Ɂu�n���������́v�́u��邵�����́v�ɑΗ�����B
�@�M�҂́u��邵�����́v��ے肵�Ă���̂��낤���B�����ł͂Ȃ����낤�B�ނ͌���̎Љ�ŁA�������g���u��邵���v���X�`�b�N�v�̂悤�ȁu�u�Ă���́v�Ɗ����Ă��邩�炾�B����́A�M�҂����f�B�A�Ŕ�������Ƃ������Ă���u�����d�b�v�u�����点�d�b�v�Ɓu�l�ԊW�̐e�����v�̋����������ݏo���S��Ȃ̂��ƍl������B�����ɂ́u���v�Ɓu���ҁv�Ƃ̊W�̕ώ�������Ă���B
�@�u�킽�������v�Ƃ́A����Ӗ��Łu�킽�����n���v�ł���B���͑��҂Ɓu���t�v��n����������u����v��n���������肷�邱�ƂŊW����茋�ԁB���ɂ́u�\�́v�����u�n�������v�Ɏg����B�������A�d�b��ʂ��Ĉ���I�ɑ�����u�V�C�\��v�̂悤�Ȍ����点�̃��b�Z�[�W�́u�n�������v�����ۂ��錾�t�ł���B��������̕֊��^�C���Ɉ�a�����犴���Ȃ��Ȃ�������̓��{�l�́A���R�⑼�҂ɑ��Ă��u��邵���v�\�ʂ�v�����Ă���B�������A���̈���ő��҂̈ӌ��d���邽�߂́u�m��Ȃ��ӂ�v�͂܂��O�ꂵ�Ă��Ȃ��B�M�҂́u��邵�����́v�̌��������Ɂu�n�������v�̗��z�����Ă���̂��Ǝ��͍l����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c���ۓI�Ȗ��Ƃ����Ӗ��ł́u����v�B
�E�o��̌X���c�������N���̌X���ł���u����Љ�_�v�̕����ɑ������蕶�ł���B�����T�m���_���I�Ȗ���N�������Ƃł��邱�Ƃ�m��Ȃ��ƁA�����q�ׂ����̂��S���킩��Ȃ������m��Ȃ��B�������A��������Ή����T�m�̕��͂ɂ͂ǂ����ŐG���͂��B�u���Љ�_�v�u����Љ�̐l�ԊW�v�Ȃǂ̃e�[�}���̂͏��_���ɕp�o�ł��邩��A�U���łȂ����_������������肵�Ă������Ȃ�ł���B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����E�Q�O�O�Q�z
�i�P�j
�@�O�̎������猾���邱�Ƃ́A���j�I�ɓ����l�Ԋ����̏ے��ł������Ƃ������Ƃł���B�o�x���̓��́u�ɉh�v�́A�A�����J�̖��V�O�́u���R�Ƌ����v�́A�����ăt���[�̃^���[�́u�l�b�g���[�N�v�̃V���{���ł���B����炪�ے�����l�Ԋ����́A�l�Ԃ����R�����߂��A�������A�x�z���悤�Ƃ������j�������Ă���B�Ƃ�킯�ߑ�ȍ~�A�����ł́u���ߖ@�v�Ɓu�͊w�v�����܂�A���E���ώ��ȍ��W�n�̒��ɕ����߂�Ȋw�Z�p�����W�����B
�@�����Q�́u�s�s���v�悷��O���b�h�v�͂����������W�n�̈�ł���B�����ł͋ώ����ƑΗ�����_�@�Ƃ��āu�����������v�𑨂��Ă��邪�A���W�n����l����A���ʂ����Ă����l�Ԃ��O�����ɍ��W���g���������ʂƂ��Ė��V�O�����܂ꂽ�ƌ�����B���V�O��������Nj����������̗��R�͌�����`�ł���B�s�s�����ʓI�ɍL���炸�ɐ��������L�т�̂́A�l�E���{�E���������ɋɌ��܂ŏW��ł��邩��ł���B
�@�������A������`���Ɍ��܂ŒNj�����A�u����������Ȃ���Ԃ͖��ʂł���v�Ƃ��������ɂ���Ď��R���͔j��A�s�s��Ԃ͐����̑��l����r�������u���҂�������������p�Ёv�ɂȂ��Ă��܂��B����ɁA�x�Ə��̏W���ɂ���Đ��E�I�ɕn�x�̍����g�債�A���V�O�����W�����i���̓s�s�́u����̃o�x���̓��v�ɂȂ邾�낤�B���ہA2001�N�X���P�P���ɋN���������V�O�ւ̃e���́A��X�ɌÂ��`���Ƌ��P��z�N�������̂ł���B
�@�o�ϐ������R���g���[�����Ȃ���l�ނ������c�邽�߂ɂ́A�t���[�̌����u�F���D�n�����v�̒��ł̐��E�l�b�g���[�N���K�v�ł���B�������A����͋Ǐ��I�ȕx�̏ے��Ƃ��Ă̖��V�O�ł͂Ȃ��A�n���S�̂���̃h�[���Ƃ��ĕ����悤�Ȕ��z�ɂ���ĉ\�ł��낤�B�����ŕK�v�ɂȂ�̂́A��剻���ꂽ�Ɍ��I�ȋZ�p�ł͂Ȃ��A�m�̃l�b�g���[�N�ɂ�鑍���I�ȋZ�p�ł���Ǝ��͍l����B
�i�Q�j
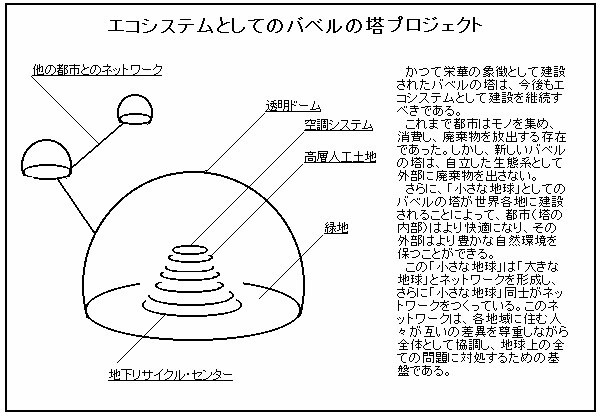

�E��Փx�c�W���I�B
�E���̌X���c����s�s�_�̊�{�I�Ȗ��ł���B�r�e�b�̑����̉ߋ���ƂȂ��肪����̂ŁA������Ă����Ό˘f�����Ƃ͂Ȃ��B�u�v���W�F�N�g�̒�āv�͍�N�ɑ����X���Ȃ̂ŁA���������͂Ȃ��������낤�B�i�r�e�b���_���[�~�̓�w���S��E�~���P���T��Ȃǂ��ޑ�B�Ċ��u�K�ȂǂŃt���[�̋Ɛт͏Љ�ς݁B�j
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�O�R�z
�@�u�l�v�̌���́uindividual�v�ł���B���̖{���̈Ӗ��́u�s���v�ł���A��������ȏ㕪���ł��Ȃ��Љ�̊�b�Ƃ��āu�l�v�͒�`�����B�������A���̌l���u�튯�̏W���v�Ƃ��Ă���ɐg�̓I�ɕ������A�������튯�́u���p�v�ɂ��Ă͑�O�҂����肷��̂��A�ۑ蕶�Ř_�����Ă���u��É����ꂽ�Љ�v�ł���B�u����������g�́v�Ƃ́A���̂悤�Ȉ�É����ꂽ�Љ�ɂ�����l�̕����E���ł�\���������t�ł���B
�@�C���@���E�C���b�`�́A���Č���́u�m���E�\�͂ɂ���Čl��������Љ�v���u�w�Z���Љ�v�ƌĂ�Ŕᔻ�����B���́u����������g�́v���w�Z���Љ�̋A���ɑ��Ȃ�Ȃ��ƍl����B��Ƃ��āu���v�ɂ��čl���悤�B�u�l�v�̑����ł���u���v�́u���Ƌ�ʂ���鐫���v����������u���l���v�̂��Ƃł���B�Ƃ��낪�A����̎Љ�Ōl�����ʁE�]�������̂́u���҂Ƃ̗l�X�ȈႢ�v�ɂ��̂ł͂Ȃ��A�w�͂Ȃǁu���ʂ̃X�P�[���v�Ŕ�ׂđ��҂��D��Ă��邩�ǂ����ɂ��B�܂�A�{���́u���v�́u�����̊�ɂ�鏘�v�ւƕώ����Ă���̂ł���B�w�Z���Љ�ł́u�������v�Ɓu���v��藣�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�������A�ߑ�I�Ȗ����`�̎Љ�ł́A���ʂɂȂ���u���v�͋�����Ȃ��B�����Łu���l�ɂ�鏘���ɂ��鋆�ɂ̌������v�����߂���B����̈ڐA�悪�u������ɒl����l�����ǂ����v�Ƃ͖��W�Ɍ��肳���̂́A���́u���ɂ̌������v�̈��ł���B�܂��A�����S���ɏZ���[�R�[�h�����āu�Z��l�b�g�v�ŊǗ�����̂��A���ꂪ�u����Ƃ��Ă̒P�Ȃ鐔���v�Ƃ������ɂ̌�������������ł���B���̂悤�ɁA�w�Z���Љ�̏��́u����̖��Ӗ����v�Ɍ������̂ł���B
�@�������A�u���ɂ̌������v�ɂ͗��Ƃ���������B�{���u�������v�͌l�ƌl�̍��ӂɂ���Đ��藧���̂ł���B�����I�ȍ��ӂ������������ӎu���x���Ă���̂ł���B�Ƃ��낪�A�u��O�҂ɂ��l�E���̖��Ӗ����v���{���̌������Ƃ���ւ��ƁA���������x����u���v�́A�g�̓I�ɂ��Љ�I�ɂ��s�v�ɂȂ�B�u���v�͑��݂��Ȃ��̂ł��邩��A�u�����g��������s�ׁv���u�����S�̔��Љ�I�s�ׁv���u�ے�I���l�v�������ċ������B�������āA�{���̌����������鋰��ɉ�X�͒��ʂ��Ă���Ǝ��͍l����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c���ۓI�Ȗ��Ƃ����Ӗ��ł́u����v�B
�E���̌X���c��N�ɑ����āu�����Ǝ��v�̕����ɑ������蕶�ł���B�ߋ���������������Ȃ�ɋ�J���Ȃ��ł��낤�B�������A����ڐA���ɂ�����肷����Ƙ_�|���B���ɂȂ�₷���̂Œ��ӂ��K�v���B���̉�́w���ꂩ��ł鏬�_���x�̉�����p�������́B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�O�R�z
���P
�@���̓t���[�G�[�W�F���g�����{�ł͍L�܂�Ȃ��ƍl����B����͓��{�Љ�̍\���Ɠ`���I�ȎЉ�ӎ��Ɍ���������B
�@�A�����J�̎Љ�́u�_��v�u���ȐӔC�v����b�ɒu���A���̌���Ōl�̎��R�d����Љ�ł���B�����炱���u��Ђ̂��߂Ȃ�ǂ�Ȃ��Ƃł�����v�̂ł͂Ȃ��A�u��ЂƎ����͂����܂Ō_��W�ɂ���A�_��ȊO�̎d��������K�v�͂Ȃ����A�_���ΐg���͎��R�ł���v�Ƃ������������\�ɂȂ�̂ł���B
�@����ɑ��āA���{�̊�Ƃɂ͉Ƒ��I�Ȍ����d����u�����Љ�v�̍\�����������c���Ă���A�Ј��͌o�c�҂̑�����u�Ŏ�����v��v�������B���ꂪ�u��Ђ𗣂��Ɛ����Ă����Ȃ��v�Ƃ����ӎ��ݏo���A��В��S��`���Đ��Y����邱�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ȑO��ɉ����āA������{�̘J�����ώ�������A�n���J���҂��s�v�ɂȂ������Ƃ��Ɨ��ւ̈ӗ~�����������Ă���B���Ɍ���̐N����̐E�ƑI���̓��@�́u�n������̒E�o�v��u�d���ɂ�鎩�Ȏ����v�ł͂Ȃ��A��Ƃ�����u�x�ɂ̑����v��u���������{�݂̏[���v�ł���B���������v������A���{�ł̓A�����J�̂悤�Ƀt���[�G�[�W�F���g�͍L�܂�Ȃ��Ǝ��͍l����B
���Q
�@���̓t���[�G�[�W�F���g�����{�ł͍L�܂�Ȃ��ƍl����B����́A�܂����ɐE�ƈӎ����u���Ȏ����^�v�ł͂Ȃ�����ł���B�u���Ȏ����^�v�Ƃ́A�����S�|�P�O�́u���R�v�̒�����I�ׂu�����̔\�͂��\����������v�u��肪����������v�Ȃǂł��邪�A�����͍ł��傫�ȓ]�E���R�ł͂Ȃ����A�ߔN���ʂ��������Ă���B����ɑ��āu��ЁE�ƊE�̏������s���v�u���^�Ȃǂ̑ҋ����悭�Ȃ��v�Ƃ����]�E���R���ł������A���Ɂu�����̕s���v�v���͑������Ă���B�����X���͎����S�|�R�ɂ�������B�����S�|�P�ōł��Ɨ��ӎ��̋����A�R�O��O���̒j���̓Ɨ��j�Q�v���̏�ʂ́u������v�Ɏ����Łu�����̕s����v�ł���B�����S�|�Q�ōł��Ɨ��ӎ��̋����Q�O�ォ��R�O��̏����ł��A�Ɨ��a�O�v���̏�ʂɁu�����̕s����v�Ɓu�x�݂̕s�K���v�������Ă���B����́u�d���̖ʔ����v�����{��Ƃɂ�����J���̗U���ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ̌���ł���B
�@���c�u�����L����Ȃ����̗��R�́u�Љ�I�o�b�N�A�b�v�̕s���v�ł���B�����S�|�R�ɂ��ƁA�j���Ƃ��R�S�Έȉ��ł́u�d����̐ӔC�������Ȃ��v�u�m�E�n�E�s���v�u������v���傫�ȑa�O�v���ł���B�u�m�E�n�E�s���v�͎d���̎������ω����Čl�́u���蕨�v�����ʉ��ł��Ȃ����ƁA�u�ӔC�E�����v�̖��͋�s�Ȃǂ����K�͊�ƂɗZ�������A�Z���̏��������������Ƃ������Ă���B�}�Q�A�����S�|�T�́A��������i�C�����̕ω��Ŏ��c�Ƃ������������Ƃ������A��������}�P�̂悤�ȋN�ƈӗ~�̌������o�Ă���̂ł���B
�@��������]���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�����S�|�V�A�S�|�X�ł͏����̓]�E�ӗ~���������A���������������͎̂Љ��Ղ̂h�s���ł��낤�B�}�R�Ŏ��c�Ƃ������Ă��鍑�́A�l�b�g��ŃE�F�u�T�C�g�������Ă��鍑�ł��邩�炾�B�܂�A�����ɂ��h�s�N�Ƃ̎x���Ȃǂɂ���ď��ς��\�������邪�A���{�̌���ł͂��������Ǝ��͍l����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c���ɓ���_�͂Ȃ��A�W���I�B
�E���̌X���c�������ԕύX�ɔ����ėl�X�ȉ��������������A����܂łƂ��܂�ς��Ȃ��������ł������B�i�������̕��Q�ɗގ����Ă���B�j�������p�ɉ���������̂ŁA�����Ԃ̊W���悭�l����K�v������B�����Ȃ����������Ԃ͂��������S�̂̍\�z�Ɏg���ׂ��ł��낤�B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�O�S�z
�@���҂͌o�ςƏ��̃O���[�o�����ɂ���āu���Ƃ̗��O�̑��Ή��v���N�������ŁA�����̍��ƓI�����ɂ��Η��������Ȃ�ƍl���Ă���B���̌������l���Ă݂悤�B
�@���㍑�Ƃ̐��i�́A���z�I�ȋ������Ƃ��Ắu�����v���猻���I�ȁu���l���v�ւƕω������ƌ�����B�����̖ʂł́A�������Ƃ��獑�Ƃ������������������̏�ɁA���A���ʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B�������A���l���̑��ʂł́A���\�A�n����O���E�ɂ����鎩���^���̍��g�����E���u����v�Ɍ����킹�Ă���̂ł���B�����A�V���Ɏ�����ڎw������n��̑�������i���ɉ�����v�����Ă���悤�ɁA�����Ɠ����ɃO���[�o���ȋ��͂����߂���p���h�N�X���A����̐��E���G�ɂ��Ă���̂ł���B
�@���̃p���h�N�X�́A�L�`�̃O���[�o�����ɗR������B�����ł̓��m�����ł͂Ȃ��A���Z�A�T�[�r�X�A�J���͂Ƃ��Ă̐l�ԁA��A�������z���đ�ʂɈړ�����悤�ɂȂ��Ă���B���č��Ƃ̎x�z���ɂ������e���o�ς͐��E�o�ς̈ꕔ�ɑg�ݍ��܂�A�s��o�ςƓ����ɂ�����x���閯���`�̃V�X�e�����������z���ė��ꍞ�ށB���ꂪ���剻�Ǝ����^���̍��g�������炵���ƌ�����B�n��I�ȑ��l���ƌo�ς̃O���[�o�������A���Ƃ̎匠�œ����ɐ��䂷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��������A�ٕ����Ԃ̖��C�Ǝ��R���̍������z�����j�����N�������B�Ⴆ�A���q���ɂ��C���N�x���Ȃǂ́u�������������v�͓r�㍑�̖��͉��̌��ʂł���A�M�щJ�т̌����Ȃǂ͐�i���̖��͉��ɂ����̂ƍl������B
�@�����ŁA���͂��ꂩ��̐��E���Ƃ��āu���Ƃ��Ă̐��E�v���l�������B�u���R���v�����E�Ɛl�Ԃ̊Ԃ̌����ߒ��������u�S�́v�ł���悤�ɁA���Ƃ̂Ȃ���ł��鐢�E���u�L�@�I�v�ȁA���Ȃ킿�u�������Ɨ����Ȃ���A�����ɑS�̂̓��������Ȃ��v�����͂����������݂ł���ׂ����B�������A���Ƃ́u�K�v�ł��邪�s���R�v�ȋt���I���݂ł��邩��A���́u�����́v��S���̂͂m�f�n�E�m�o�n�̃l�b�g���[�N�ł���B�l�b�g���[�N�𒆐S�ɂ����V�X�e���́A�����ȒP�ʂ̖��Ƒ傫�ȒP�ʂ̖����Ɉ������Ƃ��ł���B�Ⴆ�A�����n��̖��O�x����n���K�͂̊��j��ɓ����Ɏ��g�߂�̂ł���B���̂悤�ɁA���l�Ȑ�����������X�̐l�ԂƁu���Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂�������E�v�̎��R�Ȍ𗬂��V�������E���ł���Ǝ��͍l����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c�W���I
�E���̌X���c��N�܂ł̂�⒊�ۓI�ȁu�����Ǝ��v�̏o�肩��A��̓I�ȁu�O���[�o�����v�̖��ɓ��e���ω������B���ɂƂ��Ă͉��₷���Ȃ����ƌ����邾�낤�B�X�S�N�x��������w���̏o��w���ꂩ��̍��Ƒ��x�ɑ�ς悭�������ł���B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�O�S�z
�y��P-�P�z
�@���Ɏ����͈̂Í��̖��ł���B�u�P�E�P�P�E�Q�E�P�P�E�V�v�Ƃ��������̗�́u�A�J�C�J�I�v�Ɠǂ߂�Ƃ����B�ł́u�R�E�T�E�P�R�v�͂ǂ��ǂ߂悢���B
�y��P-�Q�z
�@�Í��Ɏg���Ă��鐔�����S�đf���ł��邱�Ƃɒ��ڂ���A�f���̗�u�P�E�Q�E�R�E�T�E�V�E�P�P�E�P�R�c�v���u�A�C�E�G�I�J�L�c�v�ƈ�Έ�ɑΉ����Ă��邱�Ƃ��킩��B�]���ĉ́u�E�G�L�v�ƂȂ�B
�y��Q�z�i�}�͗��j
�@�`�a�b�c�d�e�̂U�l������B���̗F�l�W�ɂ��Ă킩���Ă��邱�Ƃ͎��̒ʂ�ł���B�u�`����͂a����A�c����A�d����ƗF�B�ł���B�v�u�a����͂`����A�d����A�e����ƗF�B�ł���B�v�u�b����͂c����ƗF�B�ł���B�v����ɁA�u�F�B�̗F�B�͗F�B�ł���B�v�Ƃ������[�������悤�B�Ⴆ�A�u�`����Ƃa���F�B�ł���B�v�Ɓu�a����Ƃb���F�B�ł���B�v���������Ƃ���ƁA�u�`����Ƃb���F�B�ł���B�v���������B�������A�u�F�B�̗F�B�̗F�B�v�͂��͂�F�B�ł͂Ȃ��B�ȏ�̏�������l���āA��̂U�l�̒��Łu�S�l�ȏ�F�B�̂���l�v��S�ċ����Ȃ����B
�y��R-�P�z
�@�l�̕��͂ł͌o���I�E�q�ϓI�ȁu�f�[�^�̒~�ρv�Ɓu�V�������_�̘g�g�݁v�����ݏo���u�V���������v���A�ꌩ�A�Η��I�Ɏ�����Ă���B�����������͑Η�����̂ł͂Ȃ��A�A���������ł���B���̊Ԃ��Ȃ��̂́u�ϑ��Z�p�̔��W�v�ł���B�Ⴆ�A�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�����܂��_�@�ɂȂ����̂́A�u�����x���ǂ̏������ł����ł���v���Ƃ�u�����̋O�������z�̎��͂����]���Ȃ��炸��Ă����v���Ƃ��ϑ����ꂽ���ʂł������B�܂�A�����x��f���O���̐����ȑ��肪�ł��Ȃ���A�V�����u���݁v�����܂�Ȃ������̂ł���B�����ɁA�V�����u���݁v�ݏo�����߂ɂ́u���ԁE��Ԃ��L�яk�݂���v�Ƃ����悤�ȁA�Â��l�������玩�R�ȁu�V�������z�v���K�v�ł���B��������A�Ȋw���_�́u�f�[�^�̒~�ρ����_�����V�����Z�p�ɂ��V�����f�[�^�̔������V�������z���V�������_�̘g�g�݂̒�ā��V�������݂ƃf�[�^�Ƃ̏ƍ����V�������_�v�Ƃ����o�߂Ŕ��W����ƌ�����B�u�V�����f�[�^�v�̔����͋Z�p�I���ł��邪�A�u�V�������z�v�͌l�̎�������R���ɂ��傫�����E�����B���ꂱ�����Ȋw�ɂ�����u�V�����l�����v�̑n�������x���Ă���Ǝ��͍l����B
�y��R-�Q�z
���_�E�l�����̋�̖��F�t���N�^���w
�@���͏��w���̍�����V���t�@���ŁA���w������͎���̖]�����Ō��̃N���[�^�[�߁A�������Ɋ��������肵�Ă����B���Z�ł͓V�����̕��������߁A�{�i�I�ɓV�̊ϑ�������悤�ɂȂ����B�������A�u�F���v�Ƃ� �A�m��Βm��قǂ��݂ǂ���̂Ȃ��Ȃ�Ώۂł�����B�V�̂͂��܂�ɉ����A���܂�ɋ���ŁA�l�Ԃ������@���ő�������p�́A���̏����Ȉꕔ���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B���������āA�����u�P�Ȃ镨���I�f�[�^�v�̑��́A�q������Ɠ������u�V�̂̔������v���ӏ܂��邵���Ȃ������̂ł���B�Ƃ��낪�A�P�X�W�O�N��Ȍ�ɂ߂��܂������W�����u�t���N�^���w�v�̓��发��ǂ݁A���̎��R�ɑ��錩���͑傫���ς�����B�u�t���N�^���v�Ƃ́u�����̒��ɑS�̂Ƒ����ȍ\�����J��Ԃ�������Ă���}�`�v�ł���B�Ƃ�킯�A�t���N�^���w�̌��ݎ҂ł���}���f���u�������������u�}���f���u���W���v�̍ו����g�傷��ƁA�Q����͂̂悤�Ȑ}�`�������Ɍ����Ă���B���̑��l���́A�ǂ̂悤�ȋ�͂�_�̌`�ł����̒����猩������ɈႢ�Ȃ��Ǝv���قǂł���B���܂Łu���R�̐_��v�Ƃ����v���Ȃ������V�̂̕��G�ȑ��`�ɂ́A�����ׂ����Ƃɐ��w�ŊȌ��ɋL�q�ł���@�����������̂ł���B�������A�t���N�^���w�͓V�̂̌�����ς��Ă��ꂽ�����ł͂Ȃ������B�p�\�R���Ńt���N�^���`����\�t�g�E�F�A�𑀍삵�Ă���ƁA�f�B�X�v���[�ɐA���E�������E���̑g�D�E���i�Ȃǂɍ�������������u���R�v��������B���ɂ͎��R�S�̂��u�t���N�^���\���v�Ɍ����Ă����̂ł���B���̂悤�Ȍ���������ƁA�u�����I�Ȑ��E�̊e�X�ɐ��E�S�̂��f���Ă���v�Ƃ��������̙�䶗��̍l�������u�t���N�^���v�ŗ����ł���B�t���N�^���ݏo�����w���̂͂P�X���I�ɒm���Ă������A�R���s���[�^�̐��\�����サ�ď��߂āA���G�ȃt���N�^���}�`���������ꂽ�̂ł���B�Z�p�Ɨ��_���s���ł��邱�Ƃ����ɂ��悭�킩�����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c�n������������Ȃ̂Œ����ł͂Ȃ����A�������ԂƖ��̗ʂ��l����Ɠ�x�������B
�E���̌X���c�u��蔭���E�����^�v�̐l�ނ���Ă�A�Ƃ����r�e�b�̗��O�Ɋ�Â������j�[�N�ȏo��ł���B���N�̖��ł͓��Ɂu��������v�Ƃ����e�[�}�������ł��o����Ă���B������`���I�Ȏ��őΉ��ł�����ł͂Ȃ��B��[�~�̂r�e�b�[�~�ł́u�t���N�^���v�u�J�I�X�v�̏Љ��n�����̖����u�`���Ă���̂ŁA���͂ȑ�ɂȂ�B�w�_���w�̂��Ƃ��ʔ����قǂ킩��{�x����P�A�Q�̎Q�l�ɂȂ邾�낤�B�X�T�N�x�����w���̏o��u���G���Ɩ������̕����v���ޑ�B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�O�T�z
�@���҂́u���ʑP�v�̎��������Ƃ̊�{�I�Ȏg���ƍl���A���͎҂�ꕔ�̏W�c���������v��悤�Ȑ������u�\���v�ƒ�`���Ă���B�������A�����������͂̂�����́A������ˑR���ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�܂��A���炩�ȁu�\�́v�ɂ���č����ɋ������ꂽ���̂ł��Ȃ��B��X�����ʂ��Ă�����́A�ۑ蕶�ɂ���i�`�X�����̖\���Ɠ��l�A���z�I�Ȗ����`���f�������@�����A���̐����V�X�e�����琶�܂ꂽ�̂ł���B�܂�A���͂ɂ��\���ݏo���̂́A�����`�����Ă��鑼�Ȃ�ʍ������g�Ȃ̂ł���B
�@�Ȃ��A���̂悤�ȋt��������������̂��낤���B�{���A�����`�Ƃ���Ɋ�Â����R�Ȍo�ϊ����͐�����L���ɂ�����̂ł���B�����āA�����S�Ă̖L�����́u���ʑP�v�̈ꕔ�ł���͂����B�����A�L���������������A���̍����𑽂��̐l���ӎ����Ȃ��Ȃ�ƁA��̖ʂŁu����̋����v���i�s���A���͂ɑ��Ė����o�ɂȂ�B
�@��́u���ԓI����̋����v�ł���B����͉ۑ蕶�ɂ�����u�ߋ���Y��A���݂��ߋ�����藣���v�������ɂȂ���B�l�X�͑����̌R�������̉��\�△���ʃe������邪�A����͉ߋ��̓��{�l�̎p�A�ߋ��̐푈�̎����ł�����B�����ɑł��̂߂���A��x�Ɠ������s���J��Ԃ������Ȃ��Ɗ��������ォ��킸���ꐢ����o�������ŁA���ɂ��������ߎS�ȉߋ��́u�����Ȃ��Ȃ��Ă���v�̂ł���B
�@������́u����̋����v�́u��ԓI����̋����v�ł���B����͐g�߂ɑ����́u�n�����l�v�u�}�����ꂽ�l�v������ɂ�������炸�A�C�Â��Ȃ����Ƃł���B�����A�u�g�߁v�Ƃ͓��{�l�����̂��Ƃł͂Ȃ��A���{�ɏZ�ފO���l�A�O���[�o���o�ς̒��Ő�i���̉e������r�㍑�̐l�X���܂܂��B�s��o�ςɂ�����L�����Ƃ͕x�̕�ł���A���͖L���Ȑl�X�قǕn�����l�X�Ɏx�����Ă���̂ł��邪�A�u�����g�v�ɂȂ邱�Ƃ��錻��̓��{�l�ɂƂ��āA���̍\���́u�m���ɑ��݂��Ă���̂Ɍ����Ȃ��v���̂Ȃ̂ł���B
�@�ȏ�̍l�@����A�����̎�ŋ��ʑP��j�錠�͂ݏo���Ȃ����߂ɂ́A�����ɋ����Ȃ낤�Ƃ��鎩���̎�����A��ɍL���ۂw�͂��K�v�ł���ƌ�����B����͎����̐����������ԓI�E��ԓI�ɑ��Ή����Č������A���҂ɔz������u�����v�̑P�����߂�w�͂ł���Ǝ��͍l����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c�W���I
�E���̌X���c�@��N�́u�O���[�o�����v�̖�肩��A�Ăш��N�܂ł́u�����Ǝ��v�Ɋւ���e�[�}�ɓ��e���߂�����������B�������A��莩�̂͂悭�o��e�[�}�Ȃ̂ŏ����₷���B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�O�T�z
�y���P�z
����P
�N���[�j���O���ꂽ�ߗނ������Ă���傫�ȓ����r�j�[���܂́A�q�ǂ��ɂƂ��āu�����ۂ肩�Ԃ�v���Ƃ��A�t�H�[�h���Ă���B�����ȑ܂ł���Β��ɓ��낤�Ǝv��Ȃ����A�傫�ȑ܂͒��ɓ����ėV�Ԃ��Ƃ�U���̂ł���B�������̂�h�����߁A�܂ɂ́u���q�l�����Ԃ�Ȃ��悤�ɂ��ĉ������B�v�ƒ��ӏ��������邪�A�q�ǂ��͂���𗝉����Ȃ��B�����������̂�h�����߂ɂ́A�r�j�[���̑܂ɑ傫�ȃX���b�g���邩�A���邢�͑܂ɖڂ̑e�����b�V���f�ނ��g���A�u���Ԃ�v���Ƃ̃A�t�H�[�_���X���������A���ꂩ�Ԃ����ꍇ�����S�ł���B
����Q
�r�f�I�Ȃǂ`�u�@��̓��o�͒[�q�͓��͑����o�͑��������`������Ă���̂ŁA�Ȃ��ԈႢ���N���₷���B�ǂ���ɂ��A�����`�E�傫���̃v���O�ƃ\�P�b�g���g���Ă��āA�A�t�H�[�_���X���s�[���Ȃ̂������ł���B�Ⴆ�A�����̎��͓ˏo���Ă��邩��u�����o�Ă���v���Ƃ��킩��A�r���a�͌E��ł��邩��u�����z�����܂��v���Ƃ��킩��B���l�ɁA�u���́v�̃\�P�b�g�͌E�܂��A�u�o�́v�̃\�P�b�g�͓ˏo����f�U�C���ɂ���A�傫����`���ς��̂ŊԈႢ�����Ȃ��Ȃ�A�������[�q���̂��Ȃ������A�t�H�[�h���Ă����B
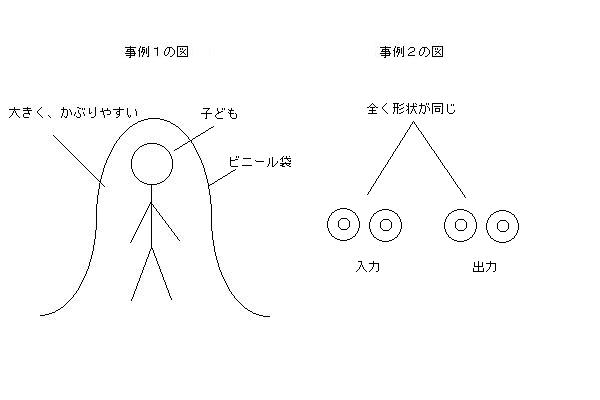
�@�q���[�}���C���^�t�F�[�X�����ɏd�v�ɂȂ錴���͓����B��́u�@�B��V�X�e���̕��G�x�����傷��v���Ƃł���A������́u���[�U�[�̓K���͂���������v���Ƃł���B���̌����́A�������̎��͂̐��i��V�X�e���Ɋւ��āA�u�f�W�^�����v�Ɓu�l�b�g���[�N���v���i���Ƃ��琶�������̂ł���B�d�b�̂悤�Ȗ��l�����̓�����ʃV�X�e�����f�W�^���������ƁA�N�����\�t�g�E�F�A�Ō��߂�ꂽ�菇�ɏ]���ăL�[�{�[�h��ł��Ȃ���Ȃ炸�A���̗��R��\�����킩��Ȃ��啔���̃��[�U�[�ɂ́A�@�B��V�X�e�����ɂ߂Ďg���ɂ������̂ɂȂ�B���̌����́A�l���\���̍�����Q�҂̎Љ�Q����i�߂邱�Ƃ��琶������̂ł���B����҂���Q�҂��A����҂̎��_�Őv���ꂽ���u��V�X�e������́u����ׂ̍����v��u��Ƃɋ����ꂽ�������ԁv�̂��߂ɑa�O����Ă��܂��B�����̂��Ƃ���A���q���[�}���C���^�t�F�[�X���d������Ă���̂ł���B
�y���Q-�Q�z
�@���͈�ÃV�X�e���̏��C���^�t�F�[�X�ɂ��čl�������B���݂̈�ÃV�X�e���ł́A�u���v�Ɋւ��ĂقƂ�ǂ̊��҂��s���������Ă���B��Â͍��x�����u�����������邪�A�����������̌��ʂ������Ă���̂��v�ɂ��Ċ��҂������ł��Ȃ��u�E�ϗ́v���K�v�Ȓi�K�ɂ���B����A����Љ�A���x��Âɂ���āA��Ẫr�W�l�X�K�͂͂܂��܂��傫���Ȃ��Ă���B���ꂪ�}�̃]�[���̈Ӗ��ł���B���݂̈�ÃV�X�e���ɂ́u�f�ÉȁA�a�@�Ԃ̘A�g���Ȃ��v�u���ÂɊւ������ґ��ɊJ������Ȃ��v�Ȃǂ̖�肪����B�����͎��̃J���e���e��t���Ɨ��ɊǗ����A��������w�����ł̂���Ă��邱�ƂɌ���������B���̖������������̎��݂́A���[�U�[�ɂƂ��Ďg���₷���f�W�^�����ƃl�b�g���[�N���ł���B�Ⴆ�A���҂��h�b�J�[�h���l�̐f�ÃJ�[�h�Ƃ��Ď��ĂA�f�ÁA����A�������ʁA�摜�̋L�^��S�ēd�q�J���e�ɓ���A���̓��e��f�ÃJ�[�h�ɏ������ނ��ƂőS�Ă̈�Ï]���҂Ɗ��Ҏ��g���������L�ł���B����ɁA�J�[�h���g���ƒ�̃p�\�R��������p����g��Ȃ���w�m���f�[�^�x�[�X�ɃA�N�Z�X���ł���B���ꂪ��ÂɕK�v�ȃC���^�t�F�[�X�ł���B
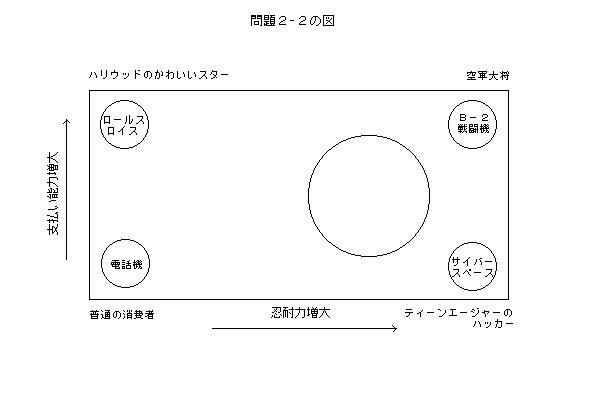
�E��Փx�c�ۑ�Ɋւ��闝�����ł���Ηe�ՂȖ��ł���B�������A�u�g���₷���v�Ȃǂɂ��Ă̖{���I�ȋc�_�ɐG�ꂽ���Ƃ��Ȃ��ƁA�ۑ蕶�̓ǂݍ��݂Ɏ��Ԃ������邩������Ȃ��B
�E���̌X���c��N���l�A�u��蔭���E�����^�v�̐l�ނ���Ă�A�Ƃ����r�e�b�̗��O�Ɋ�Â����o��ł���B�`���I�Ȏ��őΉ��ł�����ł͂Ȃ����A�X�R�N�x�����w���̏o��u�v�҂��z�����ׂ����Ƃ���͉����v�i�Ó�L�����p�X�̂r�e�b�C���e���V�u�E�R�[�X�Ŏg�p�j�Əo�T���d�Ȃ�o��ł���A�ߋ��⌤�������ɗL���ł���B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�O�U�z
��@�M�҂́u�b���v���Ƃ��u���傤���ɖ₤�v���Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��Əq�ׂĂ���B�u�₤�v���Ƃ́u�������ł��邩��������v�Ƃ������Ƃł���A�w��̊�b�ƂȂ�\�͂ł���B�܂��u�₤�v���Ƃ́u�����ɂƂ��Ă̖��͉����v���܂��������邱�Ƃł���A���Ȋm�F�Ƃ����Ӗ������B���̈Ӗ��ŋ���͖₢�����ނ̏�ł���A���̖ړI�͏�����̓I�ɑI�сA����`���ɖ𗧂Ă邱�Ƃł���ƌ�����B���̂悤�ȕM�҂̌����W�����āA���́u�₤�v���Ƃ��u����̐��v�̊m���ɂȂ���ƍl����B������`����u����̐��v�Ƃ́A�u���̎��W�E�I���E�����E���M�v����̓I�ɍs���\�͂ł���B���ꂩ��̎���A�l�b�g����̓I�ɗ��p���đ��҂ƌ𗬂���ɂ͂��̔\�͂��s���ł���B
��@�����d������_�́u���������|�C���g��_���I�ɍi�邱�Ɓv�Ɓu����̗���ɗ����Ɓv�ł���B�܂��u���������|�C���g��_���I�ɍi��v�̂́A���⑊�݂̊W��\�ߌ������A�d��������e������邽�߂ł���B����͑���̎��ԓI���S���ŏ��ɂ��邱�Ƃɂ��𗧂B���Ɂu����̗���ɗ����Ɓv�ɂ͓�̈Ӗ�������B���̈Ӗ��́u����̕����I�w�i���l�����ĕ����v���Ƃł���B�Ȃ��Ȃ�A�N�ɂ����������������������A���̈Ⴂ�ɂ���ē���������ʂ̉��߂�����邱�Ƃ����邩�炾�B���̈Ӗ��́u�����P�Ȃ���҂Ƃ��Č���̂ł͂Ȃ��A���ɐ����铯����l�Ƃ��đ��d����v���Ƃł���B������ނ��鑤��������������A����҂͐M�p���ꂸ�A�������͂ł��Ȃ�����ł���B
�O�@���́u�����ӎ��̐���Ԕ�r�v�ɂ��Ē����������B�Ώۂ͂Q�O�ォ��U�O��̐l�����ł���B����́u�����`�Ȃ�`���܂����B�v�Ƃ����`���̖₢������ނ��p�ӂ���B�Ⴆ�A�Q�O��E�R�O��̎Ⴂ����ɂ́u�������Ȃ��̋��������N�\�p�[�Z���g���オ��Ȃ�A�������A�q�������������ł����B�v�Ƃ������������B�t�ɂT�O��E�U�O��̐l�����ɂ́u�������Ȃ����R�O�ŋ��������ꂩ��Q�O�N�ԕς��Ȃ��Ȃ�A�������A�q�������������ł����B�v�Ǝ��₵�A����Ԃł̈ӎ��̍����r����B�����̗�͏��q���̌����ɂ��āu�Ȃ��q�ǂ����~�����Ȃ��̂ł����v�Ƒ���Ɏ��₷������ʓI�ł���B�Ȃ��Ȃ�l�X�͑��̐���̎���w�i��z�����A�����̖��Ƃ��ē����o������ł���B�����́u���҂�m�邱�ƂŎ����ɋC�Â��₢�v�ƌ����Ă��悢���낤�B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c�W���I
�E���̌X���c�V�X���̏o��`���ł��邪�A�����ׂ��O�̓��e�����m�Ȃ̂œ���͂Ȃ��B���́u�ǂݎ��A�܂Ƃ߂�́v�u���z�́v�u�\���́v��f���ɖ₤���ł���B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�O�U�z
��P
�����ʂɎg�����x����X�тƂ������R���{��j�Ă�����
��Q
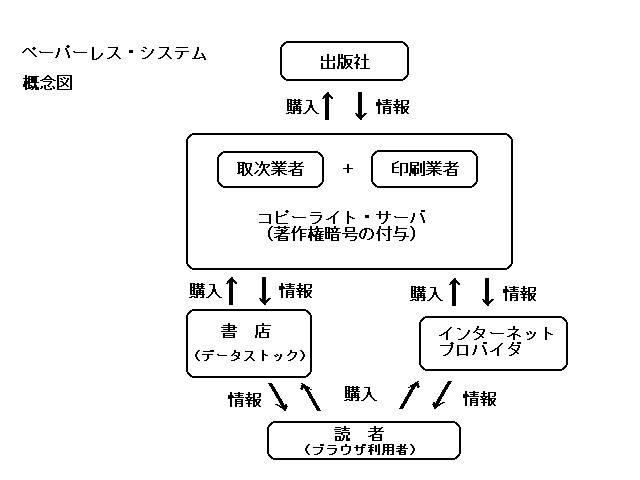
�@�����u�����v�����̂́u�y�[�p�[���X�E�V�X�e���v�̑����T�[�r�X�ł���B���̃V�X�e���̓l�b�g���[�N����ƃn�[�h�E�F�A���傩�琬��A�l�b�g���[�N����ł́u�R�s�[���C�g�E�T�[�o�v�̐V�݂ɂ��A�f�W�^�����̒��쌠�Ǘ��E�ی�Ǝg�p������������A�n�[�h�E�F�A����ł͎��}�̂ɑ���u���E�U�����B�����̐V�����Z�p�ƃl�b�g���[�N�ɂ���Ď��̎g�p�ʂ����I�Ɍ��炵�A�X�ю�����ی삷�邱�Ƃ��ł���B
��S
�@���̓y�[�p�[���X�E�V�X�e���̑����T�[�r�X���Ă������B�ȒP�Ɍ����u���̂���Ȃ��o�Łv�y������Ƃ������Ƃł���B���A������̓f�W�^���ҏW���Ă���̂ɁA�킴�킴���ŏo�ł���B���̌��ʁA����������V���̂��߂ɐX�ю����͘Q���Ă���B���̖����������邽�߂ɂ́A���̍Ďg�p�E�ߖ�Ƃ������z����E�p���āu���̕s�g�p�v��Nj����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������l�b�g���[�N�ɂ́u���쌠�ی�v�u���̒��ڔ̔��ɂ���đa�O�����Ǝ҂̕ی�v�u�ǎ҂ɂƂ��Ă̓ǂ݂₷���v�Ƃ����O�̕ǂ�����B
�@�u���쌠�ی�v�́A�{�Ɂu���쌠�Í��v�����邱�Ƃʼn����ł���B�Í������́A��ǃ`�b�v�����̋@�킾���Ń_�E�����[�h���ǂނ��Ƃ��ł���B��ǃ`�b�v�͈�@�R�s�[��h���@�\�����B���̋Z�p�͈���ƁE���ʋƁE���X�̕ی�ɂ��𗧂B��̓I�ɂ́A����Ǝ҂Ǝ掟�Ǝ҂����̂��āu�R�s�[���C�g�E�T�[�o�v�𗧂��グ��B����͒��쌠�Í���t�^����g�D�ł���B���X��v���o�C�_�̓R�s�[���C�g�E�T�[�o���璘�앨���w�����A�l�b�g��X���Ŕ̔�����B���̍ہA���X�͌l�ǎ҂ƌ_�A���앨�����X�̃f�[�^�E�R���s���[�^�ɃX�g�b�N���Ă����B�l�̂o�b�ƈႢ�A�O���̃f�[�^�x�[�X���g�����Ƃő�ʂ̏�����ۑ��ł���B���̏��X���u�l�̖{�I�v�ɂȂ�̂��B����ɂ���ď����ȋK�͂̏��X�������c���B�Ō�Ɂu�ǎ҂ɂƂ��Ă̓ǂ݂₷���v�Ƃ������́A�V�����@��̊J���ʼn����ł���B����܂ł̉t����ʂ͏����������B�����Łu�d�q�y�[�p�[�v�Ȃǂ̋Z�p�����p���u�����A�y���A�_��ŁA�a�T�ȏ�̑��ʁA�ȓd�́v�̒[�������K�v������B
�@���̃T�[�r�X�ɂ́u�R�X�g�����Ŗ{��V���������Ȃ�v�u���v�̏��Ȃ��{�ł��o�łł���v�Ȃǂ̃����b�g�ɉ����āA�u�G�R���W�[�o�ςɍv���ł���v�Ƃ����O���[�o���ȃ����b�g������B�Q�P���I�̃G�R�Ȓm�I�������x����ɂ́A���̃V�X�e�������Ȃ��̂ł���B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c�W���I
�E���̌X���c�ߋ��ɏo���u�f�W�^���R���e���c�̊��v�Ɨގ��������ł���B�ߋ��⌤�������Ă����Γ���Ȃ��B����̖��́u�f�W�^���R���e���c�v���u�G�R���W�J���ȃ��m��T�[�r�X�v�ɒu�����������́B���i�̐����̒��ŋC�Â��v�f�������A�f�W�^�����i���͏����₷���ł��낤�B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�O�V�z
�@�M�҂́u�@�v�u�����v�u���j�v�̊W�ɂ��āA���ې������a瀂��ɘ_���Ă���B���ې������a瀂Ƃ́A�푈��Q���������Ɖ��Q���̊ԂŁu���j�I�^���v���߂���Ӎ߂�ۏ�̖�肪�N���邱�Ƃł���B�������A�w��ł͈�����̗��j�I�^�����Nj������̂ɑ��āA�����ŒNj������ׂ����͓̂����҂ɂ���ĉ��߂��قȂ鐭���I���`�ł���B�����͖@�Ɛ��x�ɂ���čs���邪�A�@�����菊�Ƃ���^���́u�w��I�Ȑ^���v�Ƃ͈قȂ�u�@�I�Ȑ^���v�ł���B�䂦�ɁA�����I���`���@�I�Ȑ^���Ɋ�Â��B
�@�@�͌l�ƎЉ�̑Η����闘�v�₵�A���݂̍����I�ȋύt��}�邽�߂ɁA���̖ړI�ɕK�v�Ȕ͈͂Ő^����Nj�����B�@�I�Ȑ^���Ƃ͂��̂悤�Ɍ���I�Ȃ��̂ł���B����A�����I���`�̗��z�͎Љ�̒����ƈ��J���������邱�Ƃł��邩��A�����ł�����I�ȁu�@�I�^���v���Ӗ������B�@�̐��_�ɏ]���A�Ⴆ�Γ����ٔ��̎i�@����Ő��̌o�ϓI���W�Ƃ������v�����{�l�́A�푈�ӔC�Ƃ������̈�Y�������������ƌ�����B���̏�ŁA���{���܂߂����ې����̓����҂��ڎw���ׂ��́A���j�̐^����Nj����邱�Ƃł͂Ȃ��A�@�I�^���Ɋ�Â��������ғ��m�́u�a���v�ł���B�ȏオ�M�҂̈ӌ��ł���B
�@�ۑ蕶�ŕM�҂��q�ׂĂ���u�����I���`�v�u�@�I�Ȑ^���v�́A�Η����铖���҂����ӂ��邽�߂́u���ցv�ł���B�������A���ې������a瀂��������鎖�����߂��u���ցv�Ȃ�A�j�������x���O�ٔ��E�����ٔ��ɂ�����u�l���ɑ���߁v��u���E�l���錾�v�Ȃǂ��u���ցv�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����ł���A�����ɕ��ՓI�ȉ��l�͂Ȃ��A���㎄�������������ɂ������ďd������K�v���Ȃ����ƂɂȂ�B����͑Ó����낤���B
�@�M�҂̌��������I���`�́u�ߋ��Ɋւ��鍇�Ӂv�Ƃ��Ă̑��ʂ��������B����ɑ��Đl����l���́u�ϗ��I�^���Ƃ��Ă̐��`�v�ł���A�u���݁E�����Ɋւ��鍇�Ӂv�ɕK�v�ȕ��ՓI���l�ł���B�u�ϗ��I�^���v���@�I�^���ƈႤ�̂́A�@���u�N�����Ă��܂������ʁv�̕⏞�ł���̂ɑ��āA�ϗ��́u���N�����Ă���o�����v�u���ꂩ��N����ł��낤�o�����v�ւ̓��������ł���_�Ɋ�Â��B�u�ߋ��̘a���v�Ɠ����Ɂu���݁E�����̘a���v���\�ɂ��邽�߂ɁA�����̗������K�v���Ǝ��͍l����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c�W���I
�E���́u�ǂݎ��A�܂Ƃ߂�́v�u�_���I�\�z�́v��₤���ł���B�v��͓���Ȃ����A�ӌ����q�ׂ�u�肪����v�����݂ɂ��������m��Ȃ��B���发�Ȃǂ�ǂ�ŁA�@�ɂ͌�ʃ��[���Ȃǂ́u�������̉����v�Ɛl���N�Q�Ȃǁu�������̉����v�Ƃ�����̖��������邱�Ƃ�m���Ă����Ƃ悢�B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�O�V�z
�i�P�j
���ȑg�D���K���V�X�e����p�����S�̐��n���v���W�F�N�g
�i�Q�j
�������Ԃ͂R�N�B������z�͂R���~�B������\����͌o�ώY�ƏȁE�����ȁE�����Ȋw�ȁE�S����s����B
�i�R�j
�@����Љ�̖��ɋ��ʂ̗v�f�Ƃ��āu�S�̂ƕ����̖��v������B�Ⴆ�C���^�[�l�b�g�ɂ���L��ڎw���Ă��A�E�B���h�E�Y�ƃ}�b�N�n�r�̈Ⴂ�ɂ���ċ��ʂɃA�N�Z�X�ł��Ȃ��E�F�u�y�[�W���ł��Ă��܂��B�܂��A�ʐM�l�b�g���[�N�A��ʃl�b�g���[�N�Ȃǂɂ����āA�����I�ȏ�Q�������őS�̂̋@�\�����Ȃ���g���u���������B����ɁA������בփ��[�g�Ȃǂ̌o�ό��ۂ͕����I�ɕϓ��𑱂��Ȃ���S�̂Ƃ��Ă͈��肵�Ă���B�������A�����̕ϓ���\�����邱�Ƃ͓���B
�@�l�Ԃ������I�ȕϓ��ɋC�t���Ă��������悤�Ȋ����̖������V�X�e���ł́A�����̖��ɑΏ��ł��Ȃ��B�����Ŏ����I�ɃR���s���[�^�Ԃ̏��u�ʖ�v���s������A�V�X�e���̈ꕔ��������ꍇ�ɑS�̂��ω����Ď����I�Ɂu�V�����V�X�e���v���\�z�����悤�ȁu���ȑg�D���K���V�X�e���v���K�v�ɂȂ�B�o�ό��ۂɂ��Ă��A�o�ϑS�̂������ȑg�D�I�ȃp�^�[���ω���@�����ł���A�o�ϕϓ��ɂ�郊�X�N�������I�ɉ�����铊���V�X�e���Ȃǂ��\�ɂȂ�B�Љ�I�ȍ��ӃV�X�e�������̎��ȑg�D���K���V�X�e���ł���ƌ����邩��A���l�ȃ����o�[���ǂ̂悤�ɓ��ꂳ�ꂽ�Љ��g�D���Ă��邩���������邱�ƂŁA���݂́u�������V�X�e���v��u�����V�X�e���v�̌��������ł���B
�@������@�Ƃ��ẮA���w�E���v�w�E�R���s���[�^�Ȋw�E�F�m�Ȋw�E�����Ȋw�E�o�ϊw�E�Љ�w�̌����҂����R�Ɉӌ��������Ȃ��狤����������`�����̗p����B����܂Ŏ��ȑg�D�n�E���G�n�̌����͔]�Ȋw����Љ���܂ł̍L���͈͂ōs��ꂫ�����т�����A�u�S�̐��v�n���̌����ɂ������̕��쉡�f�I�Ȕ��z���s��������ł���B�������A���l�Ȑ��Ƃ������̌����@�ւ𗣂ꂸ�A����I�ɋ��������ł�����͂r�e�b�ɂ����Ȃ�����A���̂悤�Ȍ�����@���œK�ł���B�����o�[�͊w�����܂߂ĂR�O�����x�Ƃ���B
�@�����v��Ƃ��ĂP�N���ɂ͈قȂ����n�r�Ԃ̏�L�E�\�t�g�E�F�A���L�A�܂������̃f�[�^�x�[�X�Ԃ̈ړ����V�[�����X�ɂȂ�A��̃f�[�^�x�[�X�Ƃ��Ĉ�����Z�p�������e�[�}�Ƃ���B�Q�N���ɂ̓l�b�g���[�N�́u���ȏC���V�X�e���v����������B����������⎾�����ǂ̂悤�Ɏ��ȏC�����邩�����f�������āA�ʐM�E��ʁE�ЊQ�x���Ȃǂ́u���ȍđg�D���v�������e�[�}�Ƃ���B�R�N���ɂ͌o�ϕϓ���Љ�ۂ́u�S�̃p�^�[���v�𐔊w�I�ɕ\�����A�������烊�X�N����⍇�ӌ`���̐V���ȃV�X�e�����\�z���邱�Ƃ������e�[�}�Ƃ���B
�i�S�j
�@���́A���̃v���W�F�N�g�ɎQ������]����w���ɁA�ȖڂƂ��āu�����E���U�E�����v�u�������ƃA���S���Y���v�u�l�H�m�\�_�v�u�V�~�����[�V�����f�U�C���v�u��w�v�u���������Ȋw�v�u�����ƎЉ�v�Ȃǂ̗��C�����߂�B�܂��A�u�����E���U�E�����v�͎��ȑg�D����S�̓I�V�X�e���̊�b���_�ł���A�v���W�F�N�g�̔w�i�ƖړI�𗝉�����̂ɖ𗧂B�u�������ƃA���S���Y���v�u�l�H�m�\�_�v�́A�V�X�e���ɋN�������������A�������邽�߂́u�l�����̘g�g�݁v�������Ă����B�����́u�l�Ԃ̓��̒��g��m��v�w��ł���B�u�V�~�����[�V�����f�U�C���v�u��w�v�u���������Ȋw�v�u�����ƎЉ�v�Ȃǂ́A�Ȋw�����ɂƂ��ċ��ʂ̌���ł��鐔�w�ƃR���s���[�^�̒m����Ղ���Ă����B�������g�����Ȃ��ď��߂āA�f�[�^���������������₷���`�ŕ\�����邱�Ƃ��ł���̂ł���B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c�W���I
�E���̌X���c�X�X�N�x�ɏo���u�Q�P���I�̖��Ɖ����̎��_�v�ɗގ��������ł���B�ߋ��⌤�������Ă����Γ���Ȃ��B���ɂr�e�b�ł͂`�n�����Łu�u�]���R���v�u�w�K�v�揑�v���������Ă���A���̉�������̖��ł���B�`�n�Ŏ����o���̂���l�ɂ͗L���B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�O�W�z
�@���������ȍ~�A�m���E�v�z�̈Ӌ`���؎��Ɉӎ�����A�S����Ƃ��Ắu�m���l�v���d�������悤�ɂȂ����B����͎Љ�̐������ɂ����{�̍��ێЉ�ɂ�����n�ʂ̈��肪�ŏd�v�̉ۑ�ł���A�����`���̒m���Ƃ�������L���Ă���m���l�͓V�����Ƃ̃��x���ŗL�p�Ȃ��̂ł���������ł���B����䂦�A�����͒m���l���g�����Ȃ̎Љ�I�ȑ��݈Ӌ`�ɋ^���������Ƃ͂Ȃ������B�������A�����`���̒m���E�v�z�́A���{�Љ�̈�ʓI�Ȑl�X�̐���������ӎ�����V������ʂ��������B��������A�m���l�͑�O�ɒm���E�v�z��`�B����[�֓I�Ȗ������ʂ����ׂ����Ƃ��闧��ƁA�m���l�̗L����m���E�v�z�͑�O�̓���Ɗւ��Ȃ��䂦�ɁA���̈Ӌ`���H���ŞB�����Ƃ��闧�ꂪ�������B���ꂪ�m���l�ɓ��ʉ�����ėD�z���Ɠ����ɃR���v���b�N�X�̌����ƂȂ�A�m���E�v�z�̖]�܂���������A�m���l�Ƒ�O�Ƃ̊W��₤�m���l�_�̃e�[�}�����܂ꂽ�B�M�҂͂��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�ߑ���{�Ɂu�m���l�v��a���������̂́u����̊i���v�ł������B����������Đ��m�̌��t�ƒm����g�ɂ�����l�X�͂킸���ł���A�ނ�͕����ʂ�u�����K���v�ł�������M�҂��q�ׂ�ʂ�A�O���̒m���͓����̋ߑ㍑�ƌ��݂̍��i�ł���A�����E�o�ρE�����̂�����ʂŒm���l���D�����ꂽ�͓̂��R���ƌ�����B�܂��A��O�̑����A�m���l�̒����ʂ��ċߑ㍑�ƂɓK�����A���R�ƌ����̈ӎ�������̂��̂Ƃ����̂ł���B
�@�������A����̓��{�Љ�ł́A���Ēm���l�̒n�ʂ��x��������i�����k�����Ă���B��w��O���ɂ���đ呲�҂̓G���[�g�ł͂Ȃ��Ȃ�A��w�̖����͎�ɏA�E�̑I�ʋ@�\�ɂȂ����B�m���l�̓������������w�@����A�����ł͍L���J����Ă���B���̈Ӗ��ŁA������������s��܂ŎЉ�̒�����S�����u�m���l�v�͊��ɑ��݂��Ȃ��B���A���x�Ȓm�������L���Ă���l�X�͌���ꂽ����́u���Ɓv�ł����āA����u�Z�p�ҁv�̈��ł���B
�@���̕ω��������ŁA����̓��{�Љ�ł́u��Ɍ����Ȃ����l�v�̒n�ʂ��ቺ���Ă��܂����B�u�v�z�v����Ă����m���l�����Ȃ��Ȃ��āA�����̐l���u������e�[�}�v�������ŒT���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂ł���B���̂悤�ȉ��l�̑��l���Ƒ��Ή��́A�u�@��ϓ��v�̔��ʁu���������r���E���ߓI�������v�������ݏo���Ƃ�����肪����A�u����ɂ�����m���̂�����v��₤�V���Ȓm���_�E�m���l�_���K�v���Ǝ��͍l����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c�W���I
�E���́u�ǂݎ��A�܂Ƃ߂�́v�u�_���I�\�z�́v��₤���ł���B�v��͓���Ȃ��B�������A�ߑ���{�̌ÓT��ǂ�ł��Ȃ��ƁA����̕����������ȍ~�A�s��܂ł̏Ƃ����ɈႤ���������̖��Ƃ��čl���邱�Ƃ������������Ȃ��B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�O�W�z
���P�|�P
�P�y�v���O������[���y���ށz
�O�P�A�O�T�A�O�W�A�Q�R�A�Q�S�A�Q�T�A�R�O�A�R�P
�Q�y�l�Ɛl�̏o�����S�Ă��n�܂�z
�O�Q�A�O�X�A�P�O�A�P�X�A�R�S�A�S�T�A�S�V�A�T�O
�R�y�����Ƃ���������ǂށz
�O�S�A�P�P�A�P�Q�A�Q�P�A�Q�V�A�Q�W
�S�y���ł��E�ǂ��ł��E���ł��m�肽���z
�P�R�A�P�S�A�P�V�A�Q�Q�A�Q�U�A�Q�X�A�R�X�A�S�P
�T�y���܂ł����ɐ��������z
�P�T�A�P�W�A�R�R�A�R�V�A�S�R�A�S�X
�U�y�s���S������l�Ԃ��z
�O�R�A�O�U�A�P�U�A�Q�O�A�R�Q�A�R�T�A�S�O�A�S�Q�A�S�W
�V�y�u���v�Ɓu�������v�̊Ԃ��Ȃ��z
�O�V�A�R�U�A�R�W�A�S�S�A�S�U
���P�|�Q
�ތ^�̔ԍ��c�V
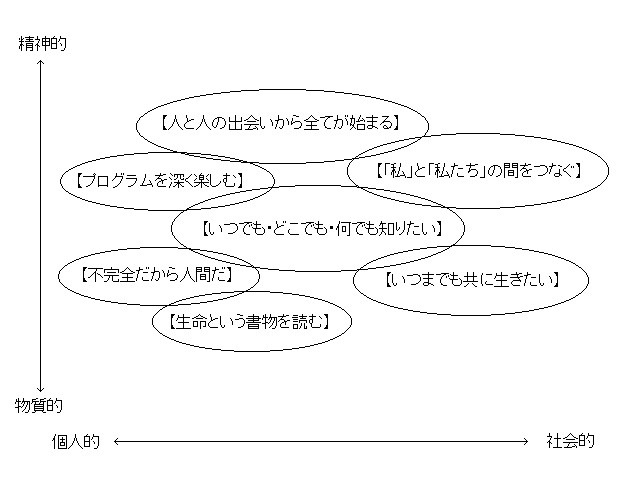
���Q�|�P
�����̃|�W�V�����c�W
���Q�|�Q
�@���͌���̈�����ɐU��ꂽ���Ȃ��A�܂��A�����ɏ��������ăg�b�v�ɗ����͎����̍D���Ȏd���ɐE�l�I�ɔM���������l�Ԃł���B�u����x�ꂾ�v�Ƃ��u�Â��v�u�I�^�N���v�ƌ����Ă��A���͋C�ɂ��Ȃ��B�a�̐l�͔S�苭�������̃e�[�}��Nj��������ŏ�x�ɗD��A�����W�͂�����l�ł���B�b�̐l�͐l�̈ӌ��ɂ����U���邱�ƂȂ��A�ڕW�B�����d�����Čv��I�ɍs������ӔC���̋����l�ł���B�c�̐l�͐V�������ɂ��₭�K�����A�l������Ă��Ȃ����ƂɐϋɓI�Ɏ��g�ސ�i�����������l�ł���B
���R�|�P
�@�����S����l������̂́A�����o�[�e�l�������\�͂������A���ȐӔC�̉��œƗ����čs�����Ȃ���S�͓̂��ꂳ��Ă���L�@�I�ȃ`�[���ł���B�e�l�͐��Ƃł���Ƌ��ɑS�̂����n���͂��v�������B���̂��߂ɒm�������L�����K�v�����邪�A���ꉻ�ł��Ȃ��u��v��u��C�v��ǂ݂Ƃ�͂��d�v�ł���B
���R�|�Q
�@�����T����l������̂́A�����o�[�e�l�̔\�͂͂���قǍ����Ȃ��Ă��A����炪�g�ݍ��킳�ꂽ���ɑS���V�����͂ݏo���`�[���ł���B�����ł͌l���V�����A�C�f�A��n������̂ł͂Ȃ��A�g�D���v���f���[�X���邱�ƂŐV�����A�C�f�A�����܂��̂ł���B�m���ɂ��Ă��A�u�V�����m����v�̂ł͂Ȃ��u�m����ҏW�������v�Ƃ�����Ƃ��傫�Ȑ��ʂށB
���R�|�R
�@�����U����l������̂́A�����̎��\�́E�m���𑼎҂̂��ߎ����I�ɒ��郁���o�[���琬������`�[���ł���B�ォ��̎w���Ŋ�������ꍇ�ɔ�ׂČl�̃��e�B�x�[�V�������傫���A�l�X�ȃA�C�f�A�����R�ɔ��W�����邱�Ƃ��ł���B���̌��ʁA�L���Ɛ[�������˔������u�W���m�v�����ݏo�����B
���R�|�S
���[�����̔ԍ��c�S
���R�|�T�|�P
��
���R�|�T�|�Q
�S�T��
���S
�@���́u�����V���̃C���^���N�e�B�u���v�Ƃ����v���W�F�N�g���Ă������B����́u���v�Ɓu�������v�A�܂�l�ƎЉ�̊Ԃ��Ȃ������̈�ł���B
�@�{���A�V���̂悤�ȃ}�X�E���f�B�A�ł́A�u����ҁv����u�w�ǎҁv�֏��͈�����I�ɗ����B���̃V�X�e���́A�����̓ǎ҂ɓ����������Ƃ����ʂł͗D��Ă���B���̔��ʁA�ǎ҂̌��ɍ��킹�����l�ȏ��ɂ͌��E������B����́A�\���ł��鎆�ʂ������Ă��邵�A�L���ȋL�҂��S�Ă̕�����������Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B
�@����A�C���^�[�l�b�g�ł͏�M�҂Ǝ�M�҂̊W�͑o�����I�ł���B��M�҂����ł����M�҂ɂȂ��B���̓����ɂ���āA���f�B�A�̃C���^���N�e�B�u�����\�ɂȂ����B�Ⴆ�A�f����u���O�͐V���E�G���̃C���^���N�e�B�u���ł���A�|�b�h�L���X�g�̓��W�I�́A��������T�C�g�̓e���r�̃C���^���N�e�B�u���ł���B
�@�����l�b�g���[�N���f�B�A�̓������}�X�E���f�B�A�ł��錻�s�̐V���Ɏ�����Ă݂����B��̓I�ɂ́A�u�L�҂̋L���A�ǎ҂���̋L�����Ɉ����v�u�ҏW�ɓǎ҂������v�u�\�ߓo�^�����ǎ҂̌��ɍ��킹�ĈقȂ������ʂ�z�M����v���Ƃ��ڕW�ł���B������������邽�߂ɂ́u�����郁�f�B�A�ɂ��L����W�v�u�l�b�g���[�N���g���������ҏW�v�u�������������p�����v�����^�̊J���v���K�v�ƂȂ�B
�@�������@�Ƃ��ẮA�����ɎQ�����郁���o�[�������I�ɓ��ӕ����I�сA�A�C�f�A��������x�W�܂����Ƃ���őS���Ō������A���̌��ʂ��Ăъe���̌����Ƀt�B�[�h�o�b�N����Ƃ����V�X�e�����̗p����B���̕��@�ɂ��A�����ɏo�Ă���E�B�L�y�f�B�A�Ɠ��l�ɍL�����[���u�W���m�v�����ݏo����邩�炾�B
�@�����̐��ʂƂ��Ắu�ǂ݂����L�������̐V�����z�B����A�Ȏ����ɂȂ�v�u�v�����g���f�B�A�̐��E�ɐV�����W���m�����������v�u�f�W�^���f�o�C�h�̏k���v�Ȃǂ����҂����B�����ɂ���ĐV���͐V���ȎЉ�ݏo�����f�B�A�Ƃ��čĐ������Ǝ��͍l����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c����
�E��N�ɑ����āu�����v���W�F�N�g�̗����グ�v�Ƃ������B�r�e�b�̂`�n�����ʼnۂ����u�u�]���R���v�u�w�K�v�揑�v�̉�������̖��ł���B��������N�ƈقȂ�A�e�[�}�I����v���W�F�N�g�`�[���̍\���ȂǁA�Љ�w�I�����@�����p���Ę_���I�v�l�͂�₤��肪��������B��萔�������A�S�Ă̖�ɓ�����͎̂��ԂƂ̐킢�ł���B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�O�X�z
�@�M�҂͐����I��ԂƂ��Ă�<�������>�̓������A�Ñ�M���V�A�̃|���X�Љ�ƌ���̃l�b�g���[�N�Љ���r���Đ������Ă���B�|���X�Љ�ł́A�u���R�v�Ƃ͎����̐ӔC�Ō����̔C���𐬂������邱�Ƃł������B���̍����́A�����̏�ŐӔC���ʂ������Ƃ�������<��>�̎咣�ƌ��т��Ă������Ƃɂ������B�u���ȁv�Ƃ́u���҂̖ڂ��猩���]���v�ɑ��Ȃ�Ȃ������B����ɑ��āA����̎Љ�ł́A�u���Ȃ̈ӌ��ƍs���Ɋւ��Ď��Ȃ��ӔC���v�Ƃ���<�������>�͑��݂��Ȃ��B����͂���������T�[�r�X���s���ɑ����Đ����I�������s���Ă��邩��ł���A���̌��ʁA���ӔC�Ȕ������������u<�������>�ł��Ȃ��A���I��Ԃł��Ȃ��ی삳�ꂽ�G��̋�ԁv���������Ă��܂��B�����ɂ͎Љ�I�ӔC���Ȃ����ʁA�Љ�I�ȁu�o��v�Ɋ�Â����s���̎��R���Ȃ��B���ꂪ���҂ւ̕s�M�ƕs���Ɋ�Â��u�Z�L�����e�B�[�Љ�v�ݏo���Ɖۑ蕶�ł͏q�ׂ��Ă���B
�@���{�̎Љ�Ɍ���A���̂悤�ȕM�҂̌����𗠕t���鎖��͊m���ɑ����B�������A�u�C���^�[�l�b�g�̂悤�ȋZ�p�̐i���́A�l�Ԃ�<�o��>���������ɐ��E��<����>���邱�Ƃ��������i�ł����Ȃ��B�v�Ƃ����M�҂̈ӌ��ɂ͎��͔��ł���B�������A�Љ�I�ӔC�ӎ��͏d�v�ł���B���������Ñ�M���V�A�ŎЉ�I���R�ƎЉ�I�ӔC����̂ł������̂́A�|���X�Љ�ł́u�s���v�ł��邱�Ƃ����Ɂu�����v�ł���A��������邽�߂̎��o�������������炾�B����䂦�A���{�̎s�������ꂩ��<�o��>�����ׂ����Ƃ���A�u���̎Љ�ɐ��܂�Ă悩�����v�Ƃ������炩�́u�����ӎ��v���K�v�ł���B
�@���̈ӎ�����Ă��i�����C���^�[�l�b�g�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�f���ւ̏������݂����҂�������͂́A�����ɂ��ꂾ���������҂Ɗւ��A���҂����͂ł�����B�l�b�g��̌�����Ԃ́A���͂�����Ă����l�X���A���͂ƑR�ł��鎩���̗͂����o�����ԂɂȂ蓾��B�������A�{�����e�B�A����������ɂ�����l�b�g�̗͂�F�߂���ŁA<�o��>�̓�ʐ������o���邱�Ƃ��ۑ�ł���B�|���X�̐����I���R�������̋`���Ɛ藣���Ȃ��悤�ɁA�l�b�g��̕\�������Ƃ����u�����v���u���҂ւ̐ӔC���ɂ݁v�ƈ�̂̂��̂ł���B���̗��ʂ�S�����o�������ƂŁA�u���l�C���ł͂Ȃ��Z�L�����e�B�[�v�����藧�̂��Ǝ��͍l����B
�y��蕪�́z
�E��Փx�c�W��
�E�ŋ߂悭�o�镪��̖��Ȃ̂ŁA�v��͓���Ȃ��B�������A���ɂƂ��Đg�߂Ȗ�肾���ɁA�c�_�̏ꍇ�͘_�_���i��̂���������m��Ȃ��B�O�����ď��_���p�o�e�[�}�ɉ���������������ǂ����ō����o����ƌ�����B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�O�X�z
���P
�@�����̋��ʓ_�́u������Ɨ�������̂��A���f�B�A����i�Ƃ��ăR���e���c�ݏo���v�Ƃ����ȑO�̍l�����̔ᔻ�ł���B�`�������ʂ�A��������ɂ́A������܊��ŏ������v�l���Ȃ���Ȃ炸�A������������ɂ́A�R���e���c�𑼎҂��܊��Ǝv�l�Ŏ�M�ł���悤�ɕ\������K�v������B�ǂ���̉ߒ��ł��A���f�B�A�͎�̂̎v�l�Ƌ������Ă���B����ɂb�ɂ��A�\����̂ł��鎩�Ȃ͊�����Ɨ��������݂ł͂Ȃ��B���Ȃ����݂̂�����Ɋւ��R���e���c�M���鎞�A����͑��҂Ɍ�����ꂽ���b�Z�[�W�ł���Ƌ��Ɂu���҂ɋ��L����鎩�ȁv�ł�����B���̈Ӗ��Łu���Ȃ͑��҂��܂ފ��ɂ���č���Ă���v�ƌ�����B���̊���m��A�����o�邽�߂̕����f�B�A�Ȃ̂ł���B���̎��ȂƑ��҂̊W�����f�B�A�̑����猩���̂��a�ł��邪�A�u���f�B�A�ɂ��R���e���c�̌������v���s�����Ƃ��u����v�ł���A�u���f�B�A�ɂ��R���e���c�̗��ʁv���x�����邱�Ƃ��u����v�ł���ƌ�����B�������āA�l�Ԑ��_����葽�l�ȃ��f�B�A�E�\�����@�ōč\������邱�Ƃɂ���āA�����Ǝ�̎�̐����L���ɏo����Ƃ��ł��d�v���Ǝ��͍l����B
�i�P�O�O�����̃X�y�[�X�ɐ}�j
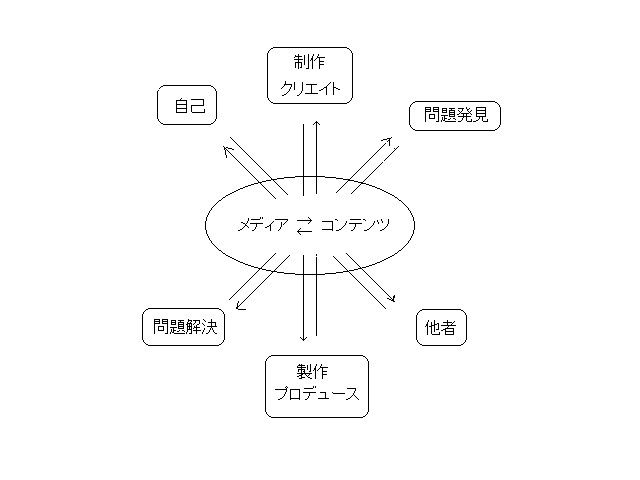
�@�w�t�������悤�x�F���́u�t�̉́v�ɂ���A�j���ɂ��f���R���e���c���Ă���B���̊�揑�̓N���G�[�^�[�Ɍ��������̂ł���B���Ӑ}�́A�R�`�P�O�̂��ǂ��̔��B�ۑ�ł���u���ȂƎЉ�̊ւ���m��v�u���͂̊����ώ@���A���[����������v�Ƃ����e�[�}�ɐe�q�ŊS�������Ă��炤���߂ł���B��̓I�ȓ��e�Ƃ��ẮA���Ɂu���R�̊ώ@�v���e�[�}�Ƃ��A�t�ɂȂ��ċC�����オ��A���Ԃ������Ȃ�A�O�ɏo��c�N�V����̉ԁA���̊������n�܂邱�Ƃ������B���Ⴊ��Ńc�N�V��������A����ǂ�������f�����g���B���Ɂu��炵�ւ̊S�v���e�[�}�Ƃ��A�~����t�ւ̕����E�H���̕ω����X����ƒ�̐H��ɂ���Ď����B�g�����□�����������铮������B����ɁA�ߕ��E���ՁE���w���Ȃǂ̍s�����G�߂̕ω��Ƌ��ɍs���邱�Ƃ������B��O�Ɂu�̂��g���Ď����̐������������v���Ƃ��e�[�}�Ƃ��A�w���L�т����ƁA�O��葁������邱�ƂȂǂ��A�j���ŕ\�����Ď��Ȃ̕ω��Ɛ��������o���Ă��炤�B��i�S�̂�ʂ��āA����̂��ǂ������Ɂu���R�͖ʔ����v�u�̂������Ƃ͖ʔ����v�Ƃ������Ƃ������Ă��炢�A�u�܊��ŖL���Ɋ����A�l���邷�炵���v���Ă���B
�i�P�O�O�����̃X�y�[�X�ɐ}�j
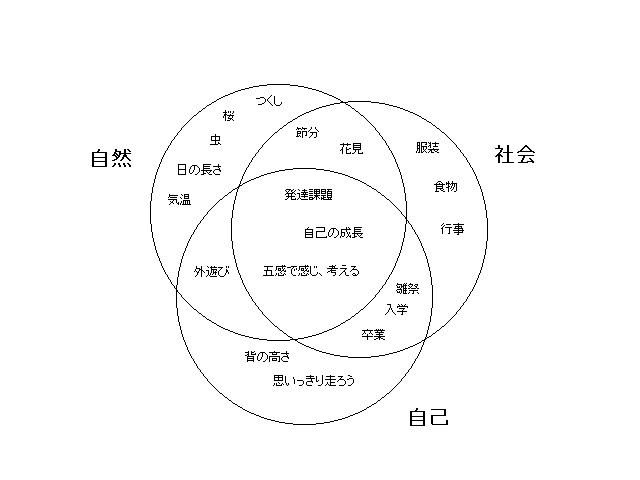
�E��Փx�c��N�����Ղ����B
�E�P�X�X�W�N�x�A�Q�O�O�P�N�x�ɏo�肳�ꂽ�u���f�B�A�E�A�[�g�v�n�̖��Ɛ[���Ȃ��肪����B�r�e�b�̃��M�����[�[�~�A�āE�~�̂r�e�b�[�~�ł����グ���e�[�}�ł���B�P�ɗ��_���q�ׂ邾���ł͂Ȃ��A��������H�I�ɕ\���ł��邩�Ƃ������Ƃ�₤�Ă���B���w����Ǝ��ۂɃO���[�v���[�N�ʼn��K����悤�Ȗ��ł���A�r�e�b�̎u�]�҂Ȃ�Ίy����œ��������肾�ƌ�����B�������A�ߋ��⌤������Ϗd�v�ł���B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�P�O�z
�@�������P�_�C���[���l�Ȃ�A���ɃA�e�[�i�C�Ƃ̋���̌����������݁A���ꂪ�������Ȃ����̂݁A�����Ɠ���������邽�߂̌���I�ȏo�������ׂ����ƍl����B���̍����͓����𐬗������邽�߂̏����ł���u���ʂ̐��`�v�������ׂ������炾�B���������O�G�Ɛ키�̂́A�N�����u���`�v�ł͂Ȃ�����ł���B�t�ɗ��Ɠ��������Ԃ̂́A�N���ɑR���邱�Ƃ��u���`�v������ł���B�����Łu���`�v�Ƃ��Ē�`����Ă���̂́u�����̗��v�����A�����Ɨ��Q�������鑼�҂̗��v����邱�Ɓv�ł���B
�@�A�e�[�i�C�Ƃ̋�����A�����͂��̂悤�ȁu���`�v�ɍ��v������̂ł������B�y���V�A�R�ɑ��鋰�|����S�Ẵ|���X�͒c�����A���ɃA�e�[�i�C�ɐ푈�̎哱����a�����̂ł���B�����ł͑S�Ẵ|���X�����`�����L���Ă����B�������A�A�e�[�i�C���F�߂�悤�ɁA�푈�̏������_�@�Ɏx�z�𐳓�������u���`�v�̈Ӗ����ω����n�߂��B�u�N���̋��|�ɑR���邽�߁v�Ƃ����x�z�̗��R���u���_�E�̖ʂ̂��߁v�ɕω����A����Ɂu�A�e�[�i�C�̗��v����邽�߁v�̎x�z�ɕώ������̂ł���B�A�e�[�i�C�̎咣�́u�A�e�[�i�C�l�ɂƂ��Ă̐��`�v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�����Ȃ�ƁA�ŏ��ɏ��|���X�����ӂ����u�����̗��v�����A�����Ɨ��Q�������鑼�҂̗��v�����v�Ƃ������`�͐������Ȃ��B�����A�R�����g�X���咣����u����������������`���v�̕������u���`�v�ɋ߂��Ƃ������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�R�����g�X���n�߂��A�e�[�i�C�Ƃ̐퓬�����P�_�C���[���l�ɂƂ��ė��v�ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ�����ł���B���̂悤�ɁA���L�����ׂ����`�̓��e���|���X�ɂ���ĈقȂ�ȏ�A�ǂ��炩�̎咣���������ƌ��肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�����ŁA�V���Ȑ��`���`���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B����́u���ӂƂ��Ă̐��`�v�ł���B�R���͂ɂ��Ȃ��@�̎x�z���������邽�߂ɂ́u����������ӂł���@�v���K�v���B�A�e�[�i�C���@�ɂ��x�z�d����Ȃ�A����̗��v�����łȂ����҂̗��v�����d���ׂ��ł���A���P�_�C���[���ƃR�����g�X�͋��ɃA�e�[�i�C�ƌ����č��ӓ_�����o���ׂ��ł���B���Ƃ����ӂ��s���̏ꍇ�ɂ��A�o���͂����܂ō��ӂ܂ł̌���ێ��Ɍ��肵�A�e�|���X�̑��l���d���Ȃ��狤�ʂ̗��v�����ߑ����邱�Ƃ��őP�̍Ǝ��͍l����B
�y��Փx�z
�@�W���I�Ȗ��B
�y���̌X���z
�@��N�Ɉ��������A�M���V���ÓT�̋c�_���琭���Ɩ@�̊�b�Â����l��������o��ł���B���N�͎��́u�_���I�\�z�́v�ɂ��͓_��u�������ɂȂ����B��N�̏o��Ɩ{���I�ȂȂ���������Ȃ̂ŁA�ߋ��⌤�����\���������ǂ����ō����o�邾�낤�B
�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�P�O�z
���P
�@�����ł͓d�q�I�Ȑ}���ق��u�O���[�o���ȃf�[�^�x�[�X�v�ł��邱�Ƃ��琶�����肪�����Ă���B����͌����p����e�L�X�g�f�[�^�̑唼���p��ŏ�����邱�ƂɂȂ�Ƃ������ł���B���E���ʂ̃f�[�^�x�[�X�ɂ͋��ʌꂪ�K�v�Ƃ���A���ꂪ����ł͉p��ł���Ƃ������ƁA�܂��A�p�ꌗ�Ńe�L�X�g�f�[�^�̃X�L���j���O���ł��i��ł��邱�Ƃ����̌����ł���B���̌��ʁA���{�ꂪ���ʂ���u�|��v�̖�肪�����`�|�Q�Ƃ`�|�R�Ɏ�����Ă���B���ɁA���{��g�p�҈ȊO�̐l�ɓ��{��e�L�X�g���f�[�^�x�[�X��Ŏg���Ă��炤���߂ɂ͖|�K�v�����A��Ƃ̈Ӑ}�╶���I�w�i�Ȃǂ̃j���A���X�͖|������Ƃł���B���̂��ߓ��{��g�p�҂́u���E���ɔ��M�ł���v�Ƃ����d�q�I�Ȑ}���ق̃����b�g�������A�l�b�g���[�N�̒��œ��{�ꂪ�����ꂽ����ɂȂ��Ă��܂��\��������B���ɁA�w�p�̐��E�ł͉p��̋��ʌꉻ���i��ł���A���{�l�����҂��p��ŕ\�����Ȃ���ΐ��E�ɔ��M�ł��Ȃ���肪����B�����ł͖|��̓���ɉ����ē��퐶���œ��{���p����Ӗ��������Ȃ�A����ɂ�������{��s�v�_�Ȃǂ����܂�鋰�ꂪ���邾�낤�B
���Q
�@�����Ɣ�r�����d�q�e�L�X�g�̒����́A���Ɏ��R�Ɍ����ł��邱�Ƃł���B������̍����ɂ͌��肳�ꂽ���ڂ����Ȃ����A�d�q�e�L�X�g�ł͒������͂���ꕶ���P�ʂ܂Ō����ł���B���ɓd�q�e�L�X�g�͒P�Ȃ�d�q���Ȃ̂ŁA�X�V�A���H�A���ʁA�����A�~�ς��e�ՂȂ��Ƃł���B�d�q�e�L�X�g�̒Z���́A���ɒ[���@����g�����ߏ������d���A�g�p�ꏊ�����肳��邱�Ƃł���B�܂��f�B�X�v���C�͈���������ǂ݂ɂ����A���̂Ńf�[�^��������\��������B���ɁA�l�b�g���[�N��̓d�q�e�L�X�g�͎��R�ɔ��M�ł��邽�߁A���e�̐��m����M�p���ɋ^�₪���邱�Ƃł���B��O�ɁA�d�q�e�L�X�g����͕����I�w�i��ǂ݂Ƃ�̂�����Ȃ��Ƃł���B
���R
�@�d�q�}���ق̈Ӗ��́A���ɏ��R�X�g�̍팸�ł���B�Ⴆ�A���ʂ̐}���ق̑ݏo���Ԃ͌����Ă���A�}���قɖ{���Ȃ��ꍇ�͎����ōw�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������͍����Ȃ��̂������A�w���ɂ͑傫�ȕ��S�ł���B���������J���ꂽ�d�q�}���قȂ�A�����ŐV���̐�发��ǂނ��Ƃ��ł���B����ɁA�d�q�}���ق͎��ԂƏꏊ��I���A���n�����̊Ԃɂ��f�[�^�x�[�X�ɃA�N�Z�X���ď����������A���Ԃ�L���Ɏg����B���ɁA��������������L�ł���̂Œn��i�����Ȃ��Ȃ�B��w�̐}���ًK�͂ɂ�錤�����̍����Ȃ��Ȃ�̂ŁA�����I�ɂ����ۓI�ɂ��������������₷���Ȃ�B
�@�d�q�}���ق̎g�����Ƃ��đ��ɏd�v�Ȃ̂́A�����@�\�̓����������Ƃł���B�w��������ꂽ���Ԃɑ����̏����ɖڂ�ʂ����Ƃ͓���B�������A�����@�\���������ꂽ�d�q�}���قł͉��f�������\�ł���B��̃e�[�}�ɂ��ĕ��L�������n�悩�當����T������A�قȂ�������Ԃ̊֘A�ׂ��肷�鎞�A���̂悤�Ȍ����@�\���͂�����B���ɏd�v�Ȃ̂́A�����ɂ�錟�ł���B�d�q�}���قɂ͕s���m�ȏ����������߁A�f�[�^�����̂܂܌����Ɏg�킸�A�����╡���̎����Ŋm�F�����Ƃ��s���ł���B��O�ɁA�p��ȊO�̌�����w�ԕK�v������B�����`�ɂ���ʂ�A�p��ȊO�̃e�L�X�g�f�[�^�͂��̌���g�p�҂̑��ɂ͗��p����Ȃ��\���������B�������A�قȂ��������ٕ����̕����I�w�i�𗝉����邽�߂ɂ́A�����Ŏg��ꂽ�A���邢�͍����g���Ă��錾��̗������K�v�ł���B�����̎g�����ɉ����Ȃ�A�d�q�}���ق͊w�K�E���������������x���Ă������̂ɂȂ�Ǝ��͍l����B
�y��Փx�z
�@��N�����Ղ����B
�y�o��̌X���z
�@�Q�O�O�P�N�x�́u�f�W�^���r�W�l�X�̊��v�A�Q�O�O�T�N�x�́u�C���^�t�F�[�X�f�U�C���v�A�Q�O�O�U�N�x�́u�Q�P���I�ɂӂ��킵�����m��T�[�r�X�v�Ȃǂ̗ޑ�ł���B���Ɏ��̂Q�O�O�U�N�x�̉�ł͍��N�x�̓��e�ɋ߂��u�d�q���쌠�v�������Ă���B�����̗�����O��ɂ��čl�����q�ׂ�Ƃ����I�[�\�h�b�N�X�ȏo��͎��g�݂₷�������ł��낤�B�o��̔w�i�ɂ́A��N���{�̕��d�𑛂������O�[�O���̓d�q�}���فE�d�q���Ж��A�܂��A�ŋ߂ǂ̑�w�ł����ɂȂ��Ă���u�E�B�L�y�f�B�A�̃R�s�[�ɂ�郌�|�[�g�쐬�v�Ȃǂ�����B�f�W�^���W�̃j���[�X�ɒ��ӂ��A�ߋ��⌤�������Ă����Γ���Ȃ��B
�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�P�P�z
�@�M�҂͂܂��A��R�����u�ǐS�̖��v�Ɓu�@���I�����̖��v�ɕ����Ă���B�ǐS�̖��Ƃ��Ă̒�R���͓����I�E�@���I�ȁu�������v�Ɋ�Â��Ă���A�����ł̒�R�Ƃ͗ϗ��I�ȈӖ��ł̕s���ɑ����R�ł���B���ꂪ���R�@�Ƃ��Ă̒�R���ł���B����A�@���ɋ�̓I����������R���͖@�̘g�g�݂̒��Œ�`����Ă���A���@�ł�����茠����ۏႳ����R�ł���B���ꂪ����@�Ƃ��Ă̒�R���ł���B
�@��̓I�ɒ�߂�ꂽ�@�ɂ��Đ���������������@���؎�`�̗���ł́A����@�Ƃ��Ă̒�R���������@�I�ɔF�߂���B���ꂪ���@�I��R���ł���B����ɑ��āA�@���Œ�߂��Ă��Ȃ���R���������͖@�����̂��̂ɑ����R��������B�@���؎�`�ł́A����������R���͔F�߂��Ȃ��B���ꂪ������I��R���ł���B�������A���ꂪ���j��u�s���v���v�Ȃǂ̐��ʂݏo�������Ƃ͎����ł���B������I��R���͍��ł��Љ�I�ȗ͂Ƃ��ĔF�߂��Ă���A�����ɂ���͗ǐS�̖��ɑ����Ă���B�ǐS�̖��ɂ��ċc�_����͓̂N�w�̖�ڂł���A����䂦�ɕM�҂͂�����u�@�N�w�̖��v���ƍl���Ă���B
�@�ŋ߁A�G�W�v�g�œƍٓI�Ȑ��i���������������s���̍R�c�s���œ|�ꂽ�B�ߑ�I�Ȍ��@�Ɩ���I�ȑI�����x������̂ɒ�R�^����������̂́A���x�������łȂ��؋��ł��낤�B�Ⴆ�A���{�ł������I���ɂ������[�̊i�����傫��������A�n�������̂Œm����s���Ƌc��Η������肷��B��[�̊i�����傫���Ȃ�Γs�s�Z���̈ӎv�������ɔ��f����Ȃ��B�܂��A�n�������̂̎��c�����Z�����I��ł���͂��Ȃ̂ɑΗ����N����̂́A�n��ɂ����闘�Q�W�����R�ȓ��[�s����j��ł��邩�炾�B�����������̍ٔ��͑������Ȃ��Ȃ��s���̑������ĂȂ��̂́A�ۑ蕶�ɂ���ʂ�A���͂�����������̒�߂��@�ƌ������u�́v�Ŏ�낤�Ƃ��邩��ł���B
�@����ɑ��钴����I��R���́A����I���x���@�\���Ă��鍑�ł��Ӗ�������B�Ⴆ�Δ{�g�D�i�m�f�n�j�̊������A�����̐�����@���Ɍ��ׂ����邽�߂ɐ��܂�邩�炾�B���Ǝ҂������A��҂�����҂������̃V�X�e�����甲�������Ă��܂��Љ�ł́A�҂��Ă��Ă������͂悭�Ȃ�Ȃ��B�����������ɐV�����������Ă���^���ݏo���̂͒�����I��R�����x����N�w�ł���A����Љ�ɂ����ꂪ�������߂��Ă���Ǝ��͍l����B
�y��Փx�z
�@��{�I�Ȗ��B
�y���̌X���z
�@���̐��N�̌X���P���āA�@�Ɛ����̊�b�Â��Ɋ֘A������ł���B���e�I�֘A�Ƃ��ẮA2007�N�́u�@�I���`�v�A2010�N�́u�M���V���̃|���X�Љ�ɂ����鐳�`�v�ɑ����āu��R�̐������Ƃ͉����v���l����������ł���B�ۑ蕶�̋c�_�����m�ł���A�Η����ڂ̍����i�T�O�̒�`�j�ɖڂ�����A�c�_������̂͗e�Ղ��낤�B��̗���ŋ߂̎Љ���ł���u�G�W�v�g���ρv�u���É��s�̏Z�����[�v�u�h�����l�b�g�J�t�F��ɑ���{�g�D�̉��������v�ȂǁA�g�߂Ȗ�肪�g����B�ߋ��⌤���Ǝ�����藝������ł���B
�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�P�P�z
��P
�@���́u���������v�𑪒肵�Љ��̊�b�ɂ������B���A���{�ł͘H�㐶���A�l�b�g�J�t�F��ȂǁA�Ƃ����������Ǝ҂��N�X�������Ă���B�A�Ƃ��Ă���l���l���炵�̗]�g�Ō������������Ă���B��w���̏A�E���������Ă���B�Љ�S�̂��u���������v���������Ȃ���ԂɂȂ��Ă���B���E����l���N�ԂR���l�����Ԃ������Ă���̂��A���������Љ��ƊW���[���B�䂦�Ɂu���������v���S�̎Љ�Â��肪�d�v�ł���B
��Q
�@�u���������v���Ȋw�I�ɑ��肷�邽�߂ɁA���́u���������w���v���Ă���B�u���������v�͎�ϓI�Ȃ��̂ƍl�����Ă������A������q�ω����邽�߂Ɂu�]�̏�ԁv�u�g�̂̌��N��ԁv�u�\��ɂ��R�~���j�P�[�V�����\�́v�̎O�𑪒肵�A�����𑍍����āu�l�������������ǂ̒��x�����Ă��邩�v��\���������B�d�v�Ȃ̂́u�\��ɂ��R�~���j�P�[�V�����\�́v�̑���ł���B�l�ԂɂƂ��ĕ\��͐S�I���e�̕\���ł���A�R�~���j�P�[�V�����̊�{�ł���B�S���}����Ԃɂ��鎞�A�\��͈Â��Ȃ�A�ω����R�����Ȃ�B�q�ϓI����̂��߂ɂ́A����𐔒l�Ƃ��ĕ\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�\���Z�p�̓J�����̏Ί猟�o�ɉ��p����Ă���B���̋Z�p�W�����A�\����\�������̗֊s�����O�����̃x�N�g���f�[�^�Ƃ��Đ����Ɍv�����A���l�ȕ����ɑ�����l�X���܂ޏ\���ȗʂ̃f�[�^����\��Ƃ��̕ω����ǂ̂悤�ȐS�I��Ԃƌ��т��Ă���̂��𗝘_������B
��R
�@�V�����P�ʂ́u���������w���v�ł���B����͐l�������Ă���u���������v���q�ϓI�ɐ��l�ŕ\��������̂��B���ɔ]�̏�Ԃ�]���̃Z���g�j���ʂƔ]�����ʂ̕��l�ŕ\���B���ɐg�̂̌��N��Ԃ𐇖����Ԃƌ��t�����l�̕��l�ŕ\���B��O�ɕ\��ɂ��R�~���j�P�[�V�����\�͂�P�ʎ��ԓ�����̕\��Ƃ��̕ω��ŕ\���B�Ί炪���_�������A�\��ɕω�������Ɠ��_�������B�ȏ�̎O�̗v�f�̘a���u���������w���v�ł���B
��S
�@���������������Ă���l�́u�Ί�ɂȂ鎞�Ԃ������v�u�{��f����y���ނ��ƂɊS�����v�u�l�Ɛڂ��邱�ƂɊS�����v�Ȃǂ̍s���ɂ���������������낤�B�����͐S���w��_��w�̗Տ��I�����Őςݏd�˂�ꂽ�f�f�ƊW���[���B�������A���ۂ̈�Ì���ł͌ʂ̃N���C�A���g�ɑ��k���Ԃ�������ꂸ�A�u�����f�[�^�ł͂ǂ��ɂ��ُ�͂Ȃ��v�ƌ����Ď��]�����f�҂������B�u���������w���v��p����ƁA�\��̓ǂݎ��ɂ���āu���莞�_�ł̋C�����v�Ɓu�R�~���j�P�[�V�����ɂ��C�����̕ω��v��m�邱�Ƃ��ł���B�]��g�̂̏�Ԃ͕��l�ŕW���������̂ŁA���ɔ]��g�̂̎������Ȃ��l�̐S�̔Y�݂𑪒�ł��邱�Ƃ��d�v�ł���B�l�ԊW�̔Y�݂�l���̌��ʂ��Ɋւ���Y�݂͖{���u�a�v�Ƃ��Ĉ���ꂸ�A���̂��߂Ɏ��E�⏝�Q�������N����x�Ɂu�Ȃ���x��ɂȂ����̂��v�����Ƃ���Ă����B�u���������w���v�����_�I�Ɍ��N�Ȑl���Ⴂ�ꍇ�A���邢�͌p���I�Ɋώ@���Ēቺ���Ă���ꍇ�́u�Y�݂�����A�������т��������Ȃ��Ȃ��Ă����ԁv�ƍl���邱�Ƃ��ł���B����̕��@���A�\����r�f�I�J�����ŎB�e���R���s���[�^�������邾���Ȃ̂ŊȒP�ł���B���̂悤�ȑ���V�X�e���͈�Â̏ꂾ���łȂ��A�w�Z�Ȃǂł��g�����Ƃ��ł���B�����̃f�[�^�����ɂ��āA�l�ɂƂ��Ắu���̐[�����v�𑼎҂��m��A�T�|�[�g�ɖ𗧂Ă邱�Ƃ��ł���Ǝ��͍l����B
�y��Փx�z
�@����B
�y���̌X���z
�@2004�N�x�u��蔭���Ɖ����̕��@�v�A2005�N�x�́u�C���^�t�F�[�X�f�U�C���v�A2006�N�x�́u�Q�P���I�ɂӂ��킵�����m��T�[�r�X�̔����v�Ȃǂ̗ޑ�ł���B�������̎������Q�l�Ɏ����A��w�ɓ����Ă���̌������@�⌤���̖ړI���q�ׂ�������ƌ�����B�������N�����Ă�����`���ł�����A�ߋ��⌤�������A�����ŏ����Ă݂����ɂƂ��Ă͓���Ȃ��B�u��w�ʼn������������v�Ƃ����ӗ~��\������_�ł́A���̎u�]���R���Ƃ������邾�낤�B
�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�P�Q�z
�@��̉ۑ蕶�ɋ��ʂ���l�����́u�@�̔ے�v�ł���B�������ƂP�ł́u�]�������Â�����v���O�����v���@�ɑ����Đl�X���x�z���A�������ƂQ�ł́u�o���O�I�ʁv���ƍߌX���̂����`�q��r�����Ė@�̈����ƍ߂̉\�����̂��̂��Ȃ����Ă��܂��B�ǂ��������u�����O�ƍ߁v��h�����Ƃɂ���āu�@�ɂ�鏈���v��s�v�ɂ��Ă��܂��̂ł���B���̗��z���́u�@�Ȃ����z���E�v�ł��낤�B
�@���̂悤�ȔƍߊǗ��ɈӖ�������Ƃ���A�܂����Ɂu�@�R�X�g�̍팸�v�ł���B��@�s�ׂ��������ꍇ�A���̓E���Ɖ����ɂ͌x�@�E���@�E�ٌ�m�E�ٔ����E�Y�����ȂǑ����̑g�D��{�݂��K�v�ł���A�ٔ��ɂ͒������Ԃ�������B�����ƍߍs�ׂ��̂��̂̔�����h�����Ƃ��ł���A�����͕s�v�ɂȂ��Ĕ���Ȑŋ���ߖ�ł���B���̃����b�g�́u�����̌������v�ł���B�ƍߍs�ׂ͓E������Ȃ���Α��݂��Ȃ��̂Ɠ����ł���B�u�߂܂�Ȃ���Ώ�������Ȃ��v�̂ŁA�ƍߎ҂͎����܂œ��S����B�����O�ɔƍ߂��������Ă��܂��u�������v�͂Ȃ��Ȃ�A���������҂Ƃ���Ȃ��҂��ł���s�����͉��������B
�@�������A�@�̈Ӗ���[���l����Ɓu�@�Ȃ����z���E�v�ɂ͍��{�I�Ȗ�肪����B���Ɂu�������Ă��Ȃ��ƍ߂͔ƍ߂��v�Ƃ������ł���B���Ƃ��u�ƍߑO�̋����d�c�v��E���ł���Ƃ��Ă��A���ꂪ�ƍ߂ɂȂ�̂͋���ⓦ����i�������ɏ�������Ă���ꍇ�ł���B�u�ƍ߂̌����ɂȂ�v�f���ƍ߂��v�ƍl����ƁA�ۑ蕶�̂悤�Ɏv�z��E���������`�q��E��������A���Ԃ������̂ڂ��Ĕƍ߂��`���邱�ƂɂȂ�B����ƁA����l�̔ƍ߉\�����ɂ����̂ڂ�A���̐l�̐e���E�F�l�E���t�ȂǁA������W��ƍ߂̌����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B����ł͔ƍ߂Ɋւ��Ȃ��l�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�@���Ɂu�P�ƈ��͎��ɂ���ē���ւ��v�Ƃ�����肪����B���m�ɂƂ��Đ��`�ł������w����������ł͔ƍ߂ł���悤�ɁA�Љ�̕ω��ɂ���Ė@�͕ω�����B���̍����͐l�Ԃ������l���Ə_��ł���B�R���s���[�^�̃v���O�����͂����Â��Ȃ邵�A���{�l�̉ƌn����ƍߎ҂��o�邱�Ƃ�����B����ɁA�����Ȑl�����ɉ߂���Ƃ��B���̂悤�Ȑl�ԑ��݂����炱���A���̕ω��ɑΉ����A������ςݏd�˂邱�Ƃ��ł����̂ł���B
�@�ȏ�̍l�@����A�u�@�Ȃ����z���E�v�̓t�B�N�V�����̈���o�Ȃ��Ǝ��͍l����B
�y��Փx�z
�@��{�I�Ȗ��B��N���Ղ����B
�y���̌X���z
�@���̐��N�̌X���P���āA�@�̊�b�Â��Ɋ֘A������ł���B�ۑ蕶�̋c�_�����m�ł���A�c�_������̂͗e�Ղ��낤�B�ŋ߂̎Љ���ł���u�Ď��J�����̑����v�u�o���O�f�f�v�Ȃǂ��r�e�̐��E�����łȂ������̖@�⍑�Ƃ̊�b�Ɗւ���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ𑣂����ł���B
�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�P�Q�z
��P
�@������ۓI�Ȋւ������������i�Ƃ��Ă����Ɏv���o���̂́u�抄��X�v�[���v�ł���B�ꎞ���͊w�Z���H�̏�ōL���g���A���݂ł��R���r�j�G���X�X�g�A�ŕٓ����ƕK�����Ă���B�`�ԂƂ��Ă̓X�v�[���̐�ɋ��̎��̂悤�Ȑꍞ�݂��O�قǓ��ꂽ���̂��B���z�̏o���_�́A�����炭�u�X�v�[���A�t�H�[�N�A�������ꂼ�ꏀ�����A�͎̂�Ԃ���p��������B��{�̐H��ōς܂������B�v�u�m�H�ł��a�H�ł��A�̂ł��t�̂ł��k�[�h���ł��H�ׂ���H�킪�ق����B�v�Ƃ������Ƃ������̂ł��낤�B
�@������g���Ď����������̂́u���ł��H�ׂ悤�Ǝv���ΐH�ׂ��邪�A����H�ׂĂ��H�ׂɂ����v�Ƃ������Ƃł���B�܂�A�ėp�̓������������A�s�����L�����Ă��܂����̂ł���B�Ȃ����͐抄��X�v�[���ɕs����������̂��B����́u�������E�h���E���ށv�Ƃ����X�v�[���A�t�H�[�N�A���̋@�\����A�ʂ̓����������Z���č��������抄��X�v�[��������ł���B�ނ����{�ɂ܂Ƃ߂邽�߂ɁA�`���I�ȐH��̂ǂ̋@�\���]���ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B
��Q
�@������l����ꍇ�ɑ�Ȃ̂́A�u���Z�p�v�����łȂ��u�g���Z�p�v�ł���B�ۑ蕶�̂��o�����ł͍D���ȋȂ��D���ȏ����ŕҏW���邱�Ƃ��\�ɂȂ褂���ł��u���y�f�B���N�^�[�v�ɂȂ��̌����ł����̂ł���B�H��ɂ����̍l�����͉��p�ł���B�u�g���₷������Ɏ����ŃA�����W�ł���v���Ƃ�ڕW�ɂ��A�f�U�C�i�[�͂��̊�Ձu�v���b�g�t�H�[���v����邱�Ƃő��l�ȃj�[�Y�������Ƃ��ł���B
�@���̍l�����Ɋ�Â��A�抄��X�v�[���̉��ǂ��l���Ă݂悤�B�܂����݂̐抄��X�v�[���̑f�ނł���v���X�`�b�N���A�Y���̂���`��L���v���X�`�b�N�ɕς���B����͎��R�ɋȂ��ĕό`�ł��A���������ɂ���ƌ��̌`�ɖ߂�f�ނł���B���T�C�N������Α��̃v���X�`�b�N���i�Ɠ����悤�ɍĎg�p�ł���B�X�v�[���̌`��Ƃ��ẮA��{�̐H��̈�[�ɃX�v�[���A�ʂ̈�[�͐ꍞ�݂���{���ꂽ�t�H�[�N��ɂ���B�S�̂̒����͂�Ⓑ�߂ł���B�t�̂����ގ��A�ĔтȂǂ����������̓X�v�[�����g���B�������h�����͔��̒[���g�����A�������œ�ɐ܂�Ȃ��A�s���Z�b�g��ɂ��ċ��ނ��Ƃ��ł���B�Y��������̂ŁA��x�Ȃ���Ƃ��̂܂܂̏�Ԃ�ێ�����B���̏ꍇ�A��{�������Ƃ��Ă��܂����Ƃ��悭���邪�A�s���Z�b�g��ɂȂ�����݂₷���B���x���g���ꍇ�́A�ہA���ɂ��炭����Č��̌`�ɖ߂��悢�B
�@�Љ�̍�����i�݁A�L���N��̐l�X���X�[�p�[��R���r�j���g���悤�ɂȂ����B��̋@�\�ɍ��킹���H��������ōH�v�ł���u�ό`���݃X�v�[���v�́A�u�抄��X�v�[���v�ɑ���A�����̐l�ɖ𗧂Ǝ��͍l����B
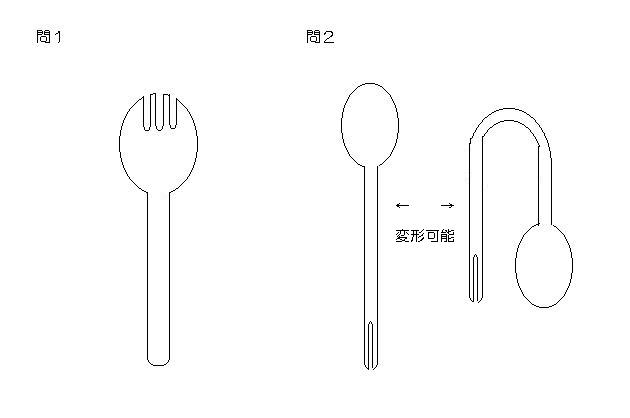
�@2005�N�x�́u�C���^�t�F�[�X�f�U�C���v�A2006�N�x�́u�Q�P���I�ɂӂ��킵�����m��T�[�r�X�̔����v�Ȃǂ̗ޑ�ł���B���퐶���̒��Ŋ����Ă���s�ւ��Ȃǂ�U��Ԃ�A���̉������@���f�U�C���Ƃ�����i�ŏq�ׂ�������ƌ�����B���x���o�Ă�����`���ł���A�ߋ��⌤�������A�����ŏ����Ă݂����ɂƂ��Ă͓���Ȃ��B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�P�R�z
�@�����O���̓��t���x���������A�����I���͎�ɎO�������B���ɎF���E���B�o�g�L�͎҂ɂ��˔������A���ɗL�͎҂�������e�Ȃ̊�����ԁA��O�ɑ�����������c�@���t���ւ̉ߓn���ɂ�����s����v�f�ł���B�����̖��ɑΉ����āA���ɓ��t�̑�b���F�������ɂ��ăo�����X���Ƃ�Ɠ����ɁA�ǐ��Ԃ̃����o�[�����I�o���邱�Ƃ��v�����ꂽ�B���Ɋe�Ȃ̑�b�������ɍ����S�̂̌���ɂ��Q�^����Ƃ������t���x�̉��ł́A�W�c�w���V�X�e���ł��鑾�������̂悤�ɂ͒k���ƒ����̃��J�j�Y���������Ȃ������B��O�ɓ��t������b�������Ɠ��[�ɂ���đI���̂ł͂Ȃ��u�ېV�̌��сv��h���͊w�őI��邽�߂ɁA����ɑ��ĐӔC���̂����s���m�ł������B
�@�ۑ蕶�Ɏ�����Ă�����t���x�a�����̏́A���݂Ǝ������ʂ������Ă���B�c�@���t���Ŏ����I����邱�Ƃ������A��b�����}���̔h����A���^�}�Ƃ̊W����u�ύt�v�����ɑI��錻��B�܂��o�g������Ȓ��Ԃ̗��Q�Η���w�i�ɓ���̏Ȓ��Ƌ������т����u���c���v�̑��݁B�����ĉ�����������b���u���Q���Η������˂Ȃ���肪�������Ƃ��ɔ�������k���E�����̖����v��S���Ă��邱�Ƃł���B
�@�����A���ݕK�v�Ȏ̃��[�_�[�V�b�v�̋����́A�ߋ��̂悤�ɋ����⊯���x�z�͂�w�i�ɂ��������͂ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�O���[�o�������i��ō��Ǝ��̂����͂⋭�͂ȓ����͂��������A���̖����͂��łɎs�v�́u�����ҁv�ɋ߂��Ȃ��Ă��邩�炾�B�Ⴆ�ً}�̐����ۑ�ł���TPP����̓y���́A�{�[�_�[���X�̎���Ɂu�{�[�_�[�v����낤�Ƃ��鎎�݂ł��邪�䂦�ɁA�ȑO�̂悤�ȁu�����v�ł͉���������Ȃ̂ł���B
�@���������āA�ɂ͖�������ۑ�Ɏ��g�ޗ��`�I�ȃ��[�_�[�V�b�v���K�v���ƌ�����B�܂��u�����̒������E��@�̎w�����v�𗼗������邱�Ƃ��K�v���B��k�Ђ���̕����⌴�����̑Ή��ɂ͗��Q�����Ɩ������̒��K�{�����炾�B���Ɂu�S�̂ɑ��ĕ����������E�X�ɑ��đË��_��T��v�����𗼗������邱�Ƃ��K�v�ł���B����Љ�ł͒n��I��肪���̂܂ܓ��{�S�́A����ɃO���[�o���Ȗ��ւƂȂ����Ă���A�����̓Ɨ��Ɠ����ɑS�̂̓�����������鍇�ӌ`������ɋ��߂��Ă��邩�炾�B
�@�ȏオ���̍l������t������b�ɕK�v�ȃ��[�_�[�V�b�v�ł���B
�y���̌X���z
�@�������ɍ��킹���^�C�����[�ȏo��ł���B2001�N�x�ɑ�������w���ŏo�肳�ꂽ�u21���I���{�̐����ƃ��[�_�[�V�b�v�v�̗ޑ�ƌ�����B�W���[�i���Y���ł��悭��������e�[�}�B�����A���߂��郊�[�_�[�V�b�v�ɂ��Đ[���_���邽�߂ɂ́u�Ό��p���̓ƍٓI���[�_�[�V�b�v�v��u��O�̐��ւ̂�������v�Ȃǂ����A�����Љ�̖ڕW�𗝉����Ă���K�v������B�����������e�ō��������낤�B
�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�����w���E�Q�O�P�R�z
��P
�@�����K�������g�̒m�̓M�^�[���t�ł���B���͒��w���̍��M�^�[��e���n�߂��B�����{���Ċ�b���K�̕��@��ǂ݁A������x��B����ƍD���ȃA�[�e�B�X�g�̊y���W�����Ȃ���R�[�h���o�����B�M�^�[���t�ʼn̂����Ƃ��傾�����̂ŁA��͂����ɑ����̃R�[�h���o���邩����肾�����B�������A������x�e����悤�ɂȂ����Ƃ���Ō��E������Ă����B���܂��e�����A�����e�����Ƃ������قǁA�~�X�������Ȃ��Ă��܂��B���l����ƁA��{�̒i�K�Ő搶�ɂ��ׂ��������B�Ȃ��Ȃ獂�Z�ɓ����Ă���v���̃M�^���X�g�Ƀ��b�X�����Ă��炤�@�����A���̌��_�������Ă��炦�����炾�B���͂܂��A�S�g�ɗ͂�����߂��������B�e���߂��Ďw�߂�ɂ߂Ă��܂�����A���K��̌�����ɔY�܂��ꂽ�肵�Ă����̂��B�搶����K�v�Ȏ������A�K�v�ȂƂ���ɗ͂�����Ƃ����A�h�o�C�X���Ď��H���Ă݂�ƁA�͂���ꂸ�ɉ��t���ł��A�Z�p�����������サ���̂ł���B
��Q
�@�M�^�[�̉��t�����コ���邽�߂ɂ́A�K�ȗ͂̎g��������ł��邱�Ƃ��킩�����B���܂ł̗��K�@�ł́A�܂������������A�e���Ƃ����u�͂�����v���삩�����B�������A������m��Ȃ����S�҂͉����o�����߂ɗ͂���ꂷ���Ă��܂��B�����ŁA���̓o�C�I�����̂悤�Ƀt���b�g�Ȃ��̓d�q�M�^�[���Ă������B���̃M�^�[�ł͌����������镔���S�̂��Z���T�[�ɂȂ��Ă���B�w���G���ʒu���M�^�[�����̃}�C�N���`�b�v�ƃZ���T�[�����m���A�t�҂��ǂ̉����o�������̂��f���ēd�q����炷�B��������ʒu������Ă��Ă��A�͂��キ�Ă��A�M�^�[�̑��Łu�t�҂̏o���������v��ǂ݂Ƃ��Ă����B�܂��A�ҏW�@�\�ł������Ȃ����t���₷�������Ă����B�������邱�ƂŁA��̑召��^���@�\�̍��ق��āA���t���y���ގp�������܂��B���ꂩ��ʏ�̊y��ɖ߂�A����ēr���Ŏ~�߂Ă��܂����Ƃ����邾�낤���A�V�����y�킾�����y���ނ��Ƃ��\�ɂȂ�B
��R
�@������Ă���Ȗږ��́w���R�ȗ͂̎g���������邽�߂̐g�̂̒E�͖@�Ɠ��͖@�x�ł���B
�@���Ƃł́A���ɐg�ْ̂̋���m�邽�߂ɂR�c�X�L�����őS�g�f�[�^���Ƃ�A�W���I�f�[�^�Ɣ�r���āu�̘̂c�݁v��m��B���ɓ���ɂ��g�̕ω��ׂ�B���̍ۂ̋Z�@�́A��w�ʂł͉���Ɋւ����U�w�I�f�f�A�S���w�ʂł͓���P���Ȃǂ̊ɂ߂Ɠ��̗͂��K�A�X�|�[�c�Ȋw�ʂł͋ؗ̓o�����X��^���@�\�̑���ł���B��O�ɁA�L�������g�̒m�̂ǂ��Ŏ��R�ȒE�͂Ɠ��͂��K�v�����e�������������p����B�M�^�[�K���o���Ō����A�M�^�[�������p���⍶��ƉE��̗͂̓�����ȂǁA������ʂŕs�v�ȓ��͂���߁A�����ɂƂ��čł����R�ȉ��t�@�����o�����Ƃ��ł��邾�낤�B������ł��A�L�[�{�[�h�̑ł���������S�ȃX�|�[�c���K�@�܂ŁA�L������Őg�̒m���[�܂�Ɗ��҂ł���B
�@�Q���w�����͂Q�O�l���x�B�]���͊e�������g�ޕ���ł̋Z�\����Ɋւ��āA���C�J�n���ƏC�����̉f����g�̃f�[�^�̔�r�ōs���B����͌l�̐g�̓����ɔz�����Ȃ���s�Ȃ���B���̉Ȗڂł͊w���Ƌ������g�̓I�o�������L���Ȃ���w�э����B�g�̂͑��l����������A�����ɂƂ��ċ��ȏ��I�Ȉ�ʘ_�͒ʗp���Ȃ��B�e�l�ƌ����������ƂŁA����������u�g�́v�ɂ��ĐV���Ȕ��������A�w�������܂ŋC�Â��Ȃ����������̐g�̂�����B���̂悤�Ȋw�т̂�������������n���m�ɂӂ��킵���Ǝ��͍l����B
�y���̌X���z
�g�߂ȂƂ���Ŗ����������̕������q�ׂ�Ƃ����o��ł���B�ߋ��́u���������ō��v�i2004�N�j�A�u�����v���W�F�N�g�̊��v�i2007�N�j�A�u����̖����v�ʂ���v�i2011�j�Ȃǂɋ������т������B�䂦�ɁA�ߋ�����������Ă��ꂼ��Ɏ����̉���������Ƃ̂�����ɂƂ��Ắu�\�z�ʂ�̖��v�Ƃ������邾�낤�B
�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�@�w���E�Q�O�P�S�z
�@�ۑ蕶�ł́u�P�A�̗ϗ��v�Ɓu���`�̗ϗ��v���Η�������̂��ǂ����ɂ��Č������Ȃ���Ă���B�����̖ړI�͐��`�̎����ł��邪�A���̓��e�́u���҂̌����Ƌ������鎩��̌����̎咣�A�����̏���ƒ����v�ł���B���́u���`�̗ϗ��v�͍��Ƃ̌��͂ɑ��āu�l�v�����l���̎v�z�Ɋ�Â��Ă���B�Ƃ��낪�A�������Ǝ��J���ɏ]�����ĉƑ��O�̎Љ�Ŋ���������ɂȂ�悤�Ȍ����́A����܂Ő��`�̗ϗ��ł͐�������Ă��Ȃ������B����͌l�̍s�ׂɂ��āu���R�ӎu���������v�Ƃ�����ґ���Ő�������A�Â������I��̑��Ɉˋ����Ă�������ł���B
�@���������M�҂̕��͂́u�q�ǂ���T�|�[�g��K�v�Ƃ����l�v���u�l�v�̘g�g�݂��甲�������Ă��邱�Ƃ������Ă���B�ߑ�I�l���u�������A�����������Ȍ��肷�鑶�݁v�ł���̂ɑ��A�P�A���Ă����Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��l�X�́u���ƂɑΗ�����l�v�ł͂Ȃ��B���̐l�����̃P�A�ɐ�O����i������Ȃ��j�������܂��A���������l�Ƃ݂͂Ȃ���Ȃ��B���̂悤�Ɏ��������l�������K�肷�鎩�R��`�I���x�̉��ł́A�����̐l����������r������Ă��܂��B�K�J���̎�ҁA�H�㐶���ҁA�����ی엘�p�҂Ȃǂ��u�����ւ̓w�͂�����Ȃ��v�ƌ��߂����A�x������̂Ă��Ă���̂͂��̎���ł���B
�@�Â����R��`�I�����ς��邽�߂ɁA�u�P�A���錠���v����{�I�l���Ƃ��ĔF�߂�l�����͗L���ł���B�M�҂͂���𐳋`�̗ϗ��ɑΗ�������̂ł͂Ȃ��A���`�̌������ɂȂ��悤�Ƃ��Ă���B�u���҂ւ̋����A���Ȕᔻ�A���ア���̂ւ̎����v�Ƃ����P�A�̗ϗ����u����E�����E�\�́E�o�����A�S�Ă̐������Ȃ��v�Ƃ����s���ɂȂ��邩��ł���B
�@�u�P�A���錠���v�̓t�F�~�j�Y���̊ϓ_�����o���ꂽ�T�O�ł��邪�A�P�A�̗ϗ��̓{�����e�B�A�Ȃǁu�����I�s���ɂ���đ��҂Ɛ[�������������v�����S�ʂɒʂ����Ղł���B�����́u���R�E�{���v�ɂ��Ƒ��P�A�_�������l�ȉƑ��̂�����A�l�̌Ǘ��ɂ���ĕ��f���ꂽ�n��Љ���Đ����銈���A�����ȂǃO���[�o���Ȏ��_����̌������ȂǁA��������Č����ł�����͑����Ǝ��͍l����B
�@�y���̓�Փx�z
�@�W��
�@�y���̌X���z
�@�������N�����Ă���u���`�v�u�����v�u���x�v�̗��_�I�Č����Ɋ֘A������B �����ی쌩�����Łu�Ƒ��̕}�{�`���v�����ɂȂ�����A�m�g�j�o�c�ψ��́u�ǍȌ��ꔭ���v�ȂǁA�^�C�����[�Șb��ƍ��v������e�ł���B �ۑ蕶�̓ǂݎ��͓���Ȃ����A�Ȗ��ɑg�ݗ��Ă�ꂽ�_���Ȃ̂Łu���e�̂܂Ƃ߁v�ɏI�n���Ă��܂����ꂪ����B �_�I�Ȕ��z��ᔻ����M�҂̈ӌ���ǂݎ��Ƌ��ɁA���ꂪ�ǂ̂悤�Ȗ��ɂȂ��邩�Ƃ������p�͂�����o��ƌ����悤�B
�@ �y�����w���E�Q�O�P�S�z
�@���P
�@�`�@�����҈ӎ����琶�܂�鍇��
�@�a�@���I�ȗ��Q�����V�X�e���ɂ�鍇�ӌ`��
�@�b�@���_��������n��
�@�c�@���l�ȕ����Ƃ��Ă̐��������ݏo�������I�����E
�@�d�@�l�K�e�B�u�ȑz���͂Ƃ��Ă̂r�e����
�@�e�@�u�����v���Ƃ���n�܂�{�����e�B�A
�@�f�@�C�ݐ��Ɍ�����{�̎��R����
�@�g�@�ϑ��Ɖ����̑��݊W
�@�h�@�������������A�I���̎�
�@���Q
�@�i�P�j�d�@�f�@�g
�@�i�Q�j
�@�����e�[�}�Ƃ���̂́u�����̑��l���Ǝ��R�ȐU�镑���d���邱�Ƃ��S�̂̂܂Ƃ܂�ݏo���v�Ƃ����l�����ł���B�`�Ƃa�͕����̎����I���������Q�����V�X�e���ނƂ������e�B����̗���d����Ƃ����e������Ɋ֘A����B�c�͐������l���������I���𐬗�������Əq�ׁA�h�͂����������̈���Ɛl�Ԃ����̗��v�̑I����₤���e�ł���B�����̋��ʓ_�͎v�z�ɂ���Đl�Ԃ̍s�����ς�邱�Ƃł���A�b�͂��̍����������Ă���B�����ɑ��A�d�̃l�K�e�B�u�ȑz���͂ŏ������r�e�����A�f�̓��{�ɂ�����C�ݐ��̉����A�g�̃I�]���z�[�������̌o�܂́A��������u�����ƑS�́v�Ƃ�����肪���m�łȂ��̂Ŏ��͍̗p���Ȃ��B
�@���R
�@���̖{��ҏW���邱�ƂɂȂ��āA�����e�[�}�Ƃ��čl�����̂́u�����̑��l���Ǝ��R�ȐU�镑���d���邱�Ƃ��S�̂̂܂Ƃ܂�ݏo���v�Ƃ������Ƃ��B���N�͑�ꎟ���E���̎n�܂肩��S�N�ڂł���B���̈ꐢ�I�A���E�͕���A���ւ̌�����̌������B�ߑ㉻��i�߂鑽���̍�������̓Ǝ������咣���ċ��������A���ɂȂ������B���̔��Ȃ��獑�ۘA�������܂ꂽ���A����͋����̗��v�z����c�ł������B����E���͖h�����A���̐��E�ł������Η��Ɍ�����D��Ɨ��v���D�̋������������B
�@������20���I�̏I�ՁA���E�͐V���Ȗ��ɒ��ʂ����B����͒n�������ł���B���̉���������̂́A��f���̎��_�Ō��鎞�A��C��C�m�ɂ͋��E���Ȃ����Ƃł���B�܂�A�����ł́u���̖��v�Ɓu���҂̖��v�͏�ɘA�����A�l�ނɂƂ��Ăǂ���u�������̖��v�Ȃ̂ł���B����̍��ۘA���́A�{�����͓�����h���ړI�ō��ꂽ�B�������A����̉ۑ�͒n��������邽�߂̘A���ł���B
�@���̕S�N�ԁA�����́u���������̗��v�����v���Ƃ������������B�����A�n�����͑����̐������݂��ɐ[���ւ�荇���Ȃ�������ۂ��Ă���V�X�e�����B�u���l�ȕ����Ƃ��Ă̐��������ݏo�������I�����E�v�̏͂͂����������Ă���B�l�Ԃ͋ɂ߂ė��ȓI�ł��邪�A�b�������ċ��͂��邱�Ƃ��ł���B���̍ۂɑ�Ȃ̂́u�������v�ӎ��ł���B�u�����҈ӎ����琶�܂�鍇�Ӂv�u�w�����x���Ƃ���n�܂�{�����e�B�A�v�̏͂͂��̎���ł���B�e�l�̈قȂ������Q��F�ߑ��d����A���v�d���̊�Ƃ��������̖��Ƃ��Ċ������l����B����́u���I�ȗ��Q�����V�X�e���ɂ�鍇�ӌ`���v�̏͂Ŏ������B
�@�������́u�������������A�I���̎��v���}���Ă���B�������A����͕S�N�O�́u�������������c�邩�A�������ɕ��]���邩�v�Ƃ����x�z�W�̑I���ł͂Ȃ��B��l��l�������ōl���A���R�ȑI�������A�������n���S�̂����肵�Ď������{�����Ԃ��ǂ��������邩�̑I���ł���B�u�������Ɨ����Ȃ���S�͈̂��肵�Ă���v�悤�ȗL�@�I�Љ�̎����͕s�\���Ƃ����ӌ������邾�낤�B�������u���_��������n��v�̏͂ɂ���ʂ�A���_�ɂ���čs����ς���̂��l�ԂȂ̂ł���B���A���̖{��ʂ��đ�ꎟ��킩��S�N�ڂ̔N�ɁA���ꂩ��́u�n���Ɛl�ԁv�̕S�N��ǎ҂ɍl���Ăق����B���ꂪ���̊肢�ł���B
�@���S
�@�w�S�N�ڂ̌������@��l��l�ƒ��a�I�S�́x
�@�y���̓�Փx�z
�@�W��
�@�y���̌X���z
�@�N�x�ɂ���ẮA�����w���̕����ۑ蕶��S���ǂޕK�v�̂Ȃ����Ƃ�����B���������N�͂��ꂼ��̕��͂Ɍ��o�������A�֘A���l���Ď����Ȃ�ɕҏW����Ƃ����ۑ�ł���B�ۑ蕶������킯�ɂ͂����Ȃ��B�u�ҏW�H�w�v�ƌĂ�镪��̖��ƌ����Ă��悢�B����͂Ȃ����A���ԂƂ̐킢�ɂȂ�B�lj�͂Ƃ܂Ƃ߂�́A�����̎咣�̕����I�_����T������͂ȂǁA�����I�ȕ��͗͂����������͎�`�I�Ȗ��ł���ƌ����悤�B
�@
�y�@�w���E�Q�O�P�T�z
�@�u�������l���v�͐�����̕ۑS�̕K�v���Əd�v�������N���錾�t���������A�������l��������Ɓu�ۑS�v�Ɓu���p�v�Ƃ����ړI�̑Η��������яオ���Ă����B����͐�����́u���L���Y�v�Ƃ��Ă̑��ʂƏ��L�E���p�����u�����v�Ƃ��Ă̑��ʂ̑Η��ł���B���ꂪ��i���Ɠr�㍑�̑Η��Ƃ��Č��݉����A�u���v�̌������t���Ȕz���v�Ƃ�����O�̖ړI�����ꂽ�B���̌�u���p�v�̑��ʂ����������悤�ɂȂ�A�������l���̓O���[�o���ȏ��i�Ƃ��Ă̌o�ω��l�E�������l�Ř_�����Ă���B�������A�������l��������Ă����S����͒n��Љ�ł���A�����ŔF�߂��Ă����͎̂g�p���l�ł���B�������݂̂Ȃ���ɉ��l������悤�ɁA�n�摊�݁E�n��Ɛ��E�̊W���d�v�ł���A�e�n��Љ�������l���̕ۑS�E���p�̎�̂Ƃ��ĖL���ɂȂ�ׂ��ł���B�������琶�܂�鉿�l�́u�W���l�v�ł���A����͒n��E���E���邢�͐��Y�ҁE����҂��Ȃ��邱�ƂŖL���ɂȂ鉿�l�ł���B
�@�M�҂̏q�ׂ�u�W���l�v�́A�ߑ�I�v�l�̑傫�Șg�g�݂����������z�ł���B�������琶�܂ꂽ�ߑ㍇����`�͎Љ�͂��āu�l�v�Ƃ����ŏ��P�ʂ����o���A�l�̎��R��~�]�̏[����D�悵�Ă����B���ꂪ�������l�����낤������o�ϔ��W�̌����͂ł��������B�������A�����I�ɖL���ɂȂ�������Љ�ł́A�n��Љ��Ƒ��̌��т����キ�Ȃ��Ă��܂����B��l��l�̌l������Ίm���ɑ��l�ł͂��邪�A�l�ԓ��m�̂Ȃ���͊ɂȂ�A�n���Ɠs��̋�ʂȂ��l�X�͌Ǘ����Ă���B�o�ϐ����ȊO�̐�����Ӗ����������A�������̖L�����A�܂�W���l�������Ă���̂ł���B
�@���{�ł́A���̓�\�N�Ԃɍ�_�W�H��k�ЂƓ����{��k�ЂƂ�����x�̎��R�ЊQ������A�u�Ȃ��邱�Ɓv�̈Ӗ����Č�������Ă����B���̔����I�ɂ킽���Čo�ϐ������Љ�̖ڕW���������A���ꂪ��~�������A�����d�v�Ȃ̂��l������Ȃ��Ȃ����̂��B�u�n�拻���v�u���v�Ȃǂ͌o�ϖ��Ƃ��Ę_�����邱�Ƃ������B���������̖{���́u�Ȃ���̉v�ł���B�R�X�g�̕��S�ȑO�ɁA���҂̐�������z�����A���҂��x���邱�ƂŁu�����͉��̂��߂ɐ�����̂��v�����o����_�@���^�����邱�Ƃ��d�v���B���ꂪ�W���l�̉ɂȂ���Ǝ��͍l����B
�y���̓�Փx�z
�W��
�y���̌X���z
�������N�Ƃ͂��Ⴄ�A�Љ�W��₢�������B�ۑ蕶�͎��R�ی�̋c�_�����A�Љ���ɂȂ��čl����Ƃ��낪�|�C���g�B���V�O�N�A��_��k�ЂQ�O�N�Ƃ����ߖڂ̔N�炵�����ƌ�����B
�y�����w���E�Q�O�P�T�z
�ݖ�P
�`�@�u��ւ̊v���v�@���]�Ԃ��n��l�͎Ԃ��ߋ��̂��̂ɂ���
�a�@�u�C���^�[�l�b�g�S�O�N�v�@�g���肪����Ƃ����V�X�e���̒a��
�b�@�u�����̂̃r�b�N�o���v�@�V���R�����l�ނɐV��������^����
�c�@�u����̖��p�v�@�z�����`�ɂȂ�R�c�v�����e�B���O
�d�@�u���_����n���ցv�@���T�C�N���͎�̉\�����Ĕ���������
�e�@�u�Ⓚ�Ŏ��Ԃ��~�߂�v�@�H�i�ۑ��̊v���Ɗ��ւ̕���
�f�@�u�Z�L�����e�B�Љ���x����v�@�Í��Z�p���l�b�g���[�N�̈��S�������
�g�@�u��������N�ƉƁv�@���z�̓]���ŃR�X�g�̂�����Ȃ����ʂ�����
�ݖ�Q
�y�ۑ�̈�z
���z�̕s����
�y�������̖��z
�@���E�o�ςɂ����āA�H�Ƃ��\�Ƃ��ĕ��z�̕s������肪�����Ă���B��i���ł͐H�c���������H�i����ʂɔp������Ă���̂ɁA�r�㍑�ł͖����I�ȉh�{�s�ǂ�쎀���������A�����ɐ��܂ꂽ�l�X�̕��ώ��������������Ă���B���������n���̓e���ɂ��������ւ̎x�������߁A�S���E�I�ȎЉ�I���S�̊�@�ɂ��Ȃ���B
�ݖ�R�|�P
���E�͑��ς�炸�n���ƃe���̉����ɋꂵ��ł��܂��B���������P�ւ̌��������Ă��܂����B����30�N�A���́u�������V�X�e���v�y�����邽�߂ɐ��E30�J���Ŋ������A�����̒��Ԃ邱�Ƃ��ł��܂����B�H�ƁE�G�l���M�[�E�ی��E����������邱�Ƃɂ���āA�n���͖{���ɂ݂�Ȃ̂��̂ɂȂ�̂ł��B
�ݖ�R�|�Q
�@�����r�e�b�̊w�����������A�ً}�̉ۑ�͊i���g��Ɩ����ʃe���ł����B���̓�ɂ͖��ڂȊW�����邱�Ƃ����͑�w�ł̍u�`�⌤����Ŋw�сA���ۂɓ�Ă֗��s���ăX�g���[�g�`���h�����̕ی�{�݂�K�˂�Ȃǂ��A���������̖ڂŊm���߂܂����B�������̂��߁A���͂ł��邱�Ƃ���n�߂܂����B���ƌ�܂��m�o�n�̐E���ƂȂ�A�����ی����l�����̎x���ɏ]�������̂ł��B�����Œ��ʂ����̂́u�\�Z�s���v�ł����B�����Ŏ����ڂ������̂́u�������v�ł��B�C���^�[�l�b�g������قǕ��y�������_�ɂ́u�����̎�M�E���M�v�Ƃ�������������܂����B�l�b�g�̃R���e���c���u���������v�ɒu����������ǂ��ł��傤���B�H�ƁE�G�l���M�[�E�ی��E����T�[�r�X�����ł���A�n���ɋꂵ�ސl�X�ɑ傫�Ȏx����ł��܂��B
�@���͂���܂Ńo���o���ɍs�Ȃ��Ă����t�[�h�T�|�[�g�E���R�G�l���M�[���p�E��Ã{�����e�B�A�E����{�����e�B�A������v���b�g�t�H�[�����l�b�g��ɍ��܂����B�����̓j�[�Y�̑����ɔ�ׂĒł��鎑����l�ނ����Ȃ��̂ł��B�����Łu�Љ�̕��Y���v��O��I�ɉ�����A���銈�����n�߂܂����B���i�ɂȂ�Ȃ��H�ށA�����H���ŏo��M�A�^�̌Â��@��A���i���������Ă��Ȃ����ƂȂǁA�Љ�ɂ͑����́u�]�́v������܂��B���������]�͂��u����Ȃ��l�X��n��v�ɕ��z���邱�ƂŐ��������̖�����������ɍL�����Ă��܂����B�ŏ��A��Ƃ͔͓I�ł������A�V�X�e�����u�����v�Ƒ�����ΈႤ�������ł��܂��B�Ⴆ�ΗA������H�A�l�ޔh���̔�p���S������A���p����l�X�Ƃ̊ԂɁu�V�����W�v���\�z����܂��B�i���Љ�ł͂��肦�Ȃ������u�l�ԂƂ��������̑Η��v���N����̂ł��B����ɂ���Ċ�Ƃ̑����u�V�������z�v�u�V�����s��v���J�邱�Ƃ��ł��܂��B���͊�Ƃ͍�����������A���ꂪ�V�X�e���̌����͂ɂȂ��Ă��܂��B
�@���u�������V�X�e���v�͍������z���A�O���[�o���ɗ��p�������܂��B���E���̕n�����l�X���[���ɐH�ƂA�d�C�Ȃǂ̃G�l���M�[���g���A�l�b�g�ŋ�����A��Ñ��k��f�@���l�b�g����n�܂�܂��B����͂����Ɛl�����A�u�l�ޗ����̖������v�������������ƍl���Ă��܂��B�����鎑���������ɕ��z����A�u��������\�͂ɉ����ē����A�K�v�ɉ����Ď��v�悤�Ȑ��E�͖��łȂ��A������Ƃ���ɂ܂ŗ��Ă���̂ł��B
�y���̓�Փx�z
�@����
�y���̌X���z
�@��N�́u�ҏW�v���̉��p�B���N�����ꂼ��̕��͂Ɍ��o��������ۑ肾���A�R�O�N���z�肵���u�����������Ƃ����V�����o��@�ł���B��ƂƂ��ē���킯�ł͂Ȃ����A���ԂƂ̐킢�ɂȂ�B��������w�ʼn����������̂��A��̓I�ȍ\�z���Ȃ��Ǝ��ԓ��Ɏd�グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�ߋ���Ɏ��g��Ŏ��ۂɏ����Ă݂���K�����ɏd�v�ł���B
�@
�i�b�j
�y�X�Q�E��II�`�E��P��z
�ݖ�i�P�j
�ݖ�i�Q�j
�y�X�Q�E��III�E����i�`�j�z
�@�u�ٕ��������v�ɂ͂������̑��ʂ����邱�Ƃ�M�҂͎w�E���Ă���B����͏�ʂɑΉ������s���l���̔F�m�E�s���̎��s�E��̋��L�Ƃ��Ă܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��邪�A�ٕ����ɐڂ��ē��Ɂu�����v������Ȃ̂́u��v�̑��ʂł���B�M�҂ɂ��A����́u��v���e�l�̐����Ă���Ӗ���Ԃƌ��т��Ă��邽�߂Ȃ̂ł���B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�R�E��III�E����z
�i�`�j
�i�a�j
�y�X�R�E��III�E�����z
�i�b�j
�i�c�j
�y�X�S�E��II�`�z
�ݖ�i�P�j
�ݖ�i�Q�j
�ݖ�i�R�j
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�S�E��III�E����z
�`
�a
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�T�E��I�E����z
�@�ۑ蕶�̎咣����������A�u�ꍑ�̎s���Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�v�̕���Ƃ�����肪������ł��낤�B�u�ꍑ�̎s���Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�v�́A�ߑ�I�ȍ������ƂƋ��Ɋm���������A�������Ƃ̌`�����ߑ�I�ȍH�Ɖ��ƌ��т��Ă������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�������A�ߑ�I�H�Ɖ����Љ�ɋy�ڂ��ώ����E��ꉻ�̈��͂́A�����Ɂu�ߑ㉻�ɂ��A�C�f���e�B�e�B�̔ے�v�������炵���B�܂�A�������Ƃ��x����u�ꍑ�̎s���v�Ƃ����[���́A�ٕ����ɑ�����҂̓�����O��Ƃ��A�����ł��Ȃ��ҁA���������ۂ���҂̃A�C�f���e�B�e�B�͔ے肳�ꂽ�̂ł���B
�y�X�T�E��III�E����z
�_��c�Ƒn���͋���ŐL���邩�B
�@�s���̓��{�̋���œ��ɏd�������悤�ɂȂ����̂́u�Ƒn���v�ł���B��w�����̋������������Ȃ�A�l�ߍ��ݎ��̈ËL�w�K���s���ɂȂ��Ă�����A�u�Ƒn���v�d���̐��͐₦�邱�Ƃ��Ȃ��B���́u�Ƒn���v���x����̂��n���͂ł��낤�B�]���āA����ɂ����āu�Ƒn���v���d�������ȏ�A����̖ړI�̈�́u�n���͂�L���v���ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�ۑ蕶�ɂ��ƁA����͉E�]���悭��������P��������Ƃ������Ƃł���B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�U�E��II�`�E��Q��z
�ݖ�P
�ݖ�Q
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�U�E��III�E����z
�@�`
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�V�E��III�E����z
�@���j��̐l���̔����Ɋւ���Η��́A�ۑ蕶�ł́A�����̐l���̍s�����u���E���_�̋Ɩ����s�v�Ƃ��čm��I�ɑ����闧��ƁA�ނ�̍s�����u�ϔY�E�~�]�ɍ������A�ʔO�E���K�����E�����s�����ȍs���v�Ƃ��Ĕے�I�ɑ����闧��̑Η��ł���B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�W�E��II�`�E��Q��z
�ݖ�i�P�j
�@�ߋ��̗��j���ӂ�Ԃ�A�Q�[�̎�Ȍ����͓V��s���ɂ��s��ł������B����͂܂��ɓV�Ђł���A�l�ׂɂ��Ώ��͓���B�������A�x���K���Q�[�ł͐H�Ƃ̐��Y�ʂ����������̂ł͂Ȃ������B���Ƃ��H�Ƃ��[���ɂ����Ă��A������Ȃ���Q���Ă��܂��B�܂�A�n�x�̍����ɒ[�Ɋg�傷�邱�Ƃɂ���Ă��A�Q�[�͋N����̂ł���B����̎Љ�ŕn�x�̍����L����v�f�ɃC���t���[�V�����⎸�Ɨ��̑��傪���邪�A�����͌o�ϓI�Ȑ����Љ���I�Ȑ���ɂ���đΏ��\�ȗv�f�ł���B�������A�x���K���Q�[�ł͂��̂悤�ȑƂ��邱�Ƃ͂Ȃ������B����䂦�A�Љ����Ȃ��������߂ɐ������Q�[�́u�Љ�I���s�v�ł���ƌ�����B
�ݖ�i�Q�j
�@�Љ�Ƃ́A�o�ρA�����A���x�A���R���Ȃǂ̏��v�f���[���ւ�肠�����g�D�ł���B�u�o�ϊJ���v���Nj�����鎞�́A�����������̂悤�ȁA���ۉ����ꂽ���ʂ������ڕW�ɂȂ�B����́u���ς���ƍ����͖L���ɂȂ����v�Ƃ����l�����ł���B�����A���ۂɂ͌���A�@���A�g�����x�ȂǁA���j�I�����I�Ɂu�Љ�I���فv�ݏo���Ă����v�f�͐���������B�����͕������x���A�`���I�Љ�̒��ɐ[�����荞��ł���v�f�ł��邾���Ɍ����ɂ����A�܂��ω����ɂ����B�����̗v�f���o�ςɔ��f�������̂��o�ϓI���ʂ�n���ł���B���������āu�o�ϊJ���v�͂܂��Љ�I�ɗ}�����ꂽ�l�X�ɉe����^����̂��Ƃ������_�́A�Q�[�Ȃǂ�h���Ƃ����_�ŏd�v�ł���B
�ݖ�i�R�j
�@�o�ϊJ���̖ڕW�́u�ߑ㉻�v�ł���B����͓`���I�ȎЉ���u�Â��Љ�v�ƌ��Ȃ��A�������̂��āu�V�����Љ�v����낤�Ƃ��铮���ł���B�`���I�ȎЉ�ɂ́A�@���⌾��A�g���Ȃǂ̈قȂ鑽���̎Љ�W�c�����݂���B����炪���l�Ȃ܂܌Œ艻����Ă���̂��u�Â��Љ�v�ł���B����ɑ��āu�ߑ㉻�v�̓����́A�����Ȓn��ɕ��U�����Љ�W�c�����đ傫�ȁu���v����낤�Ƃ���B���x��́A�����ɂ͒n��ɂ�鍷�ʂ͂Ȃ��A�����̓����ɏZ��ł���҂͂��ׂāu�����v�Ƃ��Ĉ����A�u�����v�Ȍ��������B���������ۂɂ́A�ߑ㉻�ɂ���Č��������͕������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��A�`���I�ȎЉ�I�E�����I���ق͎c��B���ꂪ����ł͌o�ϓI���ʂ��܂߂ĎЉ�ɍ��������ʂƂ��Ă�����A��������ł͍��Ƃɂ��Љ�W�c�̑��l���̔ے�Ƃ��Ă������B�ۑ蕶�́u���Â���v�Ɓu�����Â���v�́A���̂悤�ȋߑ㉻�̈��́A�J���̈��͂�\���������t�ł���B
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y�X�X�E��II�z
��P��
�ݖ�i�P�j
�@�N���E�[���B�b�c�́u��ΓI�푈�v�T�O�Ƃ́A�푈�������Ɂu�Ɨ��������ہv�Ƃ��đ����A�������闧��ł���B�����ł͐푈�͐����I�ړI�̂��߂̎�i�ł���A���̓���Ƃ��āA���̗v�f����藣����Ă���B�N���E�[���B�b�c���푈�̎�i�Ƃ��Ă̑��ʂ��Ή������ۉ����đ������̂́A���Ƃ��������ƂƂ��Ĉ�ʉ�����A���͂ȍ������ƌ`���������̕��ՓI�ړI�ƍl����ꂽ����w�i�Ɋ�Â��Ă���B����ɑ��āA�J�C�����͐푈��l�ԑ��݂́u�S�̐��v���瑨���Ă���B����́A�푈���l�Ԃ̖{���ɍ��������̂ł���A�����E�o�ς̗̈�Ɍ���ł��Ȃ��u�Љ�I�E�����I�ȑ��́v���Ƃ����l�����ł���B�J�C�����̐푈�_�́A�l�Ԃ���芪�����E�̗l�X�ȃV�X�e�������݂Ɋ֘A�������A�u��ΓI�Ȋ�v�Ƃ��Ă̊w�₪�s�\�ɂȂ������ォ�琶�܂�Ă����ƌ�����B��̐푈�_�̑���́A�푈�̎��ȖړI���ł��錻���́u���E�푈�v�f���Ă���Ƃ��l������B
�ݖ�i�Q�j
�@�u�q���[�}�j�X�e�B�b�N�Ȕ���_�v�Ƃ́A�푈�ɔ����\�́A�E�l�Ȃǂ��ϗ��I�Ɂu���v�ł���A����䂦�Ɂu��l�ԓI�Ȃ��́v�ł���Ƃ��Đ푈�ɔ�����c�_�ł���B���҂����ɂ��Ă���̂́A������������_���푈���u���݂��ׂ��łȂ����́v�Ƒ����A�ߋ��ɋN����A�܂����N�������푈��ے肷�邱�Ƃɂ���āA�l�Ԃ́u�l�ԓI�c�݁v�̈ꕔ�ɑ��Ȃ�Ȃ��푈�ɂ��Ă̍l�@����������Ă��܂��Ƃ������Ƃł���B
�ݖ�i�R�j
�@�Ⴆ�u���R�v�Ɓu�����`�v�𐭎��̗��z�Ƃ��Ă�����̐��������ɂ��čl����ƁA�����Љ�̕s���𐳂��A���`����������Ƃ����Ӗ��ł́A���̊����̖ړI���̂́u�P�v�ł���B�������A���Q�W�̑Η�����W�c���o��A���҂͎����̑��́u�P�v���咣����B���̎��A�P�Ȃ�ړI�����Ɍ����ďW�c�̍s�������邽�߂ɁA�ړI�́u���Ղ̌����v�Ƃ��Đ�Ή������B��x�ړI����Ή������ƁA��������������i�́u�ړI�����̂��߂ɂǂ�قǗL�����v�Ƃ�����ł̂ݕ]�������悤�ɂȂ�A���ꂪ�ǂ�Ȃɖ\�͓I�Ȃ��̂ł���i���̂̐������͖��ɂȂ�Ȃ��Ȃ�B�������āA����̃z���R�[�X�g�E�j�g�p�Ⓦ���Η�����̊j�e�������A�܂��ŋ߂̖��������ł̑�ʋs�E�ȂǁA�u�P�v�ł������͂��̓��@����A�R���g���[���ł��Ȃ��푈�����܂�Ă��܂��B�C�f�I���M�[�̑Η����I���A���l�ȁu�P�v�����蓾�錻��́A�ނ���u���E�푈�v�̊�@�̎���ł���B
��Q��
�ݖ�i�P�j
�@���{�̑啔���̏����͍����w�Z�܂ł̋�����I���Ă���A�E����B�������A�Q�O�Αォ��R�O�Α�ɂ����Č����ɂ���đސE���A�玙�Ɏ肪��������Ԃ͏A�Ƃ��Ȃ��l��������̂��A���̐�i���Ɣ�ׂ�ƍۗ����������ł���B���̔��ʁA�q���������E����������Ă���N��ł͏A�Ɨ����オ��A���̐�i���ł͔N�������ɓ���l�������U�O�Α���z���Ă��A�Ȃ�����������l�̊�������r�I�����ƌ�����B
�ݖ�i�Q�j
�@���{�ɂ�����j���ʒ����i���Ə����̔N��ʘJ���͗��̊W���l���邽�߂ɂ́A���{�����̏A���Ă���E�Ƃ̑啔������Ƃł̒��J���ł��邱�ƁA���{�̒����̌n���I�g�ٗp�ƔN�������O��Ɍ`������Ă������ƁA���{�̉Ƒ��ł͈玙���܂މƎ��J���̑啔�����������S���Ă��邱�ƁA�Ƃ����O�������l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏�������A�����i���͊�Ƃ̏����J���͌y�����琶����ƌ�����B����́A�A�E�㐔�N�Ō����ސE���鏗���Ɍ��C�̎�ԂƔ�p�������Ă��A�����闘�v�����Ȃ����߂ł���B���̏����ɂ���āA�����ɂ��E���̒��f�������i���ݏo�������ɂȂ�B�Α��N���ɂ���ď�����������̌n�ł́A���r�ސE�E���r�̗p�����������̒����͒Ⴍ�Ȃ�B��O�̏����͊�ƂɂƂ��Ắu������I�v�ȗv�f�Ƃ��đO�̓�̏����ɂ��i�������߂�Ƌ��ɁA�u�Ƒ��ŗB��̓�����v�Ƃ��Ă̒j���ɁA������葽���̒����z��������Ƃ����l�����ɂȂ���B
�ݖ�i�R�j
�@�P�W�W�O�N���̒n�������ł́A��ȏA�Ƃ̏�͔_�Ƃł������ƍl������B��ȘJ���̏ꂪ�_�Ƃ��邢�͏��Ƃ�Ɠ��H�Ƃ̎���ɂ́A�d����Ɖƒ낪�ߐڂ��A��������Ƒ����Ǝ��S�������A���ƂƉƎ��Ƃ����َ��̎d���𗼗������邱�Ƃ��\�ł������̂ŁA��������v�ȘJ���͂ł������B���̐�i���Ɣ�ׂĂ��N��ʂ̘J���͗��͍����A�u���C�Ȃ����͓����v�̂����ʂł������ƌ�����B�������A�Y�ƍ\�����ω����Đ����ƁE�T�[�r�X�Ƃ���̂ɂȂ��Ă���ƁA�����������߂��ƌ����̏�Ɂu�d�����ƒ납�v��I�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A���������͐��Y���ꂩ��藣����Ă������B�����Łu�j�Ƒ��v�ւ̕ω����i�s���A�Ǝ��̒S���肪��ƂɈ�l�ɂȂ�ƁA���������́u��Ǝ�w�v�ɂȂ炴��Ȃ��Ȃ�B����ɁA�������x����������{�݂̕s�������̌X�����Œ肷��B����́A�A�����J��X�E�F�[�f���ŏ����̎Љ�i�o���i�ނƋ��ɁA���ē��{�Ƃ悭���Ă����玙���Ԃ̘J���͗��̒ቺ�������Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����킩��B�������āA���{�����̘J���͗��͕S�N��ʂ��đS�̓I�ɒቺ����Ƌ��ɁA�����E�玙���Ԃ̘J���͗������ɒႭ�Ȃ���������悤�ɂȂ����̂ł���B
�y2000�E��II�z
��P��
�ݖ�i�P�j
�ݖ�i�Q�j
�ݖ�i�R�j
�y2001�E��II�z
��P��
�ݖ�i�P�j
�ݖ�i�Q�j
�ݖ�i�R�j
���T�]
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y2002�E��II�E��P��z
�ݖ�i�P�j
�ݖ�i�Q�j
�ݖ�i�R�j
���T�]
���͂����灨��X�[�~�i�[��
�y2002�E��III�z
�@�u�v�l�ƃ��m�̋��E�Ƃ��Ă̕����v
�@�O�̍�i�ɋ��ʂ���v�f������B����́A�ǂ̍�i���u���m����v�l�������オ���Ă�����E�_�v�ɂ��ĕ\�����Ă���Ƃ������Ƃł���B�����Łu���m�v�Ƃ͎��ȂƋ�ʂ����Ώې��E�̑��݂��w���A�u�v�l�v�Ƃ͎��Ȃ̈Ӗ��Â��ɂ�鐢�E�̔c�����w�����Ƃɂ���B
���T�]
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y2003�E��II�z
�ݖ�P
�@���{�Љ�̃����g�N���V�[�́u�g�[�i�����g�^�l�����f���v�ɂ���Ďx�����Ă���B���̃��f���͐₦���n�ʏ㏸�̂��߂ɑI����K�v�Ƃ��邪�A���̌��ʁA�����ڕW�����ڐ�̐����c�肪�d������A��S��ڕW�̑r�����N�����Ă���B���ɑ吳���珺�a�����ɂ����āA�w���̕w���@�������̖�S�����ڑO�̊w���l���ɂ���ւ��A�̎��ȖړI��������ꂽ�B�����A�E�Ƃ̑��l�����Ȃ��Ȃ��ċ��^�J������ʉ�����ƁA�g�[�i�����g�^�l�����f���̓T�����[�}���E���f���Ƃ��Ď��̐l�����f���ɂȂ����B�T�����[�}���̐����ł͋@�B�I�Ȏ������d���̒��S�Ŗ��m�ȐE�ƈӎ������܂�ɂ����A��������Бg�D���ێ����邽�߂ɂ͋��������d�������B����̓��{�ł́A�������Ė��ړI�Ȏ��ɐ����o���l�ԑ����T�����[�}���^�l�ԑ��ƑΉ����Ă���B
�ݖ�Q
�@�E�ƃ��f���Ƃ́u�����������ǂ̂悤�ȐE�Ƃ�I�����邩�v�Ƃ������@�ɂ���Đ��藧���f���ł���B����̐E�Ƃɂ͓���̒m���ƋZ�p���K�v�ł��邩��A���������m���ƋZ�p��g�ɂ��邽�߂Ɂu�ǂ��ʼn����w�Ԃ��v����������u����̊w��Ƃ�����C�s����w�Z�v���d�v�ɂȂ�B����ɓ���̐E�Ƃ͎Љ�ł̖��������m�Ȃ̂ŁA�������ǂ̂悤�ɂ��̖�����S���ׂ����Ƃ����s���ڕW�����m�ŏd�������ׂ����̂ɂȂ�B
�ݖ�R
�@���͓��{�^�����g�N���V�[�̒�b���h�炬�͂��߂��Ƃ����M�҂̌����ɁA��{�I�ɂ͓��ӂ���B�M�҂��w�E����悤�ɁA���{�̃g�[�i�����g�^�Љ�͎����ƃT�����[�}���̒n�ʊl���������A�����邱�Ƃɂ���Ďx�����Ă����B�u�������т��Ƃ�A�����w�Z�i�w����v���Ƃ́u������Ђ֏A�E���A���ʂ܂Ŋy������v���ƂƘA�����Ă����̂ł���B�������A���̘A�����̍����ł������u�I�g�ٗp�v�Ɓu�N������������x�v��������B�I�g�ٗp���N������������A�܂��c��̐���̏��i�E�ސE���x������ƌo�c�ɋy�ڂ����͂��_�@�ɕ��n�߂��B��Ƃ͒����Ј��ɕ����̏������f����I����������A���ѕ]���������x�����Ă���B�����ł͐l���̍���Ə��q�����u���y�ȘV�㑜�v������A�����̐l���ސE��̐l���ɕs���������Ă���B���݂̕s�i�C���u���X�g���v�Ȃǂ̌`�ŃT�����[�}���̗��z���j����������Ă���̂͌����܂ł��Ȃ��B�������ăT�����[�}���E���f���͍�������������B�������A�u������w�֓���Ηl�X�ȃ`�����X�����肻�����v�Ƃ����̎��ȖړI���̍\���ɕω��������Ȃ�����A����N�̐l���v�̓��@���u�����ڕW�v�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��Ǝ��͍l����B
���T�]
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y2003�E��III�z
�@�`�a�b�O�̕��͂ł́A�u���m�ȏ��v�̖{���Ɋւ���l�@���q�ׂ��Ă���B�����ŋ��ʂɎw�E����Ă��邱�Ƃ́u���������́A���������Ȃ����ƂƂ̗������琶�܂��B�v�u���m�ȏ��̖{���͗��m�̐����������������ł���B�v�Ƃ�����_�ł���B
���T�]
���͂����灨��X�[�~�i�[��
�y2004�E��II�z
�ݖ�P
������`�S���̂P�X���I���ɁA���ی�ɂ�鐢�E���a��ڎw�����G�X�y�����g��̉^�������ł���B
�ݖ�Q
�v�z�͐키�ׂ��G�̔ᔻ�Ƃ��Đ���������̂ł���A�G�̕ω����v�z���̂�{���I�ɕς��Ă��܂��Ƃ������ƁB
�ݖ�R
�v�z�Ƃ͓Ǝ��̎��_�Ő��E�����߂��v�z��z���B����ɑ��A�v�z�����l�͍��̐����̓����ɍ��v�������Ȋ����̎v�z��T���A���H���A�����̗e�Ղȏ��i�Ƃ��Ē���B
�ݖ�S
�u���ׂ��ׁv�́A�v�z�����l����`����V�����������v�z�Ƃ��ォ�猤���e�[�}�Ƃ��邱�Ƃł���B����́A�[���l�@�ɂ��v�z�̏n�������Љ�̕ω����������߂ɋN����B
�ݖ�T
���͉������̏ƌ��݂͎̏��Ă���ƍl����B�u���Ă鍑�v�Ɓu�������鍑�v�̑Η��͓�k���ɁA�u�����`���Ɓv�Ɓu�S�̎�`���Ɓv�̑Η��̓e���x�����Ƃɑ���킢�Ɏp��ς������������炾�B���풼�O�ɂ́A���Ă̑卑�Ƌߑ㉻�㔭���ł�����{�Ȃǂ̗��Q���Η����A�u����̎��R�ƓƗ��͕��͂ŏ�����邵���Ȃ��v�Ƃ����v�z���o����푈�ɓ������B���l�ɁA����̃e���́A�����I�o�ϓI�ɍ���������u�������鍑�v�̒�����A�i���ŗ��v���i���ɑ��Č�����ꂽ���ӂł���B�����b�������⋦�͂ɂ���ĉ��������A�u�\�͂ɂ͖\�͂őΉ�����v�Ƃ���������Ƃ�Ȃ�A�u�哱�v�z�̗\�蒲�a�v���܂��ߋ��ƈ�v����B
���T�]
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y2004�E��III�z
�u����Љ�ɂ����鋳�{�̈Ӌ`�v
�@���͌���Љ�ɂ����鋳�{�̈Ӌ`���l�@�������B
�@�`�a�b�O�̕��͂́A���Ɂu����̖ڕW�v�Ƃ��āu��Ȃ����Ɓv�u�S�̐��v�������Ă���B����͌ÓT�̉��߂╶�|�ɕ��Č`�[�������w����u���Ȃ��w��v�Ɣᔻ���A����܂ŏd������Ă��Ȃ���������̖��ɗ��w����u���w�v�Ƃ��Ē��Ă���B�a�҂͈�ʋ��{��l�ԓI�����Ɖ~�n����������̂Ƒ����Ă���B���R�ɐ��܂��Փ��E�~�]�ɕ炸�A�u�S�I�ɐ����鐶���v���������邽�߂ɁA���ɐN���Ɂu���{�v���K�v�Ȃ̂ł���B�A�[�����g�͋���̓Ɨ����ƈ�ʐ����咣���A��҂��u���肳�ꂽ�����v�ɓ����u��剻�v�Ƃ͋�ʂ��āA�u�S�̂Ƃ��Ă̐��E�v��������u����v���d�v���ƍl���Ă���B
�@�������A�����̎咣�́A���ꂼ��قȂ����w�i�����B����̎���͓��{�ɂƂ��ċߑ㉻�����̖ڕW�ł���A����܂ł̌Â��V�X�e����ς��邱�Ƃ��}���ł������B�����ČÂ��V�X�e���̑�\���u�w��v�������̂ł���B�]�ˎ���̊w��͈���ɌÓT�̈ËL������A��������Ɍ���m��I�Ȗ��{���F�̎v�z�������������B������O��錤���͗e�͂Ȃ��e�����ꂽ�B���̌��ʁA���{�̊w��͌������E�Ƃ̊ւ��������A���m�ߑ�̎��R�Ȋw�A�Љ�Ȋw�Ƃ̊Ԃɑ傫�ȍ����������̂ł���B����͂��̍��߂邽�߂ɁA����܂ŏd������Ă��Ȃ��������w���d�����Ă���ƌ�����B����͉ߋ��̐��E�����łȂ��A���݂̐��E�����L�������邱�Ƃ̂ł���S�̓I�Ȏ�������߂�l�����ł������B
�@�a�҂̎���͐푈�Ɣs��A���̖L�����ɂ܂������Ă���B�a�҂��t���̗~�]�Ƌ��{��Η������čl���Ă���̂́A��͂�u���{�̐����ɂ��~�]�̖\���v����������ł��낤�B�������A����͓����ɐt�����߂��镁�ՓI�Ȗ��ł���Ƃ�������B�L���Ȋ���͔M���I�s���Ɍ��т��A�|�p��������傫�ȗ͂ƂȂ�B�����A�����ɂ��̗͂͗�����₷���A���ɂ͑��҂ɂ���đ���ꗘ�p����邱�Ƃ�����B���{�͊���Ɨ����̃o�����X���Ƃ�A�����̈ʒu�������Ă������̂ł���B�u�c�ɂȂ�Ȃ��v�u�S�I�ɐ�����v�Ƃ́A���̃o�����X�������Ă���̂ł���B������܂��S�̓I����ɂȂ����Ă���B
�@�A�[�����g�̎咣�͈ꌩ�A����̎咣�Ɛ����Ɍ�����B�������ƌ��т������p�I�Ȋw��̕K�v�����������̂ɑ��āA�A�[�����g�͊w�Z�̋@�\���u������Z�@���w�����邱�Ƃł͂Ȃ��v�Əq�ׂĂ��邩�炾�B�������A�A�[�����g�����炷�ׂ����e�ƍl���Ă���u���Ђ̊T�O�Ɖߋ��ւ̑ԓx�v�u���^�Ƃ��Ă̐��E�v�͕���́u�n���w�v�u�����w�v�u���j�v�u�o�ϊw�v�ȂǂƏd�Ȃ��Ă���B���Ȃ킿�A����́u���p�v�͒P�Ȃ�u�����v���w���̂ł͂Ȃ��A�u���̐��E�Ƃ͂����Ȃ���̂��v��m�邽�߂̊w��́A�S�āu���p�I�v�ȁu���w�v�Ȃ̂ł���B�䂦�ɁA�A�[�����g������ɋ��߂�u�S�̂Ƃ��Ă̐��E�Ɏ�҂��v�Ƃ����������A����Ɠ��l�ɑS�̓I������d���������̂ƌ�����̂ł���B
�@�����̎咣�����ꂼ��̎����Љ�̏̒��ŏd�v�ȈӖ��������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�������A����̎Љ�ɂ����Ă͐V���Ȗ����N�����Ă���B����́u�g�����x�v�ɑΗ������āA�w�₪�Љ�I�n�ʂɌ��т��悤�ȁu���͎�`�v�����������A����́u�w���Љ�v�Ɍ��т��A�Љ�̗�������W���Ă��鑤�ʂ�����B�a�҂́u��ʋ��{�v�Ɋւ��ẮA��҂��{��ǂ܂Ȃ��Ȃ�������ɁA����ɂ������悤�ȋ��{���K�v�Ȃ̂��A���������A����������ʋ��{�̋�����u��́v������ɂł�����̂��A�Ƃ����傫�Ȗ�肪����B�Ⴆ�A���{�ł͑啔���̐l�������w�Z������A���̂��������߂��͑�w�i�w����B�������A�����̐l�S�Ă��L���ȋ��{��g�ɂ����Ƃ͌����������̂������ł��낤�B����ɁA�A�[�����g�̍l������I�����I��������Ɨ������w�Z�͗��z�ł��邪�A�Љ�̑����S�̐��������Ă��钆�ŁA����͎Љ�̈��͂Ɩ����ł����邩�A�Ƃ�����������B
�@���́A����̎Љ�ɂ����Ă����̋^��ɓ�����͂����̂́A��͂�u���{�v�����Ȃ��ƍl����B����̎Љ�́u���ɗ��������Ȃ����v�Ƃ������l���f�Ɏ�������Ă���B�������A�����Łu���ɗ��v�Ƃ����͕̂���̌����u���p�v�Ƃ͈قȂ��āu���ׂ��ɂȂ���v�Ƃ������Ƃł���B�����̏ꍇ�A�w��͒��ڂ̋��ׂ��ɂ͂Ȃ���Ȃ��B���������āA��w�̂قƂ�ǂ̊w���́u���ɗ����Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�B���̌��ʁA��w�ł͋��{�Ȗڂ��p�~���ꂽ��A�`���I�Ȋw�����k�����u��ƂƋ�����������w���v���V�݂��ꂽ�肵�Ă���B�����A����͂܂��܂��u���ɗ��v�w���ł̊w�����Љ�ł̒n�ʂ����肷�邱�ƂɂȂ��邵�A�{���́u���{�v��ے肷�邱�ƂɂȂ邾�낤�B��҂̓Ǐ�����́A�Љ�̂��������X������������ɂ܂ʼne����^���Ă���؋��ƌ�����B�܂茻��̊w�Z�͎Љ�̏k�}�ł����āA�Ɨ�������ł͂Ȃ��̂ł���B
�@���̂悤�ȎЉ�ł́A���{�Ƃ́u�S�̐��v�Ɓu�������v�̗��z�ł���B�Ȃ��Ȃ狳�{�́u���ɗ����́v�����łȂ��u���ɗ����Ȃ����́v�ɂ����āA�ʂ̍l���������邱�Ƃ��������邩��ł���B���ăI�E���^�����ɑ����̍��w���̐N���W�܂�A�e�������̉��Q�҂ƂȂ����B�ނ�́u���t�͂ǂ�ȋ^��ɂ����������Ă����v���ƂɊ������ē��M�����̂ł���B���Ƃ����I�Ȓm����Z�p�������Ă��A���Ǝ����߂���^��ƌ����������̂ɏ[���ȁu�S�̓I���{�v���Ȃ���A����ł����̂悤�ɗe�Ղɑ��삳��Ă��܂��B���A�K�v�Ȃ̂́A���{�����u�����𑊑Ή�����́v�ł���B�w�Z�Ɍ��炸�A�o�ł�l�b�g���[�N��ʂ��āA������x�u���{�v���Č�����w�͂��ɂ߂ďd�v�ł���Ǝ��͍l����B
���T�]
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y2005�E��II�z
�ݖ�P
�ݖ�Q
�ݖ�R
�ݖ�S
�ݖ�T
�ݖ�U
�ݖ�V
���T�]
���͂����灨��X�[�~�i�[��
�y2005�E��III�z
�l�Ԃ̍Ē�`�Ƃ��čl������u�����̎��R�v�̗��`���ɂ���
�@���͂`�a��̕��͂���u�l�Ԃ��`������͎̂��R�ł���v�Ƃ������ƂƁA�u�������A���̎��R�͗��`���������Ă���v�Ƃ������Ƃɂ��čl�@�������B
�@�`�̕��͂ł́A�`���p���W�[�̊ώ@��ʂ��āA�l�Ԃƃ`���p���W�[�Ƃ̓����s���w�I�ȘA�������q�ׂ��Ă���B�l�Ԃ��i���ɏ]���ēo�ꂵ�������ł���ȏ�A�c��ł��铮�������`�w�I�ȉe�����Ă���B�]���āA�l�Ԃ̑c��Ƌ��ʂ̑c������`���p���W�[�Ɛl�Ԃ̊ԂɁA�����Љ���̋��ʓ_�������Ă����R�ł���B����̓����s���w�́u����ςȂ��A�S�Ă̓����̍s���𑊑Ή����Ċώ@���A�]������v�Ƃ���������Ƃ��Ă��邩��A�����̍s�����l�ԂɎ��Ă�����A�t�ɐl�ԂƂ�������Ă��Ă��A������u�P�v��u���v�ƌ��т��邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�������A����ł��Ȃ��A�ۑ蕶�̕M�҂͓����̍s�����u�a���v��u�F��v�Ɩ��Â��邱�Ƃɑ��锽�����o�����Ă���B���̂悤�ȌX���́u�l�Ԃ͐_�Ɏ������đn�����ꂽ���ʂȑ��݂ł���v�Ƃ����L���X�g���I�Ȑl�Ԃ̒�`�Ɩ����ł͂Ȃ����낤�B�܂��A�Ⴆ�P�U���I�̎v�z�ƃ����e�[�j���́A�����u�G�Z�[�v�̒��Ől�Ԃ̒m�b���u�~�c�o�`�̑����v�Ȃǂɓ��ꂩ�Ȃ�Ȃ����Ƃ��q�ׁA�u�l�Ԃ̓����I�n�ʁv�ɂ��ċ^���悵�Ă���B�����́A�l�Ԃ������]�����邩�Ⴍ�]�����邩�Ɋւ��Ă͐����̈ӌ��ł��邪�A�l�Ԃ��u���ʂȑ��݁v�Ƃ��Ĉ����Ă���_�ł͋��ʂł���B����̉�X���u�l�ԂƂ͉����v���l����ꍇ�A���̂悤�ȁu���ʁv�Ƃ����ӎ����������邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ�ł��낤�B
�@�a�̕��͂ł́A�l�Ԃ̓Ǝ����Ƃ��čl�����Ă�����`�ł���u���t���g�����݁v�u������g�����݁v�Ȃǂ��A����Ȋw�̌����̌��ʗh�炢�ł��邱�Ƃ�������Ă���B�����Ă݂�A�����e�[�j���̎v�z������ɕ��������̂ł���B�������A�a�̕M�҂́u�l�ԂƂ͉����v�Ƃ�����`���̂��̂��A�l�ԑ��݂̓����ł���Ǝ咣���Ă���B�܂�A�l�ԂƂ͏�Ɏ���̑��݂ɂ��ċ^��������A�����T�����鑶�݂ł���Ƃ����̂ł���B�������A�u���ȒT���v��u�w��v���l�Ԃ̓����ł���Ƃ��Ă��A������x����̂͌���ł��邩��A���ǂ���́u���t���g�����݁v�Ƃ����l�Ԃ̒�`�ɊҌ������B����Ɛl�ԂƑ��̓����̘A�����̒��x�́u�ǂ̂��炢�̃��x���Ō��t���g���邩�v�ŋ�ʂ���邱�ƂɂȂ�A�u���t�̎g�p�����Ȑl�v�͐l�Ԃ̗̈悩��ǂ��o����Ă��܂��B������ɐl�Ԃ̒��Ԃɓ���悤�Ƃ���A��͂�u�l�Ԃ����͓��ʂɂ�����Ă���v�Ƃ����ӎ����Đ��Y���邱�ƂɂȂ�B
�@�����̖��ɓ����邽�߂ɁA���́u�l�ԂƂ͊���玩�R�ȑ��݂ł���B�v�Ƃ�����`���Ă������B����玩�R�ł���Ƃ́A���Ɂu����痣�ꂽ�����������Ă���v�Ƃ������Ƃł���B������ɒ��ڂ���A�l�Ԃƃ`���p���W�[�ɑ傫�ȍ��͂Ȃ��B���͂`�Ɛ}�łɎ�����Ă���ʂ�A�`���p���W�[�Ɛl�Ԃɂ́u�F��v�u����v�u�����v�ȂǑ����̋��ʂ��銴�����A�l�Ԃ̓`���p���W�[�ɋ������邱�Ƃ��ł���B�������A�����ɁA�l�Ԃ͂�����������痣��ė����I�Ȕ��f���Ȃ�����B�Ⴆ�A��X�͑�����D�����������Ɋւ�炸�A���A�����蓯���E��Ŏd�������邱�Ƃ��ł���B���̓���������̓����ɂ���čs�������肵�Ă���̂ɑ��A�l�Ԃ͊���玩�R�ɂȂ邱�Ƃŗ����I�ɍs�������肵�Ă���̂ł���B�P�V���I�̎v�z�ƃz�b�u�Y�́w�����@�C�A�T���x�̒��ŁA���|����Ȃ����s�ׂ��A���ꂪ�����I�ɂȂ���A���邢�͂�������Ȃ��u���R�v�����鎞�A�u���R�ȍs�ׁv�ƌ�����Əq�ׂ����A���|�̊����s�ׂ����肷�鎞�A����͓����̂��{�\�I�Ȏ��Ȗh�q�Ȃ̂ł���B��������R�ƌ����Ȃ�A�S�Ă̍s�ׂ��玩�R�ƕs���R�̋�ʂ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B��͂芴��玩�R�ł��邱�Ƃ��d�v���ƌ�����B
�@�������A��������Ɓu������R���g���[���ł��Ȃ��l�͐l�Ԃł͂Ȃ��̂��v�Ƃ����^�₪���R���܂�Ă���B�Ⴆ�A�{��ɔC���đ��l���E������l�́A����玩�R�ɂȂꂸ�A���������邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂Ől�Ԃł͂Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B�������A���ꂱ�����u�����̎��R�v�̗��`���Ȃ̂ł���B���l�Ƒ������A�l�Ԃ͓{�����݂�������B���������ɁA�������D�ʂɂ��鎞�A����ɑ������݂�߈�����������B�ʏ�͂��̂悤�Ȋ�������̌�����h���ł���B�����̓�����Œ��ԓ��m�̓���������I�Ȃ��̂ł���̂́A�������Ď�̐�������邽�߂ł��낤�B����ɑ��Đl�Ԃ́A���Ԃ��E�Q������A���ɂ́A���͂̐e�����l�X�̎����ɑ��銴������Ď��E�����s���邱�Ƃ�����B�u�����̎��R�v�́A���Ƃ��āA���҂Ǝ��Ȃɑ��閳���߂Ȗ\�͂Ƃ��Č�����̂ł���B
�@���������u�����̎��R�v�́A�l�Ԃ��`��������ł͂��邪�A�l�Ԃ́u���ʂɂ����ꂽ�_�v�ł͂Ȃ��B���Ȃ킿�A�u�����̎��R�v�́A����ŗ����̗̈�Ƃ��Đl�Ԃ𑼂̓����������Ȉӎ��I�ȍ������_�ɒu���B�����������Ɂu�����̎��R�v�́A�\�̗͂̈�Ƃ��Đl�Ԃ𑼂̓����������Ȕے�I�ȒႢ���_�ɒu���̂ł���B���E�I�Ȋ��j��⌃�����o�ϊi���A�召�̃e�����Y���Ȃǂ́u�����̎��R�v�������`�����琶�܂�錻�ۂł���B��X�����`�I�ȁu�����̎��R�v��l�Ԃ̍Ē�`�Ƃ��ė�������Ȃ�A�����̉�������Ȗ��ɑΏ�����V���ȑ���邱�Ƃ��ł���Ǝ��͍l����B
���T�]
�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y2006�E��II�z
�ݖ�P
�ݖ�Q
�ݖ�R
�ݖ�S
�ݖ�T
���T�]
���͂����灨��X�[�~�i�[��
�y2006�E��III�z
�����邽�߂̎��Ԃ̌���
�@�ۑ蕶�͂ǂ���u�����邽�߂̎��Ԃ̌��݁v�ɂ��ďq�ׂĂ���B�����Ŏ�����`����u���Ԃ̌��݁v�Ƃ́u�ߋ��E���݁E������藣�����A�A�������s���Ȏ��ԂƂ��Đ₦���o�����邱�Ɓv���w���B
�@�`�͂Q�O���I������Â���Ȋw�Z�p�ƃC�f�I���M�[�ɂ��āA����炪�u�l�X�̊Ԃ̉ߋ��̊W�A���݂̊W�A�����ɂ��肤��A�܂�����ׂ��W�v�Ƃ����ϗ��w�I�Ȕ��z����n�܂������Ƃ��w�E���Ă���B�Ȋw�Z�p�͉ߋ��̗��_�Ƃ̑Ό��̒��Ŕ��W���J��Ԃ��Ă������A���̔w��ɂ́u�Â����E�ςƂ̑Ό��v���������B���m�ߑ�̗͊w�I���E�ς͂���ȑO�̐_�w�I���E�ςƂْ̋��W���琶�܂ꂽ�ƌ����邵�A�͊w�I���E�ς����Θ_��ʎq�_�̐��E�ςɂ���č���I�ɔᔻ���ꂽ�B����͎Љ�ςɂ��Ă����l�ł���B�i���_���}���N�X��`�������`�̊�ՂƂȂ��ĂQ�O���I�̃C�f�I���M�[�ݏo�����̂́A���̈��ł���B�����̎v�z�I�^���͉ߋ��ƑΌ����A�������\�z����m�I�c�݂̈�ʂł������B
�@�a�͓��{���܂�̊؍��l��������u�ӂ邳�Ɓv�ɂ��āA�u���܂������Ƃ���v�Ɓu��c�������Z��ł����Ƃ���v�̕��f�ɂ���āA�u�ӂ邳�Ƃ͔��������Ȃ��v�Ƃ����ӎ������܂�邱�Ƃ��q�ׂĂ���B����ƑΒu����Ă���̂́A�M�҂̕�́u�i���{�́j�炩���������v�����[���v�Ƃ������t�ł���B�e�q�ł���Ȃ���A�ߋ��ւ̎v���ɍ��ق�����̂͂Ȃ����B����́u��c�Ƃ��������ߋ��v�u���܂�Ă���̎����̐l���Ƃ����߂��ߋ��v�u���݁v�Ƃ������ԓI�Ȃ���̗L���ɂ��B������͂����̂Ȃ���������ӎ����Ă����B�����畃�c�̒n�ł���؍��̐��B���A�q�ǂ��݁A�܂����������{�̉����A�����̐����錻�݂Ƌ������т��Ă����̂ł���B����͍��݂��ē�̍��̖������\�z����͂ɂ��Ȃ�B�������A���̎q�ǂ��̐���ɂȂ�ƁA���{�Ő��܂�āu��c�̒n�v��m��Ȃ����肩�A�؍��֖߂��āu���������܂ꂽ���{�v�Ƃ��f�₵�������𑗂�A�ߋ��ƌ��݂̘A�����͒f�����Ă���B���ꂪ�����ĊJ�ɂ���āu�߂���邳�ꂽ�悤�ȁv�C�����������Ȃ̂ł���B
�@�b�͐��́u������v�ɂ��āA�������u�ߋ���Y����v�ł��������ƁA����ɔ����I����������������ł͓��퉻���A�Љ�S�̂��ߋ���Y�p���Ă��錻�����q�ׂĂ���B�M�҂́A����̉�X���ߋ����Ȃ��A�܂��������Ȃ��u���Ԃ����ʉ������v�u���Ԃ����s��������������v�ɐ����Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���B�������A����ɂ�������u���j�ς̑Η��v�͂���B����́u�ߋ��̖Y�p�v�Ɩ������Ȃ����낤���B���̃q���g�ƂȂ�͕̂����́u�A�����J������v�ł��낤�B�s�킩��킸���ܔN�ʼn�ꂩ��r�����ꂽ�u�푈�̋L���v�́A���̊O�Łu���m�s���v�u�Z��s���v�Ƃ��Đ��X���������Ă����B�����炱��������́u�����̏�v�Ƃ��Đ����������̂ł���B���̍��̗��j�ς̑Η��́A���Ȃ��Ƃ��u�푈�v�Ƃ������ʑ̌��̏�ɗ������u���݂ƘA������ߋ��̕]���v�ł������B�䂦�ɗႦ�u�푈�ӔC�̌y�d�v�Ɋւ���c�_�͂����Ă��A�u�푈�͂Ȃ������v�Ƃ����c�_�͑��݂��悤���Ȃ������B�������A���݂́u���j�ς̑Η��v�́A�̌����Ă��Ȃ��̉ߋ��ɂ��āu���݂̗��ꂩ�牽����������ł����R�v�Ƃ����悤�ȋc�_�ɂȂ��Ă���B���̓_�ł���́u�ߋ��̖Y�p�v�ƕς�肪�Ȃ��̂ł���B
�@����������X���������g�̖��ɂ��čl���鎞�A�Ώۂł��鎩�������̎���𐳊m�ɑ����Ă���ƌ����邾�낤���B���A�����ɐ����Ă����X�́A��X�̂��̂̌����őΏۂ𑨂�����Ȃ��B����ƁA�u��X�̂��̂̌����v�ȊO�́u���̂̌����v�́A��������r������邱�ƂɂȂ�B�Ⴆ�A�����Ȃ���Ύ����̊�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ɁA�l�͎����̊O���ɂ���u���ҁv�̎��_���璭�߂Ȃ���A�������g�́u�l�����̘g�g�v�ɂ͋C�Â��Ȃ��̂ł���B
�@����䂦�ɁA���ԓI�Ɂu���ɂȂ��ߋ��v���邢�́u���j�v�ɂ��čl���邱�Ƃ́A���݂̎����̂��̂̌��������o���邽�߂ɕK�v���ƌ�����B����Ήߋ������݂��Ƃ炷���ɂȂ��Ă����̂ł���B�܂��A��ԓI�Ɂu�����ɂȂ����́v�A���Ȃ킿�a�ŏq�ׂ��Ă���悤�Ȉٕ����̎��_�ɐG��邱�ƂŁA��X���u���������S�v�ƍl���Ă��鎩�������A���҂̎��_����Ƃ炵�o�����B�������āA��X����ɐ������ƐM���ċ^��Ȃ����l�̊���A�ʂ̊�ɏƂ点�Α��Ή�����A�����̉��l��̒��̈�ɂȂ�B�`�ŏq�ׂ��Ă���u�ϗ��w�v�̎��_�́A�������đ�����ꂽ�l�ԊW�̖{�����ƌ�����B
�@���������u���Ԃ̌��݁v�̒��Ő����ď��߂āA��X�́u���܁v�u�����Ɂv����u���݁v��]�����邱�Ƃ��ł���B����������A�������Ă���l�����̘g�g���痣��Ď��������邱�Ƃ��ł���̂ł���B���́u���Ԃ̌��݁v�͖����Ƃ̘A���������ݏo���B�Ȃ��Ȃ�A��X�����݂�ᔻ���A���悢���������݂��悤�Ƃ���A���݂̍l�����E���������̂��̂�ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B���̍l�����E�������̂ǂ����ǂ̂悤�ɕς���悢�̂��B�����m�邽�߂ɂ́A�u���܁v�u�����Ɂv������̂𗣂�āA�ߋ��̗��j��ٕ����̎��_�����X���g�̌��݂����������Ƃ��K�v�ł���B���������́u�������v�́A�₦���o���Ƃ̌��т��������Ȃ���s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������ē���ꂽ�u�����邽�߂̎��Ԃ̌��݁v���A���ӂ�K�v�Ƃ���ǂ̕���ł��A���A�d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���Ǝ��͍l����B
���T�]
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y2007�E��II�z
�ݖ�P
�ݖ�Q
�ݖ�R
�y��Փx�z
�y���̌X���z
���͂����灨��X�[�~�i�[��
�y2007�E��III�z
�u�l�b�g���[�N�Љ�ɂ����鑼�҂Ƃ̎���ꂽ�A�����̉v
�@�ۑ蕶���Q�l�ɂ��āA���͎��ȂƑ��҂Ƃ̘A�����ɂ��čl�@�������B�܂��A���ȂƑ��҂̘A�����Ƃ͉������`���A���ɂ��ꂪ�����Ă�����Љ�̂�������l�@����B���̏�ŁA�����ɂ��ĘA���������邩�ɂ��Ę_�������B
�@�O�̕��͂����ʂɘ_���Ă���̂́A���ȂƑ��҂̘A�����Ƃ͉����Ƃ������ł���B���́u�A�����v�Ƃ́A�����̖��Ƃ��đ��҂̐S��ɋ������A�S��𗝉����A�������������Ƃł���B�����āA�ǂ̕��͂̕M�҂��u�g�̐��v��u��v�����ȂƑ��҂��Ȃ��ƍl���Ă���B
�@�`�ł͐l�ԂƑ��̐������Ɉ������Ƃ̍����Ƃ��āu�ꂵ��߂��肷��\�́v���������Ă���B���ʁA�l�Ԃ̓����Ƃ��Ę_������m���Ȃǂ͐l�ԂƓ����ӓI�ɋ�ʂ����ł���A���ۂ͐g�̂̉��y���ɂ�ʂ��āA�l�Ԃ����������ʂ́u���Q�v�����_�łȂ����Ă���̂ł���B�����ł͎��ȂƑ��҂̘A�����́u�ꂵ�݂�߂��݁v�ɂ���Ďx�����Ă���B
�@�a�ł͐l�ԓ��m�̏o��A�܂�A�������_�����Ă���B���ȂƑ��҂Ƃ̏o��͕�Ǝq�̊ԂɁu�����Ƌ����v�̑Η������܂�邱�Ƃ���o������B���̊W�͐l�Ԉ�ʂ̏o���_���Ƃ̏o��ɂ�������A�M�҂͂��̂�������u�����v�ƌĂԁB�����́A���ȂƑ��҂̘A�������A�g�̂�ʂ����u�M�v�̂��Ƃ�ɂ���Ċm���Ȃ��̂ɂȂ�Ƃ������Ƃł���B�����ł́A���Ȃ����҂��ǂ��M���邩�ɂ���đ���͐_���ɂ��ؐɂ��Ȃ�B�܂�A���҂͎��Ȃ��̂��̂Ɋ҂��Ă���̂ł���A�o��ɂ����鎩�ȂƑ��҂͋����A�����������Ă���̂ł���B
�@�b�ł͈ꌩ�ے�I�Ȋ���ł���u�{��v���A���͑��Ҏu���I�ȏ�ł��邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B�u�{��v�́A���҂̊��ɂ���Ď��Ȃ����Ǝ��̉��l��ے肳��邱�Ƃ��琶����B����䂦�A�u�{��v�͑��҂ɂ�铭����������n�܂�A���Ȃ̐g�̂ɋN���������҂ւ̍U���ւƍL�����Ă����̂ł���B�����ɂ͎��ȂƑ��҂̊ԂɐS��I�Ȃ��Ƃ肪����A�A�������������Ă���ƌ�����B
�@�ȏ�̂悤�ɁA���ȂƑ��҂̊Ԃɂ́A�{���u�g�̐��v��u��v�ɂ���č\�������A���������藧�͂��ł���B�������A���x��ɂ���ďo�������l�b�g���[�N�Љ�ł́A���̘A��������@�ɕm���Ă���B
�@���ɁA�l�b�g���[�N�Љ�ł́u�g�̐��v���ɂȂ�B�A�����ɂƂ��ĕs���́u���y�Ƌ�Ɂv�u�����Ƌ����v�u���҂���̐g�̓I���v�Ȃǂ́A���Ȃ̐g�̂Ƒ��҂̐g�̂��G�ꍇ���A���Ȃ̐g�̂ɋN����u�����v�����҂̐g�̂ɋN����u�����v�Ɠ������̂ł���ƈӎ������Ƃ���ɐ�������S�I��Ԃł���B�Ƃ��낪�A�l�b�g���[�N������R�~���j�P�[�V����������̑啔�����߂�ƁA��l��l�̎��Ȃ͌Ǘ����A���҂͂ǂ��ɂ����Ȃ��Ȃ�B�l�b�g���[�N��̉��z��Ԃł͐g�̓I���y����ɂ��Ȃ��A���҂͂��Ȃ����疧�����������g�̓I�����Ȃ��B�p�\�R����g�ѓd�b�ł��ł��N�Ƃł��A�����Ƃ��ɂ�������炸�A���̂Ȃ���͐g�̐��������Ă��āu�A���v���Ă��Ȃ��̂ł���B
�@���ɁA�l�b�g���[�N�Љ�ł́u��v������Ȃ����ʉ������B���ȂƑ��҂��Ȃ����̂Ƃ��Ă̏�́A�u���y�E�ɂ݁E�g�̂������o�E�{��v�Ȃǂ����҂Ƌ��L����Ă��邩�炱���S��Ɍ��������A�u���݂̏��F�v����b�Â���B�����A���҂������Ȃ���Ŏ��Ȃ̓����ɐ��܂���͔�������������A�u���������ŕ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɂ݁v�u�ǂ��ɂԂ�����悢���킩��Ȃ��{��v�ɕώ�����B�����͑��҂Ƃ̘A���������@�������ʐ��܂�銴��ł��邪�A���̓��ʓI�Ȍ������͑��҂����₵�A�܂��܂��A���������킹��B
�@���̌��ʁA�l�b�g���[�N�Љ�͌g�ѓd�b��g�у��[���Ɉ�����ˑ�����l�X�ݏo���A�u�o��n�T�C�g�v�ɂ͐^�̏o��͂Ȃ��A�l�b�g�f����u���O�ɂ͎��Ȋ����I�Ɣ��Ƒ��҂ւ̒��������Ă���B�l�b�g��ʂ��������߂����E���A���ȂƑ��҂̘A�������₽�ꂽ���ƂɌ���������B
�@���̂悤�ȏ̉��ŁA��X�͂����ɂ��Ď��ȂƑ��҂̘A����������悢���낤���B�A�����r���̌�������l����A�u�g�̐��Ə�̍Ĕ����v���K�v�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�Ⴆ�A�ۑ蕶�`���q���g�ɂ���u�����̒��Ő����̘A�������l���A���H����v�Ƃ����s�����l������B�l�ԈȊO�̐����̋�ɂ�l�Ԃ����L���A����d���邱�ƂŁA��X�͎������g�́u�ɂ݁v�Ƃ������������Ƃ��ł���B���Ȃ́u�ɂ݁v�́A����ȏɂ��鑼�҂́u�ɂ݁v�ł�����B�l�Ԃ��݂��ɂ��̎��o�������A��X�͎��ȂƑ��҂̘A�������Ĕ����ł����ƌ�����B�܂��A�ۑ蕶�a�ɂ���ʂ�A���҂ɔz�������҂d���邱�Ƃ́A���Ȃ�[���m�邱�Ƃł�����B����ɁA���Ȃ̊ւ����ɂ���đ���̂�������ς��Ƃ������Ƃ́A���Ƃ��l�b�g���[�N���_�@�ł����Ă��A���H�̏�ő���Əo��A�V�����Љ�W��z�����Ƃ��\���Ƃ������Ƃł���B�����̔F���̓{�����e�B�A�����̏�I��b�ł����邪�A�l�b�g���[�N�Љ�ŊɂȂ�Ƒ���n��A����ɑ傫�ȗ̈�̐l�ԊW���ĕ]���E�č\�z����͂ɂȂ�Ǝ��͍l����B
�y��Փx�z
�y���̌X���z
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y2008�E��R��z
����
�@
���
�@���̍ٔ��́A�@���I�M������A�������ۂ���ӎu��\�����Ă������҂ɑ��Ĉ�t����p���ɗA�����A��p��Ɋ��҂ƉƑ����u���Õ��@�Ɋւ��銳�҂̎��Ȍ��茠�̐N�Q�v���������Ƃ��ĘZ���̈�t��i�������̂ł���B��t���́u���ɂȂ��鎩�Ȍ��茠�v��ے肷��咣�ɑ��āA�ٔ����͌l�ɂ́u�����������Ȍ��肷�錠���v����{�I�ɔF�߂���Ƃ��A��t�͎�p�ɍۂ��ď\���Ȑ�����������Ŋ��҂̓��ӂ�`��������Əq�ׂĂ���B�����Ƃ��Ċ��҂͐f�@�A���@�̉ߒ��ŏ@���I�M���ɂ���Đ�ΓI���A����I������ӎu��\�����A��p�O�ɂ͂���������Ă����B���҂Ɠ���I�ɐڂ��Ă����O�l�̈�t�ɂ͊��҂ɑ��ėA���̕K�v����������A���̏�œ��@�Ǝ�p�ɑ��銳�҂̓��ӂ�`�����������B�������A�\���Ȑ����ƍ��ӂ��Ȃ���Ȃ��܂ܗA������p���s���A�O�l�̈�t�͊��҂̎��Ȍ��茠��N�Q�����ƍٔ����͔��f�����B�����ɁA���҂Ɛڂ���@��̂Ȃ��������̎O�l�̈�t�ɂ͐����`�����Ȃ��A�����̐N�Q���Ȃ������Ɣ��f�����B
�@
���
�@�T�����̎咣�ɂ��čl�@���邽�߂ɂ́A�u�����v�̈Ӗ����`����K�v������B�����Ƃ́A�Љ���������ŁA�Љ�̐����Ԃɐ�������u���݂ɑ���d�����ɍs������Ƃ������Ӂv�ł���B���̒�`����l����ƁA�u�����`�̎��Ȍ��茠�v�Ƃ́u�`�������̈ӎu�ɂ���Đl�����悤�Ƃ��鎞�A���̐l�X�����̈ӎu�d���A�ӎu�̎����̂��߂ɋ��ɍs������v���Ƃł���B������u�����̑I���v�ɓK�p����Ƃǂ��Ȃ邾�낤���B�Ⴆ�A���N�Ȑl�������Ƃ��āu���E�v��I������ꍇ�A���̐l�X�͂��̐l�̎��E�̈ӎu�d���A���E�������邽�߂ɋ��ɍs�����邱�ƂɂȂ�B�������A��X�̎Љ�́u���E�v���߂ƍl���Ă���A���̏ꍇ�ɎЉ�I���ӂ�����Ƃ͌����Ȃ��B����A�d�a�ŗ]���̒Z���l���u���y���v��u���Â��Ȃ��v���Ƃ�I������ꍇ�A���͂̐l�X�͂��̈ӎu�d���A������̓_�H��z�X�s�X�Ȃǂ̊Ŏ��ł��̐l���x���邱�ƂɂȂ�B���̏ꍇ�ɂ��Ă͎Љ�I���ӂ�����ƌ�����B
�@�]���āA�u���Ȍ��茠�v�́u����I�������肷�邩�v�ɂ���č��ӂ̗L�����ʂ��A�������܂����ł���ƌ�����B�䂦�Ɂu���Ȃ̐����̑r���ɂȂ���悤�Ȏ��Ȍ��茠�͔F�߂��Ȃ��v�Ƃ����咣�Ɓu�����鎩�Ȍ��茠�͑��d�����ׂ����v�Ƃ����咣�͂ǂ�������ՓI�ł͂Ȃ��A���ꂼ�����I�ɐ������ꍇ������Ǝ��͍l����B
����
�@
���
�@�u���ȁv�ƌ����Ε��ʂ́u��������Ԃ悭�킩���Ă���l�ԁv�̂��Ƃł���B�������A�u�����鎩�ȁv�͑��l�����������āA���l�̂��̂̌���������グ���鎩�ȑ��ł���B����͎�҂̐����I���B�ƂȂ���u�����̎��ȁv�┽�ȓI�Ɏ���������u���鎩�ȁv�Ƃ͈Ⴂ�A�����̐������Ƃ͈قȂ�ꏊ�Ő��܂��u���ȁv���ƌ�����B����䂦�Ɂu�����鎩�ȁv�́A�����̒��ɂ���Ȃ���u�����̂ӂ�����Ă���A�����ł͂悭�킩��Ȃ��l�ԁv�ł���B�����M�҂́u��̑��ҁv�ƕ\�����Ă���̂ł���B
���
�@�M�҂́u���i�v���u�����鎩�ȁv�Ƃ��đ����Ă���B����͑��҂��猩�����Ȃł���A���Ȃ̈ꑤ�ʂɉ߂��Ȃ��B����䂦�Ɂu���i�v�́u���l�p�̃n�J���Ōv�����ꂽ���ȁv�Ƃ��āA������G�l���M�[�₻�̌���ł���u�ӂ�v�Ƃ͖��W�Ȃ��̂��ƌ����Ă���B���͕M�҂��咣����悤�ȁu���Ȃ̏d�w�I�Ȃ�����v��F�߂�B�������A�u���鎩�ȁv�Ɓu�����鎩�ȁv�����S�ɕ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl����B
�@�M�҂́u�����I�Ȏ��ȁv�Ƃ́u���ʓI�Ȏ��ȁv�ł���B�����ł͐g�̓I�E�����I�ȁu�h���Ɣ����̊W�v���x�z���Ă���B���̎��Ȃ��ӎ��ł͐���s�\�ł���A���̈Ӗ��Łu���ҁv�ł���ƌ����邾�낤�B��X�͔w�̍����������Ō��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���I�Փ����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�Ⴆ�u�ӎu�ɂ���Đ��I�Փ���}����v�ƌ������A���͏Փ��͌|�p�\����X�|�[�c�ȂǕ����I�ȓ����s�ׂɌ`��ς��Ă��邾�����Ƃ��l������B
�@����ɑ��āA�u���鎩�ȁv�u�����鎩�ȁv�́u�W���̒��Ő��܂�鎩�ȁv�ł���B������X��������l�̐��E�Ő�������Ȃ�A�u���鎩�ȁv���u�����鎩�ȁv�����܂�Ȃ����낤�B�a���Ԃ��Ȃ��V�����̂悤�ɁA�����ɂ͉��ƕs���ɔ�������u���ʓI�Ȏ��ȁv�����邾���ł���B
�@�����A�u�����鎩�ȁv���`�������ɂ�A�l�Ԃ͕ς��B�ŏ��͊O����u���O�v���^�����A�Z�▅�Ȃǂ̉Ƒ��W�A�Љ�o�ϓI�n�ʁA���R�E�����I���ȂǁA�l�X�ȊO�I�v�����u���ʓI���ȁv�ƏՓ˂���B���̏Փ˂ɂ���ď��߂āu�v���ʂ�ɂȂ�Ȃ����E�v���ӎ������B���ꂱ���M�҂̌����u���l�p�̃n�J���v�ł���B
�@�������A�M�҂̌����u���l�p�̃n�J���v�́A���Ȃ��O�����猩��B��̎�i�ł�����B��X�͐�ɑ��l�ɂ͂Ȃ�Ȃ�����A���l�������l���Ă��邩��m�邽�߂ɂ́u���l�p�̃n�J���v���r���邵���Ȃ��B����ɂ���Đ��E�̑��l�Ȏp�������Ă���B����Ɠ����Ɂu���҂ɂ�鎩�Ȃ̗l�X�ȕ]���v�������Ă���B����������u���l�Ȑ��E�̒��ŁA�����͉��҂Ȃ̂��v�Ƃ����A�C�f���e�B�e�B�̈ӎ������܂��̂ł���B���ꂱ���u���鎩�ȁv�̒a���ɑ��Ȃ�Ȃ��B�]���āA�u�����鎩�ȁv�Ƃ��Ắu���i�v�́u���鎩�ȁv�ƘA�����Ă���A�A�C�f���e�B�e�B�`���̏d�v�Ȉ�i�K�ł���Ǝ��͍l����B
�y��Փx�z �@����B
�y���̌X���z �@�Љ�Ȋw�I�ȑ���Ɛl���Ȋw�I�ȑ����g�ݍ��킹�����ł��邪�A�����⎩�Ȍ`���̖{���Ɋւ��e�[�}���c�_����Ă���A�ǂ�������ۓx�������B���ɑ���͖@���p��ŏ����ꂽ����ł���A�ǂ݂Ƃ�ɂ����B�������͂ǂ�����W���I�����A�ۑ�̓��e��[���ǂ݂��܂Ȃ���Η����ł��Ȃ��B���ꂾ���ɕ��i���瓯�l�̃��x���̓Ǐ������A��U�����f���ĉߋ���Ɏ��g�ޗ��K���K�v�ł���B
�@
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�y2009�E��R��z
����
�@
���
�@
�i�P�j
�@�s�i�S���\���̈ꔪ��ܔN�Ƀv���V�A�R�����ɐN�������̂̓i�|���I���푈�ɂ�����t�����X����ł���B�ꔪ��O�N�Ƀi�|���I�������V�A�����Ŕs�k���A�v���C�Z���̓t�����X�ɐ�킷��B��l���Ε��哯���ɂ���ăt�����X�R���s�k�A�ꔪ��l�N�ɂ̓i�|���I�����c���ވʂ��A�G���o���ɒǕ������B�������A�E�B�[����c�ɂ������㏈���̍����Ɖ������Â̕s�]�����āA�P�W�P�T�N�Q���Ƀi�|���I���̓G���o����E�o���t�����X�{�y�֏㗤���čĂђ�ʂɂ��B����ɑ��đ���Ε��哯������������A�v���C�Z���R�͂U���Ƀ��[�e�����[�̓����ŃC�M���X�E�I�����_�R�ɍ������A�t�����X�R�͔s���B�i�|���I���̕����͕S���V���ɏI���A�Ăёވʂ����ނ̓Z���g�w���i���֗�����A�i�|���I���푈�͏I�������B
�@
�i�Q�j
�@�s�i�S�����\��̈ꔪ���Z�N�Ƀv���V�A�R�����ɐN�������̂̓h�C�c�̓���̉ߒ��ł������������푈�ł���B�ꔪ�Z���N�ɋ�ʂƂȂ����X�y�C���̉��ʌp�����߂����ăi�|���I���O���ƃv���C�Z���̎r�X�}���N�Ƃ̊ԂɑΗ����������B�v���C�Z�������B���w�����ꐢ�̓d����������ꂽ�G���X�d�������������ɁA�ꔪ���Z�N�V���t�����X�̓v���C�Z���ɐ�킷��B�푈�����𐮂��Ă����v���V�A�R�̓t�����X�R�����|���ăZ�_���ŕ�͂��A�X���Ƀi�|���I���O���͏����ƂƂ��ɓ��~���ߗ��ƂȂ�B���N�P���ɂ̓v���C�Z���������F���T�C���{�a�Ńh�C�c�鍑�̍c�郔�B���w�����ꐢ�Ƃ��đ��ʂ��A�h�C�c�̓��ꂪ���������B�s��̌��ʃt�����X�ł͑��鐭�����Ĉȍ~�͋��a���ƂȂ�A�A���U�X�E�����[�k�n���̓h�C�c�ɕ������ꂽ�B
�@
���
�@���̓R���o�����̎��݂��u���j�Ƃ͉����𑨂������v�Ƃ����Ӗ��ō����]������B������O�̎��_����q�ׂ����B
�@���ɁA�u�l���͌��̗͂��ꂩ�琳�������ꂽ���j�𑊑Ή�����Ӗ������v�Ƃ������_�ł���B���ꂪ�T�����ɂ���u���[���X�g���[���̎Љ�j�A���j�w�ւ̃A���`�e�[�[�v�̈Ӗ��ł���B�u���j�I�����v�͎�ɕ����Ŏc���ꂽ�����ł���A�������쐬�������ۑ��ł���̂́A���ꂼ��̎���ő傫�Ȍ��͂����l�X�ł���B���͂������Ȃ��l�X���u�����̐l�X�v�ƌ������A�{���u�����v�̐l�͂��Ȃ��B�u���j�v���l���ɂ��Ă���̂��B���j�́u�l���v�͂��̂��Ƃ���X�ɋ����Ă����B
�@���ɁA�u���j�����̎��R���v�Ƃ������_�ł���B���j�Ƃd�g�J�[�͒����w���j�Ƃ͉����x�̒��ŁA���j�I�����Ɋ�͂Ȃ��A���j�Ƃ��I���������j�ł���Əq�ׂĂ���B�J�[�������悤�ɁA�ʏ�A���͎҂̍s����푈�̋L�^���u���j�v�ƌ�����̂́A�����̗��j�Ƃ��������u���j�I�����v�ƔF�肵�Ă��邩��ł���B�䂦�Ɂu����ɂ��Ă̎����������o�����v�u�������₷���o�����v�����j�I�����ɂȂ��Ă��܂��B�t�Ɂu�����Ȃ��l�v�̎����͏��Ȃ��A�������ɂ����B�������A�l�̗��j�́u���݂��Ȃ������v�̂ł͂Ȃ��u������Ȃ������v�ɉ߂��Ȃ��B���j�Ƃ�����ɖڂ������A���ʂ̐l�����������㑜���č\�����邱�ƂŁA�u�l���̕����v�����j�ƂȂ�̂ł���B���������āA�ʏ�̗��j�ƌl���͖������Ȃ��B
�@��O�ɁA�u���A�����ɐ����邱�ƂƗ��j�̊ւ��v�Ƃ������_�ł���B�������o�������푈��ЊQ�̋L���͐��X�����B�������A�����傫���u�Ă����j�I�����́u�P�Ȃ�L�q�v�ɂȂ�A�ǂސl�ɑi��������͂͏������B���̈���ŗ��j���ނɂ���������f�悪�D�܂��̂́A�����Ɂu���j�����l�v���`����Ă��邩��ł���B�u�l�̐������v�͎��ԂƋ�Ԃ��Đl�X�ɑi����͂����B���������āA�ߋ��ɐ�����������l�́u�l���v�ɒ��ڂ��邱�Ƃ́A���j���u���A�����������Ă��錻�݁v�Ɋւ�点�邱�Ƃł���B����͗��j�ƂɂƂ��Ă��A���j���w�Ԑl�ɂƂ��Ă��ς��Ȃ����j�̈Ӗ��Â��ł���B
�@�����̐l�Ɍl����^���邱�Ƃ̈Ӗ����A�ȏ�̂悤�Ɏ��͍l����B
�@
����
�@���҂����Ƃ��Ă���u���ڌo���v�Ɓu���o���v�̍��قƂ́A�u���A�����v�ɂ��Ă̍��قƌ�����������B���́u���A���v�Ƃ͐l�ԂƊ��Ƃ̊ւ������琶�܂�銴�o�ł���ƒ�`����B�Ⴆ�A������X�ƑΗ�������̂ł���A���̒��Ő������т悤�Ƃ��鎞�ɒ�R��������A����́u����������v�ł���A�u���A���v�ݏo�����̂ł���B���ڌo���������̂悤�Ȓ�R�����A���҂́u�g�ɔ���́v�ƕ\�����Ă���B
�@����ɑ��āA���҂͏��o�����u�����̃R�s�[�v�u�^���o���v�Ƒ����Ă���B���҂����o����\�w�I���ƍl���Ă���̂́A��㔪�Z�N�㏉���̃��f�B�A���u�P��̊��o�ɑi����\����i�v�ł���Ƌ��Ɂu�Q���҂����肷��\����i�v�ł��������炾�낤�B�Ⴆ�A�d�b�͒��o�Ɉˑ������Έ�̃R�~���j�P�[�V�����E�V�X�e���ŁA����̑����z�肵�����f�B�A�ł��邽�߁A���I�ȍL���肪�Ȃ��B����A�V����W�I�͎��o�܂��͒��o��p�����Α��̃��f�B�A�ł���A�u����������ʂɒm�肽�����Ă��邱�Ɓv���e�L�X�g�≹���ōL���i���邱�ƂɗD��Ă���B�e���r�Ȃ�}���`���f�B�A�Ȃ̂ŁA���o�ƒ��o�̗������g���ĕ\�����ł���B�������A�����̃��f�B�A���}�X���f�B�A�̈�������̂��߁A�l�I�ȑ��l���̂�����j�[�Y�ɂ͉������Ȃ��B�����̖��_�̓C���^�[�l�b�g�ō������ꂽ�B
�@����ł��A�ۑ蕶�������ꂽ����A���ɕM�҂͍����̏��o�����ʓI�ɂ����I�ɂ����ڌo�������|���Ă��邱�ƁA�܂����U�̏�����ʂł������^���ɗ�����₷�����Ƃ��w�E���Ă���B���̌X���́A����Z�N��ȍ~�A�C���^�[�l�b�g�����y���Ă�����ς��Ȃ��ǂ��납�A�����x�������Ă���ƌ�����B
�@�������A�u���o���̐��E�ƒn�����̗L�����E���R�I�g�̂����������Ƃ̏Փˁv�Ƃ����ՊE�_��������邽�߂ɒ��҂���Ă���u�g�̗̂ʓI�E���I�g���v�܂��́u���o�̊g���Ɛ[���v�͗e�Ղł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���A���ڌo�����l�b�g���[�N�ƃZ���T�[�Z�p�����鉼�z�����̏��o���ɂ���ւ����邩�炾�B�l�b�g���[�N��ʂ��ĉ��z�����̐��E�ő��҂ƌ𗬂�����A�Q�[����ԂŃZ���T�[��g�ɂ��ĉ^�������肷��o���́A��R���Ɋ�Â��u���A�����v�����_�Œ��ڌo���ɋ߂��B�����ł͐g�̂����z�����̒��Ɋg������A���o�����ԂƋ�Ԃ̐���𗣂��B
�@����ł́A���x��������o���͒��ڌo���Ɠ��������̂ɂȂ�̂��낤���B�����͂Ȃ�Ȃ��Ǝ��͍l����B����́A���z��ԁE���z���E�ł̌o�����l�I�ɑ���\�Ȃ��̂ł���A���R�x���傫�����炾�B���ڌo���̒�R���ōł��傫�Ȃ��̂́u���ҁv�Ɓu���҂̘A���̂ł���Љ�v�����A���z���E�ł͂���������邱�Ƃ��ł���B���̌��ʁA�����Ƒ��҂̊W�E�Љ�͉����ς��Ȃ��̂ł���B�����ϊv�̉\���̂Ȃ��u���A�����v�́A��R���̂Ȃ������ǔF�Ɠ����ł���ƌ����悤�B
�@�u���A�����Ƃ̐G�ꍇ���v�́A���҂Əo������̑��l�Ȍo���̒��ŁA�����ƈَ��ȔN��̐l�X�A�����ƈَ��ȕ��������l�X�ƌ𗬂��ď��߂āA�S�g�̑S�̂ɂ���Ċ����������̂ł��낤�B����ɁA���������u���A�����v�͎Љ�W�̍L����������邱�Ƃ��玩�R�ƌ������銴�o�̉ɂ܂ŘA�����Ă���B���Љ�ɂ����鐢�E�o����������Ӗ���[�߂���̂ɂȂ邽�߂ɂ́A���̂悤�ȓw�͂��K�v�ł���A���ꂪ�u�v�l�Ɗ��o���ђʂ��A�������邱�Ɓv�ɂ��Ȃ���̂��Ǝ��͍l����B
�@
�y��Փx�z
�y���̌X���z �@
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�@�y2010�E��R��z
�@����
�@���
�@�I���O�ܐ��I�A�t�H����̒����ł͎������x���h�炢�ŁA���Ǝ��̐��͂�z���悤�ɂȂ����B����Ƌ��ɑ召�̍��Ƃ��������A�����ł���悤�ɂȂ����_�����x�z��ՂƂ��鏔��́A�y�n�Ɣ_�����߂����đ��̏���Ƒ������B�Ⴆ�Β��]����̌��E�z�Ƒ^�������A�卑�ł������W���ł��鰁E�E��̎O���ɕ����ꂽ�̂͂��̎���ł���B�����I�ɂ����x�������̂��߂ɐl�ނ��L�����߁A�g���Ɋւ��Ȃ��o�p�����̂ŏ��q�S�Ƃ��o�ꂵ���B���̎���Ɏi�n�J�������Ă�����A���j���I�̌n�����ނ���u�����I�Ȏ������߁v�Ƃ����_���珖�q�����ł��낤�B�i�n�J�����ۂɐ��������̕���̎���ɂ͌��͂�w��̓��ꂪ�v�z�I��b�ł������̂ɑ��A�t�H����ɂ͎Љ������Ƃ�������s�f�̕ω��𑱂��A���j�I�ȏo�����ɂ��`���⌠�Ђɕ߂���Ȃ����l�Ȍ������\����������ł���B
�@���
�@�����ƃM���V�A�̗��j�Ƃ��r����O�ɁA�܂��u���j�̐����v�Ƃ͉������`����K�v������B�ۑ蕶�ł͎i�n�J�̋Ɛт��u�ُؖ@�I���j�N�w����b�ɂ��Đ��E���I�ɔc������v�Ƃ����_�ŕ]������Ă���A���̕��i�n�k�̋Ɛт��u���̓N�w�𒆐S�ɂ����A���̏��w�h�̒��������悤�Ƃ����v���ƂƐ�������Ă���B����炩��A�M�҂͗��j���u�N�w�I�ϓ_�Ɋ�Â��A���l�Ȑ��E���I�ɉ��߂��邱�Ɓv�Ƒ����Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@���̎��_����i�n�J�̗��j���q���l����ƁA�u����I���E���������߂�v���Ƃ����j�����̖ړI�ł���A���w������O��Ƃ��āu�t�H���p���v���ƂƁu�Փ`�𐳂��v���Ƃ̗������O��Ă���B�܂�A���j�𑨂���ꍇ�A���E���s�f�ɕω����邱�ƂƁA�ω����Ȃ���������ɘA������Ƃ�����̑��ʂ����A����ɂ���đ��l�ȏo�����ɓ���I���߂�^���邱�Ƃ��d������Ă���̂ł���B����́u���E�j�Ƃ��Ă̗��j�̐����v�ƍl���Ă悢�ł��낤�B
�@����ɑ��ČÑ�M���V�A�̗��j�Ƃ̎d���́A�����̒����E�����̒T���ɂ����Ă͌Ñ㒆���̗��j�����Ƌ��ʂ��邪�A���j�̑��������S���قȂ��Ă����B���ɁA�Ñ�M���V�A�̊w��̍���ɂ́u�ω����Ȃ����ՓI���݂ɉ��l��F�߂�N�w�v������A��ɕω�������j�͘_���ׂ��Ȋw�I�F���̑ΏۂƂ͍l�����Ȃ������B���ɁA���Ƃ����j���q���Ȃ���Ă��A����͎��ԂƏꏊ�Ɍ��肳�ꂽ���_�Ɋ�Â��Ă���A���̏��w�h�̒����⑽�l�Ȑ��E�̑����I���߂ł͂Ȃ������B�܂�A�����M���V�A�ł��قȂ�������̎��_�ɗ����ė��j���l�@������A�ٕ����̎��_�܂Ŋ܂߂ė��j�I���������߂����肷�邱�Ƃ͂Ȃ������B�����ł͐��E�̑��l���ǂ��납�A�M���V�A�S�̂����n�������j�������Ȃ������̂ł���B�䂦�ɁA�M���V�A�ł͐��E�j�͂��납�M���V�A�j�������݂��Ȃ������ƍl������B
�@����
�@���
�@���c���́A���a���u�푈�̕s�݁v�Ə��ɓI�ɍl����ƕ��a�Nj��Ƃ́u�����������Ă�������悢�v���ƂɂȂ�A�u���̂��߂ɐ����邩�v�Ƃ������_����������ƍl����B��������A�ϋɓI�Ȑ������Ƃ́u�������]���ɂ��Ă����ׂ����l�����v���Ƃł���ƍl�����A����̓i�V���i���Y���I������тт�B�u���a�w�v�̗���ł͐푈�̕s�݂����ɓI���a�Ƒ�����_�ł͕��c���Ɠ��������A���ꂾ���ł͍K�������͂ł��Ȃ��ƍl����B����ɉ����ĕn����l���N�Q���Ȃ����A�Љ�`���������邱�Ƃ��u�ϋɓI���a�v�̏�Ԃł���B�����ƒ��҂̗���̈Ⴂ�́u�푈�̕s�݁v��ϋɓI�ɕ]������Ƃ���ł���B�u�s�݁v�Ƃ������t�̎g�p�@���̂����ɓI�ɑ�����̂ł͂Ȃ��A�u�a�C�̕s�݁v��u���̂̕s�݁v�̂悤�ɁA�l���ɂƂ��ĕK�v�ȏ����͐ϋɓI�ɕ]�����ׂ��ł���B�����邱�Ǝ��̂ɉ��l������A������Ƃ����ړI�̂��߂ɑ��̎�i���K�v�Ȃ̂ł���B������Ƃ����ړI�Ǝ�i����v���Ă���ꍇ�A��X�͍K����������̂ł���A���̈Ӗ��Łu���a�ɐ����邱�Ɓv�u���a���x����Љ�I�w�͂����邱�Ɓv�u�w�͂��b��Ɗ����邱�Ɓv�͖��ڂɌ��т��Ă���ƕM�҂͍l���Ă���B
�@���
�@�܂����a�̋t�́u�푈�v�Ƃ͉������l���Ă݂悤�B�Ⴆ�Ήp���̓N�w�҃z�b�u�Y�́A�l�����R�ɍs������ΕK�����̌l�̎��R�ƏՓ˂��邩��A�Љ�̎��R�ȏ�Ԃ́u���l�̖��l�ɑ��铬���v�Ɏ��邱�Ƃ��w�E�����B���ۂɐ푈��ԂɂȂ�Ȃ��̂́A���ƂƂ����������u���������~�߂Ă��邩�炾�Ƃ����B���c�P�����́A�u�푈�s�݁v�̕��a�ɂ��A�l���̈Ӌ`�⍑�ƁE�������ւ̈�������������ƍl���Ă���B�������A�z�b�u�Y�̋c�_�ɏ]���A���ǁu��������邽�߂ɍ����K�v�v�Ȃ̂ł��邩��A���̂��߂ɐ키�Ƃ͎����̂��߂ɐ키���Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�܂�A�u�푈�Ȃ����a�v�Ƃ�����`����ɐ������킯�ł͂Ȃ��B����A���a�w�҂��l����n����܂ł��܂߂āu���a�v���`����̂́A�@���E���������������Ɏv�z��M���̈Ⴂ����N����̂ł͂Ȃ��A����炪�n�x�̊i������̐��ƌ��т��ċN���邩�炾�낤�B�܂�푈�s�݂Ƃ������ɓI���a�̊�b�̏�ɐϋɓI���a�́u�l�Ԃ炵����炵�v������̂ł͂Ȃ��A�ނ���u�l�Ԃ炵����炵�v�̎������푈��h���̂ł���B�����ł��u�푈�Ȃ����a�v�Ƃ�����`�͏\���łȂ����Ƃ��킩��B
�@�����ɑ��āu�a�C�̕s�݁v�Ɠ��l�Ɂu�푈�̕s�݁v�������邱�Ƃ̖{���I�ȉ��l���x�����i���ƒ��҂͌����B���̌��ʁu���a�ɐ����邱�Ɓv�u���a�ɐ�����w�́v�u�w�͂��b��Ɗ����邱�Ɓv�����т��̂�����A���a�����̈Ӗ��ƕs���ł��邱�Ƃ͂悭�킩��B�������A�푈�̕s�݂Ƃ������a�̒�`�́u���l�ȕ��a�̌����v���\�������ł��Ă��Ȃ��B�Ⴆ�Εa�C�s�݂̏�Ԃ����N���Ƃ���A��X�����N�ł�������Ԃ͈ꐶ�̂����킸�������Ȃ��B�l�Ԃ͖{���a�C�Ɖ��J��Ԃ��Ȃ��琶������̂����炾�B
�@���l�Ɂu�ǂ̂悤�Ȑ킢���Ȃ��v���Ƃ����a�ł͂Ȃ��B���Ƃ��Ǘ����ĕ��a����낤�Ƃ�����A�N�����L���ȉƒ�ɐ��܂�A�ꐶ���҂Ƒ���Ȃ��Љ��ڕW�Ƃ��Ă��A�����͕s�\���낤�B���������j�ɂ����Ă͐푈�̂Ȃ����Ԃ̕������������B��������푈�̂Ȃ�����͂Ȃ��������A�푈�ɂ��N���푈�E�v���푈�E����푈�ȂǁA�l�X�ȈӖ������킢��������B���̑Η����Ƃ��ĕ��a�ɂ����l�Ȃ����������ƌ�����B�䂦�ɁA���a�Ƃ͗l�X�ȁu�킢�v���܂߂đ��҂Ƌ������Ă������Ƃł���B���Ƃ������Ă����҂𗝉����A����Č݂��ɑS�ł�����ł��邱�Ƃ��^�́u���a�Ȑ������v�ł���Ǝ��͍l����B
�@�y��Փx�z
�@����B
�@�y���̌X���z
�@���j�L�q�̍���₤����ƕ��a�_���e�[�}�ɂ��������g�ݍ��킹�����ł���B��N�̖��Ɣ�ׂ�ƁA����͗��j���ǂ����邩�Ƃ����e�[�}�����P����Ă���B��N���o�肳�ꂽ���̗��j�������́A���N�̕����킩��ɂ����B�u����̋@�^�v�Ƃ����L�q���{���ɂ���̂ŁA�t�H����̕����I���͋C��ސ����Ȃ��瓚���邵���Ȃ����낤�B���͔�r�I�����₷���B����́u�푈�̕s�݂Ƃ��Ă̕��a�v�ɂ��āA���ŗv��A���ōl�@���v������Ă���B���m�Ȉӌ����Ƃ肠���Ă���A�c�_�̂܂Ƃ߂͗e�ՁB���͒m�����������őg�ݗ��Ă��c�_���d������ݖ�ł���A�ߋ���������ċc�_�̍\���𑊓���������K�v������B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�@�y2011�E��R��z
�@����
�@���
�@�Ñ�M���V�A�Ɂu�Љ�v�ɑ������錾�t���Ȃ������̂́A���I�ȍs���ƌ��I�ȍs���̋�ʂ��Ȃ��A�S�Ă��u������ԁv����������ł���B�|���X�Љ�ł́u���R�v�Ƃ͎����̐ӔC�Ō����̔C���𐬂������邱�Ƃł������B�A�����g���Ñ�M���V�A�̓s�s���Ƃ��u�\�S�Ȍ�����ԁv�ƍl����̂͂��̂��߂ł���B���[�}����Ɂu�Љ�v�Ƃ������t�����܂ꂽ���Ƃ́A������Ԃ��番����āu���I��ԁv�����܂ꂽ���Ƃ������Ă���B����͋ߑ�@�̋N���ƂȂ������[�}�@�����܂ꂽ���ƂƂ��֘A���Ă���B���Ȃ킿�u�����ɑ���`���Ǝ��l�̌����v���Η��I�Ɍ����A���I��Ԃ̐����ƌ�����Ԃ̐����Ƃ͋�ʂ���邱�ƂɂȂ����̂ł���B���퉺�́u�S�̎�`�v�́A�ꌩ�Ñ�M���V�A�̂悤�ɑS�Ă�������ԂɈꌳ�������̐��̂悤�Ɏv����B�������A�������Ƃ͖{���u�����̐ӔC�Ō����̔C���𐬂������邱�Ɓv�ł���A�����ɂ́u�o��v�⎩���I�ȁu�E�C�v�������Ă���B�S�̎�`�ł́u�s���̋`���v�͂����܂Łu�ォ��̋����v�ł���A�l�X�͎��I��Ԃ���肽�����猠�͂ɏ]���ɉ߂��Ȃ��B�䂦�ɂ����Ɍ�����Ԃ�����Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B
�@���
�@�����T�[�r�X���L���Ӗ��ł̐����I�������s���錻��Љ�ł́u������ԁv�͑��݂��Ȃ��B���̔��ʁA�l�X�́u���I��ԁv�ɕ��������Ă���킯�ł��Ȃ��B�u���I��ԁv�Ƃ́A������ԂɑΗ�����u�l�̎��R�v�Ƃ����o��Ɋ�čs�������Ԃ�����ł���B����̐l�Ԃ́u���R�v�ɔ������Ă���悤�Ɍ����邪�A����͖��ӔC�Ȕ�����������郁�f�B�A���Ɉ��Z���Ă��邩��ł���B�u��O�̋�ԁv�Ƃ́A���̂悤�ȁu������Ԃł��Ȃ����I��Ԃł��Ȃ��ی삳�ꂽ��ԁv�ł���B���́u��O�̋�ԁv���u�\�S�ȁq������ԁr�v�Ƃ��ċ@�\����\��������ƍl����B���̏����́A�s�����V���ȁu�o��v�������Ƃł���B�Ⴆ�A�l�b�g�f���̏������݂����҂�������͂́A�����ɂ��ꂾ���������҂Ɗւ��͂ł�����B�l�b�g��̉��z��Ԃ́A���͂�����Ă����l�X�������̗͂����o�����ԂɂȂ蓾��B�������A�u�o��v�̓�ʐ������o���邱�Ƃ��ۑ�ł���B�|���X�Љ�̐����I���R�������Ɛ藣���Ȃ��悤�ɁA�l�b�g��̕\�������Ƃ����u���R�v���u���҂ւ̐ӔC���ɂ݁v�ƈ�̂ł���B���̗��ʂ�S�����o�������ƂŁA�u�V���Ȍ�����ԁv�����藧�̂��Ǝ��͍l����B
�@����
�@���
�@�h�q�́A��l�̎d���Ƃ͔N�v���W�߂邱�Ƃ����ł͂Ȃ��A�n��Ɛl���S�̖̂ʓ|�����邱�Ƃ��Əq�ׂĂ���B�߂�Ƃ��Ă������������Εs��ɕt������A�O��������ď������s��Ȃ������肷��̂͌��̖@�����Ă��邱�ƂɂȂ�B����䂦�@�ɑ������������K�v�ł���B�����������ɁA�̖��������o���̂͐�������������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�̖��̍s���̌�����[���Nj�����A����͈א��҂ɂ��ǂ���B�u���R����q�w�ɌX�|����Ă����̂ŁA�I�����_�Ɋ�S��I�Ȗ��𒆐S�ɋc�_�����Ă����v���Ƃɑ��A�h�q�͐����������ʂ��鎋�_�ňӌ����q�ׂ�B�Ⴆ�ΐ������ꂵ���A�����̂āA�����ŕ�e�����̂Ă邱�Ƃ͎������炷��u���v�ł���B�������A���̍��{�I�Ȍ�����������͈̂א��҂ł��邩��A�ނ��둺�ƕ�e���̂Ă��{�l�̍߂͌y���B�䂦�ɔ�����������{�����̐�������������ׂ����Ƃ����̂ł���B���������ʊW���d������h�q�́A�ʼn��w�̐g�����ʂ��{���͕a�C�̊u������n�܂������ƁA���̂Ă���l�X����������ΎЉ�s�����������ƂȂǂ������A�����Ɋ���s�����ȍ��ʂ���̕��u�����ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ��咣���Ă���B
�@���
�@�����̎Љ�͖��{�̍����j�]�ɂ���ĕn�����������Ă����B�n�����������Ŕ_�����̋����o���A�d�������߂ēs�s�ւƈړ������B��Ƃ��������Q�l�Ȃǂ��܂߁A�s�s�ł͕��Q�l����������������Ă����B�h�q�͖{���a�������Ŋu������A�g�����Œ肳�ꂽ�ʼn��w�̕��Q�l�ƐV���ȕ��Q�l�ł���u�V�������Ԃ�v����ʂ��A�V���ȕ��Q�l�̑��������O���Ă���B���Q�l�͈�ʎЉ��u�₳��A����ɐ������s����Ŏ��Ɨׂ荇�킹�Ă���̂ŁA�S���r��ł���B������א��҂��l�̌�����d���Ɏg���̂ŁA���l�Ԃ��r��Ă���B���̂悤�Ȑl�������Љ�ɑ�����Εs���̎��Ԃ���������B����A���Ƃ̘Q�l�͎�ɐE���Ȃ��̂ŁA�����Ɏ����߂�҂�����B���̂悤�Ȗ�����������ɂ́A����������P���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̂Ă�҂ɂ͌o�ϓI���������Č̋��ɖ߂��A���m�̏ꍇ�ɂ������̎��邽�߂̎d���ɏA�����Ƃ�W����ׂ��ł͂Ȃ��B�������ړI�ł͂Ȃ����畐�Ƃ̓����ɂ͔����Ȃ��B�����̖��͐����ɔ����A�א��҂̍߂ƌ�����B�䂦�ɐ����ɐӔC�����闧��̐l�Ԃ������̂��߂ɓw�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɯh�q�͍l���Ă���B
�y��Փx�z
�@�W���I�B
�y���̌X���z
�@�������ɂ��Ė₤����Ɛ����Ɠ����̊W���e�[�}�ɂ��������g�ݍ��킹�����ł���B
�@�����2009�N�x�̌c��@�w���̖��Əo�T������ŁA�o��ӏ��A����Ă�����e�Ƃ��Ɋ֘A�������B�������ƌc��@�w���̖��͉ߋ��ɂ����l�̗Ⴊ�������B���ʂɎg����u�������v�Ƃ������t���A�Ñ�M���V�A�����̕����ł́u�l�ƎЉ�̂���ׂ��p����v���Ă��邱�Ɓv�ł���A����̃l�b�g���[�N�Љ�̐l�Ԃ̂�����Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�Ƃ��낪�|�C���g�ł��낤�B
�@����̐������́A�������N�̂��Ƃł��邪�A�������ǂ̒��x�܂ŏڂ����������邩�Ŗ������B���j�I�m����₤�킯�ł͂Ȃ����A���������ł͐����s���̊�������A���͖��������m��Ȃ��B
�@
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�@�y2012�E��R��z
����
���
�@��ꎟ���E���ɂ���č�������h�C�c�ł͈��ꔪ�N�ɍc�郔�B���w�������ވʂ��A�����N�ꌎ�ɎЉ��}�E�����}�E�h�C�c����}�̃��C�}�[���A���ɂ�鐭�{�����������B�����ɂ͋��a���A�B�ɂ��A�M���A��{�I�l���̑��d�Ȃǂ����������C�}�[�����@�����z����A���C�}�[�����a�������������B�s�퍑�h�C�c�ɂ̓��F���T�C�����ŗ̓y�̍팸�A�R���E�Y�Ƃ̐����A���z�̔��������ۂ��ꂽ�B�t�����X�Ƀ��[���n�����̂��ꂽ�h�C�c�o�ς͈����N�̐��E���Q�ɂ�肳��Ɉ������A���O�Z�N�㌎�̑I���ő��}�ɂȂ����i�`�X�i���ƎЉ��`�h�C�c�J���ғ}�j�́A���F���T�C���̐��ƃ��C�}�[�����a���ɑ��鍑���̕s�����z���グ�Đ��͂��g�債���B���O��N�����̑I���Ńi�`�X�͑��}�ƂȂ�A���N�ꌎ�Ƀq�g���[���ɏA�C�����B�̍���c�������Ύ����̍ۂɔ��߂��ꂽ�ً}�哝�̗߂����@�̊�{�I�l�����~�A�i�`�X�ȊO�̐��}�͉����A����ɁA�O���̑S���ϔC�@�Ńq�g���[�̓��C�}�[�����@���������B���O�l�N�����Ƀq���f���u���N�哝�̂���������ƁA�q�g���[�͍��ƌ���Ǝ̒n�ʂ����˂鑍���ƂȂ�A���C�}�[�����a���͕����B
���
�@�������͂��|�p��i�̐���ɉ�������藘�p�����肷��ړI�́u��O�̈ӎ��`���v�ł���B�{���̃I�b�g�[�E�f�B�b�N�X�̍�i�͐푈�̔ߎS��������̂܂ܕ`�������߁A�}��E����̈ӎ��������ɍL����̂�����鐨�͂���Ƃ�e�����A��i��v�������̂ł���B
�@���l�̗�͓��{�ɂ��������B����̒e���Ƃ����_�ł͈���Z�N�ォ��s��܂ł̊ԁA�v�����^���A��Ƃ̏��������ւɂȂ�����A�V���[�����A���Y���̉�Ƃ��u����s�\�v�䂦�Ɏv�z�ƂƂ��Ď����܂�����肵�����Ƃ���������B�����́u�\�����Ă͂Ȃ�Ȃ����e���֎~����v�Ƃ����r���̘_���ł���B���̌��ʁA�����̍�i������ꂽ�B
�@�t�Ɂu�\�����ׂ����e�����シ��v�Ƃ����}���̘_�����g����B�Ⴆ�Γ��{�̗L����Ƃ��Ƃ��]�R�|�p�ƂƂ��Đ�n�ɑ����Đ��삳�ꂽ�u�푈�G��v��u�]�R���w�v�ł���B�����́u�����ɂ���Đ��삵���v�Ƃ�����Ǝ��g�̎v��������͕��ꂽ���̂������B
�@�������A�r���ƌ}���ɂ���Ă������Ȃ��|�p������i�ɂ͂���A���̗͂͐����I�Ӑ}������̂��Ǝ��͍l����B
����
���
�@���{�ɂ������w�M�Ƃ͐_���ł���B���̐��i�͑��Ɏ��R���q�̑��_���ł���A���R�̃J�~�͍��J�̑Ώۂł�������ɏh������A�R���̂��u��_�́v�Ƃ��Đ��q����A��т�����Ƃ��ꂽ�肷��B�L�I�_�b�ł����z�_�Ƃ��č��V�����x�z����A�}�e���X�A��̐��E���x�z����c�N���~�A�C���x�z����X�T�m�I�ȂǂɎ��R�ւ̐M��������B���̓����Ƃ��Ă͑c�쐒�q������B�d�v�l��������ɃJ�~�Ƃ��čՂ��邾���łȂ��A��Ƃ̎��𐋂����l��������Ƃ����M�邱�Ƃ�����邽�߂ɃJ�~�Ƃ��Đ_�ЂɍՂ��邱�Ƃ�����B���d�ɐe���̈ʔv���J�邱�Ƃ��A���̈�[�ł���B����ɁA�y�n�̃J�~�E���_�ȂǁA�n���⌌���̌��т������y���̃J�~���M�̑ΏۂƂȂ�B
�@�����̃J�~�ɋ���������A�j���������邱�Ƃ���p�I�ȍ��J�̋��ʓ_�ł��邪�A���ꂼ�ꂪ����̒��ŋ�ʂ���邱�ƂȂ��A�N���s���Ȃǂ�ʂ��Đ܁X�̐����Ɏ�荞�܂�Ă���Ƃ���ɓ��{�I��w�M�̑傫�ȓ���������B���ɔ_�k�Љ�̐��Y�T�C�N���ƌ��т����N�ԗ�̍��J�͌���ɂ��c��A���@�̍s���ɂ���������Ă���B
���
�@���Տ@������w�M���ۂ�����Ƃ��āA�L���X�g���ɂ��Q���}�������̐M��荞�݂��l���Ă݂�B�I���O���N�ɃL���X�g���̓��[�}�鍑�̍����ƂȂ�A���[���b�p�S��ōL���M�����悤�ɂȂ������A�����[�}�̖ŖS����V���Ȏx�z�҂ł���Q���}�������ɍL�������B
�@�L���X�g�����ً��k�ł���Q���}���l�Ɏ������ߒ��ŁA�Q���}���̊�w�M�ł��鑽�_���̐_�X��N���s�����L���X�g���ɕ�ۂ���邱�ƂɂȂ����B�Ⴆ�A�����Ձi�C�[�X�^�[�j�̓C�G�X�̏��Y��̕������j���s�������A�~���߂��Đ��������̕������j���Q���}���̏t���ՂƃL���X�g���̕����Ղ��Z���������̂ƌ�����B�\��\�ܓ��̃N���X�}�X���{���̓L���X�g�̒a�����ł͂Ȃ��A�����̏@���̓~���ՂƏd�Ȃ��Ă��邽�ߏj����悤�ɂȂ����B
�@�������A�����_�̎p���Ƃ�{�n��瑐��Ƃ͋t�ɁA�Q���}���̐_�X�̓L���X�g���̒��ɖ����∫���̂悤�Ȕے�I�v�f�Ƃ��Ď������ꂽ�ʂ�����B����ł��Ȃ��A���[���b�p����̒��ɖk���̐_�u�e���[���v�̓��i�Ηj���j�Q���}���̐_�u�E�H�[�_���v�̓��i���j���j�k���̐_�u�g�[���v�̓��i�ؗj���j�̂悤�ȓ��퐶���ƌ��т����`�Ŋ�w�M�͎c���Ă���B
�y��Փx�z
�@����B
�y���̌X���z
�@�|�p�\���ւ̐����I�e���ɂ��Ė₤����ƕ��Տ@���̌`���ɂ��Ė₤�����g�ݍ��킹�����ł���B��N�o�肳��Ă������E���̗��j�������͈Ղ����Ȃ����B�{�����Ƀ��C�}�[�����a���̏o������������Ă���̂ŁA�⑫��������ΉɂȂ�B
�@����A����̗����Ƃ���N�̂悤�ɍl�@��K�v�Ƃ�����ł͂Ȃ��A�m�����S�̉�������߂�����ɂȂ����B�_���I�v�l�͂̎����ƌ������̓N�C�Y�ɋ߂��B
�@�������A���p��@���ɂ��Ă�����x�̋��{���Ȃ���Γ������Ȃ��_�ŁA�����ƌ�����B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�@�y2013�E��R��z
�y��z
����
���
�@�ۑ蕶�ɂ��A�n�}�ɓT�^�I�Ɍ������ԊT�O�̓]�����̓��l�b�T���X���E��q�C����ł���B����ȑO�̎���ɂ́A�A���X�g�e���X�ɑ�\����鋁�S�I��Ԃ̃C���[�W���x�z�I�ł���A��Ԃ͈Ӗ��Ɩ��ڂɌ��т��Ă����B�ꏊ�ɂ͂��ꂼ��̈Ӗ�������A����ɐ��E�S�̂����ۂ̕�҂Ƃ��ẲF���I�ȈӖ��������Ă����B�]���āA����ꏊ�ɑ��݂���Ƃ������Ƃ͂��钁���̓��ɂ���Ƃ������Ƃł���A�ꏊ�̈Ӗ����l�Ԃ̍s���̋K�͂ɂ��Ȃ��Ă����̂ł���B����ɑ��āA���l�b�T���X�Ȍ�̋�ԊT�O�͑��肳���ׂ��ΏۂƂ��Ă̐��E�Ɋ�Â��Ă���B�f�J���g�̍��W�n�ɐ��l�Ƃ��ċq�ϓI�ɕ\�����悤�ɁA��Ԃ͈Ӗ�����藣���ꂽ�����Ȃ��̂Ƒ������A�ϑ��҂ł���l�Ԃ̊O���ɂ��闝�z�I�Ȋ�ƂȂ����B�ߑ�Ȍ�̐l�Ԃ́A�܂����z�I�Ő�ΓI�ȋ�Ԃ�ݒ肵�A�����w�i�ɋ�̓I�Ȏ��ۂ��������B���ꂪ�ߑ�Ȋw�̊�b�ƂȂ�������A���Ԃɂ����鎖�ۂ̋L�q�́A���鎋�_���猩���f�ГI�Ȃ��̂ɂȂ炴����A���ۑS�̂���Ԃɑ����ċL�q���邱�Ƃ͕s�\�ƂȂ����B
���
�@��㎵�Z�N��ȍ~�̑傫�ȎЉ�I�ω��́A�R���s���[�^�̓����Ə��̃f�W�^�����ɂ���Ă����炳�ꂽ�ƌ�����B����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ��ԊT�O���u���z��ԁv�ł���B���z��Ԃ́u���z�������v�̋Z�p�ɂ���ĉ\�ƂȂ����B���z�����̐��E�Ƃ̓R���s���[�^��ʏ�ɍ\������郊�A���ȗ��̑��ł���B�f�W�^���摜�̊�b���f�J���g�I���W��Ԃł���ɂ�������炸�A����͎������Ɂu���݂��Ȃ��z����������������ԃC���[�W�v�����B�ߑ�ȍ~�̉Ȋw���Ώۉ����q�ω��������E���A�f�W�^���Z�p�ɂ���āu�V�����Ӗ��Â��̉\�Ȑ��E�v�ɐ��܂�ς�����Ƃ��l������B����ɁA�l�b�g���[�N�Z�p�̔��W�Ől�Ԃ̃O���[�o���ȂȂ��肪�`������A�ӎ��̏�ł͋ߑ�I�Ȏ��ԂƋ�Ԃ̌��肪���Ή����ꂽ�B�ŋ߂ł͘A���I�Ƀl�b�g���[�N�Ɛڑ�����郆�r�L�^�X�Z�p���i�����A�ړ����ł��l�b�g���[�N�ɂȂ����ď��̎�M�Ɣ��M���ł���悤�ɂȂ����B����͌������E�Ɖ��z��Ԃ̋��E����苎���āu�g��������ԁv�̃C���[�W��n�o���Ă���B�R�c�v�����^�̕��y�Ȃǂ������A�����I�Ƀf�W�^����Ԃ��������̌�����Ԃ�傫���ω������邱�ƂɂȂ�Ǝ��͍l����B
����
���
�@1853�N�V���A�y���[��������������ĉY��ɗ��q���]�˖��{�ɊJ���𔗂����B���N���Ęa�e���������č����̐��͏I���B58�N��V��ɒ��J�͒����̂Ȃ��܂ܓ��ďC�D�ʏ�����������A�����Ɂu�����̑卖�v�ɂ���Ĕ��Δh��e�������B���������鐅�˔˂�F���˂̘Q�m��60�N�R���A�o��r���̈�ɂ����c��O�ňÎE����B��Ɏ���A�V���̋v���L���E�����M����͎��Ă������{�̌��͂������邽�ߌ������̂���A���R�ƖƍF���V�c�̖��E�a�{�Ƃ̌���������������B���ꂪ�����h���h�����A62�N�Q���A�V�������͍]�ˏ�≺��O�ŏP������A���r����B���N�X���ɂ͐������ŎF���ˎ哇�Ëv���̍s������f���悤�Ƃ����p���l���a������鐶���������N���邪�A���̌�̉��֎����A�F�p�푈�Ȃǂŝ��Δh�����O���ɋ������A���̔��������炩�ɂȂ�B67�N11���A����c��͑吭��҂��V�c�ɐ\���o�A68�N�P���R���ɉ������Â̑卆�߂��������Čc��̏��R�E���E�ƐV���{���������\���ꂽ�B���̌�A��A�̕�C�푈�̐퓬���s�Ȃ�ꂽ���A��������V���{�R�̏����ɏI���A71�N�W���ɔp�˒u�����f�s����Ė��ˑ̐��͏I������B
���
�@�ۑ蕶�ɂ��ƁA�u���v�Ƃ����L���X�g���r�˂ɑ��ėp����ꂽ���t�́A�������ɊO�����͂ւ̑R�Ƃ����V���ȈӖ���S�킳�ꂽ�B�������A�u���v�̋�̓I���e�͞B���ł���B���j���E�O���l�Ǖ��Ƃ��������̌p�����l�����邵�A�t�ɐ����ߑ㍑�Ƃƌ�����ׂ邽�߂ɂ́A��������ŐV�Z�p��ߑ�I���x��A�����邱�Ƃ��s���ł���B���������u���v�̖������鐫�i�̏�Ɂu�����I�v���v���i�s�����̂ł���B�]���āA���ꂪ�u�v���v�ł��������ǂ����͓����҂ɂ���ĕς��B���{�̓������������Ȃ���������̋ߑ㉻�����������̂́A�古�l�����̌o�ϗ͂����n���Ă�������ł��낤�B�ނ�ɂƂ��Ắu���v�̒�`���A�J���ƌo�ϊ����̎��R���d�v�ł������B����͈�ʂ̖��O�ɂƂ��Ă����l�ł���B����A�ېV�ɂ���ĕ����I�g�����̍������������m�����́A���͂̂��鉺�����m��O�l�̏��˂����{�ᔻ�ɗ��p�����̂ɑ��A�����������x�z�K�w�͏��O���̗v���ƕېg�̊Ԃŏꓖ����I�ȑΉ������ł��Ȃ������B�u���v�𗝑z�������l�X�͌�҂̐��͂ɑ����A�S�̂��猩��Ώ����h�ɉ߂��Ȃ��������߁A�ނ�ɂƂ��ĈېV�́u����ꂽ�v���v�������Ǝ��͍l����B
�y��Փx�z
�@��N�����Ղ����B
�y���̌X���z
�@����͂��Č��㕶�ł悭�o�肳�ꂽ���́B���̋�ԃC���[�W�̕ω��͖����Ȑ������Ȃ���Ă���̂œ���Ȃ����낤�B���́u70�N��ȍ~�̎Љ��Z�p�̕ω��v�Ƃ����|�C���g����u�f�W�^�����v�Ɓu�l�b�g���[�N���v�ɋC�Â��K�v������B��������Ƌ�ԊT�O�̕ω��Ƃ��āu���z�����v��_���邵���Ȃ��B
�@����͑�̓h���}�ɂ��Ȃ��Ă��開���j�ł���B���͓���Ȃ����A500�������Ŗ����j���o����������Ă܂Ƃ߂�̂͑�ςł���B�o��Ӑ}�ɋ^�₪�c��B���͖{���̋L�q���q���g�ɂ��Ď����̌��t�ł܂Ƃ߂�悢�B
��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B
�@�y2014�E��R��z
�y��z
�@����
�@���
�@�ߑ㍑�Ƃ��Ȃ킿�������Ƃ̕x�̌���͘J���ł��鑽���̐l���ł������B���̂��߁A�������{���ߑ㉻��i�߂�ߒ��ŁA�J���ƕ����ɏA�����Ƃ��\�Ȑl���𑝂₵�A�����́u���N�v���Ǘ����邱�Ƃ����Ƃ̊�{�I�Ȑ���ƂȂ����B���̒S����ƂȂ����̂����m�ߑ��w�ł���B�ߑ��w�͂܂����Ƃ̖@���x�ƕ��ԎЉ���V�X�e���Ƃ��č̗p����u���x���v���ꂽ�B��w�͍��Ƃɂ���Č��F����A��t�͍��Ǝ��i�ƂȂ����B���̌��ʁA�o�����玀�S�܂ł��@�߂ɂ���ĊǗ������A���Ƃ̐l�������V�X�e���Ƃ��Ă̈�Â����܂ꂽ�̂ł���B���x�����ꂽ��w�̎�Ȗ����́A��O�͗D������A���͌��N���i����̐��i�ł������B�ǂ���̐���ɂ����Ă��u���N�v�Ɓu�N�v����ʂ��A���N�łȂ�������r���܂��́u���Áv���邱�Ƃ���t�̔C���ł������B����ɐ��͗\�h��w���d������A���{�Ǝ��́u���l�a�v�u�����K���a�v�Ȃǂ̊T�O�������ɂ���č��ꂽ�B����ɏ]���A�����͍��Ƃ��w������u�����������v���퐶���𑗂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���m��w�͍����\�Z�ɂ���č��Ǝx�z����Ă��邽�߁A�V���Ȑl���Ǘ��̐����Ă����x�ɂ����ǔF���A�Ӗ��Â����������S�킳��Ă���B
�@���
�@�u���N�v�͖{���u�a�v�̑Η��T�O�ł���B�������A����̓��{�Љ�ł͈�w�I�ȁu���N�v������߂Č��肳�ꂽ��Ԃƍl�����Ă���B�����A�����l�ȂǂɂƂǂ܂炸�A�������b�A���́A�Љ�Ɏ���܂Łu����͈́v����`����A�͂ݏo���l�͑S�āu�ُ�v�Ŏ��Â�v����ƈ�t�ɂ���Ďw�������B���z�̌��N���f���́A����^�o�R�̏K�����Ȃ��A�W���̏d�Ŗ����^�����A�h�{�o�����X���Ƃꂽ��J�����[�̐H�������A�Y�݂�X�g���X���Ȃ��A�悭����č���ɂȂ��Ă������̎��������l�ł���B�������A����Ȑl���͎��݂���Ƃ��Ă������ł��낤�B�܂�A�u���N�v�͌����I�ȏ�Ԃł͂Ȃ��A�ϔO�I�ȗ��z�ɕώ����Ă���̂ł���B���̌��ʁA���퐶���𗝑z�����悤�Ƃ���l�X�́u���N�H�i�v��u���N���v�ɕq���ɔ�������B�������ϔO�I�Ȍ��N�ȂǓ����Ȃ�����A�l�X�͐V�������N���i���o�邽�тɂ��܂ł��ǂ������邵���Ȃ��B�����ɁA�B������Ȃ����N�ւ̕s�������퉻���A����ɑ��ėl�X�ȕی����i�������B�u���N�v�������炵���������ƍl����A����͈�l��l�قȂ��Ԃł���B�l�Ԃ̑��l�Ȃ������F�߁A���d�ł���Љ�̎������K�v���Ǝ��͍l����B
�@����
�@���
�@���҂̏q�ׂ�u�m���l�v���͓Ɠ��̂��̂ł���B���̒��S�I�Ȓ�`�́u�����h�v�ł��邱�ƂƁu�����̐��O�̒m�����������ҁv�ł��邱�Ƃ��낤�B�u�����h�v�͎Љ�Ɍx����炵�A���}�h���̂Ȃ����݂ł��邱�Ƃɒʂ��A�u�A�}�`���A�I�����ҁv�͗��_�ƂƎ��H�Ƃ̔}��҂ł��邱�ƁA�w��̘g�g�݂𑊑Ή�����͂������Ƃɒʂ���B�ߑ���{�ł̓h���t���X�����̂悤�Ɍ��J�̏�Ő��{�ƑΗ����錾�_���s�Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��������߁A�ۑ蕶�̂悤�ȈӖ��ł̒m���l�͂قƂ�nj����Ȃ��B�����ĒT���A��t�����ōK���H�������Y���ꂽ���Ƃɔᔻ�I�Łu����ǂ̏v�\�����ΐ��́A���҂́u�m���l�v�ɂ��߂��ƌ�����B�������A�����Ȍ�̋ߑ㉻�̎���Ɍ��_�̒��S�������m���l�̑����͉Ėڟ��̂悤�Ȋw�҂����V�@�g�̂悤�ȃW���[�i���X�g�ł���A�ǂ���������ȗ��̓}�h���Ɩ����ł͂Ȃ������B����ɉ����A�ߑ�̒m���l�͍����w�������G���[�g�̓����w�ł������B����������������A���{�ߑ�̒m���l�͗���ɂ�����炸�u���Ёv��ттĂ���A�u�f�l�Ƃ��Ď��R�ɔ�������v���Ƃ���͉����A�g�����ʂ����ΐÂ��ɑޏꂷ�邱�Ƃ��ł��Ȃ������ƍl������B
�@���
�@�ߑ�̓��{�ł͓���������҂́u�m���l�v���́A�ނ��댻��Љ�ɂ����đ傫�ȈӖ������B����͑��Ɂu��含�v���ω���������ł���A���Ƀ��f�B�A�����l����������ł���B�܂��A�m���̍ו����ɂ���Đ��Ƃ̈����̈悪�����Ȃ�A�����I�Ȓm��������Ȃ����B�Ⴆ�A��������������ϗ��ɔ����Ă��Ȃ����ǂ������������邽�߂ɂ́A�e�����铖���҂Ƃ��Ĉ�ʐl�̍��ӂ��s���ł���B���̍ہu�f�l��\�v�Ƃ��Ă̒m���l�̔����́A��ʐl���Q�l�ɂ�����A�j�ƂȂ�ӌ��̌`����������Ƃ����_�ŗL���ł���B���ɁA�l�b�g���[�N����̃��f�B�A�͑��l�����A�p�u���b�N�Ȉӌ��\�������R�ɂł���悤�ɂȂ����B�Љ�I�ɔ������邱�Ƃ������ł͂Ȃ��Ȃ����̂ł���B���ꂾ���Ƀ��f�B�A��ł̋c�_�͋ʐ����Ŋg�U�������ł���A�_���I�Ȉӌ��A�R�ӌ��̕K�v�������܂��Ă���B�����Ɋ����̊w��I�Șg�g�݂𑊑Ή��ł���u�m���l�v�̐V���Ȗ��������܂��B�������̂Ȃǂł͐��Ƃ̑Ή��͂Ɍ��E�̂��邱�Ƃ��킩�����B����̐�����l�����ŗl�X�Ȏ��_������Ɖ����@���Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���A���̖ʂł��u�m���l�v�̌��_�͗L���������Ǝ��͍l����B
�@�y��Փx�z
�@�W���I�ȃ��x���̖��B
�@�y���̌X���z
�@����͌���̊Ǘ��Љ�_�B���̂܂Ƃ߂͗v�_���`�F�b�N���Ă��������Ŋ������邩�����Ȃ��B�������ӂ𗝉����Ă���Γ���Ȃ����A��̓I�ȏ������邱�Ƃ��ł��邩�ǂ������d�v�B
�@����͒m���l�_�ł��邪�A��⒊�ۓI�ȕ��͂ŋ�̑������݂ɂ����B���͒��҂̌����u�m���l�v�Ƌߑ���{�́u�m���l�v�̎�������ʂ��Ę_����ׂ��B�`���I�Ȓm���l�_��m��Ȃ��Ə����ɂ�����������Ȃ��B���͒��҂́u�m���l�v��������ɂ����čl������B�l�b�g�ł�����������ł��鎞�ゾ���炱���u�����h�v�̈ӌ��ɂ�����������₷���B�o��Ӑ}�͂����ɂ��邾�낤�B
�@�y2015�E��O��z
�@�y��z
�@����
�@���
�@�ۑ蕶�Łu��Ώ̐��v�ƌ����Ă���̂́A�u���`�v�ɑ��Đl�X���������邱�Ƃ����Ȃ��̂ɔ�ׁA�u�s���v�ɑ��Ă͑����̐l�X���������S���ɂ߂č������Ƃ��w���Ă���B��Ώ̐��̌����Ƃ��āA���҂͂܂����`���u������O�̍s�ׁv�Ƃ��ĊS���������A�u�ߏ�Ȑ��`�v��u�s���`�v���l�Ԃ̐����ɂ�薧�ڂȊւ������u�Ӗ��̂�����v�ł��邱�Ƃ���������B�������A����́u���`���̗₽���v�ւ̔�����u���`�ւ̕s�M�ƕs���ւ̕���̋����v�Ȃǂɂ���Ĕے肳���B���ɕM�҂́u���`�Ƃ͉����v�Ƃ������`�̒�`�E���`�T�O�����m�łȂ����Ƃ��w�E���Ă���B����ɑ��āu�������`���v�Ƃ������`�����E���`�ς͋�̓I�ł���A�����₷���B�������A��̓I�Ȑ��`�ς͕����⎞��ɂ���ĕς��A�����̗D������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����A���̍���ɂ͉��炩�̋��ʓI�Ȑ��`�T�O�������āA���̏�ɑ��l�Ȑ��`�ς��������Ă���B���l�Ȑ��`�ς��\�ɂ��Ă���̂́u���`���o�v�ł���A�s�������������ɁA�l�͂��̐��`���o������ɂ��ĕ���̂ł���B�܂�A���`�ƕs���ɑ���ԓx�̔�Ώ̐��́A���`���o�̔����̂��₷���Ɉˋ����Ă���ƌ�����B
�@���
�@���{�l�]���҂��o����������u�C�X�������v�ɂ��e�������́A�C�X�������̌��i�ȋ��`���߂Ɋ�Â��u���`�v���Ǝ咣����Ă���B����ɑ��ăA�����J�A���B�̐�i���́u�����`�̐��`�v��Βu���A�e����������Ă���B�������������ɂ��āu�@���Η��v�Ƒ�����̂͐������Ȃ����낤�B�ނ���u�������`���v�Ƃ������`�����E���`�ς̈Ⴂ�Ȃ̂ł���B�������A�U����E�l���u���`�̍s�ׁv�Ǝ咣����W�c�͗����ł��Ȃ����A�Γ��Ȍ��̑���ƍl���邱�Ƃ�����B�������A�ނ�̎咣��s�ׂɋ�������l�X�����Ȃ��炸���݂���̂������ł���B���̐l�X�́u���`���o�v�ɂ���ċ������Ă���̂ł��낤�B�ۑ蕶�̕M�҂͐��`���o�ɑi����v�f�Ƃ��āu�s���v���d�v�ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B���ȂƎ��Ȃ���芪���Љ�́u�s���v���������������A�s���̋]���ɂȂ��Ă���l�X�́A����𐳂����Ƃ̂ł���u���`�v�������x������̂ł���B�䂦�ɁA�����̊�b�ɂ���Η����u���`�T�O�v�ɑi���ĉ�������͍̂���ł���B�l�X��\�͂ɋ�藧�ĂĂ���u�s���v��u�s���Ȋi���v���ŏ�������w�͂ɂ���āA���ꂼ��̐��`�ς��߂Â��Ă����w�͂��K�v���Ǝ��͍l����B
�@����
�@���
�@�u�Q���Ƃ��Ă̐��v�́A�����ʂ�u���ꂪ�����Ă��邱�Ƃ����N�Ȃ��̂̐����Q����v�Ƃ������ł���B����͑��ɁA���e�̗���̂悤�ȁu���N�Ȃ��̂ƐڐG�����Ȃ��v�����̑Ώۂł���B�u�Q���v�́A�ŏ��u�u������鐶�v�Ƃ��ĉ���������B�g�̓I�ڐG�����ł͂Ȃ��A���N�Ȃ��̂̊�ɐG��邱�Ƃ����₳���̂ł���B���̖��H�́u���݂��邱�Ƃ�������Ȃ����v�Ƃ��Ė\�͓I�ɒf�₳�����鐶�ł���B���ɁA���̐��͕�e�̗��ꂩ�炷��u���҂𗠐������v�ł���B�{���u�����������݁v�Ƃ��Ĉ�Ƃ�w�������������҂���Ă��Ȃ���A�Q���ɕω����邱�ƂʼnƑ������]�����A�u�߂��������v���o�v�Ƃ��Ă̂ݐ�������鐶�ł���B�{���A��Â͐���������\���������A��Â����͂ȏꍇ�A���̐��͖Y����A��̂Ă��Ă��܂��B��O�ɁA���̐��͖��ɉ�삳���u�����ł��Ȃ����v�ł���B�Ƒ��̈���Ƃ��Ĉ����Ă���閅�����A�Ō�͐��b�ɔ��Ė��҈�������悤�ɂȂ�u���f�Ȑ��v�ł���B�����ł͐�����삷�鑤�Ƃ���鑤�̌𗬂ł͂Ȃ��A����I�ȁu����v�ɂȂ��Ă��܂��ƌ�����B
�@���
�@�ۑ蕶�̂悤�Ȑ��̂�����Ƃ��āA���Ắu�n���Z���a�ҁv�̐��������l���Ă݂����B�n���Z���a�͉Ȋw�̖����B�Ȏ���ɂ́u���܂킵�����݁v�Ƃ��āA�Ȋw�̗c�N���ɂ́u�s���̕a�v�Ƃ��āu���N�Ȃ��̂̐����Q����v�ƍl����ꂽ�B����䂦���҂͎Љ��B����āu�×{���v�Ɋu������A�����Ō�������l�͒f�킳�ꂽ��A�D�P������������ꂽ�肵���B�{���Ɂu���݂��邱�Ƃ�������Ȃ����v�������̂ł���B���݁A�n���Z���a�͎��Ö@����������A�u���ƍ��ʂ̐��x����肾�������Ƃ����炩�ɂ���Ă���B�������u��V�����l�v�Ƃ����A���傫�Ȏ���ŕa�𑨂��Ă݂�ƁA�a�҂͍��ł��u���҂𗠐������v�u�����ł��Ȃ����v�u���f�Ȑ��v�Ƃ��Ă̂������l�X�Ȍ`�ʼn��������Ă���B�ނ�ƕa�҂łȂ��l�̊ւ����́w�ϐg�x�̕��A��A���ȊO�ɂ��蓾��̂��B���̓����Ƃ��Ắu�n�������v�����������邾�낤�B���������Q���Ƃ͐l�Ԓ��S�̌����ł���A�ǂ̐������R�̒��ʼn��炩�̖������ʂ����Đ����Ă���B���l�ɁA�������͎ア����̐l�Ɉ���I�ɉ�������邾���ł͂Ȃ��A�ނ�̎v������������A�V�����������̎��_�����o�����Ƃ��d�v���Ǝ��͍l����B
�@
�@�y��Փx�z
�@�W���I�ȃ��x���̖��B
�@�y���u�]�z
�@����͐��`�_�ł���B���̂܂Ƃ߂͗v�_���`�F�b�N���Ă��������Ŋ������邩�����Ȃ��B�������ӂ𗝉����Ă���Γ���Ȃ����A��̗�������邱�Ƃ��ł��邩�ǂ������|�C���g�B
�@����͕����Љ�_�B�J�t�J�́u�ϐg�v���ނɁA�u�Q���v�Ƃ����Z���Z�[�V���i���Ȕ�g�Ō���Љ�̔r���̘_����ᔻ���Ă���B���̂܂Ƃ߂͓���Ȃ����A���͋�̗�Ɂu�r�����ꂽ�l�X�v��������̂�����ρB
�@
�@
�@�ۑ蕶�ŏq�ׂ��Ă���u������t���������v�̐��藧���́A�u��ԁv�Ɓu���ԁv�̑��ʂ��番�͂��邱�Ƃ��ł���B �@�܂��A�u��ԁv���Ȃ킿�n���I���ʂ���l����ƁA�u������t���������v�́u���Ƌ�ʂł���n��̕����v�Ƃ������ƂɂȂ�B�������A���́u��ʁv�̍����͗l�X�ł���B�Ⴆ�A�M�҂�����N���Ă���u���{�����v��Ǝ��̂��̂ƌ��Ȃ����_�́A���{���n���I�ɌǗ����������ł��邱�Ƃ��琶�܂��̂ł��낤�B����ɑ��āA�u�t�����X�����v�ȂǑ嗤�̕����̓Ǝ����́A�t�����X�ꌗ�Ƃ����u���ꋤ���́v�𑼂����ʂ��邱�Ƃɂ���Ĉӎ������ƍl������B�����A���̌��ꋤ���̂́u�����v�ƈ�v����킯�ł͂Ȃ��B�t�����X������p��̈�Ƃ��鋌�A���n�͑S���E�ɍL�����Ă���A�����̓����ɂ��u�o�X�N��v�ȂǁA�َ��̌�����������̂�����B �@�����ŁA�u���ԁv���Ȃ킿���j�I���ʂ�����l���Ă݂悤�B���������u�����̓����͕����I�ɓ���ł���v�Ƃ����l���������܂ꂽ�̂͋ߑ�ł���B�ߑ�Ƃ́A�n��I�ȑ��l���������Ă��������̏������̂��u�����W���I�ȓ����@�\��������������Ɓv�ɓ�������Ă���������ł���A�u�ߑ㉻�v�̕����ɂ����錻��ꂪ�u�����I��������v�Ȃ̂ł���B���̓_�ł́A�n���I�ɌǗ����A���R�̍����������{�́A�u�ߑ㉻�������I���ꐫ�v�̌��z���L�߂��ŗL���ł������B���j�I�ɂ́A���̂悤�ȁu�ߑ㉻�v�̈��͂ɂ���āu������t���������v�����܂ꂽ�̂ł���B �@�ȏ�̂��Ƃ���A�ߑ�I�ȁu������t���������v���`���I�ł���ΓI�ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B�����Ȍ�̓��{�Łu�W����v�ɂ���ĕ����������Ă������悤�ɁA�Љ�̒��́u���Ӄ}�C�m���e�B���������痣�ꂽ�����h�̐l�X�v���������A����A�����K���Ȃǂ́A�����̌��͂���߂��u�������ʁv�̊�ɍ��킹��悤�u�����v����A���ꂪ�u���������v�ƌ����Ă���̂ł���B �@����䂦�A�������z���Đl�E���m�E��ړ����錻��ɐ���������ɂ́A�������̃A�C�f���e�B�e�B���Œ肳�ꂽ���̂Ƒ�����̂ł͂Ȃ��A�����E���O���킸�A�َ��ȑ��҂Ƃ̏o��̒��Łu���݂̓Ǝ����Ƌ��ʐ��v���m�F���Ȃ��琶���邱�Ƃ��K�v�ł���Ǝ��͍l����B
�y�X�P�E��III�E����z�i����ȊO�̂X�P�N�x��́w�X�[�p�[���_���x�ɂ���܂��B�j
�@�E�q�́u�l�Ԃ͓����ɏ]���Đ�����ׂ��ł���B����C�܂܂Ɉ������s�Ȃ��͈̂ꎞ�I�Ȗ����������炷�����Ŗ��H�͔ߎS�ł���B�����炨�O���P�ɏ]���̂��悢�B�v�Ɠ���ɐ����B����́u�ߋ��̐��l�N�q�A�E�q�̒�q�����͌��l���������l���̍Ō�͔ߎS�������B�܂������͈������D�ނ��Ђ��͐g�ɂӂ肩����Ȃ��B�P�s�����s���A���܂ł������ق߂�ꂽ��A������������킯�ł͂Ȃ��B�����玩���̍D�݂ɏ]���Đ�����ׂ����B���ɓ������d�邨�O����x���D��ǂ��A�q�ɂ������Ȃ��Ȃ����B���O�̌������Ƃ͂����Ă���B�������ƋA��B�v�Ɠ�����B�E�q�͂�����ƌ����ׂ����t���Ȃ��}���ŋA�H�ɂ������A��قNjC��ꂵ���̂��D���x�����O���A����������ɓ��݊O�����B����𐢂̐l�́u�E�q�|�ꂷ��v�ƌ����B�ȏオ�ۑ蕶�̗v��ł��邪�A��҂͐��l�Ƃ��Ă̍E�q����j�邱�ƂŁA�����Ȃ鉿�l�����ΓI�ł��邱�Ƃ��咣���悤�Ƃ��Ă���ƍl������B�ȉ��̕��͂ŁA���͔����闧�ꂩ�瓐��̐���_���Ă݂����B
�@����̐�������������A���̉��l���o���I�Ɏ�����Ȃ������͖��Ӗ����Ƃ������ƂɂȂ낤�B�����ɓ����I���l�͕��ՓI���ۂ��Ƃ�����肪�o�Ă���B���͓���̎咣����u���l�����̔ߎS�Ȗ��H�v�������܂ő��҂��猩�āu�ߎS�v�ł��邱�Ƃ��B���l�����͎���̐l������̓I�ɓ����ɏ]���Đ������̂ł���A�����Ɍ�����������Ƃ͍l�����Ȃ��B�ޓ��̐��������א��҂Ƒ��e��Ȃ������肵���̂͌��ʂɉ߂��Ȃ��B������u�P�s�͕���Ȃ������v�ƍl����͓̂���̌����ł���B��������A�����I���l�͎�̓I�Ȑ������Ƌ����ւ��A���҂��q�ϓI�ɗL�p�������ł�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩��B����ł́A��̓I�ɑI�тƂ��铹���I���l�́A�����鎞���ꏊ�̈Ⴄ��l��l�ɂƂ��ĈقȂ����Ӗ������l�I�Ȃ��̂Ȃ̂��낤���B���������Ȃ�A�l���͎����̍D�݂ɏ]���Đ�����ׂ����Ƃ�������̐��Ɠ������_�ɂȂ��Ă��܂��B
�@���́A�����I���l�͌l�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ր������ƍl����B�D�݂ɏ]���Đ����邱�ƂƎ�̓I�ɓ��������H���邱�Ƃ̈Ⴂ�́A�Љ�I���i�ɂ���B�܂�A�����I���l�͕K���Љ�I�K�͂Ƃ������i�����B����ɑ��A�u�D�݁v�ɏ]���đP�∫���s�Ȃ��ꍇ�ɂ́A���Ƃ����̍s�ׂ����ʓI�ɑP�ł����Ă��Љ�I���i�͂Ȃ��B����͂����܂Ōl�I�Ŝ��ӓI�ȍs�ׂł���B���オ�ς��A�ꏊ���ς���Ă��l�Ԃ��Љ�I�Ȑ������ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�]���āA�l�Ԃ̎Љ���ς��Ȃ�����A�Љ�琶�܂ꂽ�����I���l�ɂ͕��Ր�������A�����ׂ����ƌ�����̂ł���B���l�̑��ΐ������̐��b�̎��ł���ƍl�����邪�A����͓����I���l�̔ے�ł͂Ȃ��A�I�����K�͂���̐��̂Ȃ��A�ォ�牟�������錠�ЂƂȂ邱�Ƃւ̔ᔻ�ɏd�_��u�������̂Ƃ��ǂݎ��邾�낤�B
�P�X�V�O�N��㔼�܂ł̂Q�O�N�Ԃ̍��x�������ɁA���x��������Ɋ֘A����������v�����ƂɁu�V���ԊK�w�v�����������B�V���ԊK�w�̓����͐����l���ƈӎ��̋ώ����E�����������������Ƃł���B����l���̉�ꉻ�A�S���I�ȓs�s���A��������̑�O���A�}�X�R�~�̔��B�Ȃǂɂ���āA�V���ԊK�w�ɑ�����l�X�̐����ƈӎ��̊ԂɁA���ēs�s�Ɣ_���A�u���[�J���[�ƃz���C�g�J���[���u�ĂĂ�����{�I�ȍ��͂Ȃ��Ȃ����B��O�̒��Y�K���ƈقȂ�A���݂̒��ԊK�w�͎�������ʂ��ׂ����w�E��w�̊K���������Ȃ��B���̓_�ŐV���ԊK�w�͐���ˑ��I�ŕs����ł���A�������v����邽�߂̕����V�X�e�����x�����錻��ێ��I���ʂƁA������Ղ̎コ�Ɛ����̋ώ����ɕs�����������ᔻ�I���ʂ̓�ʐ������B�V���ԊK�w�͒E�Y�ƎЉ��ڎw���Ō�̗��j�I��̂ł���A���̑��ʓI���i�𑨂�����V���������I�v�l�̉\�����܂߂āA���݂̓��{�Љ�͐�i�����̃e�X�g�P�[�X�ł���B
�@���̂P�O�N�قǂ̊ԂɊK�w�A���ӎ��Ɍ���ꂽ�ω��Ƃ́A�\�P�ɂ��ƁA�����̐������x���u���̒��v�Ɠ�����l���������A�u���̉��v�u���v�Ɠ�����l�������������Ƃ��B�܂����C�t�E�X�^�C�����u�ΕׁE�㏸�u���^�v����u�������E��Ƃ�d���^�v�ւƕω������ƍl������B�\�Q�ŕ��̖L�������S�̖L�������d������l���������A�\�R�Ŏd���E��������������̊y���݂ɏ[������������l���������Ă���̂͂��̌����ł��낤�B
�@���̕ω��̌����͐V���ԊK�w�̓�ɕ����ɂ���Ǝ��͍l����B�V���ԊK�w�͌o�ς����x�����𑱂��Ă���Ԃ͈��肵�Ă����B�������A�P�X�W�O�N��ɓ��{�����E�I�o�ϑ卑�ɂȂ�A���x��������i������Ƌ��ɁA�u�卑�v�Ƃ������O����͂������ꂽ�n��ȎЉ�{�ƕs�[���ȎЉ�����x�������ӎ������悤�ɂȂ����B�Εׂɒ�N�܂œ��������Ă��ƈꌬ���Ă��A�͂��ȔN���ł͘V��̐������ꂵ�������ɁA�l�X�͐V���ԊK�w�̒��ɂ����Y�i��������A�u��������ҁv�����邱�Ƃ�V���Ɉӎ�������Ȃ������̂ł���B
�@�����l�����猩��ƁA�K���Η��ɂ��A���ӎ��������Ȃ��V���ԊK�w�́A���x�������ɂ́u���l�̎����Ȃ����v�����L���邱�ƂŎ�������ʉ������B�������u���̖L�����v���O�a��ԂɂȂ�A���Y�i�����z�����Ȃ��ǂł��邱�Ƃ��킩��ƁA�l�X�́u���_�I�����ɂ�鍷�ʉ��v�����߂�B���ꂪ�u�S�̖L�����E�������̏[���v�u���ł���ƍl������B
�@�����Ƃ��Ă̍s���l���̔F�m�E�s���̎��s�Ɋւ��ẮA�Â�����u���ɓ����Ă͋��ɏ]���v���L���ȑ�ƍl�����Ă����B����͑���̖͕�����ĎЉ����̖��C�����������@�ł���A�ٕ����Ƃ̐ڐG���Z���ԂɌ��肳��Ă���ꍇ�͎��p�I�Ȍ��ʂ����҂ł���B�������A�ٕ����Ƃ̐ڐG�������ɓn��ꍇ�ɂ́A����̍s���̐₦����͕�ɂ���āA�s����̂̑��Ɋ������N�����Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�����ł́u�m���Ă��邱�Ɓv�Ɓu�����邱�Ɓv�����Ă��邩��ł���B�]���āA�ٕ����𗝉������ōł�����Ȃ��̖��������ł��邩�ۂ��́A�ٕ����ɑ�����l�X�Ɓu��ɂȂ��镶���I�����v�܂ł����L�ł��邩�ۂ��ɂ������Ă���ƌ�����B���ɂ��̉\���ɂ��čl�@���悤�B
�@�����Ŏ����u��ɂȂ��镶���I�����v�ƌĂԂ̂́A�M�҂������́u�Ӗ���ԁv�Ɠǂ�ł�����̂ł���B�������������͕����̗L�@�I�ȑS�̂ł���A���l�̑̌n�E�Љ�̑̌n�E���R���̑̌n�ɂ܂ō����L���Ă�����̂ƌ����邾�낤�B���������̏d��Ȗ�肪������B����́A���̂悤�ȕ����I���������L���邽�߂ɂ͎������̕������̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A���邢�͈ٕ����ƕ����I���������L����҂͂��͂�ٕ����ɑ�����l�ԂɂȂ肫���Ă��܂����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������ł���B���������Ȃ�A�u�ٕ��������v�́u�������̕������邢�͔j��v�̕ʖ��ł��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@���̖��ɑ��铚���́A�����̗L�@�I�Ȑ��i���炷��Ɓu�ہv�ł���B�����A�u�������̕������̂Ă�v�Ƃ́A���̐l�����鉿�l�̑̌n�E�Љ�E���R�����犮�S�ɐ藣�����Ƃł���A���Ɏ����́u�Ӗ���ԁv���������l�Ԃ�������̂Ă�͕̂s�\�ł��낤�B����̂ɁA�Ӗ���Ԃ̋��L�E��ʂł̋����ɂȂ��铹�Ƃ��čl������̂́A�ꌳ�I�Ȏ��_���瓦���w�͂����邱�Ƃł���B���������ٕ����̒��ŕ�炵�ĔF�m�E�s���ʂƏ�ʂ�����̂́A�ٕ����̌����������̌������ɂȂ��邩�炾�B�ٕ����ɑ��鎞�A�l�͎����̑����镶������Ƃ��Ĉꌳ�I�ȕ]�������������ł��邪�A�����ɂƂ��Ă͐��̉��l�ł�����̂��A�قȂ������l�̌n�̒��ł͕��̕]�����邱�Ƃ�����B���̋��������������𑊑Ή�����ŏ��̑̌��ł���A�������̑��Ή�����Ɉٕ����̕����ɐG��Ă������Ƃ������I�Ȏ��_���\�ɂ���̂ł���B���̎��A�Ӗ���Ԃ̈ꕔ�͋��L����A�F�m�E�s���Ə�̓���́u�����v�Ƃ��ĉ\�ɂȂ�̂��Ǝ��͍l����B
�@���́u�F�v��ʂ��Č|�p���\�ɂ���l�Ԃ̐��_�����̍L����ɂ��čl�������B��̓I�ɂ́A�u���o�v�u���E�F���v�u�Ӗ��Â��v�̎O�̖ʂ���u�F�v�����Ă������Ǝv���B
�@�܂����o�̖ʂ��猩��A�F�͉������͈̔͂Ől�Ԃ̊��o�튯�ɗ^��������ł���B���̏��͐������������ŕs���̂��̂ł���A�l�Ԃ��܂���O�ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�ł������������́A�L�m�R����J�G����g�J�Q�Ɏ���܂ŁA�N�₩�ȁu�x���F�v�Ŏ���̑��݂�G�ɋ�����B�F�������̐����ɂ͎�������邱�ƂɂȂ�A�����H�ׂ悤�Ƃ���G�ɂƂ��Ă͊댯���������邱�Ƃ������Ă����̂��u�F�v�ł���B����ɁA���������Ƃ̒��ړI�Ȋւ��ɂ����āA�F�͐l�Ԃ�������������A�Â߂��肷��B�S���I�Ɋ���Ɛ[�����т��������́u�F�v�́A��p�ȂǁA�|�p�̗c�N���ƌ��т��Ă���B
�@���o�Ƃ��Ă̐F�͐l�Ԃ�����I�Ɂu���v�F�����A���E�F���̎d�����ڂ������ׂĂ݂�ƁA�l�Ԃ͐F�ɑ��Ĕ\���I�Ȋւ��������Ă��邱�Ƃ��킩��B�Ⴆ�A�i�K�I�ɔZ�x��ς����F����ׁA���̒��̈ꖇ����菜���ƁA�l�Ԃ͂��̗����̐F���璆�Ԃ̐F��ސ�����B���ۂɊ��o�ɂ͗^�����Ă��Ȃ��Ƃ����̐F���u�킩��v�Ƃ����̂́A�S�̔\���I�ȓ����ł���B���l�T���X���ȗ��̊G��Z�@�́A���̂悤�Ȑl�Ԃ̐��E�F���̕��@�����p���Ă����B�F�𗘗p������C���ߖ@�ł́A�����̕��i���������ڂ���ƕ`�����ƂŁA��X�͓��̉�ʂɉ��s����������B�I�Ȋ��o���u���琢�E���\������m�o�v�ɂȂ����Ă���̂ł���B�|�p���P�Ɂu����̕\���v�ł�������A�u�����܂܂��L�^����v���߂̂��̂ł���A�F�̋@�\�������̂��̂ɗ��܂����ł��낤�B�������A��p�����|�p����������ɂ́A����ɏd�v�Ȑ��_�����������ɉ����˂Ȃ�Ȃ��B
�@���̐��_�������u�Ӗ��Â��v�ł���B�Ⴆ�A�@���ɂ����Ă͐F���d�v�ȈӖ��������Ă���B�O�q�̃��l�T���X�|�p���ɂƂ�A����}���A�̈ߕ��̐F�͐}���w�I�Ȍ��܂�����B�]����\�킷�u�ԁv�A�Ќ���\�킷�u�v�A������\�킷�u���v�Ȃǂ�����ł���B�����̐F�͒P�Ɋ��o�ɑi����݂̂ł͂Ȃ��A�V���{���Ƃ��Ă̕\���@�\��S���Ă���̂ł���B���̈Ӗ��ŁA�G��Ƃ����|�p�̓V���{���ɂ��\���������ƌ����邾�낤�B�@���I���ЂƐ������͂����������ߑ�Ȍ���V���{���Ƃ��Ă̐F�͐��������A�t�����X�̎O�F����Љ��`���̐Ԋ��Ɂu���R�v�u�����v�Ȃǂ̗��O���\������Ă���B�������A����͓����Ɍ���̌|�p��������Љ�Ɗւ�����������Ȃ����Ƃ̏ے��ł�����B����|�p�͉���\�����ׂ����Ƃ������Ƃ��悭����邪�A�L���ȐF�ʂ��y���߂��X���Љ�I�A�����I�Ȗʂł����l�Ȍ�������e����悤���߂��Ă���ȏ�A����|�p�̎g�������l�ȗ��O�̕\���܂��͍Č����ɂ���Ǝ��͍l����B
�@���m�Ɠ��{���ׂ�ƁA�u��i�v�Ƃ��Ă̎��摜�������`����Ă���̂͂ǂ���ł��낤���B�����炭���m�ɂ����Ăł��낤�B���̗��R��T��Ȃ���A�u���摜�v�̂������I�Ӗ��ɂ��čl�@�������B
�@���m�̉�Ƃ͋ߑ�ȑO���玩�摜�A�܂��͂��̏K��𑽂��c���Ă���B����ɑ��A���{�̉�Ƃ����摜����ƂƂ��Ă̏C�s�ɑg�ݍ��܂Ȃ������̂͂Ȃ��Ȃ̂��B����͎�̂Ƌq�̂̑Η��Ƃ������m���_�݂̍���Ɍ���������B���m�ł́A��̂ł���l�Ԃ��q�̂ł��鎩�R����Ɨ����Ă���ƍl����ꂽ�B����������A�l�Ԃ͎��R��ΏۂƂ��Ēm�蓾�闧��ɂ���A���̒m���ɏ]���Ď��R�𐧌�ł���ƐM����ꂽ�̂ł���B��������A���R�E�̒����͎�̂ł���l�Ԃ̎�ςɂ���ė^�����A��̂Ƃ��Ắu�l�v�́A���҂���Ɨ����������I�ȑ��݂ł���ƍl������悤�ɂȂ����̂ł���B����䂦�ɁA���Ȃ𑼎҂̎��_���猩�邱�Ƃ́A���Ȃ��q�̂̑��ɒu���A���������Ȋm�F�ł������B���I�i���h�E�_�E���B���`��f���[���[�̎��摜����́A�u�Ȋw����l�ԁv�u�{����T������l�ԁv�̎p����������B
�@����ɑ��ē��{�����摜�̓`���������Ȃ��̂́A��q�̑Η��Ƃ����\�}�������̊�b�ɂȂ���������ł���B�m���ɁA�����Ȍ�A���m�̉e���ŗm��Ƃ͎��摜��`���悤�ɂȂ����B�������A���ꂪ���m�̉�ƂƓ������A���҂̎��_�ɗ����Ď��Ȃ����߂�p���̌���ꂾ�Ƃ͕K�����������Ȃ��ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A���������m����A������A�����Ȍ�ɏ������悤�ɂȂ����u���v�̌|�p�\���Ƃ��Ắu�����v�́A���Ȃ��q�ϓI�Ɍ��߁A���Ή�����̂ł͂Ȃ��A�u�������v�ƂȂ��Ď��Ȃ̕������E��I�o����Ƃ������������ǂ�������ł���B���ȔF���̓_�ł́A���{�I�ȁu���Ȃɑ���p���v�͐��m�̂���ɋy�Ȃ����낤�B
�@�������A���R�Ȋw�̐��ʂ������炵����́E�q�̂̍\�}�́A��ς̋y�Ȃ����R���̔j��ɒ��ʂ��A���̌��E��I�悷�邱�ƂɂȂ����B�܂���ς��̂��̂Ɋւ��Ă��A�S���w�̈����u���ӎ��v�̗̈�́A�S�̒��ɂ����A�����̒m��Ȃ����������邱�Ƃ������Ă���B�u�m���ɒm�蓾�鎩�ȁv�𒆐S�ɍ\�����ꂽ�u�����\�Ȑ��E�v�Ƃ��������ߑ㍇����`�̐M�O�́A���I�ɂ��O�I�ɂ��h�炢�ł���̂ł���B����ɁA�u���̎�̂Ɋւ��Ă͒m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�Ƃ�����ς̍\���́A���m�I�l�Ԃ��A���͂���藣����A�������M�����Ȃ��s����ȌǓƂɓ�������ł���B�t�����V�X�E�x�[�R����h���t�E�n�E�Y�i�[�̕`���c���摜�́A������������Ȏ��Ȃ̕\���ƍl������B�]���āA�ߔN�A���{���ٕ����ɑ����鐼�m��������Љ�I�E�����I�ȁu���摜�v��`���悤�ɋ��߂��Ă���̂��A��́E�q�̂̍\�}�����z���悤�Ƃ��镶���I�����ɐ[������������Ǝ��͍l����̂ł���B
�@�ۑ蕶�ɂ́u�����I�V�X�e���͈ڐA�ł��邩�v�Ƃ�����肪�܂܂�Ă���Ǝv����B�x���c�͈��A�̒��ŁA���{�l�̊w�Ԃׂ����̂��L�@�̂Ƃ��ẲȊw�I���_�ł���Əq�ׂĂ���B����́A����������A�Ȋw�I���ʂ̔w�i�ɂ͎��ԓI�E��ԓI�Ȑ������_�̍L���肪����A�����͑S�̂Ƃ��āu��v�Ȃ̂ł����āA���ʂ����̔w�i����藣���Ă͂���Ȃ鐬���͖]�߂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��낤�B�ߔN�f�Ֆ��C�ł����ɂȂ��Ă���u���{�l�͊�b������m�I���L�������Č������ʂ̖͕�ɂ�藘�v�������Ă���v�Ƃ������Ă���̔ᔻ�́A���ɖ������ɍs�Ȃ��Ă����̂ł���B
�@�x���c�̔�����ǂތ���A�ނ͋ߑ�Ȋw�����̔w�i�ƂȂ鐸�_�Ƌ��ɓ��{�ɈڐA�ł���ƍl���Ă���悤���B�u�w�i�ƂȂ鐸�_�v�Ƃ̓M���V���̎��R�N�w�Ɏn�܂�A�L���X�g���ɂ���Ĉ�Ă��A�ߑ㍇����`�ƂȂ��ĉԊJ�����������_�̂��Ƃł���B�����ł͎��R���_�̒����f�������̂Ƒ������A���R���������邱�Ƃ͐_�̈̑傳�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł��������B�Ȋw�I�T���ւ̈ӗ~�ƌ��g�͋����M�Ɏx�����Ă����̂ł���B
�@���ɁA���������Ȋw���x���鐸�_�����{�l�ɂƂ��Ď���\�Ȃ��̂ł������Ȃ�A�u�a���m�ˁv�Ƃ����X���[�K�����\�킵�Ă���悤�ɁA���̖��ƒm���̖�����K�v�͂Ȃ������̂ł���B���p���D��̉Ȋw�̎�e�́A���{�̎Љ�ɓ��݂���@���I�ϗ��K�͂��A�x���c�����̈�l�ł��鐼�m�l���u���ՓI�v�ƍl����ϗ��K�͂Ƒ��e��Ȃ����߂ɋN���������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�䂦�ɁA�����̃V�X�e���S�̂�Z���Ԃňٕ����ɈڐA���邱�Ƃ́A����̑����ɑ��镶���I�������Ȃ�����s�\�ł��낤�B
�@�������A�����V�X�e��������I�ȈڐA�ł͂Ȃ��u�����Z���ɂ��V���������̐����v�Ƃ����`�ő��ɓ`������Ȃ�A�ۑ蕶�ɂ���悤�Ɂu���{�ʼnȊw�̎����ЂƂ�łɐ����đ傫���Ȃ��v�\��������B���̌��́A���m�l�ɂƂ��Ă����{�l�ɂƂ��Ă��Ó����鉿�l�̊�E�ϗ��K�͂����o�����Ƃł���B�x���c�̌����ʂ�A���̊�͉Ȋw�Z�p���̂��̂̒��ɂ͂Ȃ��B�܂��A�ꐢ�I�O�̊�����̂܂����킯�ɂ������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�_����^����ꂽ�͂��̌����I�ȃG�l���M�[���p�̒m�b�������鐶���̐�ł������炷�j����ݏo������A�����~����w�̐i���ɂ��l������������j�A�t�ɕn�����l�X�̐������������Ă��邩��ł���B�������_�͂��̕S�N�Ԃɕ��ՓI��̍�����]�������Ƃ�������B���A�V���ȕ��ՓI�ϗ��K�͂����߂�Ȃ�A����́u���R�Ɛl�Ԃ̑Η��v�ł͂Ȃ��A�u�S�Ă̂��̂��݂��Ɏx�������Ă���v���ƂɊ�Â��A���R�̒��̒��a��_�I�ȉ��l�̕������d��������̂ɂȂ邾�낤�B���{�l���������_����^�Ɋw�Ԃ��߂ɂ́A���̂悤�Ȑ����Ɠ��{�o���̐��_�I���Ή����s�����Ǝ��͍l����̂ł���B
�@���̕�������݂悭�m���Ă��镨��Ɣ�r���ċC�����̂́A�u�c�����v�u���Q杂Ƃ��Ă̐��i�v�u���i��G�ӂ̍r�X�����v�Ȃǂ������\���Ă��邱�Ƃł���B��X���f�B�Y�j�[�̃A�j���[�V�����f��Ȃǂ�ʂ��Đe����ł���̂́A�`��I�ȃ��}���X�����Ƃ�������ł��邩��A���̍��ق͓��ɑ傫����������B�O�������b���ł́w����P�x�����ݒm���Ă���`�ƈقȂ��Ă���̂́A���ł̕��ꂪ�̏W���ꂽ���`�ɒ����ł��邩�炾�낤�B�O�������b�Ɍ��炸�A�`������Ă������b�́u���ʉ���v��u�c���Ȕߌ��v�����ɂ������̂������B���́A�����������b�̌��`�������Ă���@�\�͉����Ƃ������ƂƁA�Ȃ������ɕό`���N����̂��Ƃ������Ƃł���B
�@���b�͔N���҂ɂ���Ďq���B�Ɍ���Ă����������w�ł���B���ɂ����ɂ͋��b�E���b�̗v�f�ł��铹���I���P�������Ă���B�w����P�x�̏ꍇ�Ȃ�A���ʂڂ��i�݂ɑ�������������v�f�ł���B�����I���P�������i���邽�߂ɂ́A���Q�̋��낵�����������邱�Ƃɂ���āA�����߂ł��邩��������K�v�����邾�낤�B���b�̎c���ȓ��e�́A�܂������ɍ��������ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�@�������A�c�����̍����͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B���b�̑��̋@�\�Ƃ��āu�������Ȋ����������v���Ƃ��l������B�{���A�q���̊���͌��n�I�ȍr�X�����������Ă���B�Ⴆ�A�Ԃ��ނ�������A�����E�����肷��s�ׂ��A�q���B�͐S����y���ށB���̐����ɕs���Ȉ�i�K���[��������̂����b�̋@�\�ł���B�]���āA���̖ړI�������b�͐��X�����c�����◝�s�s�Ȕ߂��݂ɖ����Ă���B���̋@�\�͐l�Ԃ̐����Ƌ��ɔߌ��Ɏp����Ă䂭�̂ł���B
�@���b���ό`���Ă䂭�̂́A�����̋@�\����߂�ꂽ��A��菜����邱�Ƃɂ��B���ɁA�q�������I�ȋ������Љ�ł́A�ߓx�̎c�����͐S���I�Ɉ��e����^����ƍl�����A���b�̌��`�͋��ނ���r�������̂����ʂł���B
�@�m���Ɂu����I�z���v�ɂ͂���Ȃ�̈Ӗ�������B�������A�u����������ꂽ����v�͂���ɖ��b�̑�O�̋@�\�����D���Ă��܂��B����́u����ɂ�鎀�ƍĐ��̑̌��v�ł���B�Ⴆ�w����P�x�́A�܂�����P���g�̎��ƍĐ��̕���ł���A���Ɂu�Â������l�v�̎��ɂ��u�Ⴂ�����l�v�̍Đ��Ƃ����u��ւ��v�̕���ł�����B�u���v�͏��łł���A�ʗ��ł���Ɠ����ɐV���������̑n���ł���Ƃ������`���������Ă���B�q���B�Ɏ��̎c�����Ƃ��ꂪ�����炷�߂��݂�\�����A����Ɂu�Đ��ւ̊�]�v�Ƃ����u�������z����m�b�v��^���邱�ƂŎ��̗��`����̌�������B���ꂪ���b�̏d�v�ȕ����I�@�\�Ȃ̂ł���B�䂦�ɁA���b�̌��`�d���邱�Ƃ́A���Ǝ��̈Ӗ���[���l���邱�ƂɂȂ���Ǝ��͍l����B
�@���ЂɑΗ�����ꍇ�A��l�ł͎ア���W�c�ɂȂ�����Ȃ�A�Ƃ��������͐S���w�I�Ȏ����Ő����ł���B�����ɂ́u���]�v�Ɓu�����v�̗v�f���ւ���Ă���B�����ł́u���]�v�Ƃ́u���Ђɋ�������s�ׁv�ł���A�u�����v�Ƃ́u�����̍s�����w��������ʂȌ����������Ă��Ȃ��҂ɂ��Ă䂭�s�ׁv�ł���B�G�[����w�ōs�Ȃ�ꂽ�u���]�̎����v�ł́A�u���Ёv�Ƃ��Ă̎����ӔC�҂ɑ���l�̕��]��������B����A�A�b�V���ɂ��u�����̎����v�ł́A�Љ�I���͂̉��ł͐l�͎����̊��M������̓O���[�v�̔��f�ɏ]���A�Ƃ������Ƃ��m���߂�ꂽ�B���]�Ɠ����̋��ʓ_�́u�����ȊO�̎҂ɃC�j�V�A�e�B�u������n�����Ɓv�ł��邪�A���҂̖{���I�ȑ���_�͎��̎l�_�ɂ܂Ƃ߂���B���ɁA���]�̓q�G�����L�[�\���̒��ŋN����B���ɁA�����͖͕�ł���A�s���̓��������Ӗ����邪�A���]�͌��Ђɑ���͕�Ȃ��̋����ł���B��O�ɁA�s���̎w���͕��]�ł͖����I�ł��邪�A�����ł͈Öق̂��̂ɂƂǂ܂�B��l�ɁA�����͎����I�Ȃ��̂ƈӎ�����A�l�͓����̎�����۔F�������邪�A���]�͐ϋɓI�ɗe�F�����B�ȏ�̂��Ƃ���A�q�G�����L�[�̓]�|�A�܂茠�Ђւ̕��]�����ށu�v���^���v�Ȃǂ��A�����Ɋ�b�Â���ꂽ�u�W�c�s���v��K�v�Ƃ��邱�Ƃ����������B����́u���Ԃ̔��t�������ӔC�҂̌��Ђ���߂�v�Ƃ��������ɂ���Ă��m�F�ł���B
�@�M�҂́u���]�͌��Ђɑ���͕�Ȃ��̋����ł���v�Əq�ׂĂ��邪�A���]���q�G�����L�[�\���̒��Łu���Ў҂̎��s���Ƃ̓������v�������ꍇ������̂ł͂Ȃ����B������m���߂邽�߂Ɏ��̎������v�悷��B�����̑O���̓G�[����w�́u���]�̎����v�Ɠ������̂ł���B�����Ď����I����A�����ӔC�҂͔팱�҂Ɂu���͋}�p�ŐȂ��O���܂�����A�V��������A���o�C�g�̐l�ɂ��Ȃ��Ɠ������Ƃ������ĉ������v�Ǝw������B������������̌㔼���n�܂�B�����ӔC�҂͕ʎ�����C�Â���Ȃ��悤�ɔ팱�҂̍s�����ώ@����B�팱�҂͍��x�͎��炪�u���Ёv�ɂȂ����킯�ł��邪�A�u�l���I���f��������𒆎~����v�u�����ӔC�҂̎w���𒉎��Ɏ��s����v�u��茠�Ў�`�I�Ř���������ȑԓx�����A�⍓�Ȏw�����o���v�Ȃǂ̌��ʂ��l������B���E��O�̌��ʂ�����������u���Ђɕ��]����҂́A���ʂ̎҂ɑ��Ă����Ў҂Ɠ����̍s�������v�Ƃ������Ƃ�������B
�@���͑��풆�̌R���ɂ��c�s�s�ׂɁu���]�v�̃��J�j�Y������p���Ă���ƍl����B��Ƃ��ē��{�R�ɂ��������ł̏Z���A�ߗ��̋s�E�E�s�҂������悤�B���u�ɓ��R���ٔ��v�Ȃǂ�ʂ��Ė��炩�ɂȂ����Ƃ���ɂ��ƁA�u�X�p�C�|���v�̖��ڂŊm���ɑg�D�I�E�C�̎w�߂��o�Ă����悤�ł���B�����ĉ��m���╺�m�́A���߂𒉎��Ɏ��s�����̂ł���B�s���A�R���ٔ��̏�ł́A���������c�s�s�ׂ��u�l���ɑ���߁v�ɖ��ꂽ�B�Ƃ��낪�A�܂����m���╺�m�́A�u�Ђǂ����Ƃ�����Ƃ͎v�������A�㊯�̖��߂ɂ͋t�炦�Ȃ������v�Ə،������B���]�́u�q�G�����L�[���v�u���Ђɑ�������v�u�����I�Ȏw���v�u�������̔ے�v�������Ɍ����Ă���B����ɐ��ł̎w�������������܂ł��u��ނȂ����ŐE�ƌR�l�Ƃ��Ă̐E�ӂ��ʂ����������ł���v�ƍR�ق��A�u�V�c�̈ӂ�̌��������߁v�̌��Ђ��l���I�Ȕ��f�ɗD�z�������Ƃ��q�ׂ��̂ł���B
�@���t���g���̂Ă���̂́A����́u���x����Љ�v�Ō��t���܂��u���i�v�Ƃ��đ������Ă��邩��ł��낤�B�{���A�ǂݏ����ɂ���āu���t�Ɗւ��v���Ƃ́A�ۑ蕶�̕M�҂������悤�Ɂu�ߋ��▢���ƂȂ���v���Ƃւ̗~�]����o�Ă���s�ׂɈႢ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A���x����Љ�ł͗~�]�Ə���̊W���t�]���Ă���B������������͗~�]�������߂ɂȂ������̂��B�����A�����I�ɖ�������A�L���ɂȂ����Љ�ł́A�l�X�̗~�]�͎�܂�A���l������B�l�X�ɂ�葽��������邽�߂ɂ́A�܂��~�]���̂��̂��Y�ݏo���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����̎Y�Ƃ����v�ɉ����Đ��Y����̂ł͂Ȃ��A�V���Ȏ��v��n��o�����߁A�킸���Ɂu���ʉ��v�����V���i�̊J���ɒǂ��Ă���̂͂��̎���ł���B���t����O�ł͂Ȃ��A�o�ŊE�ł͎����悤�ȐV�삪���X�Ɍ����Ă͏����Ă䂭�B
�@���t�̎g���̂Č��ۂ̍���ɂ́A���t�̓R�~���j�P�[�V�����̂��߂́u�P�Ȃ�v����Ƃ����F��������ɈႢ�Ȃ��B�m���ɁA���t�͕\���@�\�����u�L���v�Ƃ�������ƌ����邾�낤�B�������A������g�����Ȃ����߂ɂ͗��K���K�v�ł���B�����āA�l�Ԃ������p����Ɠ����ɁA������l�Ԃ���Ă�̂ł���B����̑����猩��A�n���̉ߒ����l�Ԃ̐��n�̉ߒ��ł���Ƃ������ƂɂȂ�B����e���Ɉ����A������g�����߂̋Z�ʂ������Ă��܂��ƁA�l�Ԃ͐��n����@����i�v�Ɏ����B
�@���t�Ƃ�������̏ꍇ�����l�ł���B�×��A���t�̎��͂��n�m���A���t�̎g�����ɏn�B�����҂��@���╶�w�̒S����ł������B���t�̎��͂�M�����Ñォ�琭���I��`�⏤�i�L���̌��ʂ�M���錻��܂ŁA���t�ɑ����čl����A��͂�l�Ԃ͌��t�Ɉ�Ă��Ă����̂ł���B���m�̂��̂������\���A�`�̂Ȃ����̂ɕ\����^���A�`���邱�Ƃ̍���ȓ��e��`���悤�Ƃ��āA�l�Ԃ͕����I�c�݂�ςݏd�˂Ă����B�M�҂��w�E����u���ԂƂ̑R�v�́A���t���g�����Ȃ����Ƃ���u���t�ւ́v�w�͂ƁA���_�I�����Ƃ����u���t����́v��V�̊Ԃ̑��ݍ�p���琶�܂�Ă�����̂��ƌ�����B����ɑ��A�`���ŏq�ׂ��u�g���̂Ă��鐻�i�v�Ƃ��Ă̌��t�́A�l�Ԃ����ݍ�p������ň���I�ɏ���Ă�����̂Ȃ̂ł���B���̌��ʁA�l�Ԃ͌��t��ʂ��Ď������g��[���T��������A���҂̕����I�w�i��[�����@�����肷��\�͂����������Ă���B
�@�u�g���A�����Ɉ�Ă���v�Ƃ������t�Ɛl�Ԃ̑��ݍ�p�����邽�߂ɂ́A�g���̂Ă���V���i�ł͂Ȃ��A�Ⴆ�ΌÂ����t�E�ٕ����̌��t�Ƃ̊i����ʂ��Ď��Ȃ̌��t���������P�����s���ł���B�O�҂͎��Ȃ����ԓI�ɑ��Ή����A��҂͎��Ȃ���ԓI�ɑ��Ή����邩��ł���B����䂦�ɁA����ÓT�ƌ��������A����O�����ǂނƂ��납��A�u�ÓT����v�Ƃ��Ă̖�������܂��Ǝ��͍l����̂ł���B
�@�ۑ蕶�ɂ���{�����e�B�A�́u�炳�v�Ƃ́A�u�Љ�I�A�����̎��o�v�ƌ��������邱�Ƃ��ł��邾�낤�B���̏ꍇ�́u�Љ�I�A�����v�Ƃ́u���ȂƑ��҂̂Ȃ���v�̂��Ƃł��邪�A�������́u�Ȃ���v�͍L����ɂ����Ă����G���ɂ����Ă��܂��܂��K�͂��傫���Ȃ��Ă���B���̌����̈�́A����̐����o�ς��������z�����͂������Ƃł��낤�B�P�Ƀ��m������������鍑�ۖf�Ղɗ��܂炸�A���Z�A�T�[�r�X�A���A�����ĘJ���͂Ƃ��Ă̐l�Ԃ܂ŁA�������z���đ�ʂɈړ�����悤�ɂȂ��Ă���B���č��ƌ��͂̎x�z���ɂ������e���o�ς͐��E�o�ς̈ꕔ�ɑg�ݍ��܂�A�s��o�ςƓ����ɂ�����x���鐭���I�ȃV�X�e�����������z���ė��ꍞ�ށB���ꂪ�����̌����ɂ��Ȃ��Ă���̂ł���B
�@����琭���o�ϓI�Ȑ��E�̊g��́A�O�I�ȑ��ʂł͎��R���̔j��ƈٕ����Ԃ̖��C�������N�����B���̈���A���I�ȑ��ʂł́A���E�̊g�傪���ȂƑ��҂̊W���������悤�ɓ���������B�ߑ�ȍ~�A�l�Ԏ�̂��q�̂ł���Ώې��E�i���҂��܂܂��j������I�ɑ����A���p����Ƃ�����ώ�`�I�ȍ\�}����X�̐��E�ς��x�z���Ă������A�����X�͊��j��╶�����C�����Ȃ��������A���������Ȃ����̌����ɐ[���ւ���Ă��邱�Ƃ�m��A���͂̊��Ɖ�X���g�́u�𗬁v�u�����v�������Ă��邱�Ƃ����o������B
�@�����œ����鎩�o�́A�u���҂̕s�K�ɑ��ĉ�X�̗͂����܂�ɏ��������Ɓv�ł���B���́u�s�K�v�Ƃ́A�Ⴆ�u�a�v�u�ɂ݁v�u�ꂵ�݁v�u���v�Ȃǂł���B�u�a�v��ے肵�u���v���������錻��Љ�̒��ŁA��X�͑��҂̕s�K�����f�B�A�ɂ���ď��ꂽ�������Ŏ��A���������͈ꐶ���N�Ő�������Ǝv���Ă���B�������A��X�͑��҂̕s�K�ɑ��閳�͊���ʂ��āA�l�Ԃ����Ǝ��̑Η����Ɏ����Đ����Ă��鑶�݂ł���A�����Ȃ���ΐ��̋P���⑸�����킩��Ȃ����Ƃ��m�F����̂��B����������A��X�͂��́u���͊��v��ʂ��đ��҂̋ꂵ�݁A�߂��݂�m��A���҂̑��ɗ����Ƃ��ł���̂ł���A������Ă��鐶�����̘g�g�݂ɂ��C�Â��̂ł���B
�@�]���āA����Љ�Ɍ����Ă���u�L���Ȑ��̂�����v�́A�������g�̕ʂ̑��ʁA���邢�́u���ҁv�����̒��Ɏ�荞��ł䂭���Ƃ��ƌ�����B���̈Ӗ��Łu�������p���h�b�N�X�v�̉Q�Ɏ�����������ސl�A���Ȃ킿�{�����e�B�A�Ƃ́A�u���ȂƑ��҂Ƃ̑��l�ȊW�̉\���v�����o�����l���ƌ�����B���҂ɂ��āu�m��v���Ƃ��s���̑������Ƃ���A�u�m��v���Ƃɂ���Ď��Ȃ⎩�Ȃ̕����𑊑Ή�����ꂵ�݂��A�����ɖ������Ɍ������l�Ԃ̐V�����s���������Ȃ̂ł���B���{�ł̓{�����e�B�A���u���ȋ]���v��u��_�ȍs���v�ƌ��т��čl����ꂪ�������A�܂��u�m��v���Ƃ̏d�v���������ɕ]�������ׂ����Ǝ��͍l����B
�@����Ɠ������Ƃ��A���E�o�ςɂ����āA���傫�ȋK�͂ŋN�����Ă���B�e���̍����o�ς͐��E�o�ς̈ꕔ�ɑg�ݍ��܂�A�s��o�ςƓ����ɂ�����x���鋤�ʂ̐����V�X�e���̈��͂��������z���ė��ꍞ�ށB���̕ω����Љ��`��������A�A�����J�̐��E�����ւ̔����͂���߁A���W�r�㍑�ɖ��剻�Ɩ�����`�̑䓪�������炵���ƌ�����B�����āA���̌o�ϓI�������̈��͂��ے肷��̂́u�ٕ����ɑ����鏭���h�̃A�C�f���e�B�e�B�v�ł͂Ȃ��A���L�͂ȁu�����̂̃A�C�f���e�B�e�B���̂��́v�ł���B
�@�܂�A���Y��������̏ꂪ���O�Ɉڂ�A���Ǝ҂��������ĕn�x�̍����g�傷�錋�ʁA�������Ƃ̗��O�ł������u�����̌����Ƃ��Ă̎��R�ƕ����v���`�[������̂ł���B���Ƃ͐��E�s��ɗ����������u���Ɓv�Ƃ��Ă̑��ݗ��R���������Ȃ��Ȃ�B���Ƃ���Ɖ�����A��Ƃ̘_���Ő����邱�Ƃ��ł����A�����ɔs�ꂽ�s���͕n����������Ȃ��B�����ɂ͂��͂�A���Ƃɂ���đ��d�����u�ꍑ�̎s���v�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�͐��藧���Ȃ��B�����Ȃ�A�V���ȁu�g�����v�̒��ŋΘJ�ӗ~�������A�����I���������߂ĎЉ�ۏ�Ɉˑ�����l�X�A�r�O�I�Ȑ����̐��ɂ���Đ��E�o�ς���̌Ǘ����咣����l�X����ʂɐ��ݏo�����ł��낤�B
�@���̂悤�Ȗ����������邽�߂ɂ́A�Љ����ʂ��āu�x�̏z�V�X�e���v�����������Ƃ��K�v�ɂȂ�B�{���A�o�ϐ�i���͍H�Ɖ��𑁂�����B���������ł������B�������A�E�H�Ɖ��̐i�W�ŏ���T�[�r�X�̗��ʁE�����i���̌o�ϊ�ՂɂȂ�ƁA�u�s�������̋Z�\�Ɣ\�́v���Ȃ킿�u���m��A�C�f�A�̐��Y�́v�͑��ΓI�ɒቺ����B��������P���邽�߂ɂ́A��ʏ���^�̎Љ�\����ς��A�ǂ̂悤�Ȏs��̗v���ɂ���������悤�ȑn���I�\�͂ƋΘJ��������{�����鋳��̍ĕ҂��K�v�ɂȂ�B���������ۑ���������钆�ŁA�x�̌����ȏz�E���z�̈�ʂƂ��āu���ە��Ƃ̂�����v�u�f�Վ��x�s�ύt�v�Ȃǂ̌��������s�Ȃ��Ă����ł��낤�B���̌��ʁA�V���ȉ��l�ςɊ�Â������o�σV�X�e�����\�z����A����ɂ���ď��߂Đ��E�o�ς͈���Ɍ������̂��Ǝ��͍l����B
�@�������A�}�`�F���̔\�͂≹���͏��w�Z���w�N���x�̔N�߂܂łɊ������Ă��܂��ƌ����Ă���B�����A�c�������̉��y�E�G�拳���͂�������ӂꂽ���݂ɂȂ��Ă��邵�A���召�w�Z�p�̗c���m�܂ł���ɐ��ł���B����ƁA���������̖�肪�o�Ă���B��́u������̒i�K�ł́A���͂�n���͂�L���ɂ͒x������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������ł���A������́u�E�]��b�������{�l�͐��ɑ��������A���{�l�͈ȑO�ɔ�ׂēƑn�I�ɂȂ��Ă���̂��v�Ƃ������ł���B
�@���{�����ݔᔻ����Ă���_�̈�ɁA�u���{�l�͊O���̌����҂̋Ɛт𗘗p�������ŁA�O���̊w�҂Ɉ��p�����悤�ȓƑn�I�Ȋw��I�v�������Ȃ�����v�Ƃ������̂�����B����͓�Ԗڂ̖��ɑ���ے�I�ȓ����ł��낤�B�����A�������璼�ځA���̖��ɂ��ے�I�ȉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�ӎ��I�ɉE�]��b���邱�Ƃ͑��������Ȃ����A���ʂɈ�����l�Ȃ炾��ł��A��l�O�̐}�`�F���\�͂ƃv���̉��y�Ƃقǂł͂Ȃ����ꉞ�̉���������Ă���͂��ł���B����������A���w�Z�ɓ��鍠�ɂ́A�u�Ђ�߂��v��u���ρv�̔\�͂́A�قƂ�ǂ̐l�ɏ[��������Ă���͂��Ȃ̂ł���B����ł́A�Ȃ��O���̊w�҂���u���{�l�͓Ƒn�I�łȂ��v�ƌ����Ă��܂��̂��B
�@����́A���k�́u�Ƒn�v�d���鋳�t��A�u�Ђ�߂��v���`�ɂ��邽�߂̃V�X�e�������{�̊w�Z�Ɍ����Ă��邩��ł���B��̓I�Ɍ����A�`���d���œ��e����Ȃ����炪���s���Ă���Ƃ������Ƃ��B��������u��b�̌y���v�Ɓu�^�̉������v�����܂��B�u��b�̌y���v�Ƃ́A�K�n�̂��߂̎�Ԃ�ɂ��ނ��Ƃł���B�w��ł��G��A���y�Ȃǂ̌|�p�ł��A��b�I�ȌP�����I���Ȃ���A���̏�Ɏ����̓Ƒn����\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������Łu�Ƒn�v�������A�K�v�Ȓm����Z�@�̏K�����y������A�ނ��낻�̌��ʂ͓Ƒn�Ȃ�ʖ}�f�̑�ʐ��Y�ɂȂ邾�낤�B�����Ď��́A����́u�^�̉������v�ɂ��s�����悢�̂ł���B�u�ォ��̊Ǘ��v����{�����Ƃ���w�Z�ŁA�Â��g�g�݂���O���{���́u�Ƒn���v�����}����Ȃ��͓̂��R�ł���B�����A�����̓_�����P�����A������̏�ł��[���ɑn���͂̔������x�������ł��낤���A���{���瑽���́u���Ёv�u�B�l�v�u�X�[�p�[�X�^�[�v���y�o����Ǝ��͍l����B
�@�u�A�����J�̑�ЊQ�Ɣ�ׂē��{�l�͔��ɗ�Âł������v�u���{�l�͎��R�ЊQ�Ɛ܂荇���Ȃ��琶���Ă������߁A�ЊQ�������͂������Ă���v�Ȃǂ̘_�]�́A�u��Ђ͂������A���������͉��l�̍��������������Ă���l�Ԃ��v�Ƃ����l�����ɂȂ���댯�������B���̌��ʁA�����̍��ق��z���Đl�Ԃ�������������A�I�ꂽ�l�ł��邩�̂悤�ɖفX�Ƒς�����{�l�̎p����ʉ����āA���炻�̑��l�ȓ��ʂ��������悤�Ƃ͂��Ȃ��B����͐푈�ӔC�Ɋ֘A���āA����̎c�s�s�ׂƎ�̓I�Ɍ��������̂ł͂Ȃ��A������O�I�����̂����ɂ��Đ[�����ȗ��������Ă��Ȃ������ߋ��̓��{�l�̑ԓx�ɒʂ�����̂ł���B�l�Ԃ���������_�I��@����̉͂����߂ɂ��A���������_�]�̔w��ɂ���p���͖�肾�Ɠ�l�̑Βk�҂͍l���Ă���B
�@���_�I��@��ʂ��Ď��ȗ�����[�߂邱�ƂƁA���_�I��@��s���Ȃ��̂Ƃ��ĊO�̌����ɂ���Ă̂ݐ������邱�Ƃ́A�u������[���m�邱�Ƃɂ���ĖL���Ȑ��̉\�����J���v���ƂƁu��ȂɎ��Ȃ���邱�Ƃł������Đ��������������v���Ƃ��Ӗ�����ƍl������B�l�ɂ��čl����A�O�҂��ۑ蕶�̃x�g�i���A�ҕ��ɂ�����B��҂͔s������ɐ����I����𐳔��ɕς����u�A�����J�}���v��u�\�A���q�v�̓��{�l�ɂ�����ł��낤�B
�@��̑ԓx�̈Ⴂ�͎Љ�ɂ��傫�ȉe����^����B�P�X�W�T�N�A�h�C�c�̃��@�C�c�[�b�J�[�哝�͔̂s��L�O���Ɂw�r���̂S�O�N�x�Ƒ肷�鉉�����s�����B�哝�̂̓h�C�c�l���s��̓����L�O����̂́A���_���l�s�E���̈ӂɖ��������߂��e�l�����Ȃ��A�Ⴂ���オ�O����Ə��������ĉߋ��̐ӔC���A�ߋ������邱�Ƃœ�x�ƍ߂�Ƃ��Ȃ��悤����F�����s�����邽�߂ł���Ƃ����B����͎Љ�̐����S�Ă����_�I��@��ʂ��Ď��ȗ�����[�߂邱�Ƃł��낤�B����ɑ��āA�u�ߋ��̐���ɂ͐푈�ӔC�����邪�A�������̐���͕ʂł���v�Ƃ��u�푈�͗��j�̕K�R�ł��邩��A�l�ɐӔC�͂Ȃ��v�Ƃ����l���������l�����{�ɂ͑����B����͐��_�I��@�̊O�݉����ƌ�����B
�@�O�҂̍l�����͓��{�ł͏����h�����A�����炱�����́u�l�Ƃ��Ă̎��o�Ɋ�Â��ӔC�v�����ɗ��������B�Ȃ��Ȃ�A����̐��E�͑��l�ȘA���������{�[�_�[���X�Ȃ���������Ă��邩�炾�B�Ⴆ�A����̂�����o�ϊ������A�r�㍑�̕n���␢�E�I�Ȋ����Ɗւ���Ă��邱�Ƃ��������͒m���Ă���B�����������̍��̐l�X�⎟�̐���ɑ��ĉe�����y�ڂ����Ƃ��u�m���Ă���v�ȏ�A�����ɂ̓i�`�Y�����̎s���Ɠ����ӔC��������̂ł���B������l���邱�Ƃ͊m���ɋ�ɂł��邪�A���Ȃ̐��_�I��@�ƑΌ������o���邱�Ƃ́u��l��l�̌��݁v�ɑ��鎩�o�ɂȂ���䂦�ɏd�v�ł���Ǝ��͍l����B
�@�ۑ蕶����l�Ԃ̕s���ɂ��ē�̖����Ƃ肠���悤�B��́u�l�Ԃ̓��ꐫ�Ƃ͉����v�Ƃ������ł���A������́u�s���Ɛ��B�͓������v�Ƃ������ł���B
�@�f�B�I�e�B�}�͓��ꐫ��l�Ԃ̐������ɐ������Ă��邪�A����͐l�Ԃ��\�����镔���̘A�����Ɋ�Â����c�_�ł���B�Ⴆ�A���̎����Ԃ̕��i���S�Č������ꂽ�Ƃ��Ă��A�V���̕��i������̂��̂ł���A���̎����Ԃ́u����̂��́v�Ƃ����Ӗ��ňȑO�Ɠ��ꕨ�ƍl������ł��낤�B�������A�@�\��`�Ԃ��傫���قȂ������i���p������A���͂╔�i������̎����Ԃ͈ȑO�Ɠ��ꕨ�Ƃ͌����Ȃ��B����́A���鎩���Ԃ���肷��u�ʐ��v���@�\��`�Ԃɂ���Đ������Ă��邩��ł���B
�@����ł͐l�Ԃ́u�ʐ��v�͉��ɂ���Đ�������̂ł��낤���B����͎����ԂƂ͈���āA���i�̓��ꐫ�ɂ��̂ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̂ȂǂŐg�̂̋@�\���傫�����Ȃ��Ă��A�u�l�i�v�̓��ꐫ�͕ۂ���邩��ł���B���̈Ӗ��ł́A�זE�|�{�̋Z�p�ɂ���Ĉ�`�q���x���őS������̌̂����܂ꂽ�Ƃ��Ă��A����́u�����l�v�ł͂Ȃ��B�܂�A�l�Ԃ̌ʐ��́u�l�i�v�Ƃ����u���v�f�̑S�̓I����v�ɂ���Đ��藧���Ă���̂ł���B�]���āA�l�Ԃ̓��ꐫ�́u�S�̂Ƃ��Đ�������l�i�̘A�����v�ł���ƌ�����B
�@���̂��Ƃ���A�s���Ɛ��B���������ǂ������l���悤�B���̂ɐ����Ə��ł��₦�ԂȂ��N�����Ă���͎̂����ł���B����͌̂̎��ɂ���Ē��f���邪�A��`�q���x���Ō���A�q���ɓ����ߒ����p�����B�܂��A�l�Ԃ̊���ƒm���́A���������u�N��������̊����S�ɕ����Ă���v���邢�́u�N�������錾�t�ɑ��ē���̊T�O�������Ă���v�Ƃ����O��̏�ɐ��藧���̂ł���B����炪�^���ł��邩�ǂ����́A���̐l�i�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�m���߂悤���Ȃ��B�����̘_���ɗ��ĂA�s���Ɛ��B�͂قƂ�Ǔ������ƂɂȂ�B
�@�������A���́u�S�̂Ƃ��Ă̐l�i�̘A�����v�ł���B��`�I�Ȃ��肪�����ɋ����Ƃ��A�e�Ǝq���ʂ̐l�i�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�s���͓��ꐫ���ێ�����邱�Ƃł��邩��A�u�l�i�v�Ƃ����ϓ_���猩��ΐ��B�͕s���ł͂Ȃ��B�������A�l�i���\������v�f�̒��ɂ͊����m�����܂܂��B�����͐��オ����ƒf�����Ă��܂����̂ł͂Ȃ��B����́A���̓��ꐫ�ɑO�q�����悤�ȞB���������邩�炾�B�����A�t�ɂ��̞B�����ɂ���āA��X�͊����m�������ԓI�E��ԓI�Ȋu������āu�`������v�ƍl����B����䂦�A�u�s���v�����߂�Ƃ���A���̉\���͌̂̌��̂Ȃ���ɂ���̂ł͂Ȃ��A�l�i�����҂̊����m���ɉe����^���A���ꂪ�`�����邱�Ƃ̒��ɁA����������L���Ӗ��ł́u�����v�ɂ���̂��Ǝ��͍l����B
�@���͗��j��̐l���̔����Ƃ��āA��̑��ΓI�Ȏ��_���K�v�ł���ƍl����B��͌��ォ�猩�����j�I�Ӌ`�Ƃ������_�ł���A������͂��̎���̉��l��Ƃ������_�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�����Ȃ�]�������̎���̉��l�ς��玩�R�ł͂Ȃ��A����͊w��I�ȕ]���ɂ��Ă����l������ł���B�Ⴆ�A�Ñ�M���V���A�A�e�i�C�́u���吧�v�́A����ł������]������Ă���B����́A��X����X�̎���̐����I���z�ɏ]���āu�����`�v��]�����Ă��邽�߂ł���B����䂦�ɁA���ۂɂ̓A�e�i�C�̐������x���z�ꐧ�Ɏx����ꂽ���̂ł������Ƃ��Ă��A��X�́A�u���吧�v�����������Ƃ����A��X���l������j�I�Ӌ`�̓_�ŁA�A�e�i�C�ƌ����A��������Ō��т��A�]������̂ł���B
�@����ɑ��A�w�[�Q���́u���E���_�v�̂悤�ɁA�]���̐�ΓI������߂闧�ꂪ����B�O�q�̗�Ō����A�����`�͕��ՓI�ȑP�ł��邩��A�����`�𐄂��i�߂��l�����̑�Ȑl���ł���A�Ƃ���l�����ł���B���̏ꍇ�A��X�́u�������x�̒��ł�薯��I�Ȑl���v�Ȃǂ�T���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ʓI�ɁA���̂悤�Ȏ��݂́u�ߋ��ɟ��قǐl�Ԃ͕s���S�ł���A���ケ���ł��i����������ł���v�Ƃ������_�Ɍ��т�����Ȃ��B�w�[�Q����}���N�X�̗��j�ς͂��̈��ł��邵�A�Ȋw�̐i���j�ς�����Ɋ܂܂�邾�낤�B�������A���̏ꍇ�ɂ́A�]���̊���̂����Ɍ�����u�ߋ��Ɣ�ׂđP�v�Ƃ��鑊�ΐ����܂�ł���̂ł��邩��A���̂悤�Ȋ�́u��ΓI�v�ł͂��蓾�Ȃ��̂ł���B
�@��������u���̎���̉��l��v�Ƃ������_�̏d�v�����������B�D�c�M�����i�|���I�����A�s�E�҂ł���Ɠ����ɉ���҂ł���A�v�V�҂ł������B����ł͒f�ГI�ɂ����L�^����Ă��Ȃ��ނ�̎����𑨂��悤�Ƃ���A����ꂽ�f�ނ��ł��邾���W�߁A�u���̎���v���č\������K�v������B�������A�f�ГI�ȋL�^��������ł��A�ߋ��̕����������Ɍ���̕����ƈقȂ��Ă������Ƃ������Ƃ��킩��A�������l�X�̐�������Ȃǂ͕����̎�i���Ȃ�����A����Ό���́u�ٕ��������v�Ɠ�����肪�A�����ɐ�����B���̓_������A�����P�Ƃ����ΓI�Ȏ��_�ł́A�l���̑S�̑��𑨂����Ȃ����Ƃ��킩��B�ۑ蕶�ɂ���悤�ȁA�l���̓���̐��ȁE�K�����L�^�Ɏc���Ă����Ƃ��Ă��A���ꂪ���̎���̉��l�����ǂ��]������邩�ł���A�ȒP�ɂ͒f���ł��Ȃ��̂���B
�@�]���āA�u���ォ�猩�����j�I�Ӌ`�v�Ƃ������_�A�u���̎���̉��l��Ƃ������_�v�̓�����j��̐l���̕]���ɕs���ł���Ǝ��͍l����B
�@���A���n�����ł́A�Ɨ��ȑO�͎x�z�҂ł��鐼�������̌��ꂪ���ʌ�ł������B�n��ɂ���ėl�X�Ȍ��ꂪ�g���Ă������A�����I�x�z�͂������������߁A�����ꂪ���ʌ�Ƃ��Ē蒅�����B���̌��ʁA�Ɨ���͈�̎����ꂪ���p��Ƃ��ꂽ�ɂ�������炸�A�������̑��l�Ȍ���W�c�Ԃ̈ӎu�a�ʂ�A��������{�ɂ�����������ɂ͂Ȃ������ꂪ�K�v�ł���A����ɁA���ꂪ�G���[�g�w�Ɣ�G���[�g�w�̍����g�傷��Ƃ�����肪���܂ꂽ�B
�@�u�����`�v�̑O��́u�S�Ă̌l��������������F�߂��A���d����邱�Ɓv�ł���ƌ����邾�낤�B���ꂪ�\�ɂȂ��������I�����̈�́u�����̓����ɏZ�ސl�X�͓��������ł����āA�����̌��������v�Ƃ����ߑ㍑�����Ƃ̒a���ł���B
�@�ߑ�ɁA�n��I�ȑ��l���������Ă��������̏������̂͒����W���I�ȓ����@�\��������������Ƃɓ�������Ă������B���̍ہA���l�ȏW�c���܂Ƃ߂��̂��u�����̓����͕����I�ɓ���ł���v�Ƃ����l�����ł���B�܂�A���Ɠ���̕����ɂ����錻�ꂪ�����I��������Ȃ̂ł���A���̏ے����u����̓���v�ł������B
�@���A���n�����ł́A�A���n����ɂ͌���̓���͏ォ�牟�������A�Ɨ���͂��ꂪ����I�ɐ���������ꂽ�B�ǂ���ɂ���A���ʌ�́A�S�Ă̍������Γ��Șb�������ɂ���č��ӂ��`������Ƃ��������`�I�Љ�̊�b�ł���B
�@�������A�������p���b�������̃G���[�g�Ɖp���b���Ȃ������h�Ƃɕ��Ă��܂��ƁA�u�Γ��ɘb�������v�Ƃ�������������A���ƂƂ��Ă̓��ꐫ���h�炮�B�����ł͌o�ϓI�Ɍb�܂�A���x�ȋ�����������h�����͂�����A�n�����A������[���Ɏ��Ȃ������h�̖��O�ƑΗ�����Ƃ����A���n����Ɏ�������������邩��ł���B���ꂪ�������Ŏ�����Ă�����̍\���ł���B
�@���͉p�����ł̖k�A�C�������h�Ɖp�����{�̑Η��ɂ��ďq�ׂ����B�p���͌��������̌���A�����������ł���B�������A�k�A�C�������h�ł͘A�����������ȗ������ԁA�p������̓Ɨ������߂�^���������A��O�A����ʂ��ĕ��͏Փ˂�e�����₦�Ȃ������B���̌����́A�A�C�������h���{���P���g�I�ȕ����������Ƃɉ����ĉp��������ƈقȂ�J�g���b�N�̕������ێ����A���ꂪ�����I�E�o�ϓI�ȍ��ʑҋ��ɂ��Ȃ����Ă��邩��ł���B��ʂɁA�Љ�̒��̎��Ӄ}�C�m���e�B���������A����A�����K���Ȃǂ́A�����̌��͂���߂��u�������ʁv�̊�ɍ��킹��悤��������₷���B�������A�������z���Đl�E���m�E��ړ����錻��ł́A�����̃A�C�f���e�B�e�B���Œ肳�ꂽ���̂Ƒ�����̂ł͂Ȃ��A���l���d���A�Ⴂ��F�߂���ł̍��ӂ����E�I�ɕK�v�ł���B����䂦�A�n�掩�����L���F�߁A�Ɨ����Ȃ��狦�͊W��z������͍����ׂ����Ǝ��͍l����B
�@�C�����������A�������͂��̏������瓦��悤�Ƃ���B���A��؉A�ɓ�������A���������肷�镨���I�ȑ���A����̉��⒩��̉Ԃ��y���ސ��_�I�ȑ���u��ɂ�����ĕs������������悤�Ƃ��鎩�R�ȑԓx�v���琶�܂ꂽ�H�v�ł���B�����ɂ͎�������̓I�ɍs�����邱�ƂŎ��͂̊��ɓK�����A���ƒ��a���悤�Ƃ���w�͂�����B����ɑ��āA���u�ɂ���ċC�����̂��̂������邱�ƂŁu�����v�Ƃ�����ɂ������Ȃ��悤�ɂ���̂��u�s�����ĂыN�������̕��i�h���j���̂��̂��������ė��������Ƃ������@�v�ł���B������̑�͊�������I�ɕύX������̂ł���A�K���ւ̎�̓I�ȓw�͂��s�v�ȑ���ɁA����ȃG�l���M�[����Ɣp�����ɂ��������≷�g���������B���̌��ʁA�V���ȕs���̌������������A�ی��Ȃ����j�g�傷��B����̊����̍���ɂ́A���̂悤�ȁu�s���̌����̍���v�Ƃ������@������ƌ�����B
�@���Ȓ��S�I�ɐ����鎞�A�l�͎��Ȃɂ��Ĕ��Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��B����䂦�ɁA�u���Ȃ̎��R�v�͓����ɑ��l�̎��R��}�����Ă���̂ł���B�������A�E�ς��Ȃ���Ύ������������Ȃ����A�l�͏��߂Ď������Ȃ݂�B����͎��������R��}������ċꂵ���悤�ɁA���l���܂����R��D���ċꂵ���Ƃ������o�ł���B�䂦�ɁA�u�E�ς���ɔ�߂����炬�v�́A���Ȃ�}�����đ��l�̎��R�Ǝ������d���邱�ƂɂȂ���ƌ�����B
�@����̏���Љ�ɐ�����l�Ԃ́A�����ŕK�v�ȕ�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�����s�ւ�����A���������������@�͏��i�̍w���ł���B���̌��ʁA�u���i���w�����Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��v��ԂɂȂ�̂��u���y�ւ̗ꑮ��ԁv�ł���B�Ⴆ�A�u�K���ȉƒ��z���v�Ƃ����ړI�����l������Ƃ���B�ނ͉Ƒ��Ԃ̐S��I�����Ǝ��g�݁A�o�ϓI�ɋ�J���Ă͂��߂ĖړI��B���ł���ł��낤�B�����炱���A���̒B���̊�т��傫���̂ł���B�������A����Љ�ł́u�K���v�Ƃ́u���i���y�Ɏ�ɓ���邱�Ɓv�ł���B�ނ͉Ƒ��̂��߂ɏ��i���A�Ƒ������i�w�����Ƒ����J���ƍl����ł��낤�B�����ɂ͏��i����ɓ��ꂽ���́u����v�̊���͂����Ă��A�{���̊�т͂Ȃ��B����ɁA�₦�����������V���i�̂��߂ɔނ̏���ւ̗~�]�͖�������邱�Ƃ��Ȃ��A�K���̒Nj��͌��R���ɔY�܂���Ȃ���V�������m��ǂ�������s���ɂ������B���ꂪ�u���y�ւ̗ꑮ�v�̃R�X�g�ł���B
�@���e�I�ɂ͂��Ղ����B�����܂ł��Ȃ��A�p�o�̉ۑ蕶�ł���B�ǂ̐ݖ���A�������e�𗝉����Ă��邩�ǂ����A��̓I���ɑ����Đ���������Ӑ}�������Ă���B����Љ�_�̊�{�I�Ȗ��ł��邩��A���_������K���Ă������ɂ͈Ղ��������ł��낤�B
�@�Љ���̗�Ƃ��āA���͔��W�r�㍑�̉����������������B�r�㍑�͑啔�������݂̐�i���̐A���n�ł������B�A���n����ɂ͖{���̍��ɂ���Čo�ρE�Љ�̋ߑ㉻���i�܂��A���̉e���ŁA�Ɨ�����r�㍑�͋ߑ㉻�̒x��ɋꂵ��ł����̂ł���B�o�ς̃O���[�o�����́A���������r�㍑�̕�������̉�������荢��ɂ��Ă���B���m�E���E�l�E��������z���Ĉړ�����悤�ɂȂ�ƁA�r�㍑����i���Ɠ����o�ϋ����ɂ��炳���B�������A�X�^�[�g���C���Ŋ��ɍ����傫���A�r�㍑�͐�i���ɔs��č����A�Q��E���j��E�Ⴂ�q���⋳�烌�x���E����s���Ȃǂɒ��ʂ��Ă���B���̌��ʁA��i�����o�ϋ����ŏ����������قǁA�r�㍑���琶�܂ꂽ�n������e���̖�肪��i���ɉe����^���ĉ������K�v�ɂȂ�Ƃ���������������̂ł���B
�@���̍s�����j�͌l�I�ȉ����ł���B�l�œr�㍑�̂���n��ɏo�����A���K������J�́A�Z�p�̉���������B���{�l�ɂƂ��Ă͂킸���ȋ��z�ł��A���n�ł͊w�Z��a�@�����Ă邱�Ƃ��ł��A�l�X�Ɋ���ł��낤�B�������A�����ł���͈̂�̑��ȂǏ��K�͂Ɍ����A�啔���̐l�X�ɂ͖��W�ł���B���̍s�����j�̓{�����e�B�A�g�D��{�@�ւɂ�鉇���ł���B�����̋K�͂͑傫���Ȃ邪�A�n��̓����͂��݂ɂ����Ȃ�A�܂��S�Ă̓r�㍑���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��O�̍s�����j�͍��A�Ȃǂ̍��ۋ@�ւɂ�鉇���ł���B�Ⴆ�A���X���b�v�ɂ����Ə��Ŋ��j����ŏ����ɂ��A�������炷���Ƃ��ł���B�������A�ً}��v����ʂ̖��͉�������Ȃ��B��l�̍s�����j�́A�r�㍑�̎����̂��߂ɁA��i���̃O���[�o���Ȍo�ϊ������̂��̂��K�����邱�Ƃł���B�������A���̂悤�ȋK���͍��ӂ�����A��i���ԂɐV���ȑΗ��������邱�Ƃ�����B
�@���͑��̍s�����j��I�����A���ꂪ��l�̍s�����j�ɂȂ���悤�ɉ^���������B����͎�����i���̎s���Ƃ��āu������ւ̐ӔC�v�Ɓu���̐���ւ̐ӔC�v���Ă��邩�炾�B������ւ̐ӔC�Ƃ́A�r�㍑�̖��͐�i���̌o�ώx�z�ɂ����̂ł���A��i���ŖL���������Ă��鎄�ɂ��ӔC������Ƃ������Ƃ��B���̓{�����e�B�A�g�D��ʂ��Ď����Z�ޒn��ōs�����n�߁A�r�㍑�̒n��Љ�Ƃ̘A�ъ���z�������B�����ɁA���̐���ɖ���摗�肵�Ȃ����߁A���̖{���I������T��K�v������B����͋��片���Ȃǂ�ʂ��ēr�㍑�̎������x�����邱�Ƃł���A��i���̌o�ϊ�����n���K�͂Ŏ����\�Ȃ��̂ɕς��邱�Ƃł���B����ɂ���āA�r�㍑�̐l�X�̖L���Ȑ������\�ɂȂ�Ƌ��ɁA��i���̐l�X���������S�łȂ�������������ł���Ǝ��͍l����B
�@���e�I�ɂ͊�{�I���ł���B��N�ɑ����A�ǂ̐ݖ���������e�𗝉����Ă��邩�ǂ����A��̓I���ɑ����Đ���������Ӑ}�������Ă���B�������A��N�ɔ�ׂāA��莩�̂������w���Ă���̂����킩��ɂ����B�u�o�ς̃O���[�o�����̉e���v�u�������߂����i���Ɠr�㍑�̑Η��v�u�n���I�K�͂ōl���n��ōs������Ƃ����{�����e�B�A�̌����v�Ȃǂ̊�{�������Ȃ���Ό˘f�������m��Ȃ��B
�@�܂��A�u���m�v�̑��ʂ���O�̍�i�߂Ă݂悤�B�`�ł͉�ʂɎU���A���t�@�x�b�g���`����Ă���B�����Ɍ����A�u�A���t�@�x�b�g�v�͎v�l�̑�����Ώۂ��܂Ƃ߂��������ł���A���ۂɉ�ʂɕ`����Ă���̂͗l�X�Ȑ��̏W���ɉ߂��Ȃ��B�a�ł͂`�Ɠ������l�X�Ȑ��̏W�����`����Ă��邪�A�����͈��̋K���Ő��A��ʂ����R�ɉ�]����悤�ɂȂ��Ă���B�b�����������̏W���ł���B�������`�a�Ƃ͈���āA�b�̗l�X�Ȑ��͕������ꂽ���̂ł���A���ʂ̌`������������������B����̋K�������a�ɏ����Ă���B
�@���Ɂu�v�l�v�̑��ʂ���O�̍�i�̈Ӗ����l���Ă݂�B�`�́u�v�l�̃A���t�@�x�b�g�Ƃ��Ă̕����v�ł��낤�B������ʂɍ����菑���̐��ŕ������`����Ă���B�����̌`��ʒu�͑S�ĈقȂ��Ă���B�������A�������ǂ̂悤�Ȍ`�ŕ`����Ă��邩�͖��ł͂Ȃ��B���́A�`����Ă��镶���̑g�ݍ��킹�ɂ���āu��v�����܂�邱�Ƃł���B�����āA��ݏo�����߂̃A���t�@�x�b�g�́A�����ɕ`����Ă��邾���ŏ[���Ȃ̂ł���BSo FANG Es heimlich an�@�͂��̕����Q����\�����ꂽ��̏W���Ƃ��Ă̕��������Ă���B����������A���̃h�C�c��͕��ŕ\�����ꂽ�v�l�ł���B���͈Ӗ������B���̍\���v�f�ł������Ӗ������B�ł́A�A���t�@�x�b�g�̈ꕶ���͈Ӗ��������B�����ꕶ�����S���Ӗ��������Ȃ��̂Ȃ�A���Ӗ�����Ӗ����\������邱�ƂɂȂ�A������������B�]���Ĉꕶ���͈Ӗ������ƌ�����B�������A���̈Ӗ��́A�ɂ߂Ĕ����Ȃ��̂ł���B����͖����v�l�ɂȂ�Ȃ��v�l�ł���B�䂦�ɁA�ꕶ���͎v�l�̌��E�ł���A�v�l�̃A���t�@�x�b�g�ł���ƌ�����B
�@�a�͌���҂̈ӕ\������i�ł���B�m�Ԃ̎l�̔o�傪�����ꂽ�~�Ղ��ꔪ�Z�x���]����ƁA�S�Ă̔o�傪�u�ӂ邢����`�v�̋�ɂȂ��Ă��܂��B���̎��o�I�����������̂ɁA�������Ԃ����������B�G��̐��E�ł́A�㉺���t�]�����Ă��Ӗ��̂���G�Ɍ������i���u���܂��G�v�ƌĂ�ł���B���̈Ӗ��ł́A���̍�i�́u���܂����v�ł���B�������͂Ȃ����܂����̂��B�܂��A���{�̕�����ǂ߂Ȃ��ٕ����̊ӏ҂ɂƂ��āA���̍�i�͒P�Ȃ��]�Ղł��낤�B�����ɂ͈Ӗ����قƂ�ǂȂ��B���ɁA������ꂽ�����͓ǂ߂邪�ѕM��ǂ߂Ȃ��ӏ҂ɂƂ��ẮA���̍�i�͗L���Ȏl�̔o�傪�����ꂽ�F���ł���A�o��̈Ӗ��͂킩���Ă���]���邱�Ƃ̈Ӗ��͗����ł��Ȃ��B�Ō�ɁA�ѕM����ǂł���ӏ҂ɂ���ď��߂āA���̍�i���Ǝ��ɂ��Ӗ������܂��B�܂�A�u���܂����v���������邽�߂ɂ́A�����o���m���Ă��邾���ł͕s�[���ł���A�u�����v�����݂ɓǂݎ��v�l�̗͂��K�v�Ȃ̂ł���B�������A�������͕�����g�ݍ��킹�����͂Ɏv�l�̓�����F�߂Ă��A���ʂ́u�����̓ǂݎ��v���̂��v�l�Ƃ͌ĂȂ��B�܂�A�u���܂����v�͎v�l�������o��������\�����Ă���̂ł���B
�@�b�̈�������́A���͂Ƃ��Ă̓��e�������d�����ĕ\�����ꂽ���̂ł���B�]���ĕ\���̌��͋����Ȃ��B�������A�����ɏ�����Ă�����e�́A�u�����v�Ɋւ���Ǝ��̎v�l�ł���B�M�҂͈ꕶ���������A�ꕶ���������Ƃ�������̒��ɁA�u���Ȃ��L���������A���Ȃ��L���������v�Ƃ������Ƃ̈Ӗ���ǂݎ���Ă���B����̋L���͂ǂ̂悤�ȏ����������Ă����ʂ̋L���Ƃ��ėp������B�܂蓯��L���̋��ʐ��ƈَ�L���̍��ِ��ɋL���̈Ӗ�������B�L������\������錾�ꂪ�A���Ȃ̌��t�ł���Ȃ���A����ɂ��ʂ��鋤�ʐ������̂͂��̂��߂ł���B����ɑ��āA���Ȃ́u���A�����ɂ���v�Ƃ���������B���Ȃ͓�l���Ȃ��B���̎��Ȃ��u�ȁv�Ƃ����������ꕶ�����������ƁE�������Ƃɂ���āA�v�l���鑶�݂Ƃ��Ă̏𑼎҂ɔF�߂�ꂽ��A�F�߂��Ȃ������肷��B���̈Ӗ��ŁA�����菑����p�\�R���̃f�B�X�v���[�ɂ���ĕ\������镶���u�ȁv�́A�v�l�̗v�f�ł��邱�Ƃ��āA�v�l�̒S����ł��鎩�Ȃ��̂��̗̂v�f�ɂȂ��Ă��܂��B���̊Ԃɂ��u�ȁv�Ƃ��������́A�v�l�̌��E���āA���ȂƎ��ȈȊO�̃��m�̌��E�E���E����ɏ�����Ă���B
�@�������Ă݂�ƁA�������̂��͕̂����������u���m�v�ɂ���Ďx�����Ă��Ȃ���A�ǂ�Ȃɕ������琸�_�����͂���낤�Ƃ��Ă��A�����ɂ́u�v�l�v�̔����ȕ��q���K���c���Ă���B�����̑����當���̏����ꂽ�������̃C���N���킬����Ă����ƁA�Ō�ɂ́u�`�v�Ƃ������ۓI�Ȑ��i�������B�t�ɁA���_�E�v�l�̑����當���ɂ���ď����ꂽ�������̂��A�Ӗ����킬����Ă����ƁA�Ō�ɂ͕����̌��^�ł���u�Ώہv�Ƃ��������I�Ȑ��i�������B�������āA�u�v�l�v�Ɓu���m�v�̋��E�ɁA���҂̐ؒf�ʂƂ��āu�����v�������Ă���̂ł���B���A�������̎Љ�ł́A������i�����l�ɂȂ�ɂ�A�������Ƃ̐ӔC���y���Ȃ��Ă���B�����炱���A�ꕶ���̑f�ނ⏑�����̈Ⴂ���A�v�l�̑��l���A���Ȃ̑��l���ݏo���A�l�Ԃƃ��m�̐��E�Ƃ̊ւ���L���ɂ��Ă������Ƃ�U��Ԃ�A�V���Ȏv�l�����̋��E����n�߂邱�ƂɈӖ�������Ǝ��͍l����B
�@�o��̌`���͍�N�Ɠ����ł��邪�A���e�I�ɂ͍�N�������ۓI�ł���B����䂦�u����v�ƌ����邾�낤�B�������A�a��b�̍�i���l�X�Ȗ���A�z�����Ă����̂ŁA�肪����͑����B��N�Ɠ������A���p�E���w�E�N�w�ȂǁA�L���͈͂̓Ǐ��ɂ���ĖL���ȑf�ނ�g�ɂ��Ă����K�v������B
�@�V�X�e���ƐE�ƑI���̊W��₤���͎Љ�n���_���̊�{�B���K���d�˂Ă������Ȃ玩�M�������ĉł��邾�낤�B���N�x�c��E�����w���̏o��Ƃ悭���Ă��邪�A����̓T�����[�}���Љ��Ɨ��N�ƎЉ�ւ̓]����肪������{�̉ۑ�ł��邱�Ƃɂ��̂��낤�B
�@�`�̕��͂Ńx���N�\���́A���m�ȏ��ɕs���Ȃ��̂��u�������v�ł���Ǝ咣���Ă���B�����ł́u�������v�Ƃ͈ꎞ�I�Ɋ�����R���g���[�����A�S�Ă̂��̂��u���q�̑Ώہv�Ƃ��Č��邱�Ƃł���B���������������u���q�̗͂ɂ�鑊�Ή��v�ƌ�����ł��낤�B�S�Ă̑Ώۂ𑊑Ή����邱�Ƃɂ���āA�����ɂ͏���痣�ꂽ�A�V�������_�����܂��B���̎��_������I�ȏ���痣��Ă������قǁA�u���i�Ȃ�Ό��l�ȏo�����v�������̑傫���u���m�ȏo�����v�ւƑ傫���ϖe����̂ł���B
�@�a�̕��͂ɂ���u�����̃Y���v�����l�̍l�����ł���B�������A�a�̋c�_�̓����́u���m�Ȃ炴����́v���u�����ɏ]�������́v�Ƒ����Ă���Ƃ���ɂ���B�����͐l�Ԃ̒m�������ݏo�������̂ł���B�܂�A�`�ł́u���q�v���u���m�ݏo�����Ή��̗́v�Ƃ��đ������Ă���̂ɑ��āA�a�ł͒m�����u�����̒����������߂�l�Ԃ̍����I�~���v�Ƃ��đ������Ă���ƌ�����B����͐����̎咣�ł͂Ȃ��B�m���͂܂��u�S�̓I�Ȓ����v���\�z����̂ł���A���̏�ɂ��Y�����u�V���������v�ݏo���̂ł���B�u�V���������v���猩��u�Â������v�����Ή�����A�悭������悤�ɂȂ����ƌ�����B�����炱���X�E�F�C�r�[�͊��m���u���������߂�́v���Əq�ׂĂ���̂ł���B
�@�b�̕��͂ł͂a�́u�����̃Y���v���u�ْ�����̉���v�ƍl�����Ă���B�b�̕M�҂ɂ��u�����v�Ƃ́u�Ӗ��Â��̌Œ艻�v�ł���B�Ƃ��낪�A�Œ艻���ꂽ�Ӗ��Â��͓����Ɂu�Ӗ�����������́v���l�����A�����̌��Ђݏo���Ă��܂��B�����ɂ́u���߂̎��R�v�͂Ȃ��A�m���͎��R�Ɋ����ł��Ȃ��Ȃ�B���ꂪ�u�ْ��v�̏�Ԃł���B�����Ɂu�Ӗ��̋t�]�v��������ƒ����̌��Ђ����A�m���͑�������������Ď��R�ȉ��߂��\�ɂȂ�B��ʂ��猩��A����́u�����̃Y���v�ł���A�u�����v�ł���B�����Ɂu���v�u���m�v�����܂��̂ł���B�������ʂ̖ʂ��猩��A���R�ȉ��߂́u�v���Ă��݂Ȃ������Ӗ���\���v�ɉ�X�̖ڂ��J�����̂ł���B�����ł͉�����ꂽ�m�������R�Ɋ������A���̌��ʂƂ��ČÂ������⌠�͂��ے肳���̂ł���B
�@�����̎咣�܂��Ď����c�����悤�B�u�Ԃ�V���}�b�`�����݂��ށv�Ƃ������Ԃ́A���퐶���ł͐S�̓��h���Ђ��������B�������A���̏��b�ł͕�e����ÂɁu�}�b�`���Ȃ��Ȃ烉�C�^�[������v�Ƃ������̑I�������������ƂŁA����I�ȁu���h�v�Ƃ�����𑊑Ή����Ă���B��X�͐Ԃ�V�̐S�z����������A��e�́u�ӊO�ȕԎ��v���Θb�Ƃ��Ċm���ɐ������Ă��邱�ƂɁu���������v��������̂ł���B���̘b��ǂ�Łu�s�ސT���v�Ɠ{��Ȃ��l�́A����I����痣��Ēm���̓������y����ł���_�ŕ��͂`�̏ꍇ�ɊY������B�܂��A�u����ȕ�e�͎��ۂɂ͂��Ȃ��v�Ƃ����_�ł́u�����̃Y���v�Ƃ��ĕ��͂a�̏ꍇ�ɂ��Y�����邾�낤�B���l�Ɂu�܂���ρv�Ƃ������҂���锽���𗠐�Ƃ����_�ł͕��͂b�̏ꍇ�ɍ��v����B�����d�̖�����u�E�҂͔C���������ɐ��s������̂ł���̂ɁA�������������ĉו�������Ȃ��v�u�E�҂ɋC�Â������m�����œV����h���͂��Ȃ̂ɁA�������������Đ������Ă���v�Ƃ�������I�ȗތ^�Ƃ̑ΏƂ��ʔ����̂ł���B
�@���͂`�a�b�̂ǂ�����u���m�v�̖{�����������ĂĂ��邱�Ƃ�F�߂���ŁA����ɍl�@��i�߂�u���m�̖{���͉��l�̑��Ή��������炷���Ȕے�ł���v�Ƃ������Ƃ��咣�������B���m�����܂��̂͊����̒����E�Ӗ������Ή����ꂽ���ł���B�s���ɉe�����y�ڂ������E�Ӗ����u���l�v�ƌĂԂ��Ƃɂ���A�u���m�v�́u���l�̑��Ή��v�ł�����B���́A���̑��Ή��������ɂ��y�Ԃ��Ƃł���B���͂`�̌������猾���A�u���q�v�͎����̍s����l�i�����q�̉����āu�����Ŏ���������v�̂ł���B���͂a�̌����ł́A��X�́u�펯���킩���Ă���l�قǁA�������ǂ�قǃY���Ă��邩���킩��Ɩʔ����v�̂ł���A���͂b�̌����ł́u�Œ�ϔO���甲���o����A���܂ł̎����������Ɋ��m���������킩��v�Ƃ������ƂɂȂ�B�����c�̏�k�������ł���l�́A�u�Ԃ�V�͂��킢���A�������ی삳���ׂ����v�Ƃ����펯�ɂ��肵�Ă��鎩�������A���ԓI�ȉ��l�ςɏ]��������ے肵�Ă���̂ł���B�������A�����d���y���߂�l�́A�u���㌀�̒�^�V�[���v���v�������ׂȂ���A�ו��������ς��邾���őS�̂̈Ӗ����S���ς���Ă��܂����Ƃɋ����A�^�ʖڂɎ��㌀�����Ă��鎩����ے肵�Ă���̂ł���B
�@�������A�u���m�Ƃ������Ȕے�v�́u���Ȕډ��v��u���҂̐�Ή��v�Ƃ͑S���Ⴄ�B�u���������v�Ƃ́u��������荂���ʒu���猩�ċq�ϓI�ɕ]������v���Ƃł���B����ɁA����ɂ���ĐV�������_�E�V����������l�����邱�Ƃ��ł���B�܂�A���m�́u�Â����Ȃ�ے肵�A�V�������Ȃ̎�����y���ށv�Ƃ����u���ȍm��v�ɂȂ����Ă���̂ł���B�����c�̂悤�ȁu�u���b�N�E���[���A�v�A�����d�̂悤�ȁu�p���f�B�v������慎h�̗͂́A�����������ȍm��̗͂ł���B���ăX�E�B�t�g��{���e�[���́A慎h�̎�@�ɂ���Ď��Ȃ̏�������Љ��ɗ�ɔᔻ���A��������B����͓����̌��͎҂̓{��������A�ނ�̒���ɂ͐V�����Љ�ɂƂ��ĕK�v�Ȏ��Ȕے�ƐV���Ȏ���̌`������Ă����̂ł���B�䂦�ɁA��X�́A��Ɏ����𐳋`�ƍl���đ��҂������m�ł͂Ȃ��A���Ȃ������V���Ȓm���̂���������߂銊�m�����߂Ă����K�v������Ǝ��͍l����B
�@��N�͂��Ȃ�a�V�Ȏ������g���Ă������A���N�͋����قǓ���Ȃ��̂͂Ȃ��B�����`�͌��㕶�̖��ɂ悭�g���Ă������́B�����d�̖���͌c��r�e�b�ʼnߋ��Ɏg��ꂽ��ҁi�������Ђ��������j�̂��́B���������_���猩�Ă��A��{�I�ȓlj�͂Ǝv�l�́A���͍\���͂�₤���Ƃɏd�_���u����Ă���ƌ����悤�B
�@�ђB�v�́w�v�z�̉^���x�͂��Č��㕶�̕p�o���ł������B�����̂Ƃ���A���啶��ł͉ߋ��ɂ悭�g��ꂽ���͂���̏o�T���ڗ��B���e�͓���Ȃ����A�u���������ݐ����Ă���Љ�̖��Ƃ��đ����邱�Ƃ��ł��邩�v�Ƃ����_��₤���Ȃ̂ŁA���ӎ����Ȃ���I���W�i���e�B�[�̂��铚�Ă͏����Ȃ��B���A�ǂ̑�w���u�V��������̌����ɒE�炷��v���Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă��邪�A���������X���ɑ���ᔻ�I�ȈӐ}���ǂݎ���B�����ڐ�̐V����������ǂ��̂ł͂Ȃ��A��b�Ƃ��Ă̊w��I�ȗ͂�b���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@���N�͔�r�I�I�[�\�h�b�N�X�Ȗ��ɖ߂����ƌ�����B������V������w�@�������V�݂���āu�Ő�[�v�ɒ��S���ڂ��Ă��邪�A�����������Łu����̑S�̐��v��u��ʋ��{�v�ɖڂ�����������Ƃ��낪���O�炵���B��������Ƃ����lj�͂ʼnۑ蕶�̎咣�̖{�������ޕK�v������B
�@���j��@�n�x�̊i���̊g��
�@��w�̐i���̂������Ŏ������L�т����ʁA�������u�ɂ���ɂ̒��������������B
�@�y���X�g���C�J�͎����I�Ɍ���ꂽ�\�A�́u�̐����ϊv�v�ł͂Ȃ��A�����̎��R��`�I�����`�̈��͂ɋ��̐����ς��ꂸ�o�������u�����I�ȃV�X�e���v�ł���A�\�A����ɘA��������̂ł���ƒ��҂͍l���Ă���B
�@�I�E���^�����ɂ��u�n���S�T���������v�̂悤�ɁA�u�v�z�A�M���̎��R�v�Ƃ�������I�V�X�e������A�����`��ے肷��v�z�₻������H����e���s�ׂ����܂�邱�ƁB
�@������̕��S�̑���
�@���A�̏��F�Ȃ��ɃA�����J�ꍑ�����ŌR���s�����N�������ƁB
�@�����ɂ͎��{��`�w�c�ƎЉ��`�w�c���݂��ɑ�����u���v�ƌ��߂��đΗ��������A������A�����J�𒆐S�Ƃ����s��x�z�Ƃ���ɑR����C�X����������`�Ȃǂ̓_�I�Η��͍�������Ă��Ȃ��Ƃ������ƁB
�@��N�x���ݖⓖ��̉��������Ȃ��Ȃ�A�����₷���Ȃ����B���e�I�ɂ͋�̐��������āA����̍��ې����E���E�o�ς̊�{�I�ȗ�����₤���̂ƂȂ����B�Љ�n�̏��_��������Ă���Ηe�Ղɉł���B
�@�ꌩ��̓I�Ȗ��ł��邪�A���̋�̓I���Ⴉ����_�����ݎ��̂��������������Ȃ��B�u�l�Ԃ͂ǂ��܂ŃT�����v�Ȃǂ̖��ɂ��܂�[�����������Ă��܂��ƁA������v�z���痣��đ����̉Ȋw�_�c�ɂȂ��Ă��܂��������B���ۓI�ł͂Ȃ�����Ƃ����āA�����₷���Ƃ͌���Ȃ����̗�ł���B���̉�͂Q�O�O�T�N�́u�����������ʃZ�~�i�[�v�̓��e�����p���ď��������̂ł���B
���R���ۂ�ΏۂƂ����덷�@���͊ϑ��҂Ɗϑ������������ł��邪�A�P�g�����Љ�ۂɓK�p�����덷�@���͊ϑ��Ώۂł���l�Ԃ̑��l���������ƂȂ��Đ��܂��@���ł���B
�u�Љ�I���A���e�B�v�Ƃ́A��̓I�Ȍl����Ɨ����A���̍������l�ɊҌ��ł��Ȃ��Љ�I������Љ�I�ȗ͂��Ӗ�����B�P�g���̎Љ�I���A���e�B�́A���l�Ȍl�̌덷�E���Đ�������u���ϐl�v�Ƃ����C�f�A�I���݂ł���B����ɑ��ăf�����P�����l����Љ�I���A���e�B�́A���E��ƍ߂Ȃǂُ̈�Ȏ��Ԃ̑�����}���A���G�ő��l�ȎЉ�𐳏�ȏ�ԂɈ��肳����Љ�I�e���͂ł���B
�ǂ̌l�Ƃ���v���Ȃ��S�́E���ςƍl�����Ă������v���z�����āA�����W�c��̂̕���\�������B
�S���g���͂͂��߂���A�l�����Љ�̗͂�A�l�̐����⓹�������O������K������Љ�I�Ȃ���̂ɂ͊S���Ȃ������B
�@�����u���ρv�Ƃ������t�������A�܂��z�N����̂́u���ϓ_�v�Ɓu�����ӎ��v�ł���B����̎������Ɋւ��āu�N���X�̕��ϓ_�v���ׂ邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�A���ϓ_�̍����N���X�قǁu�w�͂������v�Ǝ��͍l���Ă����B�������A��������ς���Ε��ϓ_�ƃN���X�̏��ʂ��ς���Ă��邩��A���ϓ_�̍��Ƃ͎����́u�덷�v�ƌ����Ă��悢�B��N�A���ϓ_�ɑ傫�ȕϓ����Ȃ��ꍇ�A�u�w�́i�Ƃ������ϓI�ȗ́j�����肵�Ă���v�ƍl����̂̓f�����P���̔��z�ɋ߂��B�܂��A�l�X�̒����ӎ��́u�����͕��ϓI�Ȑ��������Ă���v�Ƃ������S���ɂȂ����Ă���B����́u���ϐl�v�𗝑z������P�g���̔��z�ł���B���������u�_���Ȃ镽�ρv��r�����̂��S���g���ł��邪�A�{���A�^����ꂽ�f�[�^�̒��ňʒu�Â����s����@�ł�����l���u���̖ڕW�v�ɂȂ��Ă�����{�Љ�ł́A�S���g���̈Ӑ}�ɔ����āu�������l�̗��z���v�������Ă���Ǝ��͍l����B
�@��N�x���ݖ₪���Ȃ��Ȃ�A�����₷���Ȃ����B���ɂ͂��Ȃ��݂̕��ϓ_����l�Ɋւ��镶�͂Ȃ̂ŁA���e�I�ɂ����g�݂₷���ƌ�����B
�@��N�Ɉ��������āu�l�ԂƂ͉����v�u�l�Ԃ͂ǂ�������ׂ����v�Ɋ֘A����o��ł���B���͂̐��i�i�W�������j���l�X�Ȃ̂ŁA�O�̎������狤�ʂ̖��_��ǂݎ��̂��������������Ȃ��B��͎�����`�I�Ȏ��Ԃ̑�������w�i�ɋc�_��W�J�����B�c�ƂȂ�v�z���Ȃ��Ə����Ȃ����A�ߋ������������q���g�͑����B
�@���m������o�ϓI�ł��邱�Ƃ��d�������̂́A�s�����d�����镐�m�ɂƂ��ďd�v�ȉ��l���u���v����������ł���B���́u���v�́A�ϗ��I�ȋK�͐��ƌ�����������B�ϗ��I�ȋK�͂ɍ��v���Ă��邩�ۂ��͐��_�I�ȉ��l�̖��ł����āA���̕����I�ȑ������v�ʂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�䂦�ɍs���́u���v�͔�o�ϓI�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�Ⴆ�A�v���싅�̃X�J�E�g���A�}�`���A�I��ɏ����̓��c�𖧖Č�����n�������Ƃ����ɂȂ��Ă���B�����v�����c�̌o�ϓI���v�̂��߂ɓ���̑I��ւ̋��K���^���������Ȃ�A��������Q���ł���͂��̃A�}�`���A�X�|�[�c�ɋ��K�I�i�������܂�A��������������B�A�}�`���A�X�|�[�c�͔�o�ϓI�ł��邩�炱���A�@��̕���������ȋ����ɂ���ĎQ���҂̐l�ԓI�������\�ɂȂ�̂ł���B���̂悤�ɁA��o�ϓI�ł��邱�Ƃ́A����ɂ����Ă����_�I�ȉ��l�Ƃ���Ɋ�Â����s���̋K�͂��d��������ʂő傫�ȈӋ`�����B
�@���t�̐E�Ƃ͕i���Ɨ썰�������A�l�i�̔��I������ړI�Ƃ�����̂ł���B���������Ă��̎d���͈�̐����I���l�z���邪�䂦�ɐ_���Ȑ�����тт�ƍl�����Ă���B
�@���m���ɂ��Ȃ�����V�̐��x�Ƃ́A�u���x�Ȑ�含�v�u���x�ȐE�Ɨϗ��v�ɑ���h�ӂƂ������_�I��V�ł���B����̊�Ƃł͎d���ɑ����V�����i�ƒ��グ�Ɍ��肳��A�d���̖ڕW��u���������v�͍������邱�Ƃɂ���ւ���Ă��܂��B���̏�ς��邽�߂ɂ́A�h�C�c�̃}�C�X�^�[���x�܂�u�e�����x�v�̂悤�ȃV�X�e�����K�v�ł���B����グ���тł͂Ȃ��A�ڋq�̕]���╔���̐M���A�{�����e�B�A�����ɂ��Љ�v�����Ȃǂł����ꂽ�Ј����u�Г��}�C�X�^�[�v�Ɏw������̂ł���B�����̒i�ʂ̂悤�ɁA�i�K���������i��݂��Ă��悢���낤�B�Г��}�C�X�^�[�ɋ��K�I��V�͕s�v�����A�o���ƌ��������ĎЈ��̑��k����ɂȂ�A��Ƃ̎Љ�I�ӔC�ɂ��Ĉӌ����q�ׂ�Ȃǂ̏d�v�Ȗ�ڂ�S���Ă��炤�B��]�҂ɂ͒�N����A�h�o�C�X���Ƃ��ďo�Ђ��Ă��炤�B���̐��x�ɂ���āA��Ƃ��Ј������m���I�ȍ������_�����ێ��ł���Ǝ��͍l����B
�@�W���I�Ȗ��B
�@��N�x���ݖ₪���Ȃ��Ȃ�A�����₷���Ȃ����B�ŋ߁A��V�ƋΖ����Ԃ�藣�����Ƃ���u�z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����v��c��̑�ʒ�N�ސE���傫�Șb��ƂȂ��Ă���̂ŁA�d����u���������v�ɂ��čl�������Ƃ̂�����Ȃ����Ȃ��B
�@����B
�@�ϗ��w�I�ȏ�_�ł���B�o��Ӑ}�Ƃ��ẮA�m����_���D��̌���Љ�𑊑Ή�����Ƃ����ۑ�B���ۓI�ȋc�_�ƌ����̐l�ԎЉ�̖����ǂ��֘A�Â��邩��������B�������A�R���s���[�^�Љ�Ɛl�Ԃ̖��Ƃ��Ă悭�o�肳�����e�ł����邩��A����Љ�̑傫�Ȗ������Ă����Ώ\���Ή��ł���B
�@����B
�@���j�̈Ӗ���₤����Ə��Љ�_���e�[�}�ɂ��������g�ݍ��킹�����ł���B��N�̖��Ɣ�ׂ�ƁA�]���̕��Ȉ�ނƎO�ނ̏��_����g�ݍ��킹���悤�ȍ\���ő�ޓI�ɂ͂킩��₷���B����̗��j�������́A�ǂ̒��x�܂ŏڂ����������邩�Ŏ��͖����ł��낤�B���̓_�ł��������i�荞�݂��ق��������B���i���瓯�l�̃��x���̓Ǐ������A��U�����f���ĉߋ���Ɏ��g�ޗ��K���K�v�ł���B
�y�X�V�E��ꕶ�w�z
����c��w