- 二本の線分は同じ長さです。
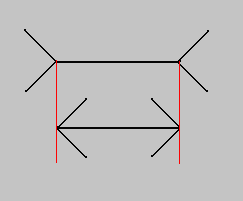
これは有名な「ミューラー・リヤーの錯視」です。線分の両側につく「羽」の長さ、角度などを変えて試してみて下さい。かなりの範囲で錯視が起こることがわかります。
- 遠近法の原理
なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。
それは「遠近法」とつながりがあると考えられています。下の図のように、私たちは先端が尖ったパターンの部分を自分に近く、先端が開いたパターンの部分を自分から遠く感じます。遠近法は、知覚のこの性質を利用した作図法です。
すると、中間の線分が同じ長さの場合、「実際の大きさ」は「遠くにあるもの」の方が大きいので、先端が開いたパターンの方を「長く」感じるのではないかと言われています。


写真はどちらも東京オペラシティ
- 二番目の図の直線がつながっているように見えましたか?
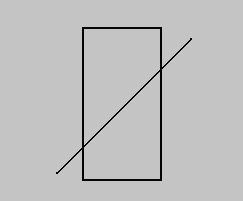
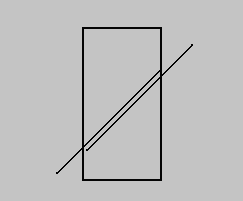
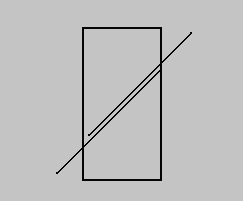
- 実は最初の図が正しかったのです。
これも、私たちの「こころの傾向」が生み出す錯視です。
私たちは「高いものはより高く、低いものはより低く」見ようとしているのです。長さ10mの線を地上に引いても、そう長くは見えません。しかし、長さ10mのポールを立てると、地上に置いた時よりもずっと「高く」見えます。天井の高い部屋が大変広く見えたり、背の高い家具、低い家具を使い分けることで、部屋の広さが変わるように見える「インテリアの常識」も、この原理に基づいています。演劇をする人なら、狭い劇場では「縦のセット」を組むことで、空間の広がりが出せることをご存知でしょう。(例えば、数年前、青山劇場で再演された『ラ・マンチャの男』のセットが、傾斜舞台の効果をうまく使っていました。)
このように、私たちは「上昇する線」をより強く知覚するので、実際につながる線より低い位置にある線を「連続するもの」と見てしまうのです。
- こころのパターン
これらは「計測できる知覚の事実」ですが、映像と関わる心の働きには、もっと深いものもあります。
心理学には絵画や模型を使って、その人の心の働きを知る技法があります。(ロールシャッハ、TAT、バウムテスト、箱庭療法など。)
例えば、バウムテスト(樹木画テスト)では、被験者に樹木の絵を描かせます。その際、絵の左側が「過去」、右側が「未来」、下側が「物質」、上側が「精神」のように、「解釈」が行なわれるのです。ここでは、図形のパターンが、人間精神の基本的な構造と深く結びついているのを知ることができます。舞台でドラマがどちら側から進行するか、教会や寺院はなぜ山の上に建てるのか、など、芸術表現の「からくり」も、ここから生まれているのです。