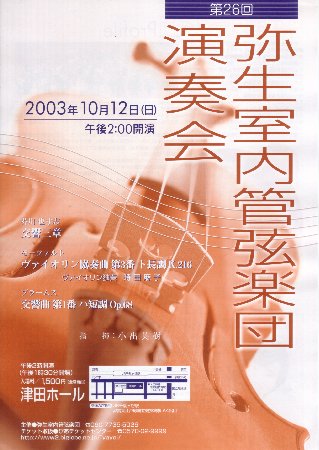
|
ブラームス:交響曲第1番ハ短調 作品68
(第1楽章)
時は日本でいえば明治初期の1876年、所はドイツの「ブラームス商会」の会議室。社長のブラームス氏は机の代わりのティンパニーを6/8拍子で強打しながら、激怒している。「諸君、わが社は未だに交響曲の1曲も市場に出せないのか! 商売がたきの『ワーグナー物産』の躍進ぶりを見たまえ。半音階などの新技術を投入して、『トリスタンとイゾルデ』のような新製品を既に開発しているではないか! わが社も半音階を駆使して新しい交響曲を開発するのだ!」
(第2楽章〜第3楽章)
会議の後。昼休み、社員食堂での会話。
社員A:うちの社長、会議で激怒してたわりにはのんびりかまえてるな。
2楽章にヴァイオリンのソロなんか書いたりして。3楽章も社長の好きなべ一トーヴェンみたいにするんだったら、もっと速いスケルツォなんだけどなあ。それに、何であんなややこしいことばかりするんだろう? 2楽章と3楽章では変な調に転調するし・・・
社員B:それはな、1楽章がハ短調だろ、長3度ずつ上がって2楽章がホ長調、3楽章が変イ長調、4楽章が八長調になる。「ハ→ホ→変イ→ハ」と一回りして元に戻るという凝った仕掛けなんだよ。
社員A:だけど、余程のマニアでもない限り聴いていてもわからないぜ。リズムだって時々何拍子かわからなくなるし・・・
社員B:そういうところが社長の芸の細かいところで、わが社の誇る新技術なんだよ。「ワーグナー物産」の連中には簡単に真似できないようにしてあるのさ。
(第4楽章)
再び会議室。新製品開発会議において。
社長:諸君、私はわが社の新製品にふさわしいメロディーを開発した。聴きたまえ。「ソードーシドラーソ、ドレーミレミードーレー・・・」
社員A:社長、なんかベートーヴェンの第9に似ていませんか?
社長:そんなことはどうでもいいのだ。これをわが社の新技術で展開して新しい交響曲の終楽章にするのだ。ついでにホルンのソロやトロンボーンのコラールもくっつけて、華々しく終わるようにしたまえ。営業部長のハンス・フォン・ビューロー君、この曲の宣伝に何か良い考えはないかね?
ビューロー:「ベートーヴェンの交響曲第10番」というキャッチコピーで売り込んではいかがでしょうか?
社長:ううむ、ちょっと気恥ずかしいがまあいいだろう。よろしく頼むよ。
以後、ブラームス商会は交響曲の業界で成功を収め、大躍進したことはいうまでもない。
(雑談コーナー)
「ワーグナー物産」の社長?はリヒャルト・ワーグナー。当時のドイツ楽界は「ワーグナー派」と「ブラームス派」に分かれていた。ブラームスはワーグナーの作品も随分研究したらしいが、実際にそれに対抗しようとしたかどうかは定かでない。ハンス・フォン・ビューローは当時有名な指揮者で、ブラームスの作品を広めるのに尽力したが、もともとはワーグナーの弟子。ブラームスに傾倒するのは実際はもっと後のことであるが、この曲を「ベートーヴェンの第10」と言い出したのは彼である。
|

















