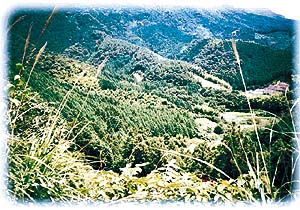
の山道は夏場になると草むす所もあった。ガイドブ
ックを見ると、鎌を持参し、後の遍路のために道を
整えて進むのがエチケットなのだそうだが、鎌も持
っていなかったので、金剛杖で草や虫を払いながら
、進んだ。半そででは危険という話も、山道を進ん
ではじめて分かった。
愛媛編(上)41番札所龍光寺から45番岩屋寺まで |
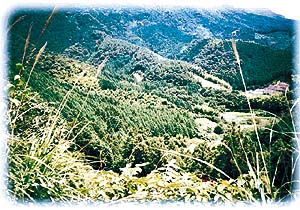 |
|
ほとんどの遍路道は整備されているが、峠越えなど の山道は夏場になると草むす所もあった。ガイドブ ックを見ると、鎌を持参し、後の遍路のために道を 整えて進むのがエチケットなのだそうだが、鎌も持 っていなかったので、金剛杖で草や虫を払いながら 、進んだ。半そででは危険という話も、山道を進ん ではじめて分かった。 |
今日はまだぜんぜん歩いていないのに、お接待を受けていいんだろうか、と思いながらも「この暑いのにお参りしようってだけでも大したもんです。その気持ちがすばらしいことだねえ」と何度も言われてスイカをいただく。こういう旅をしていると果物を食べることがないもんだから、大変うれしい。
結構な量だったが、お接待を受けたものは全部いただかないといけないそうで、何とか食べ終えた。このお婆さんも農協のツアーで何度も八十八カ所を参っておられるそうだ。だから、お接待の嬉しさを知っているんだろう。食べ終えて、さてという時に「ここから先は山越えで、食べるところは何もないし、おむすび作ったから持っていって。梅干しいれといたから」というのである。プラスチックの透明の箱の中におむすびが二個。きな粉がまぶしてある。「いやー、そんなにしてもらっちゃ」と言ったが、ありがたくいただく。バスに乗る予定だったが「山越えしないわけにはいかないな」。お婆さんを何度も拝んで出発する。ありがたいことだ。
四十二番を参拝して四十三番まで、歯長峠(五三八メートル)越えの山道を登ることにした。確かに食べるところも自販機も何もない道程。午後のまぶしい太陽を受けながら約三時間かけて登った。下りきったところの東屋で、いただいたおむすびをいただく。「うまい」。
四十三番から約三キロ歩いて午後四時すぎ、JR卯の町駅へ。特急宇和海に乗って約一時間、一気に松山へ向かう。
 |
|
道後温泉本館 |
この日は山を降りてから見つけたが、山道を延々登った末、山頂付近の車道に出ると自販機があって、時折りエビアン水(フランス産ミネラルウォーター、二七〇ミリリットル、瓶入り、百二十円)を見かけるのだった。ついつい飲んでしまうのだが、やっぱり、うーん、と考え込んでしまった。日本の、水がきれいと評判の高い四国の山を登って、山頂で飲むのは、フランスのナントカ水源の水だ。船に乗ってくるのか、飛行機で飛んでくるのか知らないが、でたらめだ。コカコーラでも、たぶん理屈は同じなのだろうが、エビアンを売っているのを見ると、そのでたらめさ加減というものが象徴的によくわかる。
日本中の水をだめにして、フランスの水を飲もうという選択。そのコストに対する意識。決して日本人の本意ではないはずだが、そうならざるを得ない現実。政治だか経済だかの仕組みで、そうなっているのだが、じゃ、われわれの意識ってどこでどうやって働いているんだろうか。
山から流れる冷たい水をすくって飲めれば、それでいいという思いがあって、割と最近までそうだった。だけど産廃の処分場がないから、飲み水が多少危険になってもダムから離れていたら処分場を作ってもいいよ、ということになってる。
「山にのぼって水を飲む人は少数だから、フランスから船で運んだらいい。缶ジュースと同じ値段なら売れる」と、どこかで誰かが言っているのだろう。水の安全をフランスに金を出して買う。ばかばかしいというか、情ないというか。ことほど左様に日本の高度成長は、山川草木を犠牲にしながら達成されたということだ。鶴が自分の羽を抜いて機を織っていたわけで、決して覗いてはいけないといわれていた現場を覗く時、日本の経済成長の夢は覚めることになる。そして決して帰ってこない鶴の羽の美しさに嘆息することになる。
国家とは山川草木である、と司馬遼太郎が書いていた。新聞は今まで誰のために何を書いてきたのだろうという反省がある。
さて、参拝を終えて道後温泉に向かい、宿を探す。せっかく道後温泉に来たので、有名な道後温泉本館に入浴。風情があるといえばあるが、風呂は風呂。明治二十七年の建築で木造三階建て。重文とはいえ、どうも締め切った部屋でじとっと湯舟に漬かるのは、解放感がない。風呂の楽しみは解放感だという気がした。
| 前へ | 次へ |