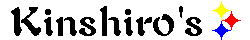
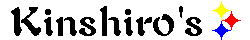
アメリカ北東部の静かな地方都市、ピッツバーグ。日本では、中学校の授業で「鉄鋼の 町」として習う程度で、あまりなじみのない町であろう。こんな鉄鋼の町の自慢がピッツ バーグ・スティーラーズ、NFL(アメリカンフットボールのプロリーグ)の人気チーム のひとつである。スティーラーズ(鉄の男たち)という名前は、もちろんこの町の鉄鋼産 業にちなんでつけられた名前だ。
このスティーラーズ、1970年代には、名将チャック・ノールの下で黄金時代を迎え、 4度にわたってスーパーボウルに出場、全て優勝という快挙を成し遂げている。その当時、 チームを支えたのは、「鉄のカーテン」の異名をとる強力ディフェンス陣と、オールスタ ークラスの選手が目白押しのオフェンス陣であった。しかし、その黄金時代を支えた選手 たちが去った80年代は、長い低迷の時期となる。そしてついに91年のシーズン終了後、 ノールはチーム再建の夢を果たせぬまま、23年間率いてきたチームを去ることになる。 そして翌92年1月21日、ノールの後任として、弱冠34歳のビル・カウアーがステ ィーラーズの新ヘッドコーチ(監督)に指名された。
年齢的には若いカウアーであるが、すでに8年間のコーチ経験を積んでいる。特に、そ の最後の3年間は、カンザスシティ・チーフスでディフェンシブ・コーディネータを務め、 強力なディフェンスをつくりあげた実績を持つ。
ディフェンシブ・コーディネータというのは、守備全般の責任を負うコーチであり、各 ポジション別のコーチ陣を統括する立場にある。チーフス時代の3年間、彼が指導したデ ィフェンスは、NFL28チーム中、常に5位以内のトップクラスの守備力を誇り、彼の 手腕は高く評価された。そういった実績から、彼は自分の生まれ育った地元のチーム、ピ ッツバーグ・スティーラーズにヘッドコーチとして迎えられたのである。
24年ぶりにヘッドコーチが交替したスティーラーズが、そのカウアーの指揮の下で戦 う最初の試合、92年の開幕戦の対戦相手は、同じAFC中地区のヒューストン・オイラ ーズである。オイラーズは地区優勝候補にあげられる強豪であり、しかもその本拠地ヒュ ーストンでの試合ということで、ルーキー・ヘッドコーチのカウアーにとっては、初戦か ら大きな試練である。
そして予想通り、オイラーズは試合開始早々から地元ファンの声援に応えて快調な滑り 出しをみせた。いきなり14対0とスティーラーズをリードしたのだ。一方のスティーラ ーズは、せっかく得た攻撃権も生かすことができず、第4ダウンの攻撃を迎える。アメリ カン・フットボールでは、攻撃側のチームが4回以内の攻撃(ダウン)で10ヤード前進す ることができれば、続けて新たな攻撃権を得ることができる。しかし、それに失敗すれば、 攻撃権は相手側へ移ってしまう。したがって、もし第3ダウンまでに、その10ヤードを進 めなかった場合には、あと1回の攻撃に失敗すると、その位置から相手側の攻撃が始まる ことになる。
そこで通常、第4ダウンでは、パントキックによってボールを前方へ蹴り込み、相手に 攻撃権を渡すかわりに40ヤード程度、相手を押し戻す作戦をとることになる。もちろん、 状況によっては「ギャンブル」といって、第4ダウンの攻撃を強行する場合もある。たと えば、第4ダウンで10センチ進めば良いといった状況であれば、成功する確率が高いので 強行する場合も多い。あるいは、ゲーム終盤で残り時間が少なく、しかも僅差で負けてい るような場合には、相手に攻撃権を渡してしまうと、そのまま時間を消費されてゲームセ ットを迎えてしまうことになる可能性が高いため、パントを蹴らずにギャンブルをするこ ともある。
しかし、このオイラーズ戦の場面は、まだゲーム序盤でもあり、当然ギャンブルをする 状況ではない。パントを蹴って相手に攻撃権を渡すのが定石である。その定石通り、ステ ィーラーズは攻撃陣に代わって、パントキック用のスペシャル・チームと呼ばれる部隊を グランドに登場させた。
アメリカン・フットボールでは、選手の分業制が確立されており、攻撃ユニット、守備 ユニットと呼ばれる部隊が交代でプレイする仕組みになっている。さらに、キックオフや パントの時には、スペシャル・チームと呼ばれる特別なユニットが編成され、プレイする ことになる。
したがって、この場面でスペシャル・チームが登場してきたということは、パントを蹴 ることを意味する。せっかく得た攻撃権を生かしきれず、また相手に攻撃権が渡ってしま うのである。
やはり「今年も苦しいシーズンを迎えるのか」とスティーラーズ・ファンは憂うつな気 分になっていたことであろう。ところがここで、そんな気分を一掃するような、思わぬビ ッグプレイが飛び出すのである。
通常のパントのフォーメーションから、パンターのマーク・ロイヤルズにボールがスナ ップされる。ここで彼は、パントを蹴ると見せかけて、なんと味方へパスを投げたのであ る。意表をついたパスは見事に決まり、一気にボールを敵陣1ヤードの地点まで持ち込む ことに成功する。50ヤードを越えるビッグゲインだ。
もしこのプレイが失敗に終わっていたならば、一方的にオイラーズペースの試合となる 危険性をはらんだプレイであった。しかし、14点と大きなリードを許した状況を考えれ ば、試合の流れを一気に取り戻すようなビッグプレイが必要な場面であったとも言える。 おそらく、キャンプ中のスペシャル・チームの練習では、シーズン中に1度使う機会が あるかどうかという、このフェイクパント・プレイを練習していたのであろうが、そのプ レイをいきなり開幕戦の序盤で使い、しかも見事に成功させるあたり、このルーキー・コ ーチ、なかなかやるじゃないか、とスティーラーズ・ファンに印象付けたプレイであった。 また、そのカウアーの期待に応えた選手たちも素晴らしかった。このプレイで勢いに乗 った選手たちは、完全にリズムに乗り、ついに試合を逆転することに成功する。結局29 対24でこの試合をものにするのである。この大逆転勝利、偶然に奇策が的中しただけの マグレでないことは、次週以降の試合結果が証明した。開幕3連勝という最高のスタート を切り、7試合終了時点で5勝2敗と快調だ。そして、次の第8戦で再びライバルのオイ ラーズとの対戦を迎える。今度は地元ピッツバーグのスリーリバーズ・スタジアムでの対 決だ。
ここまで両チームの成績は、ともに5勝2敗とまったくの同率で、AFC中地区の首位 に並んでいる。勝って1ゲーム差をつけるか、負けて一歩後退するのか、両チームにとっ て非常に大きな一戦である。
この試合、スティーラーズがリードする展開となったものの、第3クオーターには、ス ティーラーズのミスも絡んで、わずか1分の間に、たて続けに2つのタッチダウンを許し、 7対20と一気に引き離されてしまう。しかし、開幕戦でも14点差を逆転しているステ ィーラーズはあきらめる様子など微塵もなく、第4クオーターには再びペースをとりもど す。ふたつのタッチダウンを奪い、ついに21対20と再逆転に成功する。 しかし、逆転したといっても得点差はわずかに1点。同率首位に並ぶ両チームの対戦だ けに、オイラーズもここで簡単に引き下がるわけにはいかない。試合時間は、まだ4分残 っている。十分に逆転可能な時間である。
ここでオイラーズの攻撃は、自陣14ヤード地点からスタートし、約4分の間に64ヤ ードをゲイン、スティーラーズ陣内の22ヤード地点までボールを進めた。この場面で、 残された時間は6秒。あと1プレイ分の時間である。オイラーズとしては、フィールドゴ ールの3点で逆転できるわけであるから、当然最後のプレイは、フィールドゴール狙いで ある。キッカーが蹴る地点からゴールポストまでは、約39ヤードとなる。
距離的には決して難しい位置ではないが、この大事な場面、キッカーは相当に緊張する はずである。しかも、6万人近い大観衆がキッカーめがけて大声でプレッシャーをかける のである。さらに、この日は風があり、キッカーとしては気になるコンディションである。 大観衆のボルテージはますます上がり、異様な雰囲気となる中、キッカーのデル・グレコ は心を落ち着けて、呼吸を整える。さあ、いよいよ運命のキックだ。
と、その時、なんとカウアーはタイムアウトをコールする。ここは、わざわざタイムア ウトをとって、選手たちに作戦を指示するような場面でもなく、意表をついたコールであ った。
実は、このタイムアウトは、キッカーに対して、さらにプレッシャーをかけようという 作戦なのである。せっかくキッカーが蹴ることに集中し、耳をつんざく大観衆の声もシャ ットアウトし、「いざ」という瞬間に「待った」をかけた格好だ。
この仕切り直しでキッカーのグレコが、「ここで外したら地区優勝が遠のく」などと余 計なことを考えたかどうかは、本人以外知り得ないことであるが、結果はフィールドゴー ル失敗。スティーラーズはきわどい勝利を手にしたわけだ。
大観衆のサポートとカウアーの心理作戦の勝利と言っても良いだろう。結局このシーズ ンは、その後もスティーラーズの快進撃が続き、11勝5敗の好成績でAFC中地区の地 区優勝を勝ちとり、久々のプレイオフ進出を決めた。
スティーラーズが地区優勝したのは実に8年ぶりのことであった。さらに、地元のスリ ーリバーズ・スタジアムでプレイオフが行われるのは、10年ぶりのことである。当然、 ファンの盛り上がりも想像以上のものとなり、プレイオフ・チケットの売り出しには、多 くの徹夜組も出た。1月のピッツバーグといえば、最高気温が氷点下ということも珍しく ない。そんな寒空の下、多くのファンたちが焚き火を囲み、ビールを片手に、久々のビッ グゲームの話題で一晩中おおいに盛り上がりをみせた。
夜があけるとさらに多くのファンが詰めかけ、長蛇の列は午後まで絶えることがなかっ た。チケットが買えるまで、何時間も待たされるわけであるが、文句を言うファンはひと りもいない。むしろ、この10年ぶりのイベントを楽しんでいるようでもあった。
球場横のハイウェイを通る車などは、このスティーラーズファンの列を見つけるや、ク ラクションを鳴らし、車の助手席から身を乗り出して手を振り、エールを送ってくるので ある。このあたりのファンの一体感などは、いかにもアメリカらしいところである。
この年、スティーラーズはAFC中地区の優勝を飾ってプレイオフに進出したわけだが、 プレイオフには、3地区の各優勝チームに加えて、さらに3地区の2位以下のチームの中 から成績上位の3チームをワイルドカードとして加えて、合計6チームが参加し、スーパ ーボウル出場をかけて戦う。
プレイオフに出場した各チームには、1位から6位までの仮の順位がつけられる。地区 優勝した3チームは成績順に第1シードから第3シードとなる。同様にワイルドカードの 3チームも成績順に第4シードから第6シードという順位が割り振られる。プレイオフの 最初の週は、第1/第2シードのチームは試合がなく、第3シード対第6シード、第4シ ード対第5シードの試合が行われる。そして、それぞれの勝者が翌週、第1/第2シード のチームに挑戦する。
この年のスティーラーズは、AFC1位の成績であったため第1シードとなり、プレイ オフの第1週は休むことができる上、翌週以降の試合をすべてホームゲームとして行える という有利な状況となった。というのは、プレイオフの試合は、上位シードのチームの本 拠地で行われることになっているためである。第1シードになったということは、どのチ ームが勝ち上がってきても、地元で迎え撃つことになるのだ。いわゆる「ホームフィール ドアドバンテージ」を手にしたのである。
アメリカンフットボールでは、観客は「12人目の選手」と言われることがあるように、 グランドでプレイする11人の選手にとって、観客の声援は大きな味方となる。この意味 からも、地元でのゲームというのは非常に有利なのである。また、南の方の暖かい地方の チームやドーム球場を本拠地としているチームにとっては、北部の寒い地方の球場での試 合は、慣れないコンディションということで不利に作用する場合も少なくない。こういっ た意味からも、ホームフィールドで試合ができるかどうかということは、試合の結果を左 右する重要な要素なのである。
もっとも、この年のプレイオフでピッツバーグに乗り込んできたのは、ピッツバーグよ りもさらに北に本拠地を置くバッファロー・ビルズであるから、寒さの面では慣れている チーム同士ということになる。
このビルズ、スティーラーズへの挑戦権をかけたプレイオフ第1週の試合で、ヒュース トン・オイラーズを破って勝ちあがってきたのだが、その試合は歴史に残る壮絶な戦いと なった。
試合開始早々から、オイラーズの攻撃が冴えわたり、次々と得点を重ねてビルズを圧倒 していった。前半を終えて28対3の大差だ。さらに第3クオーター早々には、「ダメ押 し」ともいえるタッチダウンを奪い、35対3と点差をさらに拡げた。
70年を越える長いNFLの歴史の中でも、32点差をひっくり返したという例はない。 したがって、この時点でオイラーズの勝利は間違いないものと誰もが思ったはずである。 この試合の様子は、テレビで全国中継されていたわけだが、さすがにこの点差をみて、オ イラーズファン以外の多くのフットボールファンは、テレビを消すなり、チャンネルを変 えるなりしてしまったのではないだろうか。そのために、この後に起こる「世紀の大逆転 劇」を見逃したファンも多かった筈だ。
ビルズは、この大差で開き直りを見せ、突如として爆発的な攻撃を見せるのである。完 全に浮き足立ったオイラーズから、続けざまに5個のタッチダウンを奪い、38対35と 大逆転に成功するのだ。どんなスポーツでも、数多くの試合の中には、とても信じられな いようなプレイが起こったり、予想もしない試合展開となることはあるものだが、このゲ ームがまさにその典型であった。
終盤オイラーズも3点を返し、38対38の同点となり、サドンデスの延長戦に突入し たものの、結局ビルズの勢いは止められず、延長3分6秒、フィールドゴールで41対3 8とし、ビルズが大乱戦を制したのだ。
この勢いにのるビルズを迎えるスリーリバーズ・スタジアムは、大観衆で埋め尽くされ た。この日の観客動員数は6万を越え、球団史上最高を記録したというニュースが電光版 に表示されると、観客たちは一斉に「テリブルタオル」と呼ばれる黄色いタオルを振り回 して大騒ぎをする。このタオルがスタジアムを埋めるのは、実に10年ぶりの出来事なの だ。
と、いうのは、この奇跡を呼ぶと言われるありがたいタオルは、レギュラーシーズンの 試合では使わずに、プレイオフとスーパーボウルの応援のときにのみ登場させるという「し きたり」になっているのである。スティーラーズが地元でプレイオフを戦うのは実に10年 ぶりということで、このタオルも10年ぶりに日の目をみることになったのだ。
このタオルを「発明」したのは、地元放送局WTAEのスポーツコメンテーター、マイ ロン・コープという名物男である。彼は、スティーラーズが75年にプレイオフ出場を決 めた時、放送局内から「プレイオフの試合で、ファンが一丸となって応援できるアイテム をつくらないか」と話をもちかけられ、考案したものだと言われている。
このタオルによる応援の威力か、次々にスーパーボウルを勝ちとったため、プレイオフ 試合の応援には欠かせないものとして定着したのだ。しかし、80年代に入るとチームは 低迷し、この10年間、スタンドが黄色に染まる光景はみられなかった。70年代を知る ファンは、この久々のテリブルタオルの波をみてスティーラーズの復活を実感したことで あろう。一方、若い世代のファンは、初めて見る光景に興奮しながら試合開始を待つので あった。
さて肝心の試合の方であるが、スティーラーズがフィールドゴールで先制したものの、 第2クオーターにはビルズに逆転され、試合の主導権を奪われる。そして、その後はビル ズが一方的に攻める展開となり、結局、24対3で完敗だ。
地元のファンにとって、負けたのはたしかに残念であるが、カウアー新ヘッドコーチの 下で、クオーターバックのオドネルや、ランニングバックのフォスターなど、著しい成長 を遂げた選手たちのことを考えれば、ある程度は満足のいくシーズンであり、翌年以降に 大いに期待が持てるシーズンであった。
翌93年もスティーラーズは、ワイルドカードながらプレイオフ進出を決め、カンザス シティ・チーフスと対戦することになった。チーフスはこの年、サンフランシスコ49e rsから移籍して話題となったスーパースター・クオーターバックのジョー・モンタナを 中心としたチームである。
試合は、スティーラーズが主導権を握り、優勢にゲームを進めていった。第4クオータ ー、残り4分11秒にオドネルからグリーンへのタッチダウンパスが決まり、24対17 とリードした時には、なんとか逃げ切れるかという期待も膨らんだ。
ところが、残り2分30秒というところでスティーラーズに大きなミスが出る。自陣40 ヤード地点から、パントキックの場面であった。普通にパントを成功させていれば、チ ーフス陣の深い位置から相手の攻撃となり、2分強で20ヤード進まなければならない状 況となる。チーフスにとっては、いわゆる「モンタナマジック」にわずかな期待をかける 苦しい状況に追い込まれるはずであった。しかし実際は、パントで蹴ったボールをチーフ ス側にブロックされてしまうのである。そして叩き落とされたボールは、チーフスのジョ ーンズが確保し、スティーラーズ陣9ヤード地点まで進められてしまったのだ。
チーフスは、4回の攻撃でこの9ヤードを進んでタッチダウンにつなげれば、同点に追 いつくことができる。ここで、チーフスは2回にわたってマーカス・アレンにボールを持 たせて走らせるが、スティーラーズ・ディフェンスは、なんとかこれを合計2ヤードのゲ インに抑える。さらに、第3ダウンの攻撃でパスが失敗に終わり、いよいよ第4ダウンで 7ヤードという状況だ。このワン・プレイを守りきれば、スティーラーズの勝利が見えて くるところであったが、さすがはモンタナ。冷静にタッチダウンパスを決め、ついに24対 24の同点としたのである。その後延長戦に突入し、チーフスがフィールド・ゴー ルを決めて、27対24で、惜しくもスティーラーズは敗退する。
絶対に成功させなければならないパントを失敗したことが、大事な試合での敗戦につな がってしまった。この年は、シーズン中にもパント時のスペシャル・チームのミスが目立 っていたのだが、そのスペシャル・チームが大事な場面で、またまた大失態を演じてしま ったのである。このスペシャル・チームを担当していたコーチは、その2日後にはクビを 言い渡された。NFLでは、このようにひとつの重大なミスによって、即刻解雇されると いうことも珍しくないのだ。
逆に、もしチームに対して明らかな貢献が認められるような場合には、例えば他チーム から極めて良い条件でのオファーがきたり、チーム内での昇格の機会が得られるなど、ま さに信賞必罰の世界なのである。
日本のプロ野球などでは、監督の人選には選手時代の成績がひとつの重要な要素となる。 例えば1軍で2、3年しかプレイできなかったような選手が監督にまでなるといったこと は、まず考えられない。しかし、NFLでは選手としての実績とは別に、コーチとしての 手腕が認められれば、ヘッドコーチも夢ではないのである。また、大学チームのコーチか らプロのコーチになるなど双方向の交流もさかんで、競争は非常に激しい。こういった仕 組みが、プロのレベルをさらに引き上げる要因となっているのだ。日本でも、例えば甲子 園で優勝した高校野球チームの監督がプロの監督になるということがあっても、面白いの かもしれない。
翌94年のシーズン、スティーラーズは、スペシャル・チームの後任コーチとして、 ボビー・エイプリルを迎え、スペシャル・チームを立て直す。そして、カウアーは、再び スティーラーズを地区優勝に導いた。しかも、3地区の中でトップの成績を収めて第1シ ードとなったため、プレイオフの第1週はパス、翌週にクリーブランド・ブラウンズとの 対戦となった。好調のスティーラーズは、29対9とブラウンズをあっさり破り、スーパ ーボウル出場をかけたAFCチャンピオンシップ・ゲームへと駒を進めた。まさに三度目 の正直という言葉通り、カウアーヘッドコーチは、3年目にして初めてプレイオフ・ゲー ムでの勝利を手にしたのだった。
チャンピオンシップ・ゲームの対戦相手はサンディエゴ・チャージャーズ。試合前の予 想では、スティーラーズが有利という声が圧倒的であった。その予想通り、試合は完全に スティーラーズのペースでスタートした。ディフェンス陣が鉄壁の守りを見せ、サンディ エゴの攻撃を寄せつけない。第3クオーター途中まで13対3と一方的にリードする展開 となる。得点差は10点であるが、内容的には、それ以上の大差を感じる試合内容であった。 ところが第3クオーターのサンディエゴの攻撃で、一発狙いのロングパスが見事に成功 し、タッチダウンを許してしまう。この43ヤードのパス成功で、得点は13対10とな り、俄然緊迫感を帯びた試合展開に変わってくる。
それでも、この「一発」を除けば完全にスティーラーズがゲームを支配してきた訳で、 慌てる必要はないのだが、このあたりから次第に試合は膠着状態となり、両者得点を挙げ られないまま第4クオーターに突入する。そして、試合時間も残り5分あまりとなったと ころで、またしても一発勝負に出たサンディエゴの作戦が功を奏する。先ほどと全く同じ 43ヤードのロングパスが、またまた成功してしまったのだ。13対17、4点差であ る。
しかしながら試合時間は残り5分以上残っている。あきらめる必要はまったくない。こ こでスティーラーズの攻撃陣がようやく目を覚ましたのか、猛反撃を開始する。自陣17 ヤードというポジションからスタートした攻撃は、クオーターバック・オドネルが7回の パスを連続して決めるという離れ業を見せて、あっという間に敵陣10ヤード以内まで突き 進む。ここで残り時間は2分。この勢いならば、再び逆転することも十分に可能だ。
しかし、サンディエゴの守備陣も、ここを守り抜けばチーム史上初のスーパーボウル出 場が決まるとあって、粘りを見せる。スティーラーズの3度の攻撃をなんとか凌ぎ、ゴー ル前3ヤードの地点で、スティーラーズの第4ダウンの攻撃となる。この攻撃で3ヤード 進めなければ、スティーラーズは攻撃権を失い、同時にこの試合も落とすことになる。
この場面でのプレイは、ランニングバックのフォスターへのパスであった。しかし、そ のパスはフォスターの手に届かず、パス不成功。この瞬間にスティーラーズのスーパーボ ウル出場は夢と消えてしまったのだ。あとたった3ヤードでスーパーボウル出場というと ころまで来ていながら、その3ヤードが遠かった。試合内容では完全に勝っていたのだが、 勝負には負けてしまった。選手もファンもこんなに悔しい負け方はない。
その悔しさを忘れないために、翌95年のシーズンは、「THREE MORE Y ARDS(あと3ヤード)」を合言葉に、スーパーボウルへの再挑戦をかけた戦いを開始 した。自分たちは、スーパーボウル出場まであとたった3ヤードの距離にいるのだ、今年 こそ、その先へ進むぞ、という意気込みである。
カウアー・ヘッドコーチの4年目となる95年のシーズン開幕戦、今年こそスーパーボ ウル出場だ、というファンの願いを打ち砕くようなアクシデントがスティーラーズを襲っ た。
コーナーバックのロッド・ウッドソンが人工芝に足を取られて膝の靱帯を断裂、さらに クオーターバックのオドネルが、ボールを投げる右手の指を骨折するという大きな怪我を してしまうのである。ウッドソンは、シーズン中の復帰は絶望、オドネルも4週間程度は 出場できないという診断であった。
特に、守りの中心選手であるウッドソンの怪我は、非常に大きな痛手であった。かつて 93年に、NFLの75周年を記念して「オールタイム・オールスターチーム」というも のが発表されたことがあるのだが、彼はその時、オールスター・コーナーバックに選ばれ ているのである。この企画は、75年間の長いプロフットボールの歴史の中で、各ポジシ ョンの最高のプレーヤーを集めたらどんなチームができるか、という非常に興味深い企画 であった。
その93年当時、現役の選手でこのメンバに選ばれたのは、クオーターバックのジョ ー・モンタナやワイドレシーバーのジェリー・ライスなど、ごくわずかなスーパースター だけである。彼はそんな大選手のひとりとして選ばれたのである。
現役の選手がこのチームに選ばれることがどのくらい大変なことなのか、日本のプロ野 球にたとえて考えてみると、わかりやすいかもしれない。
日本のプロ野球も60年を越える長い歴史があり、数々の名選手を輩出している。たと えば投手部門では、伝説のエース沢村や400勝投手の金田、さらに米田、稲尾、村山、 江夏、山田と大投手が目白押しで、仮に投手部門から5人が選ばれるとしても、残念なが ら現役の斎藤や桑田、あるいは大リーグで活躍中の野茂などが、これらの大投手たちを押 しのけてNO1投手に選ばれるのは、なかなか難しそうである。
他のポジションにしても、捕手では野村や田淵、内野では、川上、中西、吉田から王、 長嶋など枚挙にいとまがない。さらに外野手では、1000盗塁の福本、3000本安打 の張本をはじめ大下、門田など、大選手がずらり並ぶことになる。
こうやって候補をあげていくと、各ポジションについて2人ずつ選んだとしても、古田 や清原などの現役トップクラスのプレイヤーといえども、このオールスター・ナインに選 ばれるのは、相当困難であることがわかる。
今の現役選手で選ばれるとすれば、落合とイチローくらいであるかもしれない。もちろ ん、技術的レベルや体力的レベルは、ここ何十年の間に大きく進歩しているのであるから、 こういったオールスターの選考はナンセンスであるのかもしれない。しかし、あえてその ような選考をするとなると、やはり伝説の名選手の方がどうしても有利になるのは仕方の ないことである。そのような、現役不利の状況を考えると、現役で選ばれた選手たちは、 いかに素晴らしい実力の持ち主であるかということがうかがえる。ウッドソンが歴代最高 のコーナーバックのひとりに指名されたということは、それほどの快挙なのである。
したがって、こんな大選手を欠いたまま今シーズンを乗り切らねばならないということ は、どれほど大きなピンチであるのか、容易に想像されるというものだ。オリックスにイ チロー抜きでペナントレースを勝ち抜けと言っているようなものである。オドネルの怪我 とあわせて、オープニング・ゲームの勝利に喜ぶどころではない、不安の幕開けとなって しまった。
そしてやはり、その不安は的中した。翌週のオイラーズ戦こそ34対17と大勝したも のの、続くマイアミ・ドルフィンズ戦では10対23と完敗。ドルフィンズのディフェン スに完全に押さえ込まれた形となってしまった。この試合はマンデーナイト・ゲーム、つ まり、この週に行われる試合の中で、ただ1ゲームだけ月曜の夜、ゴールデンタイムに全 国放送される好カードである。カウアーがヘッドコーチに就任してから、マンデーナイト ゲームは6戦全勝と勝負強いところを見せていたのだが、やはり怪我をした選手の穴が大 きかったようだ。
さらに翌週のミネソタ・バイキングス戦では、ツキにまで見放されてしまう。6対10 と4点差を追いかける展開となった前半の終了間際、ミネソタはフィールド・ゴールで3 点を狙うが、これが外れたため、そのまま4点差で前半戦が終了となるはずであった。
ところが、このフィールド・ゴールを狙うプレイで、審判はスティーラーズが12人の 選手をグラウンドに送っていたと指摘、この反則でミネソタがフィールド・ゴールに再挑 戦することになり、今度はきっちりと決めて、7点差で前半終了となった。
しかしこの時、実際には、グラウンド内にスティーラーズの選手は11人しかいなかっ たのである。カウアー・ヘッドコーチは、問題のプレーの様子を撮影したインスタント写 真を持って審判に猛抗議を行ったが審判はその写真を見ることを拒否、怒ったカウアーは、 その写真を審判のポケットに突っ込んで抗議の意志を示したが、当然受け入れられること はなく、後半は一気にミネソタのペースとなって大敗。前週に引き続いての連敗を喫して しまった。
フットボールに限らず、多くのスポーツに誤審はつきものであるが、この日の試合では、 それが試合の流れに大きく影響し、敗戦に結びつく形となってしまった。プレイヤーの数 を数え間違えてしまった審判に対して、試合後カウアーは、「うちの9歳の娘でも、そん な数え間違えはしない」と怒りをぶちまけていたようだが、なんとも運が悪かったとしか 言いようがないだろう。
このような判定のミスが起こるたびに、コーチや選手、ファンなどからは、以前導入さ れていたインスタント・リプレイ(ビデオによる判定)の復活を望む声があがる。このシ ステムは、91年のシーズンを最後に廃止されてしまったのだが、誤審の影響の大きさを 考えると、復活を望む声は絶えることがない。
確かに、適切な角度からビデオの撮影を行い、即座に判定できるようなシステムは、運 用のコストもかかるだろうし、審判にしてみれば、自分が下した判断に対して抗議され、 ビデオを見たら自分が間違っていた、などということになれば、審判の権威が脅かされる ことにもなりかねないわけで、なかなか承服しがたいところなのであろう。
他のスポーツでも、ビデオを用いた判定がうまく運用されている例は非常に少ない(陸 上競技のゴール判定などは別だが)。例えばアイスホッケー(NHL)では、パックがゴ ールしているかどうかの判定にビデオが参考にされることがあるが、実際に活用される頻 度はかなり低いようだ。また、判定に時間がかかるという点で、観客の受けも良くない。
野球やサッカーなどでは、ビデオを判定に導入しようなどという話をすると、ファンの間 からも反対の意見が聞かれることが多い。判定ミスもゲームのうち、と割り切る考え方も あるし、判定に時間をかけることで試合の流れが損なわれてしまう恐れもある。そのよう なスポーツでは、ビデオの導入は困難であろう。
もっとも、ビデオをうまく活用して判定の参考にしているスポーツがない訳ではない。 大相撲だ。もともと行司の判定に対して勝負審判が「物言い」をつけるというシステムが 確立されていたために、ビデオの導入がスムーズに行われたのかもしれない。多くのスポ ーツでは、審判の判定は「絶対」であり、その判定をチェックする「勝負審判」のような システムがないわけだが、相撲ならば、もともと行司の上に勝負審判がいてチェックして いるのだから、物言いの判定にビデオを使おうが使うまいが大差なく、導入に反対する理 由がなかったのかもしれない。
また、大相撲では、ビデオの分析結果が無線で勝負審判に迅速に伝えられるといったシ ステムが採用されているため、判定に不必要な時間がかからないという点も運用の成功に つながっているといえよう。
NFLでも、なんとかうまい知恵を絞り出して、インスタント・リプレイを再び導入し ようという方向で検討を進めているようである。今後の動きに注目していきたいところだ。 少し話が脱線してしまったが、この審判の判定がからんで痛い敗戦を喫して2勝2敗と なったスティーラーズは翌週、サンディエゴ・チャージャーズを破ったものの、その次の 週にはジャクソンビル・ジャガーズに破れ、再び3勝3敗の五分となり、なかなか調子の 波に乗れない。ジャガーズは、この年に新たにNFLに加わったチームであるが、過去の 例からみても、新規加入のチームは「寄せ集め」のチームであるため、初年度は大きく負 け越すものと考えて間違いない。従って、ジャガーズ戦は、当然勝つものとしてチームも ファンも計算していたはずである。そういった意味でも、このジャガーズに負けたことは 非常な痛手であった。
さらに翌週、過去8連勝中のシンシナチ・ベンガルズ相手に、9対27と大敗を喫する。 これで、このシーズンの通算成績は3勝4敗となり、負けが先行する形となってしまった。 何よりも、同一地区のチームに対して2週続けて敗れてしてしまったことが、非常に痛か った。
同一地区のチームに連敗を喫したことがなぜ痛かったかという説明をする前に、ここで NFLの対戦カードの決め方について簡単に仕組みを説明しておこう。 この95年から、 2チームが増えて、AFC、NFCともに15チームずつとなったのだが、NFLでは、 AFCとNFCの両カンファレンス間の交流試合も行われるため、基本的に各チームは、 どのチームとも対戦する可能性がある。ただし、1シーズンの試合数は16試合しかない ので、毎年29チームすべてと対戦するわけではない。
各カンファレンスは5チームずつ東、中、西の3地区に分けられ、次のような内訳で、 シーズン16試合を戦う仕組みになっている。
つまり、年間の試合数の半分の8試合を同一地区内のチームと戦い、残りの半分を地区外 のチームと戦うことになる。したがって、同一地区内の4チームとは毎年2回も対戦する 一方、残りの25チームに対しては、平均して3年に1度程度しか対戦する機会が回っ てこないことになる。なかなかユニークな仕組みである。
このような対戦カード決定システムのもとでは、同一地区のチームとの対戦は、地区優 勝を争う直接の相手を叩くチャンスであり、たいへん重要な試合となる。他地区のチーム に負けてもただの1敗だが、同一地区のライバルに負けてしまうと、自分たちが優勝争い から一歩後退するだけでなく、相手側が着実に一歩前進してしまうことになるからだ。勝 つのと負けるのとでは大きな違いである。同一地区のチームに連敗したのが痛いと言った のは、このような理由によるものなのである。
ところで、シーズン試合の内、半分は他地区のチームとの試合になる訳であるが、 その対戦カードの決め方も、なかなかユニークな方式が採用されている。どうユニークな のかというと、どのチームと対戦するのか決める際には前年度の成績が考慮され、上位の チーム同士、あるいは下位のチーム同士の対戦カードが多く組まれるような仕組みになっ ているのである。
このシステムは、実力のあるチーム同士の好カードを増やす効果を持つと同時に、前年 度の成績が良くなかったチームは、比較的楽な対戦カードが組まれることから、それを生 かして優勝争いに加われる可能性が生まれてくるのである。したがって、比較的多くのチ ームがシーズン後半まで優勝争いに加わってくることが可能なのだ。
このように説明すると、チーム毎にハンデをつけているようで、一見フェアではないよ うにも思われる。しかし、たとえば大相撲でも、下位の力士が勝ち続ければ、上位の力士 に当てられて、大抵は優勝争いから脱落していくのと同様、いくら対戦相手に恵まれたお かげでプレイオフに出場できたとしても、そこから先は実力がものをいう。真に強いチー ム以外、スーパーボウルには出場できないようにできているのだ。なかなかうまく考えら れている。
このような仕組みで決定された対戦カードに従って9九月の上旬から12月の下旬まで の4カ月に渡ってほぼ毎週試合が行われていく。おもしろいことに、シーズンの前半に、 ものすごい勢いで勝ち進んでいたチームが、後半には同じチームとは思えない程の大不振 に陥ったり、逆に前半が駄目だったチームが後半盛り返したりするといったことが毎年の ように繰り返される。
これにはいくつかの原因が考えられるのだが、まず第一は気候の変化があげられる。9 月初旬などは、気温が30度を越えるような暑い日も珍しくないのに対して、12月とも なれば、北部では氷点下での試合も覚悟しなければならない。冬でも暖かい地方のチーム など、寒さに慣れていないチームが次第に成績を落としていくというケースもあるのだ。
さらに、アメリカンフットボールは非常に激しいスポーツであり、怪我や故障は、避け られないものである。そうなると、選手層の厚さというものが非常に重要になってくる。 たとえば、シーズン開始当初は理想のメンバーで戦えたとしても、次第に主力が何人か怪 我をしてしまえば、力のある控え選手がいないチームでは戦力がガタ落ちになる可能性が 高い。戦力的に劣るポジションがあれば、相手は徹底的にその弱点を突いてくるため、そ れが致命傷となることも少なくない。また、たとえ大きな怪我がない場合でも、シーズン が進むにつれて、お互いに戦力の分析が進み、同じパターンで勝ち続けることが難しくな ったり、逆に自分たちの弱点をうまく克服していくことで、チームに勢いが出てくる場合 もある。
こういった様々な状況によって、各チームの成績というものは次第に変化していくのが 普通である。もちろん、シーズンを通して低迷するチームや、逆にシーズンを通して圧倒 的な力を見せつけるチームもないわけではないが、そのようなチームは非常に稀である。 いかにシーズンを通して良い成績を収め、しかもプレイオフに向かってチーム力のピーク を作っていくかがコーチの腕の見せどころである。
したがって、3勝4敗という満足のいかないスタートを切ったスティーラーズであるが、 まだまだ慌てることはないのである。ヘッドコーチのカウアーは、就任以来3年連続でチ ームをプレイオフに導いた実績がある上に、AFC中地区の他チームもあまり良くない成 績であることは、スティーラーズにとって好材料である。
ここまでの不振の原因のひとつは、もちろん、ウッドソンが怪我でシーズンを棒に振っ てしまったことと、オドネルも数試合の欠場を余儀なくされたことであったのだが、ウッ ドソンの代わりに、セーフティからコーナー・バックにコンバートされたカーネル・レイ クが目覚ましい活躍をしはじめ、オドネルも戦列に復帰してきたことで、後半戦へ向けて 戦力が徐々に整いつつあり、決して悲観する必要はないのである。
もうひとつの不振の原因は、前年までランニングバックとして活躍していたフォスター の放出により、彼のランによる攻撃を中心としてきた過去3年間の戦い方からの方向転換 に手間取ってしまったという点があげられる。しかし、まだシーズンは半分以上残ってお り、このあたりで新しい戦い方を確立できれば、十分巻き返し可能な時期である。
この7試合終了時点で、スティーラーズの攻撃陣の獲得ヤード数はかなり低いレベルの 数字となっていた。また、ある程度、相手陣内まで攻め込んでも、ゴールまで20ヤード のいわゆるレッドゾーンに入ってからの攻撃でタッチダウンを奪えずに、フィールドゴー ルに甘んじるというパターンが目立っていた。
しかしながら、さすがにヘッドコーチのビル・カウアーの手腕は大したもので、シーズ ン中盤から次第にパス攻撃をうまく使えるようになり、それにつれてラン攻撃も決まり出 すという、良い方向へチームを動かしていくことに成功するのである。
そのシーズン中盤以降、チームに大きな勢いを与えたのが、新人ワイドレシーバーのコ ーデル・スチュワートである。彼は、大学時代はクオーターバックとして活躍した選手な のであるが、スティーラーズに入ってからは、ワイドレシーバーに挑戦し、クオーターバ ックとしてではなく、レシーバーとして登録されていた。その彼が、持ち前の機動力を生 かして、第3ダウンの攻撃などの要所要所で、クオーターバックのポジションに入り、自 ら走ったり、パスを投げたりと大活躍を始めたのである。もちろん本業(?)のレシーバ ーとしてもタッチダウンパスをキャッチするなど、目立った活躍をみせ、大いにファンを 沸かせたのだ。彼の活躍とともに、チームに勢いが生まれ、急激にチーム状態が上向きに なっていった。
特に、相手にとって厄介だったのは、正クオーターバックのオドネルを中心にハドル(グ ラウンド内で円陣を組んで行う作戦会議)を組んでおきながら、実際にはワイドレシーバ ーのはずのスチュアートがクオーターバックの位置に入り、逆にオドネルがレシーバーの 位置に入るというプレイである。同じパターンで、普通にオドネルがクオーターバックで プレイする場合もあり、相手はその両方のケースに対処しなければならないのである。
ハドルを解いてから、実際にプレイが開始されるまでには数秒から十数秒しかなく、相 手はスティーラーズのフォーメーションを見ながら慌てて対応する必要がある。したがっ て、精神的に余裕のない状況でプレイしなければならないのである。
また、オドネルがクオーターバックを務める場合にも、ここ一番の場面で、スチュアー トを含めた5人のレシーバーを走らせるという攻撃パターンが大いに功を奏した。通常、 レシーバーは多くても4人までなのだが、スティーラーズはしばしばレシーバーに5人を 送り込むという思い切った作戦を採用したのである。
相手にしてみれば、5人全員をマークする必要がある訳である。3人のレシーバーを相 手にする場合と比べれば、レシーバーひとりあたりのマークは当然甘くなる。そこで、マ ークを逃れてフリーになった選手にパスを投げるという作戦なのだ。その5人の中のひと りとして、スチュワートは、時にはおとりとなって相手ディフェンスを撹乱し、またある 時はみずから見事なパスキャッチを見せるなど、大活躍を始めたのだ。
スチュワートの活躍とともに、チームの成績も急激に上向きはじめた。3勝4敗と低迷 していたチームが、ジャクソンビルを24対7と下し、さらに翌週シカゴ・ベアーズを延 長の末に37対34で破って、久々の連勝を記録する。これで調子をつかんだスティーラ ーズは、さらにクリーブランド、シンシナチ、クリーブランド、ヒューストンとAFC中 地区のライバルチームをたて続けに破って合計6連勝。あっさりと地区優勝を決めてしま ったのである。完全に自分たちの新しい戦い方をつかんだようだ。
この連勝劇の中で、地元のファンにとってこたえられなかったのが、長年のライバル、 クリーブランド・ブラウンズを連破したことであった。ピッツバーグとクリーブランドは 距離的にも約200キロしか離れておらず、また、どちらも鉄鋼の町で、ブルーカラーの 熱烈なファンがチームを支えるという共通点をもつ。そういった理由で、両チームのライ バル意識というものは相当なものであった。もちろん、同一地区のチームであるから、優 勝争いという意味でもライバル意識は強く、両者の対戦カードは毎年、最も人気のあるカ ードのひとつとなっていた。
この両チームが2週間の間に2度にわたって対決しようという時期に、ブラウンズは突 然、翌年からボルチモアへ移転することを発表した。クリーブランドのファンには非常に ショッキングなニュースであったが、ピッツバーグのファンにとっても、長年の良きライ バル関係が終わってしまうということは、非常に寂しいニュースであった。やはり「クリ ーブランド」相手だから燃えるのであって、ボルチモアに行ってしまったら、それだけの 思い入れはなくなるのではないか、というのがピッツバーグのファンの声であった。
そうは言っても、決まってしまったことならば仕方ない。そういうことならば「最後の クリーブランド戦」となる2試合(地元と敵地)を連勝して幕引きに、というのがスティ ーラーズファンの期待である。
その期待にチームは見事に応えてくれた。ピッツバーグでの試合では、スチュワートが プロ入り初のタッチダウンパスを成功させるなどの活躍で大いにスタンドを沸かせ、20 対3と圧勝した。
また、敵地クリーブランドでの試合では、ブラウンズも意地を見せて、第3クオーター 終了時点で17対17の接戦となった。しかしスティーラーズは、第4クオーターにフィ ールドゴールを成功させ、20対17とブラウンズを振り切った。この試合でも、スチュ ワートはオドネルからの31ヤードのロングパスをキャッチするとともに、クオーターバ ックとしては2度のパスを2度とも成功させるなどチームの勝利に大きく貢献した。
このスチュワートは、ワイドレシーバー、クオーターバック、ランニングバックと、3 つの役割りをこなすため、彼のポジションを示す時には、「WR/QB/RB」などとス ラッシュ(/)で区切って表記することになる。そこで、彼はいつの間にか「スラッシュ」 というニックネームで呼ばれるようになり、話題のルーキーとして一躍脚光を浴びる存在 となっていったのである。
昔は、このように複数のポジションをこなす選手が結構いたのだが、最近のNFLでは、 貴重なクオーターバックに怪我をさせてはいけないということで、クオーターバックを他 のポジションにも使うような例はまず見られない。このような使い方に苦言を呈する評論 家もいるわけだが、ファンにとっては、彼のような万能選手は非常な魅力である。彼がフ ィールドに登場すると、何かやってくれるのではないかという期待を持たせてくれるのだ。
結局スティーラーズはこのシーズン、3勝4敗のあと8連勝し、完全に立ち直った。最 後のグリーンベイとの試合で、あわや九連勝かという逆転のタッチダウンパスをレシーバ ーが落として惜しくも敗れてしまったが、11勝5敗という好成績でレギュラーシーズン を終了することができた。
西地区優勝のカンザスシティ・チーフスが13勝3敗、東地区優勝のバファロー・ビル ズが10勝6敗であったため、チーフスが第1シード、スティーラーズが第2シードとなっ た。両チームはプレイオフの第1週は試合がなく、第2週にそれぞれの地元で第1週の勝 者を迎え撃つ。
その挑戦者を決めるプレイオフ第1週の試合では、バファローとインディアナポリスが 勝ち上がったため、第2週はバファローがピッツバーグに、インディアナポリスがカンザ スシティに挑戦することとなった。
バファロー・ビルズは、3年前のプレイオフでも対戦した相手で、その時にはスティー ラーズは完敗を喫している。しかし今回は、その時のお返しとばかりに試合開始から一方 的にスティーラーズが攻め立て、40対21とビルズを圧倒し、あっさりAFCチャン ピオンシップゲームへの進出を決めたのである。
一方、カンザスシティの方は、インディアナポリスに対して、再三のフィールドゴール のチャンスにキックが決まらず、10対7という低得点の試合で敗れてしまった。氷点下十 度(風による体感温度は氷点下二十度)を下回るという最悪のコンディションがキックの 正確性を欠かせたのであろう。外した3本のキックのうち、2本は40ヤードにも満たな い距離であった。普通の気温ならば、まず外すことのない距離である。
チーフスはこの試合の前まで、地元では一年以上負け知らずであったが、肝心な試合を 落としてしまったことになる。この結果、第5シードのコルツが、ピッツバーグでスーパ ーボウル出場を賭けたAFCチャンピオンシップゲームを戦うこととなった。
もし、第1シードのチーフスが勝っていれば、第2シードのスティーラーズは敵地での 試合になるところであった。大事なチャンピオンシップゲームを有利な地元で行えるとい うことからも、第5シードのコルツの勝利はスティーラーズにとってラッキーであるよう に思われたし、戦力的にもスティーラーズ有利という評判であった。
もっとも、前年のサンディエゴ・チャージャーズとのAFCチャンピオンシップゲーム も、試合前の予想ではスティーラーズ有利のはずであったのが、最後に「あと3ヤード」 足りずに悔しい負けを喫している。したがって、このコルツ戦も決して油断することので きないゲームである。
スーパーボウル出場をかけたチャンピオンシップゲームは、試合開始早々から波乱含み の展開となった。最初に攻撃権を得たスティーラーズが、いきなりパスをインターセプト され、自陣24ヤードという不利な位置からコルツの攻撃となってしまう。結局タッチダ ウンこそ逃れたものの、フィールドゴールを決められ、試合開始後わずか3分のうちに、 あっさりと3点を先制されてしまうのである。
その後、両チームのディフェンス陣が頑張りを見せて、共にタッチダウンを許さず、各々 フィールドゴールを一本ずつ決めて6対3とコルツがリードする展開となる。次第に重苦 しい雰囲気のゲームとなりつつあったが、第2クオーター終了間際に、ようやくオドネル からスチュワートへのタッチダウンパスが決まり、スティーラーズは10対6とリードを奪 って前半を終了する。
ちなみに、このスティーラーズのロングドライブでは、スチュワートが大きな役割を果 たした。「あと1、2ヤード進めば第1ダウン獲得」という場面になると、彼はクオータ ーバックとして登場し、自らボールを持ち込み第1ダウンを獲得したり、あるいはランニ ングバックとして登場してボールを前に進め、そして最後にはタッチダウンパスまでキャ ッチするという奮闘ぶりをみせたのだ。まさに「スラッシュ」の本領発揮、八面六臂の大 活躍である。
これで前半のコルツペースから、後半はスティーラーズのペースになるかと期待された のだが、そう簡単には勝たせてくれない。ゲームは後半になっても一進一退の攻防を続け る。両チームフィールドゴールを各一本ずつ追加し、13対9とスティーラーズがわずか 4点をリードする展開で、第4クオーターを迎えた。
ここでスティーラーズは、約40ヤードのフィールドゴールのチャンスを迎えるが、な んとキッカーのノーム・ジョンソンが、ゴールを外してしまい、追加点を取ることができ ない。これで、試合の流れはコルツの方へ大きく傾いていく。
次のコルツの攻撃で、クオーターバックのハーボーがスティーラーズ・ディフェンスの 一瞬のスキをついて、47ヤードのタッチダウンパスを見事に決め、16対13と逆転す るのである。前年のチャンピオンシップゲームで、チャージャーズに破れた時と全く同じ パターンだ。選手もスタンドのファンも、前年の出来事を思い出していたに違いない。
その後、両チームは一回ずつ攻撃権を得るものの、いずれも得点に結びつけることがで きず、残りわずか3分3秒でスティーラーズが最後の攻撃のチャンスを得る。自陣33ヤ ード地点からの攻撃だ。
ここから約1分の間になんとか相手陣内38ヤードの地点までボールを進め、残り時間 2分となった。プロのフットボールの試合では、残り時間が2分となると、自動的にタイ ムアウトとなる。テレビ中継ではCMタイムとなる訳だが、同時にフィールドでは次のプ レイについてじっくりと作戦を立てる時間になる。ここでスティーラーズは一発狙いのロ ングパスを投げる作戦に出た。そしてその作戦通り、レシーバーのミルズが37ヤードの パスを見事にキャッチし、ゴールまで残り1ヤードに迫る。6万の観衆で埋め尽くされた スタンドは、まさに興奮のルツボと化した。
ここで、モリスが着実に1ヤードのタッチダウン・ランを決め、ついに20対16と再 逆転に成功する。残り時間は、あと1分34秒である。
コルツ最後の攻撃は自陣の16ヤード地点から。得点差は4点。したがってフィールド ゴールでは追いつかない点数である。つまり、約1分半のわずかな残り時間で、84ヤー ド進んでタッチダウンに結びつけなければコルツに勝ち目はない。スティーラーズの勝利 はほぼ確定的なものにも思われた。 しかし、ここからコルツのクオーターバック、ハーボーが驚異的な粘りを見せる。まさ に綱渡り的なプレイの連続なのだが、なんとか攻撃をつなぎ、ゴールまで29ヤードの地 点へボールを進めたところで、残り時間が5秒となった。次が最後のプレイである。
この状況で、コルツの取り得る作戦は、ただひとつである。イチかバチかの「ヘイル・ メアリー」パスだ。自軍選手がキャッチすることを信じ、運を天にまかせて、エンドゾー ンへロングパスを放り込むのである。コルツの選手がキャッチすれば逆転サヨナラ勝ち、 逆にスティーラーズの選手がそのパスをキャッチするか、地面にタタキ落とせば、スティ ーラーズの逃げ切りとなる。このゲーム、試合開始から約3時間の戦いが繰り広げられて きたのだが、結局は最後の5秒、ワンプレイの結果によって、AFCチャンピオンが決ま るのだ。
コルツは、クオーターバックのハーボーの右側に、3人のレシーバーを並べ、ダッシュ の構えに入る。そして、ハーボーがスナップを受けると同時に、その3人のレシーバー陣 は、いっせいにエンドゾーン右寄りの一角を目指してスタートを切る。同時に、スティー ラーズのディフェンス陣も相手レシーバーのカバーに走る。観客は息をのみ、テリブルタ オルを振る手も止まる。
タイミングを見計らって、ハーボーがパスを投げる。一秒。二秒。三秒。大きな弧を描 いてボールはエンドゾーンへと向かう。すでに、エンドゾーンには、コルツの3人のレシ ーバーと、5人のスティーラーズ・ディフェンスが入り乱れてパスを待ち受けている。ボ ールがゆっくりと彼らに向かって落ちてくる。スリリングな一瞬である。
ようやく落ちてきたボールに向けて、選手たちが一斉にジャンプ。手をのばす。運命の ボールはスティーラーズのディフェンシブエンド、フラーの指先に当たった。
ところが、そのブロックされたボールの落ちていく先には、背中から倒れこんでいくコ ルツのレシーバー、ベイリーの姿があった。そして、彼の背中が地面を叩くのとほぼ同時 に、ボールは彼の右足でバウンドし、宙に浮く。まだボールは生きている。跳ねたボール は、倒れている彼の左脇へ向かって落ちていく。そしてまさに地面に触れるか触れないか という微妙なタイミングでベイリーはボールをすくい上げる。彼はすぐさま立ち上がり、 チームメイトとともに両腕を突き上げてタッチダウンのポーズだ。一方、その横でスティ ーラーズの選手たちは、両手を拡げてパス不成功のジェスチャーをしている。
両軍の選手がこのように、それぞれの判定のパフォーマンスを見せるのを横目に、本物 の審判が淡々とパス不成功のジェスチャーをしていた。その瞬間、観衆は歓喜の大爆発だ。 スティーラーズの勝利であった。
コルツの選手たちは、一瞬の天国から地獄へ突き落とされた思いであろう。スタッフに 肩をたたかれて慰められても、呆然として一歩も動けない選手もいる。気をとりなおして、 スティーラーズの選手と握手を交わしてスーパーボウルでの健闘を祈る選手もいる。ステ ィーラーズベンチサイドでは、抱き合って喜ぶ選手たちの姿がみられる。ヘッドコーチの ビル・カウアーは、潤む目を見ひらき、口を真一文字にむすんで喜びをかみしめている。 彼がそのような表情をファンに見せるのは初めてのことだ。
両チームとも最後の最後まで全力でぶつかり合った素晴らしいゲーム。これぞフットボ ール、というナイスゲームであった。勝った方は、後で思い出すたびにぞっとするような 冷や汗ものの勝利であったし、負けたコルツの選手にとっては、一生わすれることのでき ない悔しい試合であったに違いない。
翌日から、コルツの選手たちは、ストーブリーグに突入する。一方のスティーラーズは、 2週間後に控えた最後の大仕事へ向けて、もうひとがんばりだ。
全米の注目の的となるスーパーボウルであるが、出場するチームの地元では、出場が決 まってから本番当日まで、まさにお祭り騒ぎの毎日となる。
各々の地元のファンが、いかに自分たちがチームをサポートしているのかを様々な形で みせつけるあたりもひとつの見どころである。例えば、スティーラーズの対戦相手となっ たダラス・カウボーイズの地元であるテキサス州には、「ピッツバーグ」という名前の小 さな町があった。しかし、スーパーボウルでカウボーイズが対戦する敵の本拠地と同じ名 前では具合いが悪いということで、この期間に限って町の名前を「カウボーイズ」と変更 してしまったのである。そしてこの変更に伴って、道路標識を塗りかえるといったセレモ ニーまでおこなってしまうという力の入れようだ。一方、スティーラーズの地元、ピッツ バーグでも、「ダラス通り」という名前の通りは「スティーラーズ通り」に変更するなど、 こちらも負けてはいない。
それから、各地元の新聞、テレビ、ラジオも連日スーパーボウルの話題で持ち切りとな る。いかに地元チームが有利であるかを示すデータを様々な角度から見つけてくるあたり は、なかなかおもしろい。たとえば、次のような「スティーラーズ必勝理論」などは、地 元のファンを大いに喜ばせた。
アメリカには、いわゆる4大プロスポーツとして、野球、アメリカンフットボール、バ スケットボール、アイスホッケーが人気を誇っているが、ピッツバーグには、このうちバ スケットボールを除く3つのプロスポーツのチームが本拠地を置いている。MLB(野球) のパイレーツ、NHL(アイスホッケー)のペンギンズ、そしてNFLのスティーラーズ である。
これらのスポーツの頂点を争うチャンピオンシップ・ゲームは、MLBならばワールド シリーズ、NHLはスタンレイカップ、そしてもちろんNFLではスーパーボウルである。 実は、これらのスポーツのチャンピオンシップ・ゲームで、ピッツバーグのプロチームは、 70年近く負けなしの9連勝中なのである。
1927年に、パイレーツがワールドシリーズでニューヨーク・ヤンキースに破れてし まったが、その後、60年、71年、79年と3度のワールドシリーズには、全て優勝し ている。また、スティーラーズも74、75、78、79年と4度のスーパーボウルに全 勝、さらにペンギンズは91、92年と2年連続してスタンレーカップ・チャンピオンと なっている。あわせて9戦全勝なのだ。
従って、スーパーボウルへの出場が決まった時点で、これはもう勝ったも同然、十連勝 だ、というのが地元ファンの言い分なのである。このような、まことしやかな必勝の論理 をみつけてきては、久々のスーパーボウル優勝を夢見るというのも、試合前2週間の正し いファンのすごし方なのだ。
スーパーボウルの話題は、地元ばかりではなく、全米のマスコミも連日大きく取り上げ る。スター選手へのインタビューなどは、大きな関心の的となるのだが、特にカウボーイ ズのディオン・サンダースなどは、何かと話題を提供してくれる選手であるため、マスコ ミの格好の取材対象となる。
このサンダースには、非常な「目立ちたがり」というイメージが定着しているのだが、 今回も期待通りにその本領を発揮してくれた。マスコミが「スラッシュ」スチュアートの 多才なプレイぶりを取り上げて、攻守に活躍するサンダース(彼はコーナーバックに加え て、レシーバーとしてもプレイしている)とさかんに比較するのだが、そうなるとサンダ ースは「彼よりも目立ちたい。彼がクオーターバックをやるのだから自分もクオーターバ ックをやりたい」などと発言をするなど、やはり自分が一番でないと気がすまないようで ある。
まあ、こういった彼の言動は今に始まったことではない。彼がこの95年のシーズンま で、大リーグの選手としても活躍していたのは有名な話であるが、それも目立ちたがりの 彼の性格によるものだ、ということになっている(もちろん真偽の程は本人のみ知るとこ ろであるが)。 そんな彼が、前代未聞のチャレンジをして大いに人々の注目を浴びたことがある。それ は92年のことなのだが、当時、彼は大リーグのアトランタ・ブレーブスとNFLのアト ランタ・ファルコンズの両方に所属していた。春から秋までは大リーグでプレイし、秋か ら冬にかけては、NFLでプレイするという仕組みだ。そのブレーブスがナショナルリー グ西地区の優勝を果たし、東地区の優勝チーム、ピッツバーグ・パイレーツとワールドシ リーズ出場をかけてプレイオフを行うこととなった。
ところが、そのプレイオフ期間の最中に、NFLの試合がある日曜日が重なってしまっ たのだ。野球のプレイオフの方は、土曜も日曜もピッツバーグでナイターで行われる。一 方、その日曜の昼には、マイアミでフットボールの試合が組まれているのである。重要な プレイオフであるから、フットボールは一週休んで野球に集中するだろうというのが一般 の考え方であるが、彼は、両方の試合に出場しようと試みるのである。
この「変則ダブルヘッダー」となる日曜日の前日、夜中の12時前にピッツバーグでの パイレーツ戦を終えたサンダースは、深夜の1時には、ピッツバーグ空港からチャーター 機でマイアミへ向けて飛びたち、夜明け前にホテルに入った。そして翌日(正確には当日 と言うべきか)の午後時開始のフットボールの試合に出場したのである。さらに、その 試合の終了と同時に、彼は近くの空港へ直行し、待たせてあったヘリに飛び乗る。さらに 飛行機を乗り継いで、夜の8時にはピッツバーグ空港へ戻ってきたのだ。そして、待たせ てあったヘリコプターで球場近くのテレビ局の屋上へ飛び、8時40分の試合開始にぎり ぎり間に合うという離れ業をやってのけたのである。
もっとも、ブレーブス球団の方は、この彼の計画にもともと反対だったようで、試合に は出してもらえず、ベンチを暖めるだけ、という結果に終わっている。新聞などの論調は、 「チームメイトは皆、試合開始の何時間も前からユニホームを着て準備しているのに、試 合開始15分前に駆け込んでくるなど論外」といったきびしいものであった。義理人情を 重んじる日本ならばともかく、アメリカならば、こんな派手なパフォーマンスは喝采を浴 びるものと考えがちであるが、意外にそうでもないのである。どうも、彼のあまりにも自 己中心的な性格が、ファンやマスコミの反感をかう結果となってしまったようである。
ちなみに、マイアミ往復の旅費は200万円とも300万円とも推定されるのに対して、 フットボールの試合を1試合欠場した場合、彼の年俸の減額分は、千数百万円ということ で、採算的には、この「日帰り旅行」は黒字という計算になる。しかし、彼の場合は、お 金のためというよりは、単に目立ちたかったんだ、という説明で大方が納得してしまう所 など、なんとも彼らしいエピソードである。
もっとも彼は、このようにグラウンドの外でばかり目立っていた訳ではない。野球選手 としても立派な記録を残している。この92年のシーズン、彼は三塁打王に輝いているの だ。しかもこの年、彼は162試合のうち、たった97試合しか出場していないのである。 他の「本職」の大リーガーたちが、162試合出場してもサンダースほど多くの三塁打を 記録することができなかったことになる。
過去、これだけ少ない出場数で三塁打王になった選手はいない。いかに彼の足が速くて も、大リーグの投手が投げる球を長打コースへ打ち返せなければ、三塁打にはならない。 彼は、バッターとしても非凡な才能をもっていたのである。性格はどうであれ、彼のスポ ーツ選手としての能力は卓越したものがあるのだ。
この彼が、アリゾナのサン・デビルスタジアムで、今度はフットボールの選手として、 あっと驚くビッグプレイをみせてくれるのか、サンダースファンはもちろん、アンチ・サ ンダースのフットボールファンにとっても、目が離せないところである。
一方、スティーラーズの方にも非常に個性的で何かと注目を浴びる選手がいる。ライン バッカーのケビン・グリーンだ。彼のトレードマークはなんといってもヘルメットから大 きくはみ出す長い金髪だ。彼は、「スーパーボウルに勝ったら、この長髪を切る」と言っ ており、ピッツバーグのファンは、彼のショートヘアーを見るのを楽しみにしている。 彼の人気の秘密は、その独特の風貌とともに、攻撃的なプレイぶりにある。この年のレ イダースとの試合では、相手クオーターバックを引きずり倒した時に、相手のユニホーム を引きちぎってしまった。NFLのユニホームは、相当丈夫に作られていて、まず破ける ことなどないように出来ている筈なのだが。
そんな力いっぱいのプレイを決めて大喜びする彼の姿は、やはりファンにとっては大き な魅力である。さらに、彼が多くのファンの支持を集める理由はそれだけではなく、非常 にファンを大切にしてくれる点にもある。
チームの地区優勝に伴って、プレイオフ・ゲームのチケットが売り出された時に、地元 のファンがスタジアムに何時間も並んでいるところへ彼がひょっこり現れ、山のようなハ ンバーガーを差し入れるといったことをしている。これがグリーン流のファンへの感謝の 気持ちの表現方法なのだろう。このような彼の行動が、さらに多くのファンをひきつける のだ。
その彼が、チームメイトとともにアリゾナ入りした後、信じられないような行動をして みせた。スーパーボウルまで1週間もないこの時期に、スケジュールの合間を見つけて、 ラスベガスに飛び、友人のプロレスラー、ハルク・ホーガンの試合場へ駆けつけてセコン ドについたのである。試合では相手の反則にレフェリーが気づかず、ホーガンが負けてし まう。レフェリーにアピールしても聞き入れられない。そこで、彼はリングへ上がり、ホ ーガンを助けて相手をリングの外へ放り投げるなど、大暴れをしたのである。
まあ、このあたりは「筋書き通り」のパフォーマンスなのであろうが、それにしても大 事な試合を前に怪我でもしたら大変なことになるわけで、普通では考えられない行動だ。 しかし、彼にとっては、これが大試合を前にリラックスする一番の方法だったのであろう。 さて、この彼の行動には誰もが驚かされたが、実は全く別の意味で、もっと驚くべきこ とをやってのけた男がいた。その男の名前はロッド・ウッドソン。開幕戦で膝の十字靱帯 を断裂するという大けがをした男である。過去のNFLの歴史の中で、この怪我をした選 手が、そのシーズン中に試合に復帰した例はなかった。しかし彼は、なんとしてもスーパ ーボウルには出るという強い意志で治療、リハビリを続け、そしてついに、スーパーボウ ルの出場選手リストに名を連ねたのである。驚異の回復力である。
普通であれば、怪我をした時点で彼を故障者リストに移し、代わりの選手を登録するこ とになるのだが、そうすると、彼はこのシーズン中に復帰してプレイすることが許されな くなってしまう。それで彼の登録は抹消されず、出場選手登録したままリハビリを続けて いたのだ。スーパーボウルでの彼の復帰に賭けて、選手登録枠をひとつ犠牲にした格好で ある。それほど、彼への期待は大きなものだったのだ。そして、ついにウッドソンは試合 に出られるまでに回復してきた。彼の精神力の強さとリハビリへの努力が並み大抵のもの でないことは、ファンにも容易に想像がつく。ピッツバーグのファンにとって、彼の復帰 は、感動的な出来事であり、また、彼のような選手を持ったことを皆非常に誇りに思って いる。
1996年1月28日、アリゾナ州サンデビル・スタジアムに両チームの選手が入場し てくる。その中にウッドソンの元気な姿も見える。これをファンは5カ月の間待ち続けて きたのである。
この日のスタンドは、圧倒的にスティーラーズを応援するファンの方が多かった。黄色 いテリブルタオルがスタンドのいたるところで揺れている。スティーラーズのファンに加 えて「アンチ・カウボーイズ」の観客もかなり多いようだ。カウボーイズの選手たちが出 てきた時の声援に比べて、スティーラーズの選手たちが出てきた時には一段と大きな声援 が浴びせられた。絶対不利と言われるスティーラーズの方を応援したいというファンもか なり多いようだ。アメリカでも「判官贔屓」というのがあるらしい。
7万6千人のファンが見守る中、試合は、スティーラーズのキックオフでいよいよ開始 された。カウボーイズの最初の攻撃では、クオーターバックのトロイ・エイクマンからマ イケル・アービンへの20ヤードのパス、さらにエミット・スミスの23ヤードのランが たて続けに決まり、あっという間にスティーラーズ陣内28ヤード地点までボールが進む。 カウボーイズ得意の攻撃パターンが、いきなり炸裂した格好だ。このピンチに、スティー ラーズのディフェンスも粘りを見せて、なんとかタッチダウンは免れるが、フィールドゴ ールが決まって、3点をダラスが先制した。試合開始から、わずか三分ほどの出来事であ る。
一方、続くティーラーズの攻撃では、10ヤード進むことができずにパントキック、再 びカウボーイズの攻撃となる。ここでダラスは、サンダースへの47ヤードのパスを成功 させるなどして一気にスティーラーズ陣内へ攻め込んで、最後はノバチェクへのタッチダ ウンパスを決めて10対0とリードを拡げる。ダラス自慢の多彩な攻撃パターンがおもしろ いように決まり、完全にダラスのペースだ。このあとも、スティーラーズの攻撃はダラス 陣内まで攻め入ったものの結局パントに終わったのに対して、ダラスはフィールドゴール に結びつけて13対0とスティーラーズを圧倒する。
鉄壁のディフェンスを誇るスティーラーズなのだが、シーズン中からスロースタートと いう特徴があり、第1クオーターは相手の出方をみて、次第に適応していくという展開が 多かった。しかし、この試合では、相手の様子を見ている間に13点も奪われてしまった のだ。このままでは大差の試合になりかねない展開である。
第2クオーターも残り5分を切った時点で、両チームはそれぞれ3回ずつの攻撃をおこ なったことになるのだが、ダラスがフィールドゴール2本とタッチダウン1本であったの に対して、スティーラーズは、3回ともパントであった。しかし、このあたりからようや く鉄のカーテンが本領を発揮しはじめる。次のダラスの攻撃では、スミスのランを止め、 アービンへのパスを不成功に終わらせた。やっとスティーラーズ・ディフェンスが目を覚 ましてきたようだ。
さあ、そうなると今度は、攻撃陣が頑張りをみせる番である。モリスのラン、オドネル のパスが決まる。そして、最後はシグペンへのタッチダウンパスが成功し、7対13と6 点差で前半を終了することができた。このタッチダウンが決まった時には、サンデビル・ スタジアムを埋めた多くのファンがテリブルタオルを振って、スタンドは一面黄色に揺れ た。まるでピッツバーグのスリーリバーズ・スタジアムを思わせるような光景だ。この大 応援団がバックについているということは、スティーラーズの選手たちを大いに元気づけ たに違いない。
前半30分のうち、最初の25分間は完全にダラスのペースだったことを考えると、 前半を終えて6点差というのは、幸い最小限の点差である。試合の後半に十分に逆転の期 待が持てる点差だ。スタンドのファンの多くがスティーラーズの味方をしてくれるという のも心強い。試合後半のドラマを信じて選手たちはハーフタイムを迎えた。
しかしその後半戦、先に得点したのはカウボーイズの方であった。スティーラーズの攻 撃の時に、オドネルが投げたパスが、カウボーイズのラリー・ブラウンの正面へ行ってし まったのだ。インターセプションだ。ブラウンは44ヤードを走り、ゴールまで18ヤー ドと迫った。痛いミスである。
ここでカウボーイズは、17ヤードのパスを決めた後、スミスの1ヤードのランで、あ っさりタッチダウンである。20対7となり、流れは再びカウボーイズである。続くステ ィーラーズの攻撃も相手陣内へ進むことができず、再びカウボーイズの攻撃となる。
このいやな流れを断ち切ったのは、やはりスティーラーズのディフェンス陣であった。 スミスが6ヤード走った後、第2ダウンではパスを試みるのだがロイドがボールを叩き落 としてパス不成功。さらに第3ダウンでは、アービンへ投げたパスをウッドソンがカバー して、またまたパス不成功。ダラスはパントを蹴ることになる。
このロイド、ウッドソンというスティーラーズ・ディフェンスの顔とも言うべき2人の 活躍で、カウボーイズペースの試合の流れをスティーラーズ側へ少し引き戻すことになる。 次のスティーラーズの攻撃では、なんとかフィールドゴールを奪い、20対10とした。 しかし、もう残り時間は約11分である。ディフェンス陣が好調であるから、次のカウボ ーイズの攻撃をきっちり止めればスティーラーズにもチャンスは十分あるのだが、もし、 相手が時間をかけてじっくり攻めてくれば、次にスティーラーズが攻撃権を得るころには、 試合時間が3、4分しか残っていないということも十分考えられる。そうなると10点差を ひっくり返すのは容易ではない。
ここで、カウアーヘッドコーチのカンピューターがひらめく。なんと「フェイク・オン サイドキック」に打って出たのだ。通常のキックオフでは、敵陣深くボールを蹴り込み、 ゴールまで70ヤードから80ヤードという位置から相手の攻撃を開始させるのだが、オ ンサイドキックは、ボールを10ヤードほど転がし、自分たちでそのボールを確保して、攻 撃権を奪おうという作戦である。もちろん、相手側はそのボールを待ち受ける格好である のに対して、味方のプレイヤーはボールの後から追いかける形になるので、ボールの取り 合いという意味では、不利であるのだが、だ円形のボールがイレギュラーバウンドするた めに、蹴った方のプレイヤーがボールをおさえる可能性もあるわけだ。
当然、このプレイが失敗した場合には、相手チームはゴールまで50ヤード程の良いポ ジションから攻撃開始することになってしまうため、このプレイを選択する際には、成功 する確率と失敗したときのリスクなど、さまざまな要因を考慮して判断することになる。
通常は、本当に追いつめられた時に使う作戦で、この場面では、まだ残り時間が11分 以上あるのだから冒険はしないのが普通である。相手もまさかここでオンサイドキックを してくるとは予想していないはずだ。そこで、この場面でカウアーが指示したプレイはフ ェイク・オンサイドキック、つまり、通常のキックオフを行うフォーメーションから、オ ンサイドキックを行うのである。
キッカーのノーム・ジョンソンは、ボールに向かって何くわぬ顔で助走を開始する。そ して、ボールを高く蹴り上げると見せて、右斜め前方へボールを転がしたのである。ここ で慌てるカウボーイズの選手たちを尻目に、スティーラーズのフィギュアスが、ボールへ 一直線に走り込み、見事にボールを確保。攻撃権を得ることに成功したのである。誰もが あっと驚くトリックプレイであった。
こうなると流れは一気にスティーラーズのものとなる。オドネルがたて続けにパスを成 功させ、最後はモリスが1ヤードのタッチダウン・ランを決めて、20対17と3点差に 詰め寄った。
次のカウボーイズの攻撃であるが、またしてもスティーラーズのディフェンスが見事な 守りを見せ、再びカウボーイズはパントに追い込まれる。残り時間4分強で、スティーラ ーズの攻撃となる。
この4分という時間を使ってタッチダウンに結びつければ、逆転して4点差をつけるこ とになる。しかも相手の攻撃時間はほとんど残っていないはずだ。4点差ということは、 フィールドゴールの3点では追いつけないわけで、タッチダウンを狙うしかない。そんな 状況になれば、スティーラーズの勝利がかなり濃厚となる。試合の流れ、残り時間、点差、 これらの要因を総合すると、むしろ3点リードされているスティーラーズの方が有利かと も思える状況だ。
しかし、ここで大きな落とし穴が待っていた。フットボールの神様というのがいるとし たら、とんでもない筋書きを書いてくれたものである。スティーラーズのクオーターバッ ク、オドネルがパスを投げた先には、本来いるはずのスティーラーズのレシーバーの姿は なく、そのかわりに、カウボーイズのコーナーバック、ラリー・ブラウンが待ち受けてい たのである。第3クオーターにも彼にパスをインターセプトされているのだが、またして も、彼に「ストライク」を投げてしまったのである。そのままボールはピッツバーグ陣の 6ヤードまで持ち込まれ、その地点からカウボーイズの攻撃である。スミスが2ヤードと 4ヤードのランを簡単に決めて、27対17。勝負あり、だ。最後のスティーラーズの攻 撃も得点には結びつかず、そのまま試合終了である。
スーパーボウルの名にふさわしい、終盤まで勝負の行方がわからない好試合であった。 特にスティーラーズのディフェンス陣は、序盤こそダラスの快進撃を許したものの、後半 は完全に押さえ込むことに成功した。カウボーイズのエース・ランニングバック、エミッ ト・スミスも、結局たったの49ヤードしか走ることができなかった。しかも、そのうち 23ヤードは、試合開始早々の最初のランで稼いだものであり、それ以後は、17回走っ て合計26ヤードと、スミスにしては信じられないような低い数字に抑えたのである。
もっとも、この中には、1ヤードと4ヤードのタッチダウン・ランが含まれている。こ れらは共に、オドネルが投げた2回のインターセプションによって、ダラスがゴールを目 の前にした位置からの攻撃権を得た時に記録したものである。いくらスティーラーズのデ ィフェンスが良いといっても、ゴール直前からの攻撃では、スミスが走るのを防ぐことは 難しい。相手は、リーグNO1のランナーだ。
つまりダラスは後半、スティーラーズ・ディフェンスに攻撃を完全に封じられた時に、 スティーラーズ・オフェンスのミスをうまく利用して、得点を重ねたことになる。やはり 大試合では大きなミスを犯した方が負けということなのであろう。しかも、一度ならず二 度のミスは致命傷であった。
ビル・カウアー38歳、スーパーボウルに出場した最年少のヘッドコーチとなったが、 残念ながら今回は、勝ち星をあげることはできなかった。しかし彼は就任以来4年間、毎 年プレイオフにチームを導くとともに、着実にチーム力をステップアップさせてきた。フ ァンの間からは、早くも「将来フットボールの殿堂入りするだろう」という期待の声もあ がっている。そんな大監督を目指すカウアーにとっては、今回の敗戦はひとつのステップ であり、スティーラーズ黄金時代の復活への大きな一歩なのである。
スーパーボウルに出場するチームの中には、常連のチームと、その年だけなぜか好成績 を収めて勢いに乗って出場してくるチームとがある。後者の場合には、ここで勝っておか なければ、次のチャンスは何十年先になるかわからないわけで、敗戦のショックは大きい かも知れない。しかし、スティーラーズの場合は、カウアーという類い希な才能をもった ヘッドコーチを擁しており、今後もスーパーボウルの「常連」となっていくべきチームで ある。この敗戦が悔しいのは確かだが、それよりもチームとして良い経験を積んだと考え るべきであろう。
長いシーズンが終わった。スティーラーズは雪辱を期して新たなチャレンジを開始する。 ここまでの1年間は、前年にスーパーボール出場まであと3ヤード足りなかったことから 「THREE MORE YARDS!」を合言葉に戦ってきたが、今後1年間のスティ ーラーズとファンの合言葉は、「UNFINISHED BUSINESS!(やり残し た仕事)」である。
Copyright(C) 1997 by Kinshiro Nishiodachime